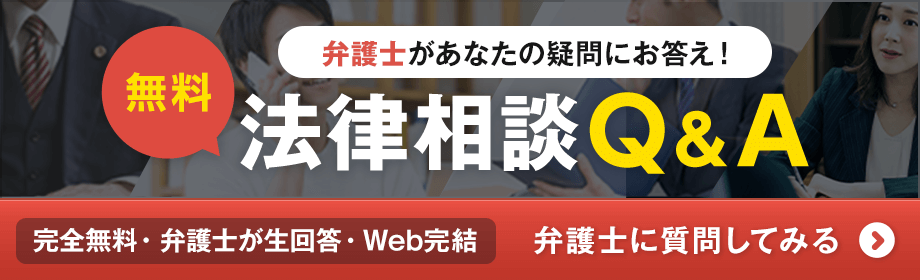離婚する専業主婦の年金はいくら?損しない年金分割ガイド


離婚の財産分与では、夫の年金も分与の対象になります。
専業主婦の場合、最も不安なのが金銭面という方も多いかもしれません。離婚後の生活のためにも、できるだけお金をもらっておいた方が良いでしょう。
離婚時に配偶者の年金を分けることを「年金分割」といいます。年金分割は、まだ自身が年金を受け取る年齢でなくても請求することが可能です。
この記事では、年金分割に関する基礎知識や夫に請求する方法、受取額の計算例などを解説します。
専業主婦の「年金分割」に関する5つの基礎知識

ここでは、年金分割に関する基礎知識を解説します。
1:年金分割の対象は厚生年金のみ
「年金分割」といっても、すべての年金の分割を請求できるわけではありません。
請求できる年金の種類は、厚生年金に限ります(共済年金は2015年10月より厚生年金制度に統一)。

なお配偶者が結婚してからずっと自営業という場合には、年金分割が請求できない可能性もあります。
ただし自営業であっても、会社組織(有限会社・株式会社)として働いている場合は請求できます。
2:結婚期間中の分しかもらえない
年金分割では、夫の厚生年金・旧共済年金すべてのうちの半分を得られるわけではありません。対象になるのは婚姻関係が成立していた期間分です。
別居が長い場合でも、戸籍上は婚姻関係になっているため、期間内に含まれます。
事実婚の方が関係解消する場合にも、年金分割を請求することができます。
その場合には、夫の扶養に入って第3号被保険者(※)だった期間が対象になります。
例えば「夫の厚生年金・共済年金の加入期間が50年で、結婚していた期間が30年」というケースでは、対象になるのは50年のうちの30年、つまり「年金の5分の3」となります。
妻が得られるのは、最も高い場合で半分の金額です。つまり、最高で10分の3の年金を得ることが可能です。
- 民間企業の従業員や公務員に従事する配偶者に扶養されている、年収130万円未満の人のことです。
3:年金は離婚後すぐにもらえない可能性もある
年金分割したとしても、すぐには年金を受け取れないこともあります。
例えば、「自身がまだ年金受け取りの対象年齢になっていない」というケースなどが該当します。
分割した年金は、受け取れる年齢になってから支払われます。
また、自身が年金を受け取る年齢になる前に夫が亡くなってしまった場合でも、受給することができます。
4:2008年の3月と4月で割合の決め方が異なる
2008年4月に「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度」が導入されたことにより、2008年4月以降から離婚するまでの間の年金の割合は、自動的に2分の1になります。
夫婦で話し合う必要も、裁判所で決めてもらう必要もありません。
しかし、2008年3月以前も婚姻関係にあった場合、結婚した時点から2008年3月までの年金の割合については夫婦で話し合う必要があります。
年金分割の割合は最も高い場合で2分の1ですが、夫が「半分も払いたくない!」と主張した場合は、調停で決めることになります。
調停の申立てについて詳しくは「年金分割の割合を決める調停の流れ」で後述しています。
5:年金分割は離婚後2年を過ぎると請求できなくなる
年金分割にも請求期限があり、離婚(事実婚や内縁の場合は婚約解消)した日の翌日から起算して2年以内です。
過ぎてしまった場合には請求できなくなりますので注意しましょう。
【モデルケースあり】離婚した専業主婦は年金をいくらもらえる?
「2:婚姻期間中の分しかもらえない」で解説した通り、年金分割で対象となるのは婚姻期間中の分だけです。
それを踏まえると、以下のような計算式が成り立ちます。

夫の厚生年金(共済年金)の全受給額は、ねんきん定期便の「厚生年金保険」という項目からチェックできます。
また、年金分割の割合については、2008年3月以前も婚姻関係にあった場合には話し合って決める必要があるため、注意しましょう。
年金については物価や経済の状況で変わるため、あくまでおおよその金額となり、正確な金額を出すことはできません。
ここでは、離婚した専業主婦がいくら年金を受け取れるのか、計算例を紹介します。全受給額は「厚生年金保険・国民年金事業の概況|厚生労働省」を参考にしています。
実際は掛金額が変動するため、上記のように単純に計算できるものではありませんが、あくまで一つの参考としてご覧ください。
詳しい金額を知りたい場合は、日本年金機構に相談しましょう。
結婚年数が20年で年金分割の割合が2分の1の場合
「結婚年数:2000年〜2020年の20年間、夫の勤務年数:40年、年金分割の割合:2分の1」という場合、受け取れる金額は以下のようになります。
|
年金の全受給額(万円) |
もらえる金額(万円) |
|
200 |
50 |
|
180 |
45 |
|
160 |
40 |
|
140 |
35 |
|
120 |
30 |
結婚年数が30年で年金分割の割合が2分の1の場合
「結婚年数:1990年~2020年の30年間、夫の勤務年数:40年、年金分割の割合:2分の1」という場合、受け取れる金額は以下のようになります。
|
年金の全受給額(万円) |
もらえる金額(万円) |
|
200 |
75 |
|
180 |
67.5 |
|
160 |
60 |
|
140 |
52.5 |
|
120 |
45 |
年金分割の割合を決める調停の流れ
夫婦間の話し合いで年金の割合が決まらなかった場合には、裁判所に「年金分割の割合を定める審判又は調停」の申立てを行います。
申立てからの流れは以下の通りです。

ここでは、調停の流れについて解説します。
調停の申立て
年金の割合が話し合いでも決まらない場合、夫の住所地の家庭裁判所もしくは夫婦で定めた家庭裁判所へ、年金分割の割合を定める調停を申立てます(裁判所一覧)。
もし、年金分割以外の離婚に関わること(慰謝料・親権・財産分与・養育費など)を決める場合には、年金分割の割合を定める調停ではなく「夫婦関係調整調停(離婚)」を申立てます。
調停では、夫婦が別室に入って調停委員に仲介してもらいながら、話し合いと合意によって問題解決を目指します。
必要書類
必要書類は以下の通りです。
- 申立書と写し
- 年金分割のための情報通知書
年金分割のための情報通知書は年金事務所へ申請します。詳しくは「離婚時に年金分割をするとき」をご覧ください。
必要費用
必要費用は以下の通りです。
- 収入印紙:1,200円
- 連絡用の郵便切手:状況や裁判所によって変わるため、詳しくは裁判所へ確認してください(裁判所一覧)。
調停成立・不成立
調停が成立した場合には、「年金分割の請求手続き」を行います。調停でも話がまとまらず不成立になった場合には、「審判手続き」へ移ります。
できるだけ調停を成立させるためには、お互いに譲歩しながら話し合うことが大切です。また調停では、弁護士と一緒に出頭することもできます。
早期解決を望むのであれば、「弁護士に依頼して代わりに交渉してもらう」というのが有効でしょう。
審判手続き
審判手続きでは、裁判官が提出された資料や双方の事情などを考慮して割合を決定します。
この決定に不服がある場合は、2週間以内に不服の申立てを行います。これによって、高等裁判所での再審理を受けることができます。
その際の必要書類は、審判の申立書と写し・年金分割のための情報通知書などです。
ただし、状況によっては追加で書類を請求されることもあるでしょう。
申立て費用としては、1,350円の収入印紙と連絡用の郵便切手が必要です。
年金分割の請求手続き
調停または審判で割合が決まった後は、年金事務所または各共済組合にて、年金分割の請求手続き(標準報酬改定請求等)を行わなければいけません。
この手続きは、離婚が成立した日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。
なお、離婚成立後に調停や審判で年金分割を申立てて、その手続き期間中に期限を迎えてしまった場合は、手続き終了後1ヶ月以内に対応しなければいけません。
年金分割の請求手続き先一覧
厚生年金か共済年金かによって請求手続きをする場所は異なります。参考としてご覧ください。
|
職業の種類 |
年金の種類 |
手続き先 |
|
民間企業の従業員 |
厚生年金 |
住所地の年金事務所 |
|
地方公務員 |
地方公務員共済年金 |
各所属(元所属)共済組合 |
|
私立学校の教師 |
私立学校教職員共済年金 |
|
|
国家公務員 |
国家公務員共済年金 |
各省庁の共済組合 ※退職している方は国家公務員共済組合連合会
|
必要書類
必要書類は、どのように割合が決まったかで異なります。
|
決まり方 |
必要書類 |
|
夫婦間の話し合いで決まった場合 |
|
|
調停で決まった場合 |
|
|
審判で決まった場合 |
|
確定証明書については、交付請求しなければいけません。請求していない方は、審判を行った裁判所に問い合わせましょう。
このほかにも書類を追加請求されることもあるため、不安な方は年金事務所または各共済組合に直接確認することをおすすめします。
標準報酬改定通知書の受け取り
手続き後、標準報酬改定通知書が日本年金機構または共済組合から届き、完了となります。
年金分割のための情報通知書の申請方法

「年金分割のための情報通知書」には年金分割の対象期間などが記載されており、正しい割合を決める際の重要な書類となります。
申請には以下の書類が必要です。
- 年金分割のための情報通知書
- 妻(請求する側)の国民年金手帳
- 年金手帳・基金年金番号通知書
- 婚姻期間が記載されている市区町村の証明書または戸籍謄本、もしくは戸籍抄本
また、籍を入れていない事実婚の方は、事実婚関係にあったことを証明できる書類(世帯全員の住民票の写しなど)が必要です。
これらの書類を準備したのち、「年金分割の請求手続き先一覧」を参考に、それぞれ該当する機関に申請します。
まとめ
年金分割では、夫婦間で話し合いが必要であったり書類作成に追われたりなど、労力がかかります。
自身で対応すると揉めてしまう可能性もあるうえ、作成書類の不備に気づかないこともあるかもしれません。
その点、弁護士であれば、交渉対応や書類作成などの必要な手続きを依頼できますので、まずは気軽に相談してみましょう。


【初回面談60分無料】【不倫慰謝料請求/不倫絡みの離婚など】離婚問題は経験豊富な当事務所へご相談を。幅広い案件に対応可能です◆別居前相談/財産分与/養育費/面会交流◆ご依頼者様の人生の再スタートを全力でサポート!<面談のご予約はメール・LINEがおすすめです>
事務所詳細を見る
【不倫慰謝料/協議/財産分与/国際離婚(中国)/養育費】など幅広く対応!◤多額の財産分与・慰謝料・婚姻費用(養育費)を請求したい・請求された方/相手が資産をお持ちの方/離婚を決意した方◢【初回相談:1時間無料】※新規のご相談者さま専用のお問い合わせ窓口です※
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

その他に関する新着コラム
-
子どもの連れ去りは、状況によって違法となるケースがあります。本記事では、子どもの連れ去りが違法となるケース・違法とならないケースの具体例や、連れ去りが発覚した際...
-
配偶者の不機嫌な態度、いわゆるフキハラ(不機嫌ハラスメント)に悩んでいませんか?無視されたり威圧的な態度をとられたりといった行為は、フキハラといえます。この記事...
-
調査官調査とは、親権について争いがある場合におこなわれる調査です。必ずおこなわれるわけではなく、事件が長引きそうなときや裁判所が判断しにくいケースで実施されます...
-
育児放棄を理由に離婚することは可能です。ただし、裁判離婚で離婚が認められるには「法定離婚事由」に該当する必要があり、単なるワンオペ育児では認められない可能性が高...
-
パートナーが統合失調症で、離婚を考えていませんか?話し合いで離婚できない場合の手続きや、裁判になった場合の「法定離婚事由」について詳しく解説。離婚が認められない...
-
妻が勝手に家出した場合、離婚や慰謝料請求が認められますが、家出に正当な理由がある場合は認められないため注意しましょう。本記事では、妻が家出した場合の離婚や慰謝料...
-
夫の家出は「悪意の遺棄」として離婚理由になる可能性があります。生活費や慰謝料の請求も可能です。本記事を読めば、離婚を有利に進めるための証拠集めや法的手続きの全ス...
-
離婚届を書き間違えても焦る必要はありません。原則として、訂正印などは不要で、一部を除いて記載者本人以外の代筆による訂正も可能です。本記事では、離婚届を書き間違え...
-
本記事では、離婚時のマンションの選択肢3選をはじめ、売却で失敗しないための査定のタイミングや手続きの流れ、ローンの残債別(アンダーローン、オーバーローン)それぞ...
-
妊娠中の別れは、感情的な問題だけでなく、法律上の義務や経済的負担が大きく関わるデリケートな問題です。 妊娠中の彼女・妻と別れることが可能かどうか、そして別れた...
その他に関する人気コラム
-
事実婚をする人の中には同性であったり夫婦別姓が認められないために事実婚を選択していたりとさまざまなケースがあります。この記事では事実婚と認められるための要件や要...
-
【弁護士監修】夫や妻と離婚したくない場合に、どうすればよいのかわからない方に対して、今すべきこととNGなコトを徹底解説。離婚を回避するための詳しい対処法もご紹介...
-
産後から夫婦生活がなくなってしまう人は少なくありません。実際産後どのくらいの期間から再開すればよいのかわかりませんよね。この記事では、「産後の夫婦生活はいつから...
-
マザコンにはいくつか特徴があり、母親への依存心が強すぎると夫婦関係が破綻することもあります。状況によっては別居や離婚などを選択するのも一つの手段です。この記事で...
-
「旦那と一緒にいてもつまらない」「旦那が家にいるだけでストレスになる」と思いながら生活していませんか。ストレスを我慢して生活することはできますが大きなリスクも伴...
-
当記事では、夫婦別姓のメリット・デメリットをわかりやすく解説。制度の仕組みや日本の現状も簡単に説明します。
-
子連れで再婚したいけれど、子供の戸籍をどうすべきか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。戸籍によって子供の苗字や相続権なども変わるため、決断は慎重に行う必要が...
-
夫婦間の話し合いで離婚の同意が取れず裁判所を介して離婚をする場合、法律で認められた離婚理由を満たしていることが不可欠です。この記事では法定離婚事由と夫婦が離婚す...
-
弁護士会照会とは、弁護士法23条に定められた法律上の制度で、弁護士が担当する事件に関する証拠や資料を円滑に集めて事実を調査することを目的としています。
-
婚姻費用を払ってもらえたら、専業主婦の方などでも別居後の生活費にできるので、安心して離婚を進めることができるでしょう。この記事では、婚姻費用がいつからいつまで、...
その他の関連コラム
-
重婚的内縁の定義や法律上の扱いについて解説します。重婚的内縁が不倫になったり保護されたりするなどの要件は複雑です。本記事でそれぞれについて解説しますので、ご自身...
-
夫婦が離婚する場合、いずれか一方は婚姻中の戸籍から外れ、別の戸籍へ移ることになります。 その際の選択肢は、婚姻前の戸籍に戻るか、または新しく作られる戸籍に入る...
-
浮気が原因で婚約破棄をした場合、元婚約者や浮気相手に対して、慰謝料をはじめとした損害賠償請求ができます。本記事では、婚約破棄後に請求できるお金の種類や慰謝料の相...
-
再婚の際は、今後どちらの苗字を名乗るのか、養子縁組をするかなど、事前に検討しなければならないことがいくつかあります。本記事では、再婚を進めるうえで検討すべき点や...
-
「旦那と一緒にいてもつまらない」「旦那が家にいるだけでストレスになる」と思いながら生活していませんか。ストレスを我慢して生活することはできますが大きなリスクも伴...
-
新築離婚は新築の家を建てたり購入したりした後に離婚することを指し、増加傾向にあります。本記事では新築離婚の原因をはじめ家の処分方法や財産分与のポイントを解説し、...
-
「結婚後悔症候群」という俗称ができるほど、結婚を後悔する人は多くいます。あまりにも夫婦関係の溝が深い場合には離婚などを考える必要があるでしょう。この記事では、結...
-
専業主婦の場合、最も不安なのが金銭面という方も多いでしょう。年金分割は、まだ自身が年金を受け取る年齢でなくても、請求することが可能です。この記事では、年金分割に...
-
妻がしゃべらない。話しかけても無視をされる。『妻が口をきいてくれません』という漫画が話題になったようにそんな悩みを抱えている夫は多いです。そんな夫へしゃべらない...
-
妻が勝手に家出した場合、離婚や慰謝料請求が認められますが、家出に正当な理由がある場合は認められないため注意しましょう。本記事では、妻が家出した場合の離婚や慰謝料...
-
別居中でも婚姻費用を負担する必要はあります。しかし、別居の理由や別居後の生活に不満があり、支払いに納得できないという方もいるでしょう。そこで本記事では、婚姻費用...
-
離婚に向けて別居している場合でも婚姻費用の支払い義務は免れません。ただし、別居や離婚の理由が配偶者にある場合や、離職・病気などの理由で減収した場合は婚姻費用の減...
その他コラム一覧へ戻る