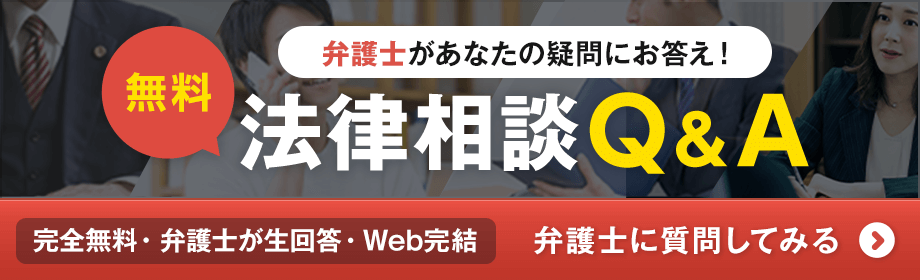財産分与の時効(除斥期間)は2年!時効後にできること


財産分与は2年以内に請求しないと時効(除斥期間)が成立し、請求する権利が完全に消滅してしまいます。
離婚時に話しをまとめておければいいのですが、家庭の事情や離婚時の状況によっては難しいこともあるでしょう。
早めに申立てをしなければ、大きな損をしてしまいますし後悔する可能性もあります。この記事では、離婚後に確実に財産分与請求をするための方法について説明します。
|
離婚時の財産分与は 弁護士に相談することで |
|
一部ではありますが、弁護士に依頼することで以下のようなメリットがあります。
|
財産分与の時効に関する2つの権利

財産分与の時効(除斥期間)を考える際に重要な2つの権利について紹介します。
1:相手に財産分与を求める権利(財産分与請求権)
この権利は民法第768条に2年の除斥期間と定められています。そのため、離婚後2年以内に財産分与を請求しなければ完全に権利が消滅します。
また、この権利は離婚届が役所に受理され、離婚が成立した時点から発生します。なので、別居を2年以上していた場合でも離婚成立時から2年以内であれば財産分与の請求が可能です。
もちろんですが、2年を過ぎた場合、相手が任意で応じてくれない限り財産分与の請求をすることはできません。
2:財産分与の結果を踏まえて財産の引き渡しを求める権利(財産分与に基づく財物引渡し請求権)
離婚後2年以内に協議、調停、裁判などで財産分与についての権利が確定した場合、この権利は10年間消滅することはありません。
財産分与請求について除斥期間は2年と定められていますが、その請求によって確定した権利は一般の債権と同様に10年の時効となるためです。
仮に10年が経過しそうであれば、同権利を求める訴えを提起することで時効を中断させることも可能です。
財産分与は2年以内に請求を

相手に財産分与を求める権利が消滅してしまうと、財産分与に基づく財物引渡し請求権を行使することができません。
なので、財産分与を離婚後に話し合う場合は、必ず2年以内に協議を開始し、協議が整わないのであれば調停を申し立てましょう。
財産分与請求は消滅時効ではなく除斥期間!消滅時効と除斥期間の2つの違い

財産分与請求権についての2年間という期間は時効期間ではなく、除斥期間です。そのため、これを止めたり延期したりすることはできません(除斥期間は不変です)。
消滅時効(時効)はドラマやニュースで聞く機会があるかもしれませんが、除斥期間はあまり聞かないですよね。ここでは2つの違いについて紹介します。
消滅時効とは
消滅時効(時効)は所定の手続きによって時効満了時期を延長したり、時効期間そのものをリセットすることが可能です。また、時効期間を過ぎても相手がこれを援用しない場合は、請求権は消滅しません。
除斥期間とは
除斥期間は消滅時効と違い、権利の有無を確定する不変期間です。時効期間と異なり延長やリセットをすることができません。
消滅時効と除斥期間をまとめると以下のような違いがあります。
|
内容 |
消滅時効 |
除斥期間 |
|
延長 |
できる |
できない |
|
リセット |
できる |
できない |
|
消滅方法 |
時効の援用によって消滅する |
期間が過ぎたら自然に消滅する |
|
離婚成立後に裁判での請求 |
できる |
できない |
除斥期間が過ぎた場合には弁護士への相談が有効
上項でも説明した通り除斥期間を過ぎての請求は基本的にできません。ただ、相手が任意で財産分与に応じてくれる可能性はゼロではありません。
この場合弁護士に依頼して適切な分与方法を提案してもらうということも検討に値するでしょう。
なお、離婚から2年が経過しており、かつ相手が財産分与を拒否しているにもかかわらず、執拗に財産分与を求めることは、場合によっては脅迫罪・恐喝罪・強要罪などに該当する可能性があります。
金銭が関わってくる分お互いに熱くなりやすく、刑事事件に発展する可能性もありますので注意しましょう。まずは手紙で請求するなど冷静な対応が必要です。
共有名義の不動産について財産分与を求める権利が失われた場合の対処法

不動産が共有名義の場合でも請求権が消失してしまうことがあります。ここでは、そのような場合の対処法についてご紹介します。
相手から不動産を買い名義を変更する
相手から買い取ることで名義を変更することができます。売買価格を適正に決めたいという場合は、不動産鑑定士に依頼する必要がありますが、相当な費用がかかってしまいます。
弁護士に相談すれば他の適切な価格算定方法を提案してくれるかもしれません。なお、売却にかかるその他費用の目安として『相続した不動産の売却時の手続きと発生する費用』をご覧ください。
相手から贈与という形で名義を変更する
財産分与として不動産を受け取ることはできませんが、『贈与』という形で譲ってもらうことはできます。贈与の場合、買取費用もいらないためお得と感じる人は多いかもしれませんが、贈与税の支払いが必要になります。事案によって金額は異なりますので、どのくらい税金が必要なのかはこちら『夫婦間の居住用不動産の贈与』からご確認ください。
まとめ
財産分与には2年の除斥期間が定められており、原則、それを過ぎると財産分与を受けることはできません。
離婚時の理由(心身の不調や家庭の問題)などにより、離婚から2年経ってしまう場合もあるでしょう。早めの対処が肝心ですので注意しましょう。
また、財産分与について疑問がある場合には弁護士の無料相談を活用しましょう。最善の選択を取るためのアドバイスをもらうことができるかもしれません。
|
離婚時の財産分与は 弁護士に相談することで |
|
一部ではありますが、弁護士に依頼することで以下のようなメリットがあります。
|


【初回相談料60分5500円】ご自身又はお相手が経営者・不動産を多数所有している方など複雑な財産分与も◎◆経験豊富な弁護士がご満足のいく解決を目指します◆別居・不倫など幅広い離婚問題に対応◎【茅場町・日本橋駅から徒歩5分・東京証券取引所前】
事務所詳細を見る
【表参道駅から1分/初回相談1時間無料/オンライン相談可】離婚問題でお困りの際は全力で手助けいたします。ご相談者様の力強い味方として一緒に解決を目指しましょう。ぜひお電話でお問い合わせください。
事務所詳細を見る
【初回相談料60分3300円】代表弁護士が離婚問題の解決を目指して直接対応!◆離婚調停を申し立てられた/申し立てたい/弁護士名義の書面が届いた等、離婚のご相談はお任せください◆事前予約で休日相談も対応◆
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

財産分与に関する新着コラム
-
ここでは、離婚時に専業主婦も財産分与を受けられる理由や対象となる財産の種類、相場よりも金額が低くなるケースを解説します。当記事を参考に、納得のいく金額で財産分与...
-
離婚時の財産分与で不動産がある場合、どのように分ければよいのでしょうか。今後も住み続けたい場合や、ローンがある場合などさまざまなパターンがあるので、悩んでしまい...
-
離婚するにあたって財産分与をする場合、どのような書類が必要なのか分からないという方もいるでしょう。預貯金や不動産など、婚姻期間中に築いた財産はさまざまあるはずで...
-
離婚後に財産分与の請求ができることは意外と知られていないかもしれません。本記事では、離婚後の財産分与の請求方法、離婚後の財産分与で注意すべきこと、離婚後の財産分...
-
夫婦が離婚するときは財産分与をおこない、預貯金や不動産などを分け合います。本記事では、離婚時の財産分与で通帳開示する方法や、弁護士に請求依頼するメリットを解説し...
-
離婚時に財産分与を請求された場合、退職金は原則として財産分与の対象となり得ます。本記事では、離婚時に退職金は財産分与の対象となるのか、離婚時に退職金を取られない...
-
離婚する際には、お金に関する様々な取り決めが必要になります。そのため、何かトラブルが生じるのではないかと不安に感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では...
-
離婚時の財産分与の対象に、結婚前の資産は含まれません。しかし、例外的に財産分与の対象となることもあります。財産分与は、夫婦で揉める問題のひとつです。この記事では...
-
離婚の際、争いの種となりやすいのが財産分与です。 本記事では、離婚前の財産分与について気を付けるべきポイントや、財産分与に関する問題を弁護士に相談するメリット...
-
自身が専業主婦であることから、離婚する際にしっかりと財産分与を受けられるのか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では、専業主婦が離婚する際におけ...
財産分与に関する人気コラム
-
離婚手続きを進めていくうえで、財産分与についても考える必要がありますが、財産を分ける際に税金がかかる場合があるということを知っていますか?本記事では、離婚時の財...
-
離婚の際に年金分割を拒否したいという方もいるでしょう。この記事では、年金分割を拒否できるのか解説しています。年金分割をしない場合の手続きについても、あわせて紹介...
-
離婚時の財産分与では、結婚前からの貯金や子ども名義の貯金など、貯金の種類によって分け方が異なります。隠し口座がないか不安な方は、弁護士などの力が必要になる場合も...
-
熟年離婚の財産分与は婚姻期間が長いほど高額になりやすく、1,000万円を超える夫婦も少なくありません。できるだけ多くの財産を受け取り、離婚後も経済的な不安がない...
-
共有財産(きょうゆうざいさん)とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産のことをいいます。財産の所有名義が一方の配偶者である場合でも、もう一方の貢献があったとみなさ...
-
財産分与は2年以内に請求しないと時効(除斥期間)が成立し、請求する権利が完全に消滅してしまいます。この記事では、離婚後に財産分与の請求を時効までにするため、財産...
-
社長や経営者と離婚すると、多くの場合、生活水準の低下などの事情から後悔する気持ちも出てくるかもしれません。しかし、この記事で紹介する3つの問題を踏まえ、離婚に望...
-
財産分与の放棄は相手方の承諾がなければおこなえません。なぜなら、財産分与請求権は夫婦それぞれの権利だからです。少しでも財産分与の内容を有利にするには、財産調査や...
-
夫婦が婚姻期間中に協力して株式を取得した場合、当該株式は財産分与の対象に含まれます。ただし、預貯金と違って株式は分割するのが困難なので、財産分与の方法などで争い...
-
離婚する際の夫婦の財産と損をしない財産分与の方法についてまとめました。
財産分与の関連コラム
-
離婚で財産分与をした場合、税金についても注意しなければなりません。本記事では、財産分与をおこなう際に注意したい税金について詳しく解説します。どのようなケースで贈...
-
離婚時の財産分与で不動産がある場合、どのように分ければよいのでしょうか。今後も住み続けたい場合や、ローンがある場合などさまざまなパターンがあるので、悩んでしまい...
-
離婚時、婚姻中に夫婦で築いた財産である家も、財産分与の対象です。家を財産分与する際には、家を売る方法もありますが、家を売らない選択肢もあります。本記事では、離婚...
-
離婚手続きを進めていくうえで、財産分与についても考える必要がありますが、財産を分ける際に税金がかかる場合があるということを知っていますか?本記事では、離婚時の財...
-
不動産を財産分与する際、夫婦でどう分ければいいのか、どんなことに注意したらいいのかなど、知りたいことが沢山あるでしょう。この記事では、不動産の財産分与で失敗しな...
-
夫婦が婚姻期間中に協力して株式を取得した場合、当該株式は財産分与の対象に含まれます。ただし、預貯金と違って株式は分割するのが困難なので、財産分与の方法などで争い...
-
扶養的財産分与とは、離婚後に元配偶者から生活費を一定期間負担してもらうことです。本記事では、扶養的財産分与の概要、扶養的財産分与が認められやすいケースなどについ...
-
離婚後に財産分与の請求ができることは意外と知られていないかもしれません。本記事では、離婚後の財産分与の請求方法、離婚後の財産分与で注意すべきこと、離婚後の財産分...
-
離婚することになったら、財産分与についても話し合わなければなりません。財産分与は夫婦で折半が基本的な考えではありますが、家はどのように分ければいいのでしょうか。...
-
特有財産に該当する財産や判例をわかりやすく解説します。
-
財産分与の放棄は相手方の承諾がなければおこなえません。なぜなら、財産分与請求権は夫婦それぞれの権利だからです。少しでも財産分与の内容を有利にするには、財産調査や...
-
夫婦が離婚する際には、共有財産について財産分与をおこないます。財産分与の対象となるのは、婚姻中に取得した財産です。本記事では、離婚時の財産分与の対象となる財産の...
財産分与コラム一覧へ戻る