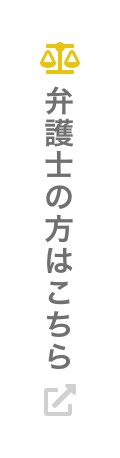離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える


年金分割(ねんきんぶんかつ)とは、夫婦が納めた厚生年金保険料を離婚時に分割し、保険料に応じた年金の給付を受けることですが、年金分割を請求された側は拒否できるのでしょうか。
結論から先にお伝えすると、原則として拒否はできません。ただし、年金分割をしなくてもよい場合もあります。
この記事では、年金分割を拒否できるケース、年金分割をしない場合の手続きについてくわしく解説します。
|
「離婚」と「年金分割」に関連するこちらの記事も読まれています |

年金分割には、合意分割制度と3号分割制度があります。「年金分割を拒否できるケース」の解説の前に、まずこちらを確認しておきましょう。
合意分割制度は、共働きの夫婦が離婚するときに適用される制度です。
2007年4月1日以降に離婚した場合、結婚期間中に納めた厚生年金の標準報酬部分を最大で50%まで分割できます。
分割の割合は基本的に話し合いで決めますが、双方の同意を得られない場合は、家庭裁判所での調停や審判が必要となります。
割合の決定後、年金事務所に年金分割を申請します。
3号分割制度の「3号」は国民年金の第3号被保険者のことで、専業主婦を指します。
2008年4月から離婚するまでの間、妻が専業主婦だった期間中の夫の厚生年金の標準報酬額の50%を受け取ることができます。
話し合いや調停、審判をすることなく決められた割合で分割できる点が、合意分割制度と大きく異なります。
なお、離婚後、妻が年金を受給できる年齢に達すると、老齢厚生年金として亡くなるまで支給され続けます。

年金分割は法律で定められた制度ですので、基本的に拒否できません。
離婚の際には、預貯金の分割や慰謝料などによって、ある程度の財産を得ることができますが、それだけでは生活がままならないケースがあります。
そこで2007年4月から実施されたのが年金分割です。配偶者が希望すれば年金分割が可能であり、もう一方の被保険者は基本的に拒否できません。
話し合いや調停で分割割合を決める合意分割制度であっても、一切の分割を拒否することはできないと覚えておきましょう。
ただし、次のような場合は結果として年金分割をせずに済む可能性があります。
年金分割は、夫婦間での合意、あるいは夫婦のいずれかの希望のもと、定められた方法で手続きしなければ実行できません。
離婚が成立してから2年以内が手続きの期限となっているため、離婚後2年以上が経過している場合は年金分割を拒否できます。
とはいえ、年金分割に関しての情報を配偶者に与えないと、後々トラブルに繋がる可能性があります。
子供がいて、配偶者が親権を持っている場合は、子供に会わせないなどの報復を受けることになるかもしれません。
年金分割の対象となるのは、結婚後に納めた保険料です。そのため、結婚前に納めていた保険料に関しては、年金分割できません。
晩婚の場合、結婚から離婚までよりも、結婚前に納めた保険料の方が圧倒的に多く、年金分割による不利益を抑えられることがあります。

年金分割は、夫婦の合意があれば行わずに済みます。この場合、離婚協議書において、「年金分割はしない」という条項を含める必要があります。
ただし、「3号分割」に関しては、相手の同意なく行える方法であるため、離婚協議書に年金分割をしないと明記されていても、離婚成立後2年以内であれば年金分割が可能となります。
なお、どちらか一方が年金分割を拒否し、話し合いでは解決しなかった場合、調停を行うことになります。
調停を申し立てる際は、夫婦の戸籍謄本と年金情報通知書、調停の申立書を管轄の家庭裁判所に提出します。
調停では、調停員が双方の言い分を考慮した上で円滑な話し合いをサポートするため、年金分割トラブルが解決する可能性があります。
調停でも話がまとまらなかった場合は、審判で分割の割合を決定します。離婚訴訟という選択肢もあり、そのときの状況によって選ぶべき方法は異なります。

年金分割の割合については、誤解している方が多い傾向にあります。再手続きを求められないように、間違えやすいポイントを確認しておきましょう。
年金分割は、年金を分割する側が受給に必要な加入期間を満たしていなければ適用できません。厚生年金の場合は、受給に10年の加入が必要です。
10年以下の場合は、年金分割を求められても実質のところ拒否できます。
合意分割制度では最大2分の1、3号分割制度では標準報酬額の2分の1の厚生年金を分割します。
ただし、対象期間は結婚してから離婚するまでの間であるため、必ずしも厚生年金の半分を受け取れるわけではありません。
例えば、厚生年金の加入期間が20年で、そのうち婚姻関係にあったのが10年の場合は、10年間に納めた厚生年金保険料が年金分割の対象となります。
厚生年金保険料を納め始めたときから納め終わるまでの間、ずっと婚姻関係にあった場合には、結果として厚生年金の半分を妻が受け取ることになります。
夫が亡くなると、分割した厚生年金の支給そのものがなくなると思っている方もいますが、実際には夫の生死に関係なく厚生年金を受給できます。
年金を受給できる年齢に達する前に離婚した夫が亡くなった場合にも、分割した年金は妻に支払われ続けます。
ただし、亡くなった夫の年金を離婚した妻が代わりに受け取ることはできません。
年金分割では、受給できる金額が多い方から少ない方へ分割するため、夫よりも妻の方が多くの厚生年金を受け取れる場合は、妻の年金を夫へと分割します。
また、国民年金は年金分割の対象外のため、夫が自営業で妻が会社勤めの場合も、妻の年金が夫へと分割されます。
年金分割の対象となるのは、厚生年金保険および共済年金の部分のみであり、厚生年金基金は対象にはなりません。
厚生年金基金を多くかけている方に、年金もそれだけ多く妻に渡すことになると思い、間違った老後の計画を立ててしまうケースが見られます。
離婚を考える際、年金分割を考慮して厚生年金基金を解約するといったことのないよう注意が必要です。

基本的に、年金分割を拒否することはできませんが、弁護士に相談することで分割割合の割合を抑えられる可能性があります。
弁護士に相談するメリットや依頼費用の相場について見ていきましょう。
弁護士に相談することには、次のようなメリットがあります。
話し合いで方針がまとまらなかった場合には、調停や審判、離婚訴訟を検討することになります。そのときの状況次第で行うべきことが変わります。
適切でない方法を選ぶと、年金分割トラブルが長引き、余計な費用もかかってしまうでしょう。
弁護士に相談することで、どの方法が最適かアドバイスを受けられるため、早い段階での解決が期待できます。
弁護士は、年金分割トラブルの事例を知っているため、客観的な視点からさまざまなアドバイスをしてくれます。
年金分割を一切拒否したいという考えが変わったり、最小限の経費で最大の利益を得られたりする可能性があります。
話し合いに時間がかかることで日常生活に支障をきたす場合もあるため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
法的な知識が豊富な弁護士に依頼することで、依頼人に有利な形で話し合いをまとめられる可能性があります。
法律の専門家である弁護士と話すことで、感情を優先した交渉ではなく、論理的な交渉ができるようになるでしょう。
年金分割に関する書類の作成をすべて任せられます。戸籍謄本の取得や申立書の提出といった面倒な手続きも一任できるため、話し合いに集中できるでしょう。
年金分割トラブルに時間を取られ、日常生活に支障をきたしている状況を解消できます。
弁護士に依頼した場合、配偶者と話す必要がなくなります。年金分割トラブルが白熱し、相手と顔も合わせたくないという方もいるでしょう。話し合いの度にストレスを感じることもなくなります。
年金分割後の年金支給額は、妻が専業主婦か共働きかで大きく異なります。計算を誤ると、年金支給額を踏まえた老後の計画を適切に立てられなくなる可能性があります。
弁護士に依頼することで、正確に年金支給額を算出してくれるでしょう。
弁護士に依頼した場合の費用ですが、相談料・着手金・報酬金があり、調停や審判を行う場合はさらに出張費や交通費などもかかります。
弁護士によって大きく異なりますが、それぞれの相場は次のとおりです。
相談料は、1時間5,000~8,000円、40分3,000~5,000円など、時間と費用に差があります。多くの場合は数千円で相談できます。初回のみ30分無料で相談できるという弁護士事務所も多いため、複数の弁護士を訪ねて自分に合った人物を見つけましょう。
着手金の相場は20~30万円程度です。年金分割に関して弁護士に依頼することで、数百万円規模の利益になるケースもあるため、決して高い金額とは言えないでしょう。
弁護士が事務所から離れて依頼に対応した場合には、日当がかかります。
年金分割の話し合いの代理人として配偶者のもとへ出向いたり、調停のために裁判所へ行ったりする場合に発生します。
拘束時間によって変わるため、事前に確認しておきましょう。相場は、半日で3万円、1日で5万円程度です。
報酬金の計算方法は弁護士によって異なります。
50%の分割を求められていたところを30%に抑えられたような場合には、差分の20%の金額に独自の数式を当てはめて報酬額を算出するなどの方法があります。
出張費は1回2万~3万円、交通費は実際にかかった分だけ、という弁護士が多いようです。
出張回数が増えれば、依頼総額が予定よりも大幅に上がることもあるため、調停を依頼する際には注意しましょう。
年金分割は、基本的に拒否できません。ただし、離婚後2年以上が経過すると、年金分割制度を利用できなくなるため、実質のところ年金分割を拒否できます。
多くのケースでは、年金分割について妻が情報を得るため、2年を待たずに請求されてしまうでしょう。
妻をだますようなことをしても、後々トラブルになる可能性があるため、年金分割の割合を抑えることに力を入れることが大切です。
弁護士に年金分割の話し合いの代行や書類の作成を依頼することで、依頼人に有利な条件で話がまとまる可能性があります。
書類の作成代行や調停でのサポートなどさまざまなメリットがあるため、年金分割でお困りの場合は弁護士に相談することをおすすめします。
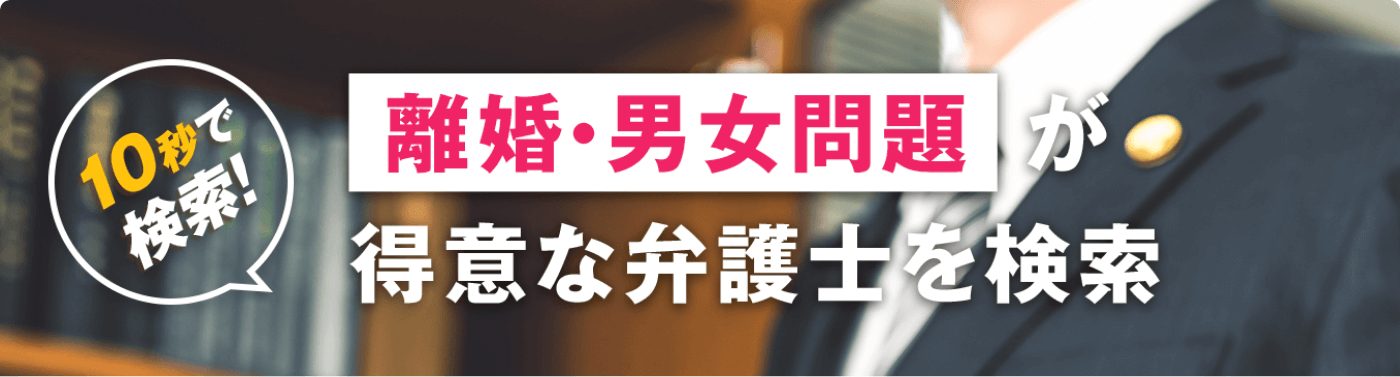

【初回相談無料】ご相談から一貫して同じ弁護士が対応致します。離婚問題に悩まれたら、できるだけお早めにご相談下さい。20年の弁護士歴を活かし、解決に向けたトータルサポート!
事務所詳細を見る
【離婚に特化】【女性の離婚に注力】【銀座駅徒歩3分】親権・養育費等の子育て中の方の相談や熟年離婚の相談等、幅広い女性の悩みに対応。離婚交渉、離婚調停の豊富な経験を持つ女性弁護士が親身にサポートします
事務所詳細を見る
◆「おためし無料相談」<夜間休日もOK>実施中!◆不倫・不貞の慰謝料請求したい/請求された方◆「離婚を決意」した方◆実績豊富な弁護士が、あなたにぴったりの具体的な解決策をアドバイス!【相談実績300件超】
事務所詳細を見る
夫婦が離婚するときは財産分与をおこない、預貯金や不動産などを分け合います。本記事では、離婚時の財産分与で通帳開示する方法や、弁護士に請求依頼するメリットを解説し...
離婚時に財産分与を請求された場合、退職金は原則として財産分与の対象となり得ます。本記事では、離婚時に退職金は財産分与の対象となるのか、離婚時に退職金を取られない...
離婚する際には、お金に関する様々な取り決めが必要になります。そのため、何かトラブルが生じるのではないかと不安に感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では...
離婚時の財産分与の対象に、結婚前の資産は含まれません。しかし、例外的に財産分与の対象となることもあります。財産分与は、夫婦で揉める問題のひとつです。この記事では...
離婚の際、争いの種となりやすいのが財産分与です。 本記事では、離婚前の財産分与について気を付けるべきポイントや、財産分与に関する問題を弁護士に相談するメリット...
自身が専業主婦であることから、離婚する際にしっかりと財産分与を受けられるのか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では、専業主婦が離婚する際におけ...
扶養的財産分与とは、離婚後に元配偶者から生活費を一定期間負担してもらうことです。本記事では、扶養的財産分与の概要、扶養的財産分与が認められやすいケースなどについ...
夫婦が離婚する際には、共有財産について財産分与をおこないます。財産分与の対象となるのは、婚姻中に取得した財産です。本記事では、離婚時の財産分与の対象となる財産の...
財産分与に伴う不動産登記について詳しく解説します。登記をおこなう際の流れやよくある質問についても解説するのでぜひ参考にしてください。
離婚で財産分与をした場合、税金についても注意しなければなりません。本記事では、財産分与をおこなう際に注意したい税金について詳しく解説します。どのようなケースで贈...
離婚手続きを進めていくうえで、財産分与についても考える必要がありますが、財産を分ける際に税金がかかる場合があるということを知っていますか?本記事では、離婚時の財...
熟年離婚の財産分与は、婚姻期間が長いほど高額になる傾向にあり、1,000万円を超える夫婦も少なくありません。財産分与をできるだけ多く受け取り、離婚後も経済的な不...
離婚の際に年金分割を拒否したいという方もいるでしょう。この記事では、年金分割を拒否できるのか解説しています。年金分割をしない場合の手続きについても、あわせて紹介...
財産分与は2年以内に請求しないと時効(除斥期間)が成立し、請求する権利が完全に消滅してしまいます。この記事では、離婚後に財産分与の請求を時効までにするため、財産...
離婚時の財産分与では、結婚前からの貯金や子ども名義の貯金など、貯金の種類によって分け方が異なります。隠し口座がないか不安な方は、弁護士などの力が必要になる場合も...
社長や経営者と離婚すると、多くの場合、生活水準の低下などの事情から後悔する気持ちも出てくるかもしれません。しかし、この記事で紹介する3つの問題を踏まえ、離婚に望...
共有財産(きょうゆうざいさん)とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産のことをいいます。財産の所有名義が一方の配偶者である場合でも、もう一方の貢献があったとみなさ...
本記事では、まず財産分与の基礎知識について説明したあと、財産分与の対象や流れ、注意点など財産分与について知っておくべきことを解説します。
離婚する際の夫婦の財産と損をしない財産分与の方法についてまとめました。
財産分与の放棄は相手方の承諾がなければおこなえません。なぜなら、財産分与請求権は夫婦それぞれの権利だからです。少しでも財産分与の内容を有利にするには、財産調査や...
この記事では、財産分与にかかる手続きなどを依頼した場合の弁護士費用の相場や、弁護士費用を抑えるポイントなどについて解説しています。
財産分与はローンなどの負債についてもおこなわねばなりません。特に不動産に住宅ローンが残っている場合は複雑です。不動産の評価額に対して上回るのか下回るのかを確認し...
持ち家がある夫婦が離婚する場合は、持ち家の名義や住宅ローンをどちらが返済し続けるのかなどを協議しなくてはなりません。ローンの契約者や持ち家の売却価値によっても対...
熟年離婚の財産分与は、婚姻期間が長いほど高額になる傾向にあり、1,000万円を超える夫婦も少なくありません。財産分与をできるだけ多く受け取り、離婚後も経済的な不...
財産分与に伴う不動産登記について詳しく解説します。登記をおこなう際の流れやよくある質問についても解説するのでぜひ参考にしてください。
本記事では、まず財産分与の基礎知識について説明したあと、財産分与の対象や流れ、注意点など財産分与について知っておくべきことを解説します。
離婚するときの財産分与は基本的に夫婦間で取り決めます。相手に主導権を握られると損する可能性があるので、専門家に相談しておくと安心です。ここでは、財産分与の無料相...
財産分与の放棄は相手方の承諾がなければおこなえません。なぜなら、財産分与請求権は夫婦それぞれの権利だからです。少しでも財産分与の内容を有利にするには、財産調査や...
配偶者と離婚する際には、財産分与が対立のポイントになることが多いです。離婚時の財産分与を円滑におこなうためには、弁護士への無料相談をおすすめします。財産分与につ...
共有財産(きょうゆうざいさん)とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産のことをいいます。財産の所有名義が一方の配偶者である場合でも、もう一方の貢献があったとみなさ...
離婚時、婚姻中に夫婦で築いた財産である家も、財産分与の対象です。家を財産分与する際には、家を売る方法もありますが、家を売らない選択肢もあります。本記事では、離婚...
社長や経営者と離婚すると、多くの場合、生活水準の低下などの事情から後悔する気持ちも出てくるかもしれません。しかし、この記事で紹介する3つの問題を踏まえ、離婚に望...