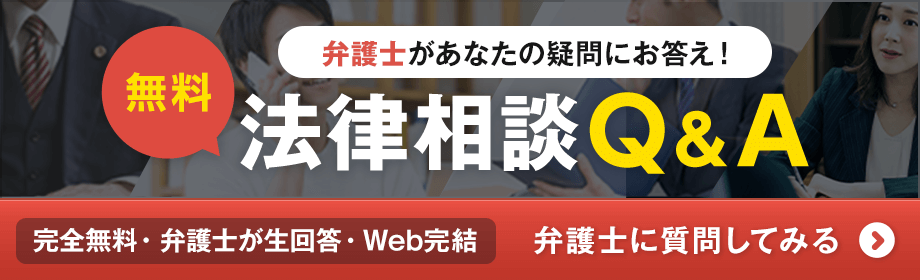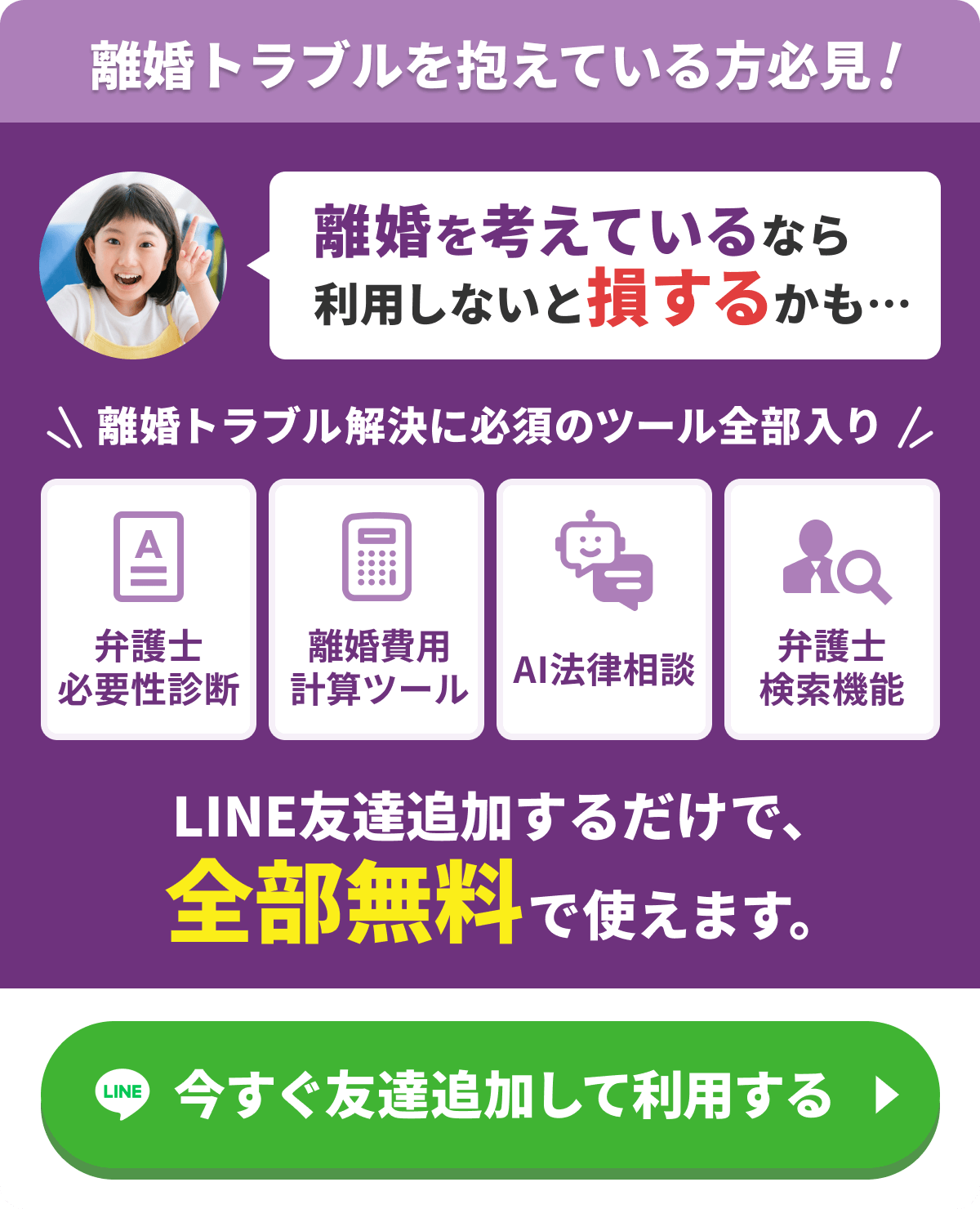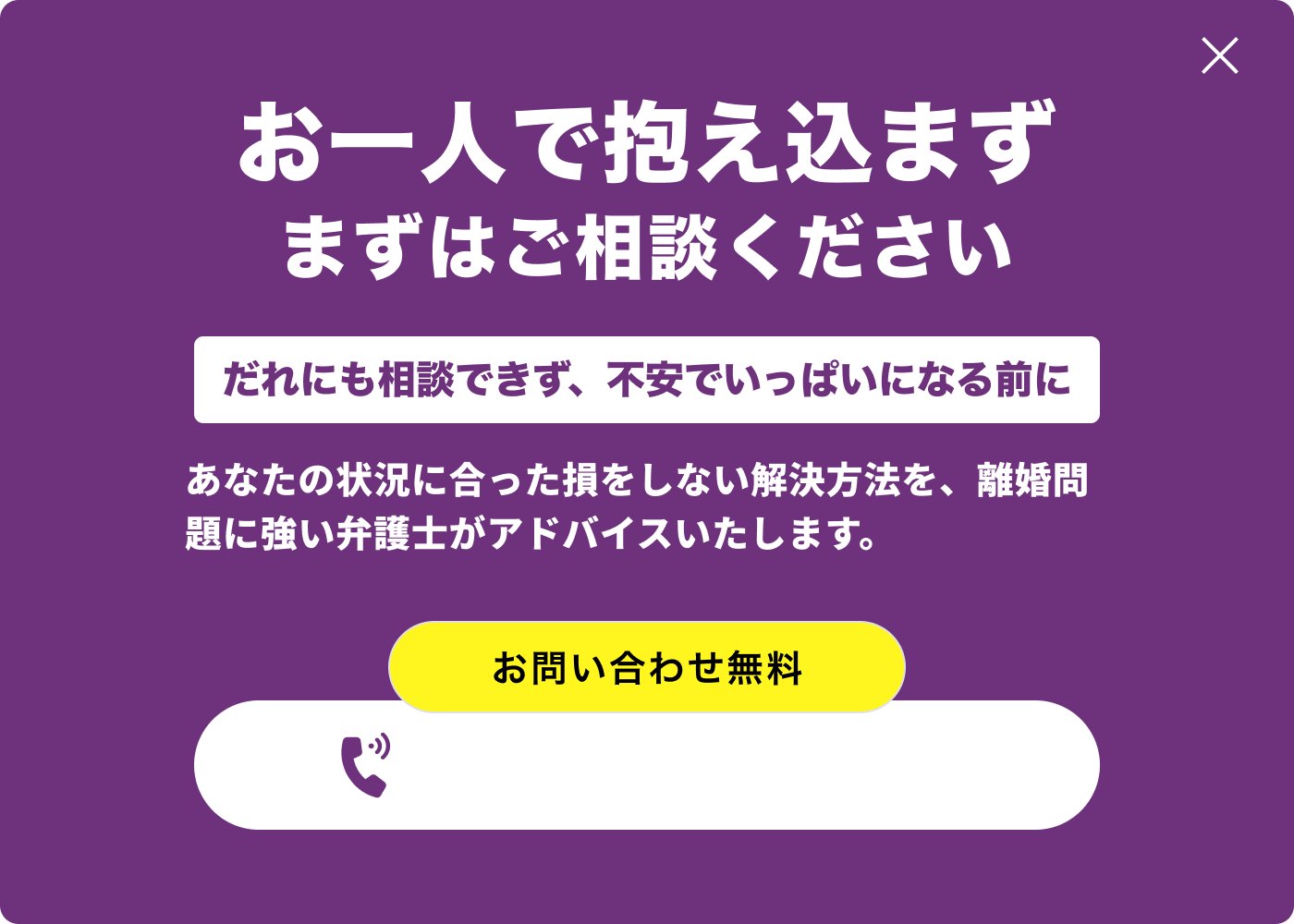母子家庭には国が援助する様々な手当が存在するのをご存知でしょうか。
現在、日本では夫婦の3組に1組は離婚しているといわれており、2021年に厚生労働省から発表された統計によると、全国でシングルマザーは119.5万世帯おり、平均年収は272万円、就業率は86.3%前後となっています。

最近では子連れ離婚も珍しくありませんが、子連れ離婚の不安要素のひとつに金銭的な問題があります。母子家庭の収入は決して高いものではなく、切り詰めた生活を送る必要があります。そこで助けになるのが、母子(父子)家庭を助けてくれる手当や割引制度です。
この記事では少しでもシングルマザーが頼れる支援や手当をみつけられるように、17種類の支援制度をご紹介しますので、うまく活用し収入を増やし支出を減らすための参考にして頂ければ幸いです。
離婚後に旦那から養育費が払われずお困りの方へ
養育費の取り決めをしたのにも関わらず、元旦那から養育費が支払われずに、お困りの方もいらしゃるのではないでしょうか。
未払い養育費問題は、弁護士に依頼をしたら解決するかもしれません。
弁護士に依頼すると下記の様なメリットを受けることができます。
- 弁護士に依頼する事で元旦那にプレッシャーを与える
- 元旦那との交渉の代理
- 回収手続きかかる手間の解消
当サイトでは、養育費の未払い問題について注力している弁護士を地域別で検索することが可能です。
初回相談が無料の事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
この記事に記載の情報は2024年06月07日時点のものです
母子家庭(シングルマザー)が利用できる10の手当と助成金
母子家庭の方は生活上で助成や手当てを有効活用することが重要です。まずは主な手当金、助成金をまとめましたのでお役に経てば幸いです。

1.児童手当
児童手当とは、母子(父子)家庭の子供を対象として支給される助成金ではなく、全ての家庭を対象とした支援策です。
児童手当は、子供がいる家庭の生活の安定に寄与することと、次の社会を担う子供の健やかな成長を支えることを目的に、国から支給されます。
支給対象者
0歳〜15歳の国内に住所がある子供。15歳は中学校卒業の年度末までを意味します。
支給される金額
| 対象年齢 |
支給金額 |
| 0歳〜3歳未満 |
一律15,000円 |
| 3歳〜12歳(小学校卒業) |
第一子/二子:10,000円
第三子以降:15,000円
|
| 中学生 |
一律10,000円 |
※児童手当には所得制限世帯が設けられており、年間の所得が約960万円を越える世帯の子供に対しては、支給金額が5,000円とされています。詳しくは後述します。
支給時期
支給は年間3回行われます。毎年6月(2月〜5月分)、10月(6月〜9月分)、2月(10月〜1月分)という割り振りです。
居住地の市区町村にもよりますが、だいたい支払い月の12日頃に指定した口座に振り込まれます。
児童手当の支給を受ける上での注意点
児童手当の支給条件を満たしているかどうかは、毎年6月1日に判定されます、そのため、毎年居住地の市区町村役所に現況届を提出しなければいけません。詳細は毎年6月に役所から郵送されてくるので、月末までの手続きを忘れずに行うようにしましょう。
また、母子家庭の方が結婚を機に氏名を変更した場合や、転居した場合にも届け出が必要となります。もし転居先が元の居住地の市区町村外であった場合は、転出した日の次の日から数えて15日以内に、必ず転入先で申請を行わなければなりません。
万が一、15日以内に申請が行えなかった場合は、残念ながら遅れた月分の児童手当の支給は行われないので注意が必要です。
児童手当には所得制限がある
児童手当を受給できる条件として世帯の所得制限があり、扶養親族の人数によって所得制限が異なります。詳しくは以下の一覧を参考にしてください。
|
扶養親族などの人数
|
所得額
|
収入の目安金額
|
|
0人
|
630万円
|
約833万円
|
|
1人
|
668万円
|
約876万円
|
|
2人
|
706万円
|
約918万円
|
|
3人
|
744万円
|
960万円
|
|
4人
|
782万円
|
1,002万円
|
|
5人
|
812万円
|
1,040万円
|
※以降ひとり増えるごとに所得額に38万円を加算する
※端末によって右にスライド可能
この条件で該当する扶養親族などの人数は、生計を共にしている子供や親、兄弟などで年間所得が38万円以下の人数と、血縁関係はないものの養育している子供の人数の合計を指します。
もし所得制限額を越えている場合は、子供の人数や年齢には関わらず、子供一人当たりに対して月額5,000円が支給されます。
2.児童扶養手当
 児童扶養手当は、国が支給を行っている制度で母子家庭及び父子家庭を対象としています。母子家庭及び父子家庭になった原因は離婚でも死別でも、理由は問われません。
児童扶養手当は、国が支給を行っている制度で母子家庭及び父子家庭を対象としています。母子家庭及び父子家庭になった原因は離婚でも死別でも、理由は問われません。
支給対象者
母子家庭及び父子家庭の、0歳〜18歳に到達して最初の3月31日までの間の年齢の子供が対象です。
支給される金額
児童手当と同様に扶養人数や所得によって、支給金額が異なるので注意が必要です。支給区分は「全額支給」「一部支給」「不支給」の3区分に分かれています。
全額支給の場合
子供が1人のケース:月額43,160円
子供が2人のケース:加算額10,190円⇒計月額53,350円
子供が3人目以降のケース:1人増えるごとに月額6,110円が加算されます。
一部支給の場合
扶養者の所得などにより全額支給されないケースでは、以下のような計算式が用いられ、金額に幅が生まれます。
一部支給の手当月額計算式:43,150円ー(申請者の所得ー全額支給所得制限限度額)×0.0230559
第2子加算額計算式:10,180円ー(申請者の所得ー全額支給所得制限限度額)×0.0035524
第3子加算額計算式:6,100円ー(申請者の所得ー全額支給所得制限限度額)×0.0021259
※10円未満は四捨五入されます。
子供が1人のケース:月額43,150円~10,180円
子供が2人のケース:月額10,180円~5,100円
子供が3人目以降のケース:1人増えるごとに月額6,100円~3,060円が加算されます。
※一部支給の計算例
- 例1
- 母親の所得が150万円で他に扶養者がおらず、子供が1人のケースでは、「14,530円」削減されます。
計算式:43,150円ー(母の所得額1,500,000円ー所得制限限度額870,000円)×0.0230559
支給金額は28,620円となります。
- 例2
- 母親の所得が180万円で他に扶養者がおらず、子供が2人のケースでは、「12,680円」削減されます。
計算式:43,150円ー(母の所得額1,800,000円ー所得制限限度額1,250,000円)×0.0230559
- 加えて第2子加算額が「1,950円」削減されるため、合計の児童扶養手当支給額は38,700円となります。
- 加算額計算式:10,180円ー(母の所得額1,800,000円ー所得制限限度額1,250,000円)×0.0035524
所得制限の一覧表
児童扶養手当受給に関する所得限度額は以下の表をご参考ください。
|
扶養親族などの人数
|
本人全額支給所得額
|
本人一部支給所得額
|
孤児などの養育者
配偶者・扶養義務者所得額
|
|
0人
|
490,000円
|
1,920,000円
|
2,360,000円
|
|
1人
|
870,000円
|
2,300,000円
|
2,740,000円
|
|
2人
|
1250,000円
|
2,680,000円
|
3,120,000円
|
|
3人
|
1,630,000円
|
3,060,000円
|
3,500,000円
|
|
以降1人増えるごとに
|
380,000円の加算
|
380,000円の加算
|
380,000円の加算
|
※端末によって右にスライド可能
上記の表の活用方法をご説明します。母と子供1人の母子家庭のケースを例とします。このケースでは、扶養親族は1人であるため、1人の列をみます。母親の所得が57万円以下であれば児童扶養手当が全額受け取れるということがわかります。
所得が57万円を越えるものの230万円以下であれば、先に紹介した計算式を用いて一部支給の該当する金額の手当が支給されます。表の右端の274万円は、母親と生計をともにしている者(母親の両親など)に所得があり、その者の所得が274万円を越えていれば児童扶養手当が支給されないという意味になります。
支給時期
支給は年間6回行われます。5月(3,4月分)、7月(5,6月分)、9月(7,8月分)、11月(9,10月分)、1月(11,12月分)、3月(1,2月分)という割り振りです。
居住地の市区町村にもよりますが、だいたい支払い月の10日頃に指定した口座に振り込まれます。受給を継続させたい場合は、毎年8月に児童扶養手当現況届を提出しなくてはなりません。
参考:
児童扶養手当について|厚生労働省
児童扶養手当|新宿区
3.母子家庭の住宅手当

母子家庭の住宅手当とは、母子(父子)家庭で20歳未満の子供を養育しているケースで、家族で居住するための住宅を借りて、月額10,000円を越える家賃を払っている人を対象としている制度です。
この制度は市区町村独自の制度であるため、なかには実施していない市区町村もあるので、あなたの居住地の市区町村では適応されるのかどうか調べる必要があります。
※所得制限があります。
支給対象者
支給条件は市区町村によって異なりますが、主に以下のようなものです。
支給条件
- 母子(父子)家庭で20歳未満の子供を養育している
- 民間アパートに居住し、申請先の住所地に住民票がある
- 申請先の住所地に6ヶ月以上住んでいる
- 扶養義務者の前年度の所得が、児童扶養手当の所得制限限度額に満たない
- 生活保護を受けていない
支給される金額
支給される金額は市区町村によって異なりますが、平均で5,000円〜10,000円が相場です。いかがその一例です。
支給金額
- 東京都国立市:家賃の3分の1の額で月額1万円まで
- 東京都武蔵野市:10,000円
- 千葉県君津市:5,000円が限度
- 神奈川県鎌倉市:家賃から15,000円を控除した額。ただし、9,000円が限度
- 神奈川県海老名市:一律5,000円
4.母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成制度

母子(父子)家庭を対象に、世帯の保護者や子供が病院や診療所で診察を受けた際の健康保険自己負担分を居住する市区町村が助成する制度です。
助成内容は市区町村によって異なるので、居住地の制度を確認しましょう。
支給対象者
母子(父子)家庭で、0歳〜18歳に到達して最初の3月31日までの間の年齢の子供が対象です。
支給金額
保険医療費の自己負担額の一部を市区町村が助成してくれます。
なお、母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成制度には所得制限があり、この額を越えていると制度を利用できません。詳しくは下記の表をご参考ください。
|
扶養親族などの人数
|
母子家庭の母
父子家庭の父の所得
|
孤児の養育者
同居の扶養義務者の所得
|
|
0人
|
192万円
|
236万円
|
|
1人
|
230万円
|
274万円
|
|
2人
|
268万円
|
312万円
|
|
3人以上
|
1人増えるごとに38万円が加算される
|
※端末によって右にスライド可能
5.こども医療費助成

前述した「母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成制度」は、所得制限が有り該当しない家庭もあります。そのような家庭は、こども医療助成が該当するケースがあります。
しかし、こちらの助成では、親に対する医療費助成はないため注意が必要です。
支給対象者
小学校就学前、小学4年生まで、中学卒業までなど市区町村によって対象者が異なります。居住地の役所で確認しましょう。
支給される金額
通院や入院による保険診療で支払った医療費の自己負担分の一部が助成されます。
助成金額や所得制限を定めているかどうかも市区町村の自治体によって異なるので、利用前に居住地の役所で確認しておきましょう。
6. 特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは、国が支給を行っている制度です。20歳未満の子供で後述する条件を満たしていればすべての家庭に支給されます。
所得制限があるため、該当する金額を自身で把握するようにしましょう。
支給対象者
支給には以下のような、精神または身体に障害があるという条件が必要です。
支給条件
- 精神障害があり精神の発達が遅れている
- 日常生活に著しい制限を受けている
- 身体に障害があり、長期にわたる安静が必要な症状がある
- 日常生活に著しい制限を受けている状態にある
※具体的な基準については「特別児童扶養手当(国制度)|東京都福祉保健局」も合わせてご確認ください。
支給される金額
特別児童扶養手当の金額は子供の人数と、障害の度合いによって変わってきます。詳しくは以下の表を参考にしてください。
|
子供の人数
|
等級1級
|
等級2級
|
|
1人
|
52,500円
|
34,970円
|
|
2人
|
105,000円
|
69,940円
|
|
3人
|
157,500円
|
104,910円
|
※端末によって右にスライド可能
等級は以下の条件が該当します。
|
等級1級
|
身体障害者手帳1〜2級・療育手帳A判定程度に該当する児童
|
|
等級2級
|
身体障害者手帳3〜4級・療育手帳B判定程度に該当する児童
|
支給時期
支給は年間3回、毎年8月(4月〜7月分)、12月(8月〜11月分)、4月(12月〜3月分)に振り込まれます。居住地の市区町村にもよりますが、手当が振り込まれるのはだいたい支払い月の11日頃です。受給を継続させたい場合は、毎年8月に児童扶養手当現況届を提出する必要があります。
7. 障害児福祉手当

障害児福祉手当とは、国が支給を行っている制度です。20歳未満の子供で後述する条件を満たしていればすべての家庭に支給されます。
所得制限があるため、該当する金額を自身で把握するようにしましょう。
支給対象者
身体的または精神的な重度の障害があるために日常生活を自力で送ることができず、常時介護を必要とする20歳未満の子供が対象となっています。
支給される金額
支給金額は一律月額で14,480円です。受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の所得が一定金額以上ある場合は、手当が支給されません。
その所得額については以下の表を参考にしてください。
|
扶養親族などの人数
|
本人の所得額
|
配偶者及び扶養義務者の所得
|
|
0人
|
3,604,000円
|
6,287,000円
|
|
1人
|
3,984,000円
|
6,536,000円
|
|
2人
|
4,364,000円
|
6,749,000円
|
※端末によって右にスライド可能
支給時期
支給は年4回。毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が、居住地の市区町村にもよりますが、だいたい支払い月の11日頃に指定した口座に振り込まれるでしょう。受給を継続させたい場合は、毎年8月に児童扶養手当現況届を提出する必要があります。
8. 生活保護
生活保護とは、何らかの理由で生活に困っている人に対して、国が必要な保護をして最低限度の生活を保障しながら、本人が自立することを目的とした制度です。
支給対象者
生活保護の支給を受けるには4つの条件があります。
-
条件1
援助してくれる身内や親類がいない
- 生活保護申請者は、自身で生計を立てるしかなく、かつ親や兄弟3親等以内の親類からも援助を受けられないことが必要です。 生活保護を申し込んだ時点で、申込者の親や兄弟3親等以内の親類に扶養照会という書類が届き、申込者を援助できるかどうか確認が行われます。もし申込者を援助できる場合は、生活保護を受けることができません。
-
条件2
資産を一切持っていない
- 貯金・土地・持ち家・車などの資産を持っているケースでは、その資産を売却しない限り生活保護を受給することはできません。 また車やパソコンなどは資産とみなされることもありますが、一方で用途によっては必要なものとされるため、生活保護を申請する前にケースワーカーに相談するといいでしょう。
-
条件3
やむをえない理由で働けない
- 上記した①と②の条件を満たしており、病気や怪我などでどうしても働けない場合、生活保護を受ける権利があります。
-
条件4
月の収入が最低生活費を下回り、上記①〜③の条件を満たしている
- 上記した3点の条件を満たしており、かつ年金などの収入があっても厚生労働省が定めている最低生活費の基準額を満たしていなければ、その差額分の生活保護を受けることができます。
支給される金額
支給される生活保護の金額には、厚生労働省が定めた支給計算式があります。
この差額が生活保護費として支給されます。
生活保護の中には生活を営む上で必要な8つの経費それぞれに対して必要な費用が扶助されます。
必要な経費
- 生活扶助
- 住宅扶助
- 教育扶助
- 医療扶助
- 介護扶助
- 出産扶助
- 生業扶助
- 葬祭扶助
9. 母子家庭の遺族年金
母子家庭の遺族年金とは、夫もしくは妻が死亡した場合に受取れる年金が遺族年金になります。加入している年金の種類によって受取れる金額が異なります。
支給される金額
死亡した親権者が加入していた年金や、子供の有無とその年令などによって給付内容が変わってきます。また、具体的な支給金額はそれぞれの年金によって異なります。以下の一覧をご参考ください。
❶:遺族基礎年金
780,900円に第1〜2子は1人当たり224,700円を加算。
第3子以降は1人につき74,900円が加算。
■支給対象者
配偶者が死亡しかつ18歳未満の子供または20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子供と同居している家庭が対象となります。
また、支給対象に年間850万円以上の収入または年間655万5,000円以上の所得がないことが必要です。
■支給期間
子供が18歳になるまで。
❷:遺族厚生年金
本人が受け取る予定だった厚生年金のおよそ3/4の金額が支給されます。
■支給対象者
なくなった人によって生計が維持されていた「子のある配偶者(夫は55歳以上)または子」「子のない妻」など
■支給期間
妻が受け取る場合は、妻が死亡するまで。例外的に妻が夫の死亡時30歳未満であったケースでは、夫の死亡または子供が18歳に達するなど、遺族基礎年金の資格を失ってから5年間で停止となる。
❸:寡婦年金
亡くなった本人が国民年金の第1号被保険者として保険料納付を10年以上行っていた場合(平成29年7月31日以前の死亡の場合、25年以上の期間が必要)、亡くなった本人が65歳に受け取る予定だった老齢基礎年金の3/4の金額が受け取れます。
■支給対象者
亡くなった本人と10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた65歳未満の妻
■支給期間
妻が60歳から65歳までの間
❹:死亡一時金
遺族基礎年金を受給できる者がいないケースで、亡くなった本人の国民年金納付期間が一定以上あると、その納付期間に応じて12〜32万円の一時金を受け取れます。
■支給対象者
亡くなった本人と生計を同じくしていた人で、配偶者や子供や両親などが該当する。
■支給期間
死亡一時金であるため、まとめて一度だけ給付されます。
参考:遺族年金ガイド|日本年金機構
10. 児童育成手当
児童育成手当とは、18歳までの児童を扶養する母子家庭が対象で、児童1人につき月額13,500円が支給されます。
各市町村で受給の制限が異なるため、お近くの市役所に問い合わせてみると良いでしょう。
支給対象(東京都の場合)
都内に住所があり、以下のいずれかの状況にある18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している人
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1級・2級程度)
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が生死不明である児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父又は母がDV 保護命令を受けている児童
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに不明
支給額
児童1人につき、月額13,500円
所得制限
保護者の前年の所得が別に定める限度額以上の場合は支給されません。
支給方法
申請のあった翌月から、毎年6月・10月・2月に、その前月までの分が金融機関の本人口座に振り込まれます。
申請先
区市町村の子供担当課など(区市町村によって担当窓口が異なります)
母子家庭(シングルマザー)が利用できる7つの減免と割引手当制度

母子家庭に対しては収入を増やすための手当や助成金だけでなく、支出を減らすための減免と割引制度もあります。安定した生活を送るためにも両制度をうまく活用していきましょう。
1.寡婦控除
寡婦控除(かふこうじょ)とは、死別や離婚によって夫から離れて再婚していない女性が受けられる所得控除です。
該当する条件
一般の寡婦控除
以下の2点の条件のいずれかの条件を満たしている人が寡婦控除を受けることができます。
- 離婚や死別などで夫と離れて単身で生活をしており、かつ生計を同じくする子供がおり、その子供の総所得金額が38万円以下の場合
- 離婚や死別などで夫と離れて単身で生活をしており、かつ合計所得金額が500万円以下の場合
特定の寡婦控除
一般の寡婦控除に該当する人で次の3つの条件全てを満たしている場合は、特定の寡婦控除を受けることができます。
- 離婚や死別などで夫と離れて単身で生活をしている
- 合計所得金額が500万円以下のケース
- 扶養家族が子供のケース
控除金額
| |
所得税
|
住民税
|
|
一般の寡婦控除
|
27万円
|
26万円
|
|
特定の寡婦控除
|
35万円
|
30万円
|
※端末によって右にスライド可能
合計所得について
合計所得とは次の2点の合計金額に、退職所得金額と山林所得金額を足した金額です。
- 事業所得・不動産所得・利子所得・給与所得・総合課税の配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額の1/2の金額
2. 国民健康保険の免除
母子家庭に限らず全ての人が対象となりますが、前年より所得が大幅に減少したケースや病気や怪我などで生活が困難に陥ったケースでは、国民健康保険の免除が用意されています。
免除金額
免除金額は各市区町村の応益割合によって異なるため、以下の表を参考にしつつ各市区町村役所に問い合わせをしましょう。
- 世帯の被保険者の総所得金額が33万円以下のケース
- 世帯の被保険者の総所得金額が33万円から33万円+24万5,000円×世帯主以外の被保険者数以下のケース
- 世帯の被保険者の総所得金額が33万円から33万円+35万円×被保険者週以下のケース
|
市区町村の応益割合
|
①
|
②
|
③
|
|
45%以上55%未満
|
7割減額
|
5割減額
|
2割減額
|
|
35%未満
|
5割減額
|
3割減額
|
なし
|
|
上記以外
|
6割減額
|
4割減額
|
なし
|
※応益割合とは、均等割(扶養家族人数分の保険料)と平等割(一世帯毎に課せられる保険料)の合計が占める割合で、市区町村によって数値が異なります。
※端末によって右にスライド可能
3. 国民年金の免除
所得がない、もしくは少なく年金を収めることが難しいケースでは、国民年金の免除が受けられます。
免除金額
国民年金には4つの免除区分があります。
❶:全額免除
前年所得が以下で計算した金額の範囲内。
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
❷:3/4免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内。
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
❸:半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内。
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
❹:1/4免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内。
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4. 電車やバスの割引制度
児童育成手当を受給しているケースに対して、各自治体が設定している割引制度です。市区町村によって異なりますが、JR通勤定期乗車券は3割引と設定している自治体が多いです。
また、生活保護や児童扶養手当を受けている世帯の中で1人に対して、都営交通(都電・都バス・都営地下鉄・日暮里・舎人ライナー)の全区間の無料乗車券が発行されています。
割引手当の手続き
手続きはそれぞれ該当する世帯に合わせて、所定の窓口で行ってください。また詳しい情報は居住地の役所へお問い合わせください。
5. 粗大ごみの手数料を減免
粗大ごみの手数料免除は、市区町村による制度です。そのため詳しい情報は居住地の市区町村役所へお問い合わせください。減免を採用している自治体で、減免を受けられる条件としているのは以下のような世帯です。
- 児童扶養手当受給家庭
- 特別児童扶養手当受給家庭
- 生活保護世帯
6. 上下水道料金の割引
上水道料金・下水道料金の基本料金等を減免は、市区町村による制度です。そのため詳しい情報は居住地の市区町村役所へお問い合わせください。減免を採用している自治体で、減免を受けられる条件としているのは以下のような世帯です。
7. 保育料の免除や減額
保育料の免除や減額は、4月1日時点の保育所入所児童の年齢と保護者の前年所得額または住民税金額によって決まります。特に、母子(父子)家庭などで所得が低い世帯については保育料が無料や減額になるケースが多いようです。
母子家庭(シングルマザー)の自立支援訓練給付金というものもある
自立支援給付金とは
自立支援給付金は、正式には「自立支援教育訓練給付金」と呼ばれています。この給付金は雇用保険から教育訓練給付を受給できない人が対象となる教育訓練を受講し、修了した際に支給される給付金のことを指します。
この給付金は、厚生労働省が各自治体と協力して作られた制度です。給付金によって母子(父子)家庭の自立支援を促すことを目的としています。
自立支援訓練給付金の支給対象者
20歳未満の子供を扶養している母子(父子)家庭の母又は父で以下の4つの条件を全て満たす人が対象となっています。
- 児童扶養手当を受給している又は同等の所得水準である
- 雇用保険法における教育訓練給付の受給資格がないこと
- 就職経験・スキル・取得資格の状況などを考慮し、適職に就くために教育訓練受講が必要であること
- これまでに同様の訓練給付金を受給していないこと
日本における母子家庭の現状
日本における母子家庭の現状をデータを踏まえて解説します。
下記の図は令和3年時点で厚生労働省が調査した「ひとり親家庭の現状と支援施策の課題について|厚生労働省」から抜粋したものですが、母子家庭世帯の推移は平成5年には79.9万世帯、令和3年には119.5万世帯、約40万件近くも増加していることがわかります。

母子家庭となった理由
母子家庭(シングルマザー)になった一番多い理由は「離婚」で全体の約80%を占めており、次いで約10%の「未婚」、そして約5%の「死別」と続きます。

母子家庭となった方の年齢
母子世帯の母の平均年齢は41.9歳であり、年齢階級別でみると「40~49歳」が50.1%と最も多く、「30~39歳」が27%とこれに次いでいます。末子の平均年齢は11.2歳であり、年齢階級別でみると「15~17歳」が21.6%と最も多く、「12~14歳」が20.2%とこれに次いでいます。

母子家庭の平均収入は272万円
2021年の厚生労働省の発表された統計では、母子家庭の約86%が何らかの形で就労をしています。そして、残りの約14%(不詳含む)のシングルマザーは就労せずして子供と共に暮らしています。
また、母子家庭世帯の平均年収は272万円となっており、平成28年の243万円から30万円ほど増加しています。ただし、国民生活基礎調査による児童のいる世帯の平均所得を100として比較すると、45.9と低い水準であることに違いはありません。

ここで着目すべき点は母子家庭(シングルマザー)の労働収入の低さです。労働収入の低さを招いているのかは、シングルマザーのパート・アルバイト率の高さです。

就労しているシングルマザーの約39%は非正規雇用で働いており、正規雇用は約49%にとどまっています。このような状況もあり、母子家庭向けのサービスが整えられているのです。
つまり、シングルマザーとして生活していくうえで考えるべきことは以下の2点です。
1. 手当と助成金を活用し収入を増やす
2. 減免と割引制度を活用し支出を抑える
児童扶養手当の受給者数は90万人(令和4年末時点)
母子家庭の増加により比例して、児童扶養手当の受給者数も年々増加していましたが、平成24年を境に減少に転換。一時期は100万人を超えていた受給者が、令和4年度末には全部支給者427,287人(53.0%)、一部支給者は378,481人(47.0%)の計805,768人となっています。

養育費は子供を育てる際に、最も頼りにすべきお金。しかし、母子世帯の養育費の受給率は高くなく、令和3年時点で「現在も受けている」が28.1%、「過去に受けたことがある」が14.2%、「受けたことがない」が56.9%となっています。

父子世帯の養育費受給率はさらに低く、令和3年時点で「現在も受けている」が8.7%、「過去に受けたことがある」が4.8%、「受けたことがない」が85.9%となっています。

そもそも養育費に関する取り組みをしていないという、母子・父子世帯も少なくありません。


父子世帯のほうが養育費の受給率が低い要因としては、男女の経済格差が挙げられるでしょう。
【養育費の取り決めをしていない理由ベスト3】
|
順位
|
母子家庭の場合
|
父子家庭の場合
|
|
第1位
|
相手と関わりたくない
|
相手に支払う能力がないと思った
|
|
第2位
|
相手に支払う能力がないと思った
|
相手と関わりたくない
|
|
第3位
|
相手に支払う意思がないと思った
|
自分の収入等で経済的に問題がない
|
参考:養育費について|厚生労働省 子ども家庭局家庭福祉課
離婚した場合は養育費の獲得も行おう
離婚後、親権を持たなかった配偶者にも、未成年の子供に対しては養育義務があります。そのため、民法に定められているように養育費の支払い義務がなくなることはありません。
養育費の支払いは子供に対する最低の義務です。親として子供に自身と同程度の生活を保証することが必要となります。
また、もし養育費を支払う義務のある親が、失業やローンなどで経済的な余裕が無い場合でも、養育費を払わないということは通用しません。経済的困窮の具合によっては、費用の減額はありますが、単に無収入や負債を理由に養育費の支払いを拒否することは認められていません。
養育費に含まれるもの
養育費は、子供を育てる上で必要となる費用であるため、親権者の生活費は含まれないことを注意しておきましょう。以下が子供の養育費に含まれる8つの出費です。
- 衣食住に関わる費用
- 幼稚園・保育園〜高校・大学までの教育費や授業料
- 健康維持や病気を治すための医療費
- 保育園や小学校などの教育機関への通学に必要な交通費
- 習い事などの費用
- 適度な娯楽費
- 毎月の小遣い
- その他自立した社会人として成長する為に必要な費用
この中で比重が高いのが教育費です。どの程度の教育を受けさせるかによって必要な教育費が異なりますが、養育費として請求可能な額は支払う者の学歴水準と同程度とされています。
養育費の支払期限は子供が何歳になるまで請求可能か
養育費の支払期限は、子供が社会人として自立するまでが目安とされていますが明確には決まっていません。そのため支払期限は家庭で異なりますが、だいたいの家庭で大学卒業までとされているのが多いようです。
養育費の相場
養育費の相場は家庭裁判所が定めた「養育費・婚姻費用算定表」という基準表を用いて算出するのが一般的です。
養育費算出は、以下の項目によって用いる表が異なります。
- 子供の人数
- 子供の年齢(0〜14歳・15〜19歳の2区分)
- 養育費を支払う側の年収
- 養育費を受け取る側の年収
- 養育費を支払う側が、給与所得者か自営業者か
以上5つの要素を考慮し、あなたが表の中で該当する金額枠が義務者の負担すべき養育費の標準的な金額といえます。
母子家庭の手当に関するまとめ
今回紹介した17種類の手当・助成金・減免・割引制度の全てを受けられる人は少ないでしょう。しかし、あなたの状況に応じたサービスを受けることで生活の負担が軽くなることは確かです。該当するサービスがあれば、それぞれの担当窓口などに一度問い合わせをしてみることをオススメします。
離婚後に旦那から養育費が払われずお困りの方へ
養育費の取り決めをしたのにも関わらず、元旦那から養育費が支払われずに、お困りの方もいらしゃるのではないでしょうか。
未払い養育費問題は、弁護士に依頼をしたら解決するかもしれません。
弁護士に依頼すると下記の様なメリットを受けることができます。
- 弁護士に依頼する事で元旦那にプレッシャーを与える
- 元旦那との交渉の代理
- 回収手続きかかる手間の解消
当サイトでは、養育費の未払い問題について注力している弁護士を地域別で検索することが可能です。
初回相談無料の事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。