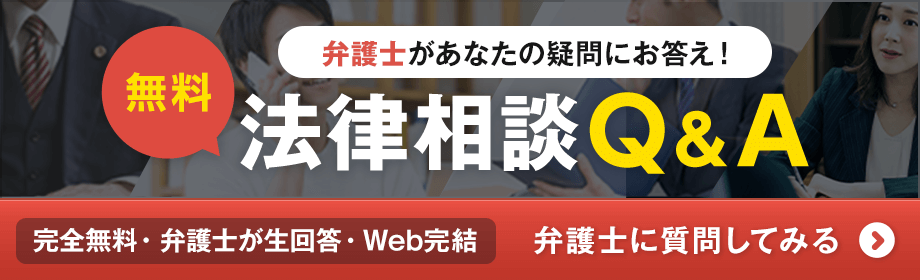「養育費」が得意な弁護士に相談して悩みを解決!
お悩み内容から探す

養育費の支払いは公正証書に残しておくと良いことをご存知でしょうか。その理由は、公正証書の形で合意した場合、裁判手続きを経ることなく配偶者(元)の財産を差し押さえるなど、強制執行に移行することが可能になるためです。
|
【公正証書に残しておくべきその他の内容例】
- 離婚に合意したという事実
- 財産分与について
- 慰謝料について
- 親権者は誰か
- 面会交流について
- 年金分割について
|
養育費とは離婚する時に子供がいた場合、親権者とならない親から親権者となる親に支払われる、子供を育てるために必要な費用です。しかし、実情は養育費の取り決めをして離婚する夫婦は少数であり、養育費を受け取り続けているケースは更に少ないという統計結果がでています。
離婚後に金銭面で子供に不自由をさせないためにも、養育費の支払いについて話し合いをしたら公正証書に残しておくことも検討に値します。また、改正民事執行法が令和2年4月1日に施行。改正民事執行法により上記のような養育費の不払いに悩む家庭の救済の途が広がったとされています。
この記事では、養育費の支払いについて公正証書に残すべき理由に加えて、公正証書の書き方から手続きの流れ、民事執行法改正において公正証書作成から生じる影響についてご紹介します。
養育費についての取り決めを公正証書に残したい方へ
養育費についての取り決めは、公正証書に残しておくのがおすすめです。しかし、実際にどのように公正証書を作るのかわからず、悩んでいませんか?
結論からいうと、養育費に関する公正証書についての問題は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
- 養育費に関する公正証書の書き方について相談できる
- 養育費に関する公正証書の作成にかかる費用がわかる
- 依頼すると、離婚協議書の作成・添削依頼ができる
- 依頼すると、公正証書化の手続きを一任できる
当サイトでは、養育費に関する公正証書についての問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
民事執行法の改正による養育費支払いへの影響
民事執行法の改正により「第三者からの情報手続」という新しい制度が新設されたため、債務者の財産開示手続の実効性が増しています。以前は公正証書で養育費の取り決めを行っているだけでは財産開示手続きを利用することはできませんでしたが、改正後は金銭の支払いを目的とする内容の公正証書でも財産開示手続きを利用することができるようになりました。
また、従前、財産開示に協力しない債務者に対する制裁も過料のみと弱かったものが、裁判所に正当な理由なく出頭しないなどの行為に対し6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになりました。
養育費に関する内容を公正証書に残しておくべきメリット
まず始めに、なぜ養育費に関する取り決めを公正証書に残すべきなのかメリットについて解説します。
合意内容について争われる余地が少ない
公正証書は、各当事者が公証人の前で内容を確認しながら作成するものであるため、後日、合意した内容について争いにくくなります。また、公正証書は公証人が疑義のない明確な文言で作成しますので、文言解釈で後日紛糾するということも少ないといえます。
このように、公正証書は当事者間の合意を確定的なものとする証拠として、信用性の高い資料となり、その後の紛争・トラブルを予防するのに有用と言えます。なお、公正証書化した書類は当事者に交付されますが、仮に当事者が書類を紛失しても、公証役場に原則20年は保管されているので、保管の観点からも安心といえます。
裁判手続を経ないで強制執行ができる
養育費の支払義務が公正証書に記載され、かつ執行受諾文言が付されている場合は、相手が支払いをしない場合に裁判手続きを経ることなく相手の財産を差し押さえるなどの強制執行を行うことができます。
心理的拘束が大きい
上記のとおり、公正証書は後々内容を争いにくく、かつ約束を破れば即強制執行に進んでしまう強力な文書です。そのため、債務者に対する心理的拘束が強く、債務者が約束を守って任意の支払いを継続してくれるということは、期待できそうです。
【関連記事】【令和版】2つの差し押さえ(強制執行)で養育費を回収する基礎知識
養育費の内容を公正証書にするデメリット
養育費に関する取り決めを公正証書に残すことのデメリットについて確認していきましょう。
①作成に費用がかかる
公正証書を作成するには費用が必要です。その費用は、養育費の合計金額によります。金額については以下の表を参考にして下さい。
表:公正証書作成の手数料
|
目的の金額(養育費の合計金額)
|
公正証書作成の手数料
|
|
100万円以下
|
5,000円
|
|
100万円超、200万円以下
|
7,000円
|
|
200万円超、500万円以下
|
11,000円
|
|
500万円超、1,000万円以下
|
17,000円
|
|
1000万円超、3,000万円以下
|
23,000円
|
|
3000万円超、5000万円以下
|
29,000円
|
|
5000万円超、1億円以下
|
43,000円
|
参考:日本公証人連合会
また、自分で作成した場合、費用はかかりませんが弁護士に依頼すると上記の費用とは別に弁護士費用がかかります。
弁護士費用について詳しく知りたい方は「離婚に必要な弁護士費用はいくら?支払う際の3つの注意」をご覧ください。
②作成に相手の協力が必要
公正証書は作成当事者双方が公証役場に出頭して作成する必要があります。そのため、相手の協力が得られない場合には公正証書の作成は不可能です。また、実際に公正証書の作成を依頼するには、公証役場の窓口が開いている平日の9時から17時の間に当事者が揃って出向く必要があり、相手がなかなか時間を作ってくれないということは十分あり得ます。
この点は、公正証書を作成する上での最大のハードルと言えるでしょう。
離婚協議書を公正証書にする手順と書面に記載する内容
離婚に際して、話し合ったことをまとめた離婚協議書を、公正役場に持っていくことで公正証書は完成します。
当事者で離婚条件について取り決める
まずは、離婚する当事者間で離婚の条件を話し合い、これを書面にまとめましょう。
公証役場に行き公正証書にしてもらう|まずは公正役場の公証人と面談を行う
離婚条件が調った場合、自身や相手の近くの公証役場に事前に相談し、公正証書作成のスケジュールを決めましょう。
また、事前に相談するに当たり、当事者間で作成した合意書面を公証人に送付しておけば、その後の処理もスムーズでしょう。
作成当日の手続き
公証人と調整したスケジュールに従い、公証役場に当事者双方が出頭し、公正証書の内容について確認する処理を行います。このとき免許証などの身分証や印鑑など公証人から指定されたものを持参して下さい。なお、手数料は当日に現金で支払う場合が多いようです。
最寄りの公証役場は「日本公証人連合会」から検索できます。
作成費用
|
夫婦で合意を得た養育費や慰謝料の金額
|
手数料
|
|
~100万円
|
5,000円
|
|
~200万円
|
7,000円
|
|
~500万円
|
11,000円
|
|
~1,000万円
|
17,000円
|
|
~3,000万円
|
23,000円
|
|
~5,000万円
|
29,000円
|
離婚協議書に記載する内容
離婚協議書に取り決める内容について特段のルールはありませんが、主に以下の7項目について記載することが多いでしょう。この内容についてまずは夫婦間で話し合いを行いましょう。無論、全てを記載する必要はなく合意がされたものだけ記載するという処理もあり得ます。
- 離婚を合意した旨の記載
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権者(監護権者)の指定
- 養育費
- 面接交渉
- 年金分割
①離婚合意
離婚が合意によるものであることを確認しつつ、離婚届を誰が、いつ、どのように提出するかなどを取決めます。
②慰謝料
夫婦間で不貞行為やDVなど違法な権利侵害行為があった場合にはこの項目を設けることも検討しましょう。
主に記載する内容は、「慰謝料を支払うかどうか」「慰謝料の金額」「支払う日時」「支払い方法」などです。
③財産分与
夫婦で協力して築いた財産を分け合う場合にはこの項目を設けましょう。
主に記載する内容は、「財産分与の対象とする財産」「財産分与として譲り渡す財産のリスト」「財産分与の支払い期日」「支払い方法」などです。
④親権・監護権の指定
夫婦に子供がいる場合は、親権・監護権も記載しましょう。記載する内容は、「子供の名前」「長男・長女など」「夫婦どちらが親権者なのか」などです。
親権は監護権なども含めた、子供を育てていくために必要な管理権限を与えられた者のことです。例えば、子供に対する住居指定・懲戒権、職業許可権・財産管理権等がこれに含まれ、通常は子に対する監護権(子を保護して監督する権限)を含みます。

⑤養育費
夫婦間で養育費のやり取りを行う場合にはこの項目を設けましょう。主に記載する内容は、「養育費を支払うかどうか」「養育費の金額」「支払い期間」「支払い方法」などです。
⑥面会交流
離婚後に親権を持たない親が子供と合う面会を設定する場合は、この項目を設けましょう。
主に記載する内容は、「子供との面会頻度」「面会の日時と面会できる時間」「面会方法の取り決め」などです。
⑦年金分割
離婚後に結婚期間中に支払った保険料を将来分け合う年金分割を利用するのであれば、この項目を設けましょう。
主に記載する内容は、「年金分割をするかどうか」「年金分割の金額」「年金分割の期間」などです。
参考:離婚協議書の書き方とサンプル|離婚後に約束を守らせる方法
公正証書を作成する前の準備|養育費について協議しておくべきこと

養育費の金額
養育費の金額は、養育費を支払う側の生活レベルと同等の生活を子供が送れるだけの金額だとされています。そのため、養育費の相場はあるものの当事者同士で自由に決めることが可能です。
ただし、養育費の支払いは基本的毎月行われるもので、かつ、子供が幼ければ幼いほど長期間にわたります。そして、子供が複数いれば1人あたり月額でいくら支払うのかを決めていかなければなりません。
最初に無理な金額設定をしてしまうと、徐々に支払いが厳しくなる、支払いへの意欲が下がるなどのリスクが生まれます。
養育費算定表に基づいて金額を決めることも
無理な金額で合意させ、支払いが滞るなどのトラブルへと発展することを防ぐために、裁判所などで提示している「養育費の算定表」を元に養育費の金額を決めることも少なくありません。

引用:裁判所
例えば、夫の年収が500万円で妻の年収が100万円とした場合、養育費の目安は以下のようになります。
|
子供の人数
|
年齢(0~14歳)
|
年齢(15~19歳)
|
|
1人
|
4~6万円
|
6~8万円
|
|
2人
|
6~8万円
|
8~10万円
|
養育費の目安は子供の年齢や人数によって養育費算定表を元に算出されます。詳しくは「【令和改定版】養育費算定表と見方をわかりやすく解説」をご確認ください。
養育費の支払い開始時期
離婚する前に養育費の支払い開始時期を決める場合は、「離婚届が受理された月(翌月)の◯月から支払う」などと決めるのが一般的です。一方、すでに離婚している場合は、具体的に「平成◯年◯月から支払う」というように決めると良いでしょう。
養育費の支払い終了時期
養育費の支払い終了時期は、家庭によって異なります。よくあるケースは以下のとおりです。
よくあるケースは
- 高校を卒業するまで
-
20歳まで
- 大学を卒業するまで
|
しかし、「大学卒業まで」としてしまうと、浪人や留年または大学院への進学など想定していたより支払い期間が長くなってしまう可能性があります。
終了時期は具体的な数字で決めるのが良い
後のトラブルを防ぐためにも、養育費の支払い終了時期は具体的な数字で決めておくのがおすすめです。
例えば、
-
大学を卒業する年の3月まで
-
高卒で就職したなら18歳の誕生日以後の最初の3月まで、大学に進学した場合には22歳の誕生日以後の最初の3月まで
|
などにしておくと良いでしょう。
自分で公正証書を作成する際の注意点
公正証書の元となる離婚協議書は自分で作成することが可能ですが、注意しなければならない点もあります。

 引用:社団法人探偵協会
引用:社団法人探偵協会
ひとつ目は、作成にかなりの労力を費やすことです。離婚協議書の作成は決して容易なものではありません。インターネット上で無料テンプレートが簡単にダウンロードできますが、必要な項目を増やし不要な項目を削除するなど、自分用にカスタマイズする必要があります。
ふたつ目は、離婚協議書の精度が高いものかどうか確約できないことです。インターネット上でダウンロードできる無料テンプレの中には、法律の観点に基づいていないものも見受けられます。
費用がかからないのは魅力的ですが、記載漏れなどの不備があった場合、後にトラブルを招いてしまうかもしれません。慎重に作業を進めていくことが大切です。
【関連記事】離婚協議書の書き方とサンプル|離婚後に約束を守らせる方法
弁護士に作成依頼する方法も
自分で離婚協議書の作成することに不安がある方は、弁護士に依頼することをお勧めします。法律に基づいて離婚協議書を作成してくれるだけでなく、公正証書化の手続きもあわせて手配してくれます。
弁護士費用の相場は5~20万円です。離婚協議書の作成または個人で作成した協議書の添削のみであれば費用は安くなり、公正証書への変更手続きや離婚協議の同席なども依頼すると費用は高額になります。
まとめ
離婚協議書の作成は決して難しいものではなく、離婚をする際に話し合うべき内容を書面に残すだけで作成できます。養育費の取り決めを行った場合は、離婚協議書を作成し公正証書化することも検討しましょう。
後のトラブルを極力避けたいと考えるなら弁護士に相談・依頼して公正証書にするのがおすすめです。法律を元にあなたをサポートしてくれるため、心強い存在になるはずです。
※応体制や営業時間は事務所によって異なります
養育費についての取り決めを公正証書に残したい方へ
養育費についての取り決めは、公正証書に残しておくのがおすすめです。しかし、実際にどのように公正証書を作るのかわからず、悩んでいませんか?
結論からいうと、養育費に関する公正証書についての問題は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
- 養育費に関する公正証書の書き方について相談できる
- 養育費に関する公正証書の作成にかかる費用がわかる
- 依頼すると、離婚協議書の作成・添削依頼ができる
- 依頼すると、公正証書化の手続きを一任できる
当サイトでは、養育費に関する公正証書についての問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。