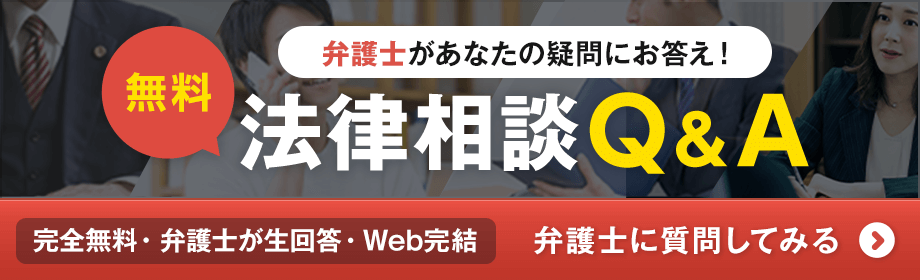「養育費」が得意な弁護士に相談して悩みを解決!
お悩み内容から探す

「離婚後、元配偶者から養育費の減額請求をされている」「現在養育費を支払っているが、生活が厳しいため減額したい」など、離婚してから養育費の減額について争いになることがあります。
養育費を受け取る側が「減額請求には応じたくない」と考えるのは当然でしょう。一方、養育費を支払う側としても、生活の変化によって「少しでも養育費を減らしたい」と考えることもあるはずです。
養育費の減額については条件があり、扶養関係や収入状況などを考慮したうえで、減額が認められることもあります。自分の場合は減額条件に該当するのかどうか、この記事で確認しておきましょう。
養育費の減額が認められるケース・認められないケース、養育費の計算方法や減額請求の流れ、養育費の減額について争う際のポイントなどを解説します。
養育費を減額したいあなたへ
離婚時に取り決めた養育費を減額したい…と悩んでいませんか。
結論からいうと、離婚時に取り決めた養育費は減額できるケースがあります。
しかし、養育費が減額できるかどうかは自分で判断するのが難しいため、自分のケースで養育費の減額が可能かどうか確認するためにもまずは弁護士に相談してみましょう
弁護士に相談することで、以下のようなメリットをえることができます。
- 自分のケースで養育費を減額できるかわかる
- 養育費減額を弁護士に依頼すべきか判断できる
- 依頼すれば、養育費の減額交渉を一任できる
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費問題を得意とする弁護士を多数掲載しています。
無料相談・電話相談など、さまざまな条件であなたのお近くの弁護士を探せるので、ぜひ利用してみてください。
養育費を支払うのは親の義務!支払わない場合はどうなる?
まずは、養育費の概要や、最初に決めたとおりの養育費が支払われない場合、どのような流れになるのか解説します。
養育費とは「子どもが自立するまで支払う費用」のこと
離婚後は、子どもが自立して生活できるようになるまで、養育費が支払われます。ケースによって異なる場合もありますが、子どもが20歳になるまで支払われるのが一般的です。
親権を失った親には、子どもに対して養育費を支払う義務があります。これは民法第877条1項に起因するものです。正当な理由なく、取り決めどおりに養育費が支払われない場合には、裁判所への申し立てなどを経て回収手続きに移行することが可能です。
養育費を支払わない場合は資産などが差し押さえられる
養育費について取り決めたにもかかわらず、減額したいという一方的な理由で合意内容どおりの金額が支払われない場合、最終的に強制執行という手続きに移行できます。強制執行とは、土地・家・家具・給料などの資産を差し押さえる手続きのことです。
裁判所にて強制執行の申し立てが認められれば、養育費の支払義務者に対して、強制的に差し押さえがおこなわれます。給料が差し押さえられた場合には、勤務先から親権者に対して直接支払われるため、養育費を支払っていなかったことが勤務先にも知られることになります。
養育費はどのような場合に減額される?減額が認められるケース・認められないケース
養育費には支払い義務がありますが、正当な理由がある場合には裁判所が減額を認めることもあります。ここでは、養育費の減額が認められるケースや、認められないケースなどを解説します。
養育費の減額が認められるケース
まずは、養育費の減額が認められるケースについて解説します。
受け取る側が再婚して、再婚相手が子どもと養子縁組した場合
養育費を受け取る側が再婚し、再婚相手が子どもと養子縁組を結んだ場合、子どもの扶養義務者が増えることになります。この場合、再婚相手は第一次的な子どもの扶養義務者で、養育費を支払う側である元配偶者は二次的な子どもの扶養義務者です。
元配偶者の扶養義務が軽くなったことで、それを理由に養育費の減額が認められる可能性があります。再婚相手の収入状況などによっては、養育費の支払いが全額免除されることもあります。
支払う側が再婚して扶養家族が増えた場合
養育費を支払う側が再婚し、再婚相手との間に子どもができた場合には、再婚相手や子どもを扶養しなければいけません。再婚によって経済的負担が大きくなったことで、それを理由に養育費の減額が認められる可能性があります。
受け取る側の収入が増えた場合
養育費の金額は、支払う側と受け取る側の収入のバランスによって決まるものです。したがって、離婚後に養育費を受け取る側の収入が大幅に増えて、収入のバランスが変動した場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。
支払う側の収入が減った場合
病気やケガによって仕事ができなくなったり、倒産やリストラによって職を失ったりして、養育費を支払う側の収入が大幅に減った場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。
養育費の減額が認められないケース
次に、養育費の減額が認められないケースについて解説します。
支払う側が自己都合で退職して減収した場合
養育費を支払う側の収入が減ったからといって、必ずしも養育費の減額が認められるわけではありません。
「今よりも大きな会社で働きたい」「自分のやりたいことが見つかった」など、自己都合で退職して減収した場合には、養育費の減額が認められない可能性があります。
減額請求の理由が「子どもに会わせてもらえないから」という場合
離婚する際、「離婚後も、毎月1回は子どもと面会する機会を設ける」などと取り決めても、お互いのスケジュールが合わなかったりして、なかなか会えないこともあります。また、当初の取り決めどおり子どもに会わせてくれないことが続けば、養育費を減額したいと考えるのも無理はありません。
しかし、子どもとの面会交流と養育費は別の問題です。子どもと面会できないことを理由に養育費の減額を求めても、基本的には認められません。
減額請求の理由が「毎月の支払額が一般的な相場よりも高いから」という場合
なかには、養育費の一般的な相場を知らないまま離婚手続きを済ませてしまい、あとになってから毎月の支払額が相場よりも高いことに気付く場合もあります。
しかし、すでに離婚条件について合意したうえで離婚しているわけですので、交渉時に気付かなかった側にも責任があります。毎月の支払額が一般的な相場よりも高いことを理由に養育費の減額を求めても、基本的には認められません。
減額請求の理由が「自分の子どもではないということがわかったから」という場合
法律上、婚姻中の妻が懐胎した子どもは、夫の子どもとして扱われます(民法772条1項)。DNA鑑定などによって、血のつながりがないことが判明しても、それだけを理由に養育費の減額が認められることはありません。
ただし、法律上の手続きによって親子関係が否定されれば、養育費の支払い義務がなくなります。法律上の手続きとしては、「嫡出否認の訴え」や「親子関係不存在確認の訴え」などがあります。できれば嫡出否認の訴えができる期間内に処理をすることが望ましいといえます。
なお、上記の手続きをおこなうには、必要書類を作成したり、裁判所とやり取りをしたりしなければいけません。法律に関する専門知識なども必要になりますので、弁護士に相談することをおすすめします。
養育費は、夫婦の年収・子どもの年齢・子どもの数をもとに計算する
養育費については、「自分の場合はいくらが妥当なのかわからない」という方がほとんどでしょう。養育費の知識がないと、一般的な相場よりも高い金額を支払い続けてしまったり、逆に低い金額しか受け取れなかったりする恐れがあります。
養育費を減額したい、または減額を要求されているなら、養育費の計算方法により正しい養育費を算出してみましょう。現在の収入や生活指標などに則った養育費の額がわかれば、交渉もしやすくなります。
ここでは、養育費を計算するために必要な知識を解説しますので、自分の場合はいくらになりそうか確認してみてください。
養育費は、以下の計算式で求められます。※ただし後婚の場合や連れ後の場合など、他の要素を加味しなければならないケースはあります。
|
子どもの生活費×養育費を支払う側の基礎収入÷(養育費を支払う側の基礎収入+養育費を受け取る側の基礎収入)
|
以下では、各項目の計算方法について、計算例を交えて解説します。
基礎収入の計算方法
基礎収入とは、総収入から税金や特別経費(住居関係費や医療費など)を差し引いた金額のことです。給与収入ごとに基礎収入割合が設定されており、給与所得者と事業所得者ではそれぞれ異なります。
給与所得者の場合
給与所得者の場合、給与収入ごとの基礎収入割合は以下のとおりです。
| 給与収入 |
基礎収入割合 |
| 0~75万円 |
54% |
| ~100万円 |
50% |
| ~125万円 |
46% |
| ~175万円 |
44% |
| ~275万円 |
43% |
| ~525万円 |
42% |
| ~725万円 |
41% |
| ~1,325万円 |
40% |
| ~1,475万円 |
39% |
| ~2,000万円 |
38% |
参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について|裁判所
例えば、「養育費を受け取る側が年収400万円の給与所得者」という場合、基礎収入は以下のとおりです。
事業所得者の場合
事業所得者の場合、事業所得ごとの基礎収入割合は以下のとおりです。
| 事業所得 |
基礎収入割合 |
| 0~66万円 |
61% |
| ~82万円 |
60% |
| ~98万円 |
59% |
| ~256万円 |
58% |
| ~349万円 |
57% |
| ~392万円 |
55% |
| ~563万円 |
54% |
| ~784万円 |
53% |
| ~942万円 |
52% |
| ~1,046万円 |
51% |
| ~1,179万円 |
50% |
| ~1,482万円 |
49% |
| ~1,567万円 |
48% |
参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について|裁判所
例えば、「養育費を支払う側が年収1,000万円の事業所得者」という場合、基礎収入は以下のとおりです。
生活費指数の計算方法
生活費指数とは、親を100と設定した場合、子どもにあてられるべき生活費の割合のことです。養育費の計算で用いる「子どもの生活費」を求めるために必要な項目で、子どもの年齢ごとに以下のように定められています。
| 区分 |
生活費指数 |
|
親
|
100
|
|
0~14歳の子ども
|
62
|
|
15歳以上の子ども
|
85
|
子どもの生活費の計算方法
子どもの生活費は、以下のような計算式で求めます。
|
養育費を支払う側の基礎収入×子どもの生活費指数合計÷(100+子どもの生活費指数合計)
|
例えば、「養育費を支払う側の基礎収入が510万円で、10歳の子どもが1人、15歳の子どもが1人いる」という場合、子どもの生活費は以下のとおりです。
|
510万円×(62+85)÷(100+62+85)=303万5,222円
|
※小数点以下は切り捨てて計算
養育費の計算方法
最後に、以下の計算式で養育費を求めます。
|
子どもの生活費×養育費を支払う側の基礎収入÷(養育費を支払う側の基礎収入+養育費を受け取る側の基礎収入)÷12
|
これまで用いてきた計算例をまとめると、各項目の金額は以下のとおりです。
- 子どもの生活費:303万5,222円
- 養育費を支払う側の基礎収入:510万円
- 養育費を受け取る側の基礎収入:168万円
上記の金額を当てはめた場合、養育費の月額は以下のとおりです。
|
303万5,222円×510万円÷(510万円+168万円)÷12=19万260円
|
※小数点以下は切り捨てて計算
養育費の減額について争う場合はどうすればいい?減額請求の流れを解説
養育費の減額について争う場合は、段階を踏んで手続きを進めていきます。ここでは、減額請求の流れについて解説します。
まずは当事者同士で話し合う
まずは、当事者同士で直接話し合います。これは最も手軽な方法で、話し合いだけで合意が取れれば、裁判所とのやり取りなども不要ですし、特に費用もかかりません。
交渉が成立した際は、合意内容についてまとめた合意書を作成します。合意書を作成しておくことで、のちのち「言った言わない」などのトラブルにならずに済みます。
交渉不成立の場合は養育費減額調停を申し立てる
当事者同士では解決できそうもない場合は、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てます。養育費減額調停とは、養育費を減額すべき特別な事情が発生したときに、調停委員を介して裁判所で話し合う手続きのことです。
養育費減額調停を申し立てる際は、以下のような書類や費用を準備する必要があります。
【養育費減額請求調停の必要書類】
- 養育費調停申立書
- 事情説明書
- 調停に関する進行照会書
- 子供の戸籍謄本
- 申立人の収入関係の資料(源泉徴収票・給料明細・確定申告書等の写しなど)
【養育費減額請求調停にかかる費用】
- 収入印紙:1,200円分(子供1人あたり)
- 郵便切手:800円~1,000円程度(裁判所によって異なる) ※たとえば東京家裁の場合:1,022円
参考:養育費(請求・増額・減額等)調停の申立て|裁判所
養育費減額調停によって両者が納得する結論がでれば調停成立となり、合意内容についてまとめた調停調書が作成されます。
調停不成立の場合は養育費減額審判に移行する
養育費減額調停が不成立になった場合は、養育費減額審判の手続きに移ります。調停不成立になると自動的に移行するため、申し立て手続きなどをおこなう必要はありません。
養育費減額審判では、当事者双方の主張をもとに、裁判官によって養育費の減額を認めるかどうかの判断が下されます。
養育費の減額について争う際は何を注意するべき?有利に進めるための3つのポイント
養育費の減額について争う際、相手に交渉の主導権を握られてしまうと、自分にとって不利な条件で終結してしまう恐れがあります。できるだけ有利に交渉を進めるためにも、以下で解説するポイントを押さえておきましょう。
養育費の相場を把握しておく
養育費の相場を把握しておかないと、一般的な相場とかけ離れた金額を主張してしまって交渉が難航したり、自分の主張を認めてもらえなかったりする恐れがあります。
スムーズに問題を解決するためにも、あらかじめ養育費を計算して、いくらであれば妥当なのかを把握しておきましょう。自分で正しく計算できるか不安な方は、弁護士に相談することをおすすめします。
自分の主張を裏付ける証拠を準備しておく
調停などで自分の意見を主張する際、何の証拠もなければ、調停委員などに「説得力に欠ける」と判断されてしまいます。自分の意見を認めてもらうためにも、少しでも多くの証拠を集めることが大切です。
例えば、離婚後に収入状況が変動したことで、養育費の減額について争っている場合には、預金通帳の写し・給与明細書・課税証明書・源泉徴収票などが証拠になります。
自力での対応が難しい場合は弁護士に相談する
弁護士は、法律面から養育費トラブルの解決をサポートしてくれます。自力での対応に限界を感じた場合は、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
当社では『ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)』というポータルサイトを運営しており、養育費問題に注力している弁護士を地域ごとに検索可能です。無料相談可能な事務所もありますので、お気軽にご利用ください。
【関連記事】離婚問題を弁護士に無料相談できる窓口|相談すべきケースやタイミング、選び方を解説
養育費の減額に関する疑問や不安は弁護士に相談!弁護士にサポートしてもらう3つのメリット
養育費の減額について疑問や不安がある場合は、弁護士に相談することで大きなメリットが望めます。ここでは、弁護士に相談するメリットについて解説します。
養育費の減額条件を満たしているかどうかをアドバイスしてくれる
養育費の減額条件を満たしているのかどうかを判断するためには、十分な法律知識が必要です。法令や裁判事例などに触れたことのない素人では、正確に判断するのは難しいものです。
弁護士に相談すれば、法的視点から的確なアドバイスが望めます。養育費の減額条件だけでなく、減額請求の進め方や養育費の適正額なども教えてくれますので、何かわからないことがあれば相談してみましょう。
法律知識やノウハウを用いて対応してもらうことで早期解決が望める
お互いの主張が真っ向から対立している場合、養育費減額審判にまでもつれ込んで、問題解決が長引くことも考えられます。調停や審判となると、書類準備や裁判所とのやり取りなどに手間もかかります。
弁護士には、養育費の減額請求に関するやり取りを一任することが可能です。弁護士に対応を代わってもらうことで、調停や審判などの煩雑な手続きに時間を取られずに済みますし、交渉のノウハウを知っている弁護士であれば、調停や審判に至る前に解決する可能性もあります。
元配偶者と直接連絡を取る必要がなくなるため精神的負担が軽くなる
なかには、「元夫・元妻とは、なるべく関わりたくない」という方もいるでしょう。そのような方が、元配偶者と連絡を取ったり、交渉対応をしたりすれば、大きなストレスを感じてしまいます。
弁護士に依頼すれば、弁護士が窓口になって代わりに対応してくれます。依頼後は、元配偶者と直接連絡を取らずに済みますので、精神的負担も大きく軽減します。
最後に|養育費トラブルについて無料相談可能な法律事務所もあります
離婚後に扶養関係や収入状況などが大きく変わった場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。養育費の減額について争う際は、まずは当事者同士で交渉し、交渉不成立の場合は調停に移行し、調停不成立の場合は審判に移行するという流れが一般的です。
自分にとって少しでも有利に話を進めたい場合は、弁護士に相談しましょう。弁護士に相談することで、そもそも養育費の減額条件を満たしているかどうかが明確になりますし、養育費の適正額もわかります。
また、養育費の減額請求に関するやり取りを一任することもでき、依頼者にとって心強い味方になってくれます。弁護士事務所の中には初回相談無料のところもありますので、まずは一度相談してみましょう。
養育費を減額したいあなたへ
離婚時に取り決めた養育費を減額したい…と悩んでいませんか。
結論からいうと、離婚時に取り決めた養育費は減額できるケースがあります。
しかし、養育費が減額できるかどうかは自分で判断するのが難しいため、自分のケースで養育費の減額が可能かどうか確認するためにもまずは弁護士に相談してみましょう
弁護士に相談することで、以下のようなメリットをえることができます。
- 自分のケースで養育費を減額できるかわかる
- 養育費減額を弁護士に依頼すべきか判断できる
- 依頼すれば、養育費の減額交渉を一任できる
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費問題を得意とする弁護士を多数掲載しています。
無料相談・電話相談など、さまざまな条件であなたのお近くの弁護士を探せるので、ぜひ利用してみてください。