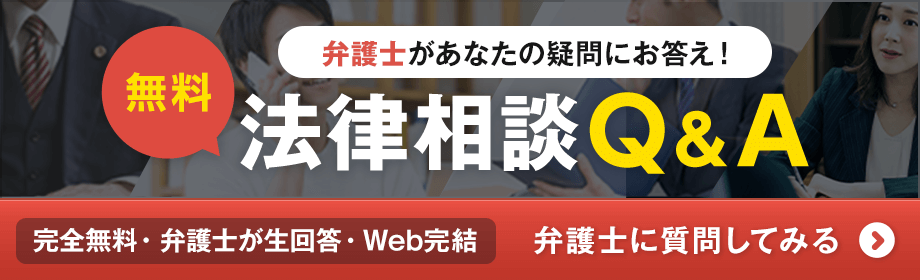ひとり親(母子)家庭が医療費免除(助成)を受けるための所得条件と申請方法


母子家庭の医療費は『ひとり親家庭等医療費助成制度』を受けることで全額負担してもらえる可能性があります。
医療費を全額負担してもらえたら、生活が少しは楽になりますし、安心して病院に行けますよね。実際に母子家庭における保険医療費は以下のような割合を占めています。

(参考:平成26年全国消費実態調査|総務統計局)
この1万7,713円のなかには家事用品・被服費も含まれておりますので、6,000円前後が毎月かかる保険医療費として考えられます。
毎月6,000円の出費を抑えられれば、その分貯金や子供の教育費などに充てることができます。この記事では、「ひとり親家庭等医療費助成制度でどのくらい助成してくれるの?」「受けられる条件はあるの?」などといった疑問について解説します。
また、申請方法や受けられなかった場合に検討をおすすめする類似制度も紹介します。
ひとり親家庭等医療費助成制度とは

ここでは、母子家庭の医療費を負担してくれる、ひとり親家庭等医療費助成制度で助成される金額・対象者・助成対象の医療費などについて紹介します。
ひとり親家庭等医療費助成制度で助成される金額
ひとり親家庭等医療費助成制度は住民税を課税されているかどうかで全額負担か1割負担か変わります。住民税非課税の人は全額負担になります。
住民税課税者は、医療費に対し1割は自己負担になります。ただし、自己負担額に上限が決められていますので、上回った部分は役場に申請することで返金してもらえます。
上限金額は、個人で月1万2,000円(外来)また世帯で月4万4,400円(外来)になっています。
助成の対象になる・ならない医療費
対象になる医療費
助成の対象になる医療費とは、医療保険の対象になる以下のようなものです。
- 身体の不調に関する診療費
- 処方された薬代
- 処置・手術などの治療費
- 治療材料(コルセット・包帯など)の費用
入院も対象になりますが、月額の上限が決まっている場合があります。また、差額ベッド代については全額自己負担です。
対象にならない医療費
助成の対象にならない医療費は以下のようなものになります。
- 医療保険の対象にならない医療行為の費用:美容整形・マッサージ・健康診断・予防接種・中絶や不妊治療など日常に支障がないものの治療
- 学校の管理下でけがをして『災害救済給付制度』の対象になる医療費:給付金でから支払い、負担します。足りない部分は自己負担
- 高額療養費・附加給付に当たる医療費
他の制度と二重に助成してもらうことはできません。もししてしまった場合は、不正受給となるので注意してください。
助成の対象になる人・ならない人
対象になる人
母子(父子)家庭で18歳未満の子供がおり、所得が限度額を満たしていない人が助成の対象になります。ひとり親家庭になった経緯は関係ないので、離婚・死別は問いません。
子供に障害がある場合、自治体によっては20歳未満まで対象になりますが、対象者の範囲が変わることもあるため、各市区町村のホームページで確認しましょう。
東京都あきる野市では、両親が揃っていても所得が低くどちらかに重度の障害がある場合は助成対象です(詳細:ひとり親家庭等医療費助成制度|あきる野市)。
対象にならない人
対象にならない人は以下の通りです。
- 母子(父子)家庭でも所得が限度額以上ある人
- 生活保護を受けている人
- 施設や刑務所などに入所している人
生活保護を受けている場合、医療扶助があり医療費が無料になるので、併用することはできません。
母子家庭の医療費が控除される所得の限度額はいくら?

ひとり親家庭等医療費助成制度を受ける上で重要な条件の1つである所得限度額はいくらなのでしょうか。ここでは、所得の限度額について紹介します。
所得の限度額
所得の限度額は市区町村によって変わってきます。新宿区では、以下のように定められています。
|
子供の人数 |
ひとり親の所得額 |
|
1人 |
230万円 |
|
2人 |
268万円 |
|
3人 |
306万円 |
|
4人以上 |
1人増えるごとに38万円の加算 |
(参考:ひとり親医療費助成|新宿区)
所得額とは
所得額は年間収入から給与所得控除・必要経費と次に紹介する控除額を差し引いた金額になります。また、元配偶者から受け取っている養育費は、年間合計金額の80%を所得として考えます。
所得から差し引く控除額
以下のようなものを所得から差し引きます。ここで紹介する控除額も市区町村によって変化しますので注意してください。
- 一律所得(社会保険料相当):8万円
- 障害者・勤労学生・障害者扶養控除:27万円
- 雑損・医療費など:課税したときに実際に控除された金額
母子家庭では以上のようなものが控除の対象になります。自身で計算するのが難しい場合は市区町村役場に相談してみてください。
ひとり親家庭等医療費助成制度の申請方法

自身が対象に当てはまったなら、市区町村窓口で申請を行いましょう。ここでは申請方法について紹介します。
申請に必要なもの
申請する際は主に以下のものが必要になります。
- 申請者と児童の戸籍謄本(1ヶ月以内のもの)
- 申請者と児童の健康保険証
- 現在の年度の住民税課税(非課税)証明書:前年度の所得・控除・扶養の内容が記載されているものが必要です。
- 申請者の身元が確認できるもの
- 障害認定診断書(親もしくは児童が障害を抱えている場合に限る)
- 児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給している場合に限る)
状況によっては上記以外の書類も求められることがあります。申請前に市区町村役場に連絡し、確認しておくと書類不足になる心配がありません。
申請から利用開始までの期間
申請し助成が認められたら、市区町村役場から『ひとり親医療証(マル親)』が送られてきます。
申請から1ヶ月~数ヶ月かかってしまうこともありますので、1ヶ月を過ぎて何も連絡がない場合は市区町村役場に相談することをおすすめします。
ひとり親医療証が届くまでの医療費は、後日返金される可能性がありますので、領収書はしっかりとっておきましょう。
申請が認められなかったら?
申請しても認められないということもあります。そのような場合は、窓口になぜ受けられないのかをしっかり説明してもらいましょう。もし、受けられない場合は『小児医療費助成制度』が利用できるか確認することをおすすめします。
小児医療費助成制度とは
小児医療費助成制度は、15歳未満の児童が健康保険を利用して受けた医療行為の医療費を助成する制度です。親の分は助成されませんが、ひとり親家庭等医療費助成制度よりも対象が多くなりますので、受けられる可能性が高いでしょう。
助成を受ける方法

ひとり親医療証が手元に届いた後に病院にかかる際どのように助成を受ければよいのか紹介します。
申請した市区町村内の医療機関を受ける場合
助成対象になる医療行為を申請した市区町村内の医療機関で受ける場合は、健康保険証と一緒に『ひとり親医療証』を提示することで助成を受けられます。
申請した市区町村以外の医療機関を利用した場合
申請した市区町村以外の医療機関で対象になる医療行為を受けた場合は、いったん窓口で費用を支払い、その後に市区町村役場で医療費助成の申請を行いましょう。
申請の際は以下のようなものが必要になります。
- 医療証に記載されている保護者名義の金融機関の口座番号がわかるもの。
- 医療機関の発行する保険点数と受診した人の名前が記入されている領収書(コピー不可)。
- 印鑑(認め印可)
助成適用外(高額療養費)の医療を受ける場合
治療や入院が長引くなど、医療費が高額になってしまう場合は、ひとり親家庭等医療費助成制度ではなく『高度療養制度』が利用できる可能性があります。
高度療養制度は、所得や年齢に応じて決められた上限額を1ヶ月の医療費が超えた場合、超えた部分の費用を支給してもらうことができる制度です。受ける際は、加入している健康保険先までご相談ください。
ひとり親家庭等医療費助成制度が受けられなくなるケース
生活環境の変化に伴い、助成を受け続けられなくなることがあります。以下のような場合、助成を受け続けることはできませんので注意してください。
- 生活保護を受けた
- 市区町村を転出した
- 子供の年齢が18歳に達した
- 所得が制限額を超えた
- 再婚または同棲などによる事実婚をした(父親が家に戻った場合も含める)
- 児童が施設や里親に預けられた
- 申請者または児童が死亡した
資格がなくなったにもかかわらず、ひとり親医療証を利用して医療を受けた場合は、後日返金が求められるので注意しましょう。
まとめ
この記事で紹介したひとり親家庭等医療費助成制度などの制度を上手に利用することで、家計にかかる負担を軽くすることができます。
このほかにも、児童扶養手当など母子家庭を支える制度がありますので、市区町村役場などで説明を受けることをおすすめします。


【初回相談料60分5500円】ご自身又はお相手が経営者・不動産を多数所有している方など複雑な財産分与も◎◆経験豊富な弁護士がご満足のいく解決を目指します◆別居・不倫など幅広い離婚問題に対応◎【茅場町・日本橋駅から徒歩5分・東京証券取引所前】
事務所詳細を見る
●夜間・休日対応●夫婦カウンセラー資格有●キッズルーム有●【30代・40代の離婚案件の実績豊富】離婚する決意をした方、財産分与で揉めている方、不倫の慰謝料請求を検討している方などぜひご相談ください。
事務所詳細を見る
【弁護士歴25年】離婚案件を多く経験した弁護士が、培ったノウハウを活かして交渉に挑みます。面談にて、依頼者様のお気持ちを伺った上でどうサポートできるか全力で考えますので、まずは面談にいらしてください。
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

離婚後の生活に関する新着コラム
-
離婚すると、本籍地はどこになるのかが気になりませんか?本記事では、離婚後に本籍はどこになるのかやケース別に新たな戸籍を作る必要性や影響について解説します。当記事...
-
別居中に恋愛をしたい場合、どのようなことが問題になるか気になる方は少なくないでしょう。現在の夫婦関係や状況によっては、恋愛をすることで訴えられたり慰謝料を請求さ...
-
離婚を検討しているなかで、母親が親権をもつ場合に子どもの苗字を変えたくないと思っている方は少なくないでしょう。本記事では、離婚時に子どもの苗字を変えない場合は戸...
-
面会交流権とは、離婚に伴い、離れて暮らすことになった親と子が交流する権利のことです。定期的な面会交流は、子どもの健やかな成長にもつながります。この記事では、離婚...
-
離婚した後、子どもの苗字だけそのままにできるかが気になりませんか?本記事では、離婚すると子どもの苗字はどうなるのかや苗字を変えるための方法、苗字をそのままにする...
-
離婚をするには、どのような流れで進めればいいか気になりませんか?本記事では、離婚するための具体的な方法や流れ、注意点などを解説します。離婚に関する疑問や不安をな...
-
離婚後に再婚した際、戸籍謄本に離婚歴が載る場合と載らない場合があります。再婚相手に離婚歴や元配偶者の名前を知られたくない方に向けて、本記事では再婚後の戸籍謄本が...
-
専業主婦が離婚した場合、国民健康保険は自分で納める必要があります。 本記事では、専業主婦が離婚した場合の国民健康保険について、支払金額の目安や減額する方法など...
-
夫との離婚を検討しているものの、自身がパート主婦であるため、その後の生活に不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。本記事では、離婚後の生活費や配偶者に請求...
-
離婚に伴い発生する手続きのひとつが、健康保険の切り替えです。手続きを忘れてしまうと、医療費が自己負担になることもあります。本記事では、離婚後の健康保険について、...
離婚後の生活に関する人気コラム
-
【母子家庭(シングルマザー)の手当て・支援制度を完全解説!】母子家庭の場合、1人で子供を抱えて生きていくのは大変です。実感も頼れない場合、母子家庭の方が貰える手...
-
両親が離婚をしたという事実は、子供にどのような影響を与えてしまうのか、15個の項目をご紹介するとともに、どうすれば離婚が子供へ与える影響を最小限にできるのかご紹...
-
この記事では、だれでもできる児童扶養手当の計算方法から2018年に改正された所得制限限度額や控除対象など、児童扶養手当の計算に関するすべてを解説します。また、モ...
-
母子家庭の医療費は『ひとり親家庭等医療費助成制度』を受けることで全額負担をしてもらえる可能性があります。この記事では、『ひとり親家庭等医療費助成制度』の基礎知識...
-
母子家庭になったが、持病や子供の障害など働けない事情により生活に困っている場合生活保護を受けることをおすすめします。離婚のせいで子供に貧しい思いをさせたくないで...
-
離婚後はやらなければならない手続きが盛りだくさんです。できるだけ早く新しい生活を始めるためにも離婚後の手続きは確実&効率的に行うことが大切です。本記事では離婚...
-
育児休業給付金とは、育児休業を取得する父母に対する休業中の給付金です。受給条件を満たしていれば、月給の50%前後を受け取ることができます。この記事では、育児休業...
-
離婚したら、何をすれば良いか悩むこともあるかと思います。子供のことや今後の生活のこと、新しい住居や仕事のことなど、そういった不安要素を取り除く手段をご紹介します...
-
2010年、始まった当初は「子ども手当」と呼ばれていましたが、2012年から「児童手当」となりました。この記事では、東京などの支給日や支給が確認できなかった場合...
-
母子家庭の心強い味方である生活保護と児童扶養手当は全く別物になります。そのため、生活保護を受けながら児童扶養手当も受け取ることが可能です。この記事では、生活保護...
離婚後の生活の関連コラム
-
離婚を検討しているなかで、母親が親権をもつ場合に子どもの苗字を変えたくないと思っている方は少なくないでしょう。本記事では、離婚時に子どもの苗字を変えない場合は戸...
-
離婚後に再婚した際、戸籍謄本に離婚歴が載る場合と載らない場合があります。再婚相手に離婚歴や元配偶者の名前を知られたくない方に向けて、本記事では再婚後の戸籍謄本が...
-
離婚に伴い発生する手続きのひとつが、健康保険の切り替えです。手続きを忘れてしまうと、医療費が自己負担になることもあります。本記事では、離婚後の健康保険について、...
-
母子家庭の医療費は『ひとり親家庭等医療費助成制度』を受けることで全額負担をしてもらえる可能性があります。この記事では、『ひとり親家庭等医療費助成制度』の基礎知識...
-
大阪で浮気調査を行いたい方へ大阪の探偵事務所を紹介します。探偵事務所ごとの特徴・料金をまとめているので、大阪で探偵事務所を探している方はぜひ参考にしてください。
-
一度愛し合った人との離婚は踏みとどまる人が多いのも当然でしょう。今回は、離婚のメリットとデメリットを整理していきます。あなたが今後の生活を考えていく上で参考にし...
-
育児休業給付金とは、育児休業を取得する父母に対する休業中の給付金です。受給条件を満たしていれば、月給の50%前後を受け取ることができます。この記事では、育児休業...
-
両親が離婚をしたという事実は、子供にどのような影響を与えてしまうのか、15個の項目をご紹介するとともに、どうすれば離婚が子供へ与える影響を最小限にできるのかご紹...
-
2010年、始まった当初は「子ども手当」と呼ばれていましたが、2012年から「児童手当」となりました。この記事では、東京などの支給日や支給が確認できなかった場合...
-
離婚を検討しているものの、経済的に余裕がないため住まい探しに頭を悩ませている方もいるのではないでしょうか。本記事では、お金のない方が離婚後に住むところを見つける...
-
面会交流権とは、離婚に伴い、離れて暮らすことになった親と子が交流する権利のことです。定期的な面会交流は、子どもの健やかな成長にもつながります。この記事では、離婚...
-
離婚後の戸籍と氏は変更する必要があります。引き続き婚姻期間中の氏を使用する際も手続きが必要です。
離婚後の生活コラム一覧へ戻る