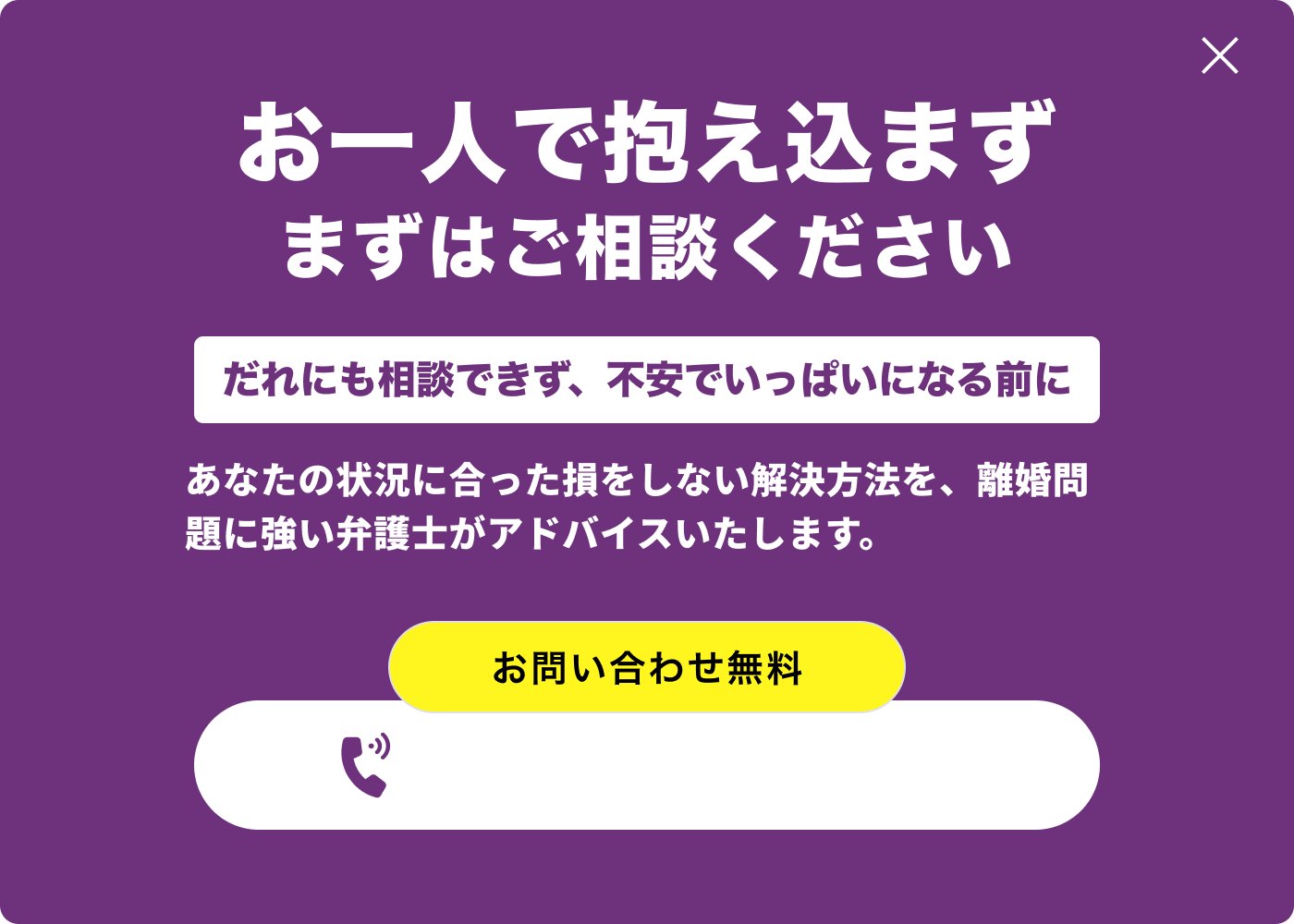離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える

離婚で財産分与をした場合、税金についても注意しなければなりません。
ケース次第ではあるものの、財産分与した側・された側ともに税金が発生したり、確定申告が必要となったりしますが、ルールは複雑で理解するのに時間がかかってしまいますよね。
本記事では、財産分与をおこなう際に注意したい税金について詳しく解説します。
どのようなケースで贈与税や譲渡取得税がかかってしまうかや、確定申告をする際の注意ポイントについても説明するので、ぜひ参考にしてください。
原則として財産分与をおこなったとしても確定申告をする必要はありません。
財産分与とは婚姻中に2人で築いた財産を分け合うための手続きであり、財産を分け与えられたとしても一般的には税金がかからないためです。
ただし、あくまで原則としてであり、中には税金がかかったり確定申告が必要になったりするケースも存在します。
財産分与をおこなうことで課税される税金には以下に挙げた4つがあります。
どのような場合に課税されてしまうかとあわせて解説します。
離婚をして相手から財産を受け取ったとしても、基本的に贈与税の課税はありません。
しかし、以下のケースに当てはまる場合には、贈与税がかかります。
財産の額が多すぎて贈与税がかかる場合には、財産全体ではなく多すぎた部分にのみ課税されます。
一方で、贈与税や相続税を逃れるために離婚をおこなったと判断された場合、贈与された財産全体に課税されます。
不動産取得税は不動産の所有権を獲得した際に課せられる税金です。
財産分与で不動産を取得したとしても、不動産取得税の課税は一般的にはありません。
ただし、以下のケースにおいては課税されます。
登録免許税とは財産分与にあたって新たに不動産の所有者となる人がいて、不動産の名義変更・登記申請をおこなう際に必要となる税金です。
登録免許税は不動産の固定資産評価額の2%発生します。
原則では資産を分与した側と資産を受け取った側が共同で税金を納めるよう定められていますが、どちらかがまとめて納付することも可能です。
のちにトラブルとならないよう、どちらが負担するか話し合っておくことをおすすめします。
譲渡取得税とは、財産分与によって不動産や株式などの資産を与えた際に、資産の取得時より価値が向上した場合に分与する側にかかる税金です。
譲渡取得税の税率は不動産の保有期間によってことなりますが、長期譲渡取得(保有期間が5年以上)であれば15%(住民税も5%かかります)の課税となります。
財産分与をした際に課税される可能性のある贈与税と譲渡取得税について、それぞれの申告手続きの方法を解説します。
贈与税の申告が必要な場合、以下の流れに沿って手続きをする必要があります。
まずは、贈与税の申告に必要な書類を集める必要があります。
贈与税の申告には以下の書類が必要になります。
【贈与税の申告をする際の必要書類】
続いて贈与税の申告書を作成します。
贈与税の申告書のフォーマットは、税務署・国税局のWebサイトからダウンロードできるほか、e-Taxを利用して提出することができます。
贈与税の申告書は、申告の内容によって選択する必要があります。
【第一表(兼贈与税の額の計算明細書)】
第一表は、贈与税の申告をする際に必ず必要になる書類です。
第一表には暦年課税の贈与財産の明細を中心に、受贈者・贈与者の情報、暦年課税分・相続時清算課税分の税額や納税額の記入をおこないます。
最後に申告書などの提出をおこないます。
申告書の提出は、原則として財産を受け取った人が受け取った年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告をする必要があります。
提出方法には、郵送での送付や税務署の時間外収受箱への投函や、e-Taxからの提出などがあります。
続いて譲渡取得税の確定申告をする際の流れを解説します。
確定申告の流れは、以下のとおりです。
譲渡取得税の申告には、以下の書類が必要となります。
【譲渡所得税の確定申告をする際の必要書類】
続いて所得税の確定申告書を作成します。
確定申告書のフォーマットは、税務署・国税局のWebサイトからダウンロードできるほか、e-Taxを利用して提出することができます。
最後に確定申告書などの提出をおこないます。
確定申告書の提出は、資産を譲渡した年の翌年2月16日から3月15日までの間に申告をする必要があります。
提出方法には、税務署への郵送や提出もしくは、e-Taxがあります。
財産分与に伴う税金や確定申告に悩んだら、以下の窓口を利用して相談するようにしましょう。
税務署では納税に関する相談を受け付けています。
なかでも具体的に書類等の確認を交えながら進める必要がある場合は、面接による相談に対応してもらえます。
ただし、面接相談を利用する場合は事前の予約が必要となるため、あらかじめ確認しておきましょう。
日本各地に設置されている税理士会では無料の税務相談会をおこなっている場合があります。
たとえば、東京税理士会の納税者支援センターでは平日10時00分〜12時00分、13時00分〜16時00分の間に税務に関する問題の相談を受け付けています(最終受付は15時30分まで)。
各市区町村では、定期的に専門家による相談会を開催している場合があります。
税務相談の窓口を開いていれば、税理士に直接税の相談をすることが可能です。
相談会の開催状況は各市区町村によって異なるため、事前に確認のうえ参加するようにしてください。
離婚に伴って精算しなければいけない金銭問題について、場合によっては課税の対象となるものがあります。
離婚に伴って婚姻費用や養育費用の請求をする場面がありますが、一括請求をしてしまうと課税される可能性があります。
理由として、婚姻費用や養育費用は生活や教育のためのお金として非課税となりますが、金額が大きくなると必要以上のお金を得ていると捉えられる可能性があるためです。
婚姻費用や養育費用を一括請求することにはメリットもありますが、税金のことを考えると慎重になる必要があります。
離婚時の慰謝料は原則非課税ですが、あまりに高額だった場合は課税の対象となる可能性があります。
理由としては、脱税や資産隠しを疑われるためです。
財産分与に関する税金の問題は非常に複雑で、本来であれば手続きが必要なものを見逃してしまったり、勘違いしてしまったりする可能性があります。
そのため、財産分与の税の問題や確定申告の手続きについては、専門家である税理士に相談するのがおすすめです。
本記事を参考に税理士に相談して、財産分与の問題の解決を目指してください。


★離婚弁護士ランキング全国1位獲得★【日本で唯一「離婚」の名を冠した事務所】経営者/開業医/芸能人/スポーツ選手の配偶者等、富裕層の離婚に強み!慰謝料相場を大きく上回る数千万〜億超えの解決金回収実績!
事務所詳細を見る
【メール相談は24時間365日受付中】離婚問題でお悩みの方へ。離婚専門チームがあるベリーベストがあなたのお悩み解決のお手伝いをします。信頼性とプライバシーを守りながら、解決の一歩を踏み出しましょう。【初回相談60分0円】
事務所詳細を見る
【LINE無料相談がお勧め】◆早く離婚したい◆慰謝料を減額したい◆不倫の責任をとらせたい◆家族や会社に知られたくない◆早く解決して日常に戻りたい
事務所詳細を見る
ここでは、離婚時に専業主婦も財産分与を受けられる理由や対象となる財産の種類、相場よりも金額が低くなるケースを解説します。当記事を参考に、納得のいく金額で財産分与...
離婚時の財産分与で不動産がある場合、どのように分ければよいのでしょうか。今後も住み続けたい場合や、ローンがある場合などさまざまなパターンがあるので、悩んでしまい...
離婚するにあたって財産分与をする場合、どのような書類が必要なのか分からないという方もいるでしょう。預貯金や不動産など、婚姻期間中に築いた財産はさまざまあるはずで...
離婚後に財産分与の請求ができることは意外と知られていないかもしれません。本記事では、離婚後の財産分与の請求方法、離婚後の財産分与で注意すべきこと、離婚後の財産分...
夫婦が離婚するときは財産分与をおこない、預貯金や不動産などを分け合います。本記事では、離婚時の財産分与で通帳開示する方法や、弁護士に請求依頼するメリットを解説し...
離婚時に財産分与を請求された場合、退職金は原則として財産分与の対象となり得ます。本記事では、離婚時に退職金は財産分与の対象となるのか、離婚時に退職金を取られない...
離婚する際には、お金に関する様々な取り決めが必要になります。そのため、何かトラブルが生じるのではないかと不安に感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では...
離婚時の財産分与の対象に、結婚前の資産は含まれません。しかし、例外的に財産分与の対象となることもあります。財産分与は、夫婦で揉める問題のひとつです。この記事では...
離婚の際、争いの種となりやすいのが財産分与です。 本記事では、離婚前の財産分与について気を付けるべきポイントや、財産分与に関する問題を弁護士に相談するメリット...
自身が専業主婦であることから、離婚する際にしっかりと財産分与を受けられるのか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では、専業主婦が離婚する際におけ...
離婚手続きを進めていくうえで、財産分与についても考える必要がありますが、財産を分ける際に税金がかかる場合があるということを知っていますか?本記事では、離婚時の財...
熟年離婚の財産分与は、婚姻期間が長いほど高額になる傾向にあり、1,000万円を超える夫婦も少なくありません。財産分与をできるだけ多く受け取り、離婚後も経済的な不...
離婚の際に年金分割を拒否したいという方もいるでしょう。この記事では、年金分割を拒否できるのか解説しています。年金分割をしない場合の手続きについても、あわせて紹介...
離婚時の財産分与では、結婚前からの貯金や子ども名義の貯金など、貯金の種類によって分け方が異なります。隠し口座がないか不安な方は、弁護士などの力が必要になる場合も...
財産分与は2年以内に請求しないと時効(除斥期間)が成立し、請求する権利が完全に消滅してしまいます。この記事では、離婚後に財産分与の請求を時効までにするため、財産...
社長や経営者と離婚すると、多くの場合、生活水準の低下などの事情から後悔する気持ちも出てくるかもしれません。しかし、この記事で紹介する3つの問題を踏まえ、離婚に望...
共有財産(きょうゆうざいさん)とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産のことをいいます。財産の所有名義が一方の配偶者である場合でも、もう一方の貢献があったとみなさ...
財産分与の放棄は相手方の承諾がなければおこなえません。なぜなら、財産分与請求権は夫婦それぞれの権利だからです。少しでも財産分与の内容を有利にするには、財産調査や...
離婚する際の夫婦の財産と損をしない財産分与の方法についてまとめました。
夫婦が婚姻期間中に協力して株式を取得した場合、当該株式は財産分与の対象に含まれます。ただし、預貯金と違って株式は分割するのが困難なので、財産分与の方法などで争い...
離婚で財産分与をした場合、税金についても注意しなければなりません。本記事では、財産分与をおこなう際に注意したい税金について詳しく解説します。どのようなケースで贈...
離婚の際、争いの種となりやすいのが財産分与です。 本記事では、離婚前の財産分与について気を付けるべきポイントや、財産分与に関する問題を弁護士に相談するメリット...
特有財産に該当する財産や判例をわかりやすく解説します。
離婚の際に年金分割を拒否したいという方もいるでしょう。この記事では、年金分割を拒否できるのか解説しています。年金分割をしない場合の手続きについても、あわせて紹介...
財産分与はローンなどの負債についてもおこなわねばなりません。特に不動産に住宅ローンが残っている場合は複雑です。不動産の評価額に対して上回るのか下回るのかを確認し...
熟年離婚の財産分与は、婚姻期間が長いほど高額になる傾向にあり、1,000万円を超える夫婦も少なくありません。財産分与をできるだけ多く受け取り、離婚後も経済的な不...
離婚時の財産分与では、結婚前からの貯金や子ども名義の貯金など、貯金の種類によって分け方が異なります。隠し口座がないか不安な方は、弁護士などの力が必要になる場合も...
離婚する際の夫婦の財産と損をしない財産分与の方法についてまとめました。
借金などの債務は、基本的には、財産分与の対象とならないと考えられています。しかし、一定の債務については、財産分与において考慮される可能性があります。財産分与の考...
社長や経営者と離婚すると、多くの場合、生活水準の低下などの事情から後悔する気持ちも出てくるかもしれません。しかし、この記事で紹介する3つの問題を踏まえ、離婚に望...
離婚時、婚姻中に夫婦で築いた財産である家も、財産分与の対象です。家を財産分与する際には、家を売る方法もありますが、家を売らない選択肢もあります。本記事では、離婚...
離婚後に財産分与の請求ができることは意外と知られていないかもしれません。本記事では、離婚後の財産分与の請求方法、離婚後の財産分与で注意すべきこと、離婚後の財産分...