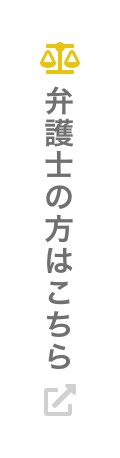離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える


公正証書とは、公証人が当事者の合意を踏まえ法律に従って作成する公文書のことをいいます。公正証書は離婚に伴う給付や養育費の支払いの取り決めをした際や金銭の貸し借りをしたときなどに利用されます。遺言などでもよく利用されます。
公証人は法律の専門家で元裁判官、元検察官、元法務局長など法律実務を経験した人が選ばれるとされています。中立で公正な立場の公証人が作成していますから、公正証書は強い証拠力を持ちます。全国中の町中にある、公証役場において、公正証書を作ることはできますが、文章案の作成や各種必要な文書など、厳格に決まっています。
また、公正証書は公証人が作成した後に原本を公証役場(法務省が管轄する役所)で20年間保管されます。従って改ざんや偽造などの心配がないとされています。
公正証書には証拠としての高い価値や、(強制執行認諾条項を記しておけば)強制執行時の執行力がありますので、合意後に起こりがちなトラブルを避ける余地が生まれることもあります。
このように公正証書は有用な文書であることがわかりますが、実際に公正証書の作成方法を知らない方がほとんどでしょう。
そこでこの記事では公正証書を作成するにあたって必要な知識をわかりやすく解説します。
公正証書には高い安全性と信頼性があることを前述しましたが、以下で公正証書を作成するメリットを具体的に解説します。
離婚協議の内容を公正証書にまとめることには4つのメリットがあります。「証拠として価値が高い」「執行力がある」「心理的拘束力が高い」「公証役場が原本を保存する」の4つです。
公正証書は法律の専門家である公証人が法律に従って、作成当事者の身元や合意の意思を確認してから作成します。また、公正証書は公証人が明確な文言で作成するため、内容の解釈でその後のトラブルも少ないといえます。
公正証書は当事者同士の合意を確定的なものにする証拠として信用性の高い資料となり得ます。なお、公正証書化された書類は当事者両方に交付されますが、万が一、当事者が書類を紛失したとしても原則20年間は公証役場に保管されていますので、安全性も高いといえるでしょう。
公正証書は信頼性の高い合意文書であるため、例えば、養育費など金銭債務の場合には公正証書に「強制執行認諾条項」を記しておけば相手方に対して強制執行の申立を直ちに行うことができます。本来であれば、強制執行をするには裁判所に訴訟を提起して勝訴の判決を受けることで初めて強制執行が確定されます。予め公正証書に強制執行認諾条項を記載しておくことで、これらの労力を省くことができるでしょう。
(債務名義)
第二十二条 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
一 確定判決
(中略)
五 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
六 確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。)
六の二 確定した執行決定のある仲裁判断
七 確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)
引用:民法
ただし、公正証書に記した全ての内容について強制執行できるというわけではないので注意が必要です。
公正証書には証拠として優れた効力があります。更に、公正証書に強制執行認諾条項の記載があれば、申立をすることにより直ちに強制執行ができますので、公正証書を作成した債務者にとっては心理的な圧力となり得るでしょう。
また、公正証書は裁判でも有力な証拠となり得ますので、債務者としては裁判で争うことを困難と自覚してできる限り履行しようとする可能性が高くなるでしょう。
債務者に対しての心理的な圧力も公正証書の重要な効力となり得ますので、公正証書を活用することである程度、紛争を避けることが可能でしょう。
私文書の離婚協議書は、失くしてしまえば終わりです。加えて、公的な機関に保存してもらうこともできません。
公正証書であれば公正証書作成の翌年から20年は原本が保存されますので、紛失したときにも対処できるというメリットがあるのです。
離婚協議の公正証書を作成するデメリットは4つです。
強制執行を視野に入れるなら、公正証書の執行認諾文言が抜けてしまうと致命的です。特に注意したいポイントになります。
また、公正証書の作成には当事者の出頭が基本的に必要なので、夫婦の片方が作成を拒んでいる場合は作成が難しくなるのです。
離婚協議書とは、離婚条件など離婚のときに決めたことをまとめた書面です。私文書と公文書の離婚内容についてまとめた書面を広義に離婚協議書と呼んでいます。 私文書として作成したものを「離婚協議書」と呼び、離婚協議書の中でも公正証書で作成したものを「離婚公正証書」と呼び分けることもあります。
離婚協議書の書き方とサンプルについては以下記事に詳しくまとめておりますのでご覧ください。
公正証書作成の流れとかかる費用を簡単に解説します。
公正証書の内容について特段ルールが定められているわけではありませんが、事前に当事者間で法律関係を整理して明確に合意する必要があります。例えば、離婚時に公正証書を作成する場合、には以下の項目について当事者間で話し合いをしましょう。
当事者間の合意が前提となっていますから、合意された項目だけを記載するという処理も可能です。
当事者間で合意を確認した後に、公正証書を作成する際に必要な資料を収集します。以下は離婚について公正証書を作成する場合に必要な資料になります。
また、財産分与に不動産がある場合には不動産の登記簿謄本や物件目録などが必要です。年金分割を行う場合には年金手帳など年金分割に必要な資料が必要です。

前項の必要資料を持って公証役場に出頭し、公証人と面談を行います。必要資料があれば、当事者の一方だけで面談を受けても問題ありません。その後、公証人が合意内容を踏まえて公正証書の原案を作成し、当事者が原案を確認します。
なお、公正証書の作成は容易であると考える方もいるかもしれませんが、当事者のみで公正証書の合意内容について話し合いをまとめることは簡単ではありません。作成に不安がある場合には弁護士に依頼することをおすすめします。
離婚公正証書は財産分与や養育費の額で費用が変わってきます。
たとえば100万円以下の価額では手数料が5,000円になり、200万円超500万円以下では11,000円です。この他に、公正証書の枚数による加算もあります。 離婚公正証書の原案が決まった段階で公証役場や弁護士に試算をお願いすれば、大体の費用を把握できます。
離婚公正証書とは決めた離婚条件などをまとめる書面ですから、作成の段階で離婚条件を固めておく必要があります。
公正証書に記載すべき内容は以下の通りです。
まず記載するのは、離婚に合意したことです。離婚公正証書にまとめる離婚条件は離婚の合意を前提にしているため、離婚の合意についても記載します。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に培った財産を離婚に際して分割することです。
財産分与の割合は基本的に夫と妻で2分の1ずつになります。ただし、夫婦の話し合いで自由に分けることが可能なので、必ずしも半分ずつにする必要はありません。
財産分与の対象になるのは、預金や不動産、有価証券などです。この他に、住宅ローン残債などについても決める必要があります。
慰謝料は離婚において必ず発生するわけではありません。不貞行為やDV、モラハラ、悪意の遺棄などがあれば、慰謝料の問題になります。
慰謝料の支払い原因があり、慰謝料について取り決めた場合は、公正証書に記載します。慰謝料の額や支払い方法については、夫婦の話し合いで決めることが可能です。
離婚するためには、親権者は絶対に定めなければいけません。子供がいるのに親権者が決まっていないと、そもそも離婚が認められないのです。
親権者は基本的に監護権者を兼任しますが、別々に定めることもできます。
子供がいる場合は離婚の公正証書に親権や監護権者についても記載するのが基本です。
養育費は子供の養育のための費用です。離婚しても子供の父母であることは変わりませんから、子供を養育するための養育費の支払いが必要になります。
養育費の額などについては、父母の話し合で決めることが可能です。この他に、進学や入院費用などが発生したときの父母の分担などについても決め、離婚公正証書に盛り込むことができます。
離婚しても子供の親であることは変わりませんから、非親権者も離婚後に子供と会うことが可能です。父母に激しい対立があるわけではない場合は、「面会交流する」という合意を公正証書に盛り込むかたちでも問題ありません。
婚姻期間中の厚生年金や共済年金は、離婚に際して夫婦で分割可能です。
離婚の時点で分割の取り決めをしても、すでに納めた分を現金として受け取れるわけではありません。年金をもらう段階になって、分割分が反映されるかたちになります。
年金分割の合意などがあれば、離婚公正証書に記載します。
1~7の他にも、婚姻費用や住居の使用、住所変更の通知などがあれば離婚公正証書に記載します。
重要な記載事項として清算条項があります。清算条項とは「記載の内容以外に債権債務ないことを確認する記述」です。
清算条項を記載することで、支払いなどを蒸し返されることを防止可能です。
この他に、約束違反の際に強制執行できるよう、執行認諾文言を記載しておくことも重要なポイントになります。
離婚協議で公正証書を作成する際によくある4つの質問について補足します。
公正証書の作成は原則的に当事者の出頭が必要です。ただし、離婚事情などによっては、代理人によって進めることも可能になっています。
まずは公証人や弁護士に相談してみてください。
私文書として離婚協議書を作成した場合でも、後から公正証書を作成することが可能です。この場合は離婚協議書の内容を離婚公正証書にするという流れになります。
離婚公正証書は夫婦の合意で作成するため、夫婦の片方が作成を拒否している場合は、作成が困難です。どのような理由で拒否しているのか確認して、弁護士に対応を相談してみてはいかがでしょう。
つけられます。
ただし、保証人になる人の承諾が必要です。夫婦の一存で親などを承諾なく保証人にすることはできませんので、注意してください。
公正証書とは、公証役場で作成する公文書のことです。
離婚の際には離婚条件を記載した離婚公正証書を作成することで、いざというときに強制執行できたり、約束を破らないように心理的な圧力を与えたりするメリットがあります。
離婚公正証書は個人でも作成できますが、作成のための離婚条件を決めるときは、法的な知識が必要です。離婚公正証書には記載できない取り決めがあったり、記載しても効力を発揮しなかったりする可能性があるからです。
離婚公正証書は離婚成立後でも作成できます。ただ、離婚後のトラブルを防ぐために、可能であれば離婚前に作成しておくことが重要です。
公正証書を有効活用するために、そしてスムーズに離婚公正証書を作成するために、離婚問題を得意としている弁護士にサポートを受けてはいかがでしょうか。
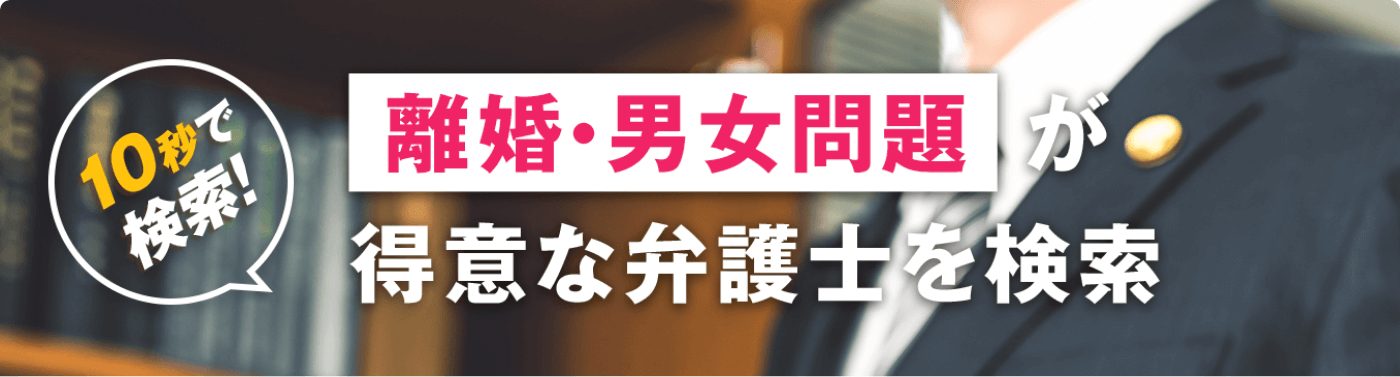

【LINE無料相談がお勧め】◆早く離婚したい◆慰謝料を減額したい◆不倫の責任をとらせたい◆家族や会社に知られたくない◆早く解決して日常に戻りたい
事務所詳細を見る
★離婚弁護士ランキング全国1位獲得★【日本で唯一「離婚」の名を冠した事務所】経営者/開業医/芸能人/スポーツ選手の配偶者等、富裕層の離婚に強み!慰謝料相場を大きく上回る数千万〜億超えの解決金回収実績多数!
事務所詳細を見る
【メール相談は24時間365日受付中】離婚問題でお悩みの方へ。離婚専門チームがあるベリーベストがあなたのお悩み解決のお手伝いをします。信頼性とプライバシーを守りながら、解決の一歩を踏み出しましょう。【初回相談60分0円】
事務所詳細を見る
公正証書とは公証人に作成される証明力と執行力を備えた文書のことをいいます。この記事では公正証書を作成するメリットや作成の手順を解説します。
本記事では、オーバーローン状態の住宅をもっている夫婦が離婚する際に直面する財産分与の問題と、その解決策について解説します。
本記事では、離婚時において家の査定をおこなう重要性をはじめ、査定の依頼先や財産分与の流れなどについて解説しています。
新築離婚は新築の家を建てたり購入したりした後に離婚することを指し、増加傾向にあります。本記事では新築離婚の原因をはじめ家の処分方法や財産分与のポイントを解説し、...
離婚を機に、夫婦の共有財産であるマンションの売却を検討するケースは少なくありません。本記事では、離婚時にマンションを売却するメリットをはじめ、実際の売却方法や流...
離婚という人生の大きな転機に直面した際、家を売却するかどうかは避けて通れない課題となります。本記事では、離婚時に家を売却するメリット、適切な売却のタイミングや売...
別居中でも婚姻費用を負担する必要はあります。しかし、別居の理由や別居後の生活に不満があり、支払いに納得できないという方もいるでしょう。そこで本記事では、婚姻費用...
「もっと子どもと面会交流する頻度を増やしたい」など、離婚後にさまざまな要望が生まれることも少なくはないでしょう。そこで本記事では、他のご家庭の面会交流の頻度を知...
婚姻費用分担請求審判は、婚姻費用の分担額を決定する法律的な手続きです。審判で有利な結果を得るためにも、審判の概要や適切な進め方を知っておきたいところです。本記事...
婚姻費用の審判結果に納得できない場合は、即時抗告を申し立てて争うことが考えられます。本記事では、婚姻費用の審判結果に納得できない場合の対処法について、即時抗告の...
事実婚をする人の中には同性であったり夫婦別姓が認められないために事実婚を選択していたりとさまざまなケースがあります。この記事では事実婚と認められるための要件や要...
産後から夫婦生活がなくなってしまう人は少なくありません。実際産後どのくらいの期間から再開すればよいのかわかりませんよね。この記事では、「産後の夫婦生活はいつから...
「旦那と一緒にいてもつまらない」「旦那が家にいるだけでストレスになる」と思いながら生活していませんか。ストレスを我慢して生活することはできますが大きなリスクも伴...
マザコンにはいくつか特徴があり、母親への依存心が強すぎると夫婦関係が破綻することもあります。状況によっては別居や離婚などを選択するのも一つの手段です。この記事で...
夫婦別姓にすることで、氏の変更手続きをしなくて済み手間が省ける・旧姓のままでいられるという大きなメリットがあります。この記事では、夫婦別姓にした場合の4つのメリ...
離婚に条件がついているケースもあります。裁判所を介する離婚では、法律で認められた離婚の理由が不可欠です。この記事では、法律で定められた離婚の理由と、夫婦が離婚す...
婚姻費用を払ってもらえたら、専業主婦の方などでも別居後の生活費にできるので、安心して離婚を進めることができるでしょう。この記事では、婚姻費用がいつからいつまで、...
専業主婦で離婚しようと思った場合、不安を感じますよね。この記事では、専業主婦が離婚するときのお金の不安、離婚にかかる費用、住居や子供、就職の不安と、離婚に向けて...
単身赴任は離婚の危機が高まると言われています。この記事では、単身赴任が原因で離婚するリスクから、単身赴任でよくある離婚の原因、単身赴任中の浮気、単身赴任中の浮気...
専業主婦の場合、最も不安なのが金銭面という方も多いでしょう。年金分割は、まだ自身が年金を受け取る年齢でなくても、請求することが可能です。この記事では、年金分割に...
夫婦カウンセリングは夫婦間の問題を解決する方法の一つです。この記事では夫婦カウンセリングの効果やメリットをわかりやすく解説します。
離婚を機に、夫婦の共有財産であるマンションの売却を検討するケースは少なくありません。本記事では、離婚時にマンションを売却するメリットをはじめ、実際の売却方法や流...
離婚に条件がついているケースもあります。裁判所を介する離婚では、法律で認められた離婚の理由が不可欠です。この記事では、法律で定められた離婚の理由と、夫婦が離婚す...
「旦那と一緒にいてもつまらない」「旦那が家にいるだけでストレスになる」と思いながら生活していませんか。ストレスを我慢して生活することはできますが大きなリスクも伴...
アンガーマネジメントの目的は、『怒り』の管理・コントロールになります。アンガーマネジメントを学ことでイライラするのをおさえられたり怒りの感情を相手にうまく伝えら...
公正証書とは公証人に作成される証明力と執行力を備えた文書のことをいいます。この記事では公正証書を作成するメリットや作成の手順を解説します。
偽装離婚(ぎそうりこん)とは、一緒に暮らすことや精神的な繋がりがある夫婦であるにもかかわらず、離婚届を提出して正式に離婚し、あたかも離婚しているかのように振る舞...
新築離婚は新築の家を建てたり購入したりした後に離婚することを指し、増加傾向にあります。本記事では新築離婚の原因をはじめ家の処分方法や財産分与のポイントを解説し、...
マザコンにはいくつか特徴があり、母親への依存心が強すぎると夫婦関係が破綻することもあります。状況によっては別居や離婚などを選択するのも一つの手段です。この記事で...
実は離婚協議書の作成などは司法書に依頼することができます。弁護士への依頼とどう違うのででしょうか。また離婚にかかる問題はどちらに相談、依頼するのが適切なのでしょ...
離婚という人生の大きな転機に直面した際、家を売却するかどうかは避けて通れない課題となります。本記事では、離婚時に家を売却するメリット、適切な売却のタイミングや売...
婚姻とは民法で定められた条件を満たした男女が社会的に夫婦と認められることをいいます。婚姻の条件や効果などを解説します。