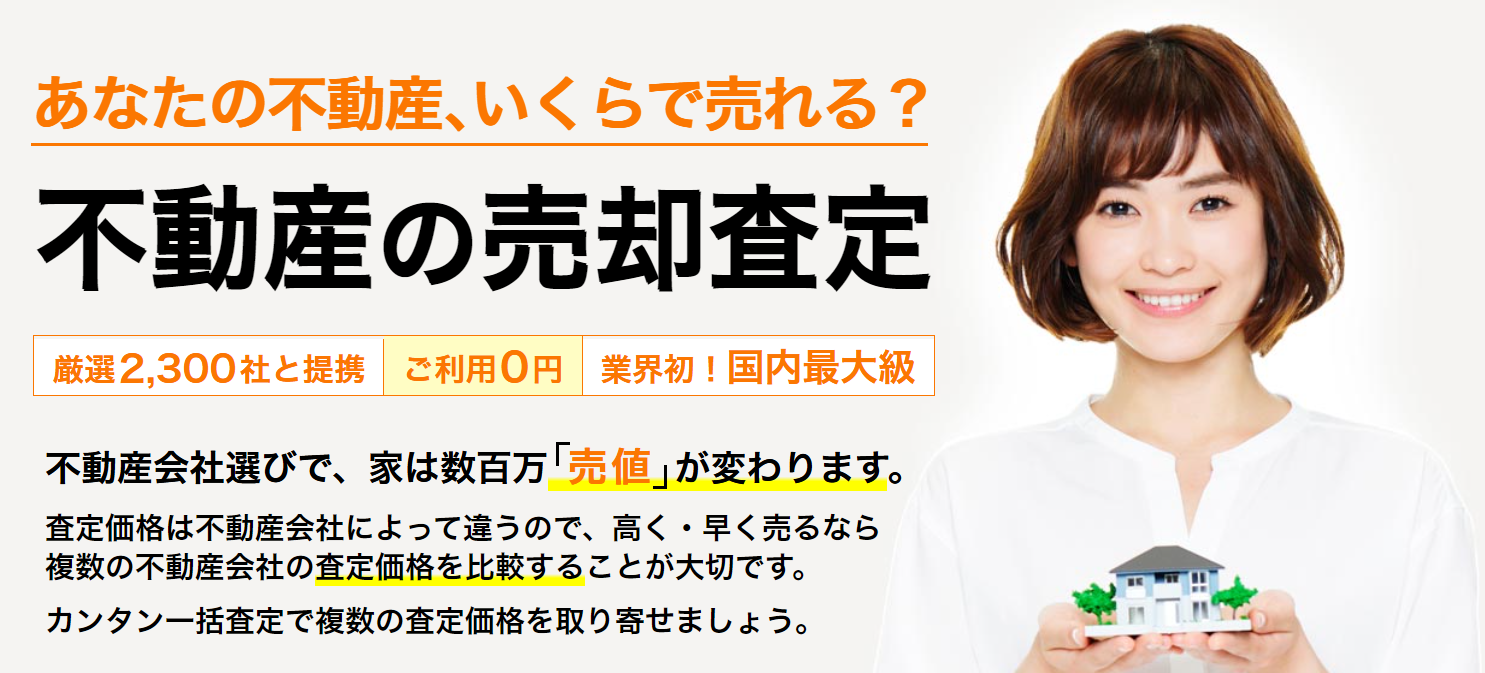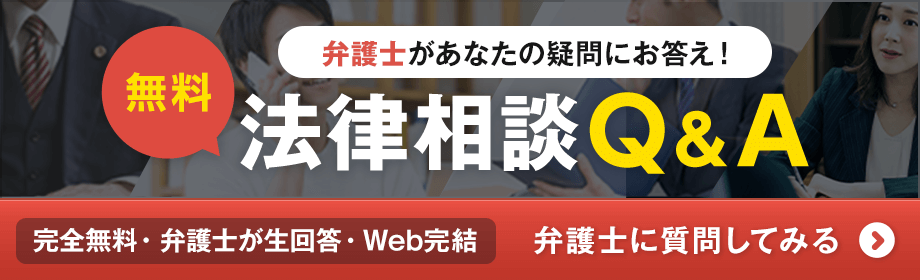本コンテンツには、紹介している商品(商材)の広告(リンク)を含みます。
ただし、当サイト内のランキングや商品(商材)の評価は、当社の調査やユーザーの口コミ収集等を考慮して作成しており、提携企業の商品(商材)を根拠なくPRするものではありません。
厚生労働省が公表する令和2年人口動態統計の概況をみると、2020年の離婚件数は約19万3,000件のうち、約90%が協議離婚を選択しています。
協議離婚は事務負担や費用負担が少なく、法的な理由も必要としませんが、子どもの親権や養育費などを当事者だけで決める必要があります。
そこでこの記事では、自分たちで進めるうえで、進め方や決めておくべきことや、万が一協議離婚がうまくいかなかったときの対処法を解説します。
協議離婚でお悩みのあなたへ
離婚協議が控えているけど、何を決めたらいいかわからない、揉めずに進められるか不安、と悩んでいませんか?
結論からいうと、協議離婚でお悩みなら弁護士への相談がおすすめです。弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットを得ることができます。
-
- 協議離婚の進め方についてアドバイスがもらえる
- 協議離婚で取り決めるべきことを教えてもらえる
- 協議離婚の注意点や話し合いのコツを教えてもらえる
- 万が一揉めても、依頼すれば話し合いを代行してもらえる
- 依頼すれば、調停や裁判に発展しても対応を任せられる
ベンナビ離婚では、協議離婚について無料相談できる弁護士はもちろん、電話相談や休日夜間に相談できる弁護士も多数掲載しています。まずはお気軽にご相談ください。
離婚後の生活設計にお悩みの方へ
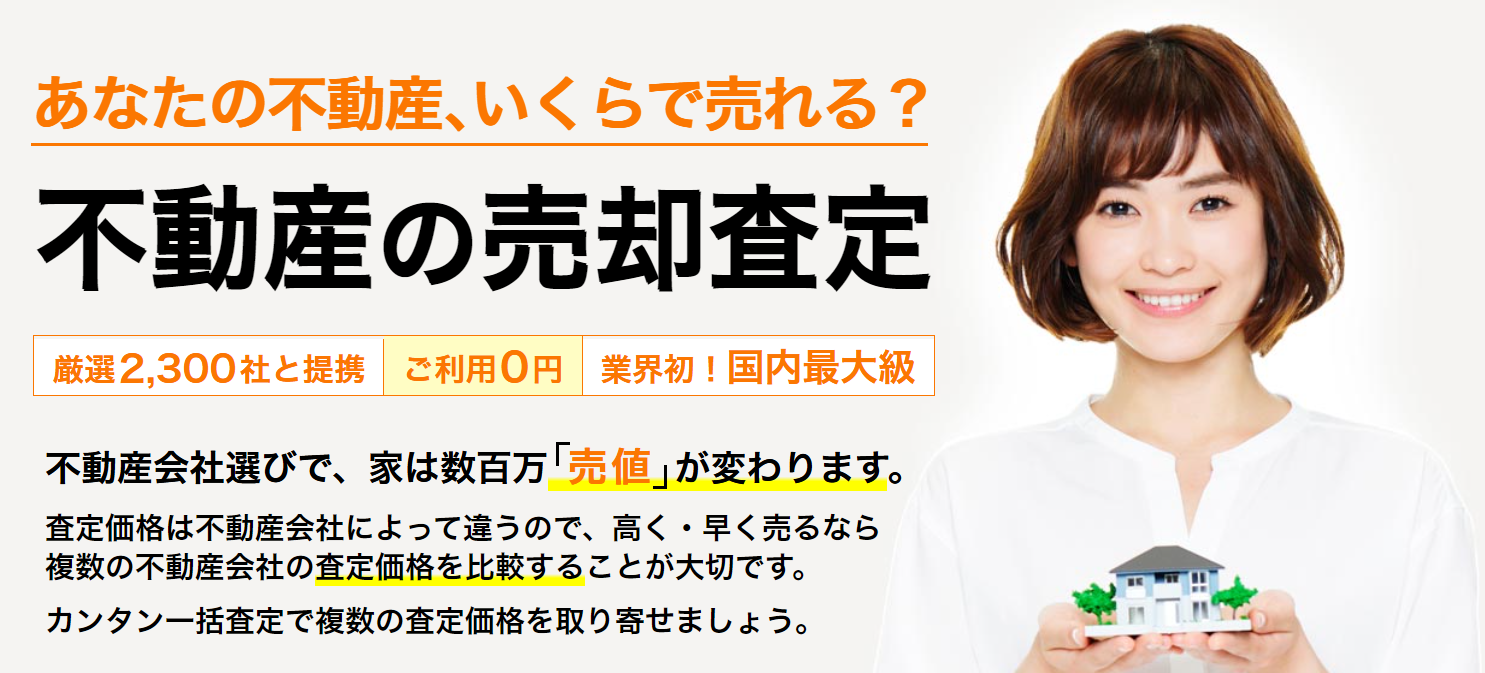
離婚検討時には様々な不安があります。
その中でも最も多いのが「離婚後の収入やお金の不安」です。
離婚後の生活設計に見通しを立てたい場合は、共有財産の中でも最も大きな割合を占めるご自宅の価格を確認すると良いでしょう。
入力はたったの1分で完了します。
まずは無料のAI査定で、ご自宅の価格をチェックしてみませんか?
1分で完了! 無料査定スタート
協議離婚とは?
「協議離婚」とは、夫婦の話し合いによって決定する離婚の方法です。
夫婦間で話し合い、お互いが条件に合意すれば離婚決定となります。
そのため、離婚の理由は問われず、時間や費用がかからないのが特徴です。
実務的には地方自治体の窓口に離婚届を提出するだけなので、裁判所の手続きも必要ありません。
協議離婚の成立に必要なこと
協議離婚を成立させるためには、以下のことを取り決めることが必要です。
夫婦双方が合意すること
協議離婚は裁判所を利用することなく、夫婦の話し合いで取り決める離婚の方法です。
そのため、夫婦双方が離婚について合意することが必須となります。
離婚する意思があること、離婚の条件面についてお互いに納得していることが協議離婚の成立につながります。
子どもの親権者を決めること
夫婦に未成年者の子どもがいる場合、親権者を決めなければなりません。
なぜなら、離婚届には子どもの親権者を記載する箇所があるからです。
親権者の記載がないまま届け出ても離婚届は受理されません。
父母どちらが子どもの親権者になるのか、あらかじめ決めておくことが協議離婚の成立には必要です。
協議離婚以外の離婚の種類
協議離婚が成立しないときには、それ以外の離婚方法を検討します。
協議離婚以外の離婚の種類には、以下のようなものがあります。
調停離婚は裁判所を介した離婚方法であり、協議離婚がまとまらない場合の選択肢になります。
裁判所の判断を仰ぐというより、中立的な立場の調停委員に間に入ってもらい話し合いで着地点を見出す方法なので、相手と顔を突き合わせることもほとんどなく、調停委員を介した話し合いになります。
調停離婚でも決着しなかったときには、審判離婚や裁判離婚へ移行することになります。
審判離婚では合意できない一部の条件について、裁判官に和解案を決めてもらう方法です。
合意できれば離婚決定となります。
一方、審判離婚でも決着しなければ裁判離婚となり、離婚条件などを裁判官に決定してもらう形で、離婚が決定します。
協議離婚の進め方
協議離婚は当事者同士の話し合いからスタートしますが、成り行き任せで話を切り出すとまとまらないケースが多く、夫婦関係もさらに悪化してしまう可能性があります。
相手と離婚協議するときは、次のように下準備をおこない、考えを整理してから話し合いを始めてください。
離婚後の生活を考えておく
協議離婚を検討している方は、必ず離婚後の生活を考えるようにしてください。
離婚によって経済的に不利にならないか、会社の昇進に影響しないか、子どもにシワ寄せが行かないかなど、デメリットになりそうなことは全て洗い出しておきましょう。
離婚後の住居にも目星をつけておき、家賃や生活費がいくらになるかも想定しておく必要があります。
いずれ養育費や慰謝料、財産分与についても話し合うことになるので、希望額も考えておいてください。
離婚には十分なメリットもありますが、一時的な感情で離婚した結果、後悔するケースも少なくないため、マイナス面は慎重に考えておきましょう。
相手に離婚を切り出す
離婚を切り出すためには勇気も必要ですが、相手もショックを受けるため、日頃は冷静な人でも逆上してしまうケースがあります。
ものを投げつけられたり、叩かれたりする可能性もあるので、子どもは友人などに預かってもらい、部屋の中も片付けておきましょう。
相手の暴力も想定し、友人宅や実家に避難できるよう、数日分の衣服や薬なども荷物にまとめておいてください。
また、離婚を切り出すタイミングも重要なので、相手と冷静に話し合えるシーンも想定しておきましょう。
相手がお酒を飲んでいる状況では冷静に話し合いができないので、休日の午前中に話を切り出すなど、最適なタイミングを考えておく必要があります。
LINEやメールで離婚を切り出す方法もありますが、かえって相手の感情を逆なでする可能性もあるので、要件だけを伝え、相手が冷静になるのを待ってから話し合うようにしてください。
相手と離婚の条件を決める
相手と冷静に話し合える状況になれば、具体的な離婚条件として、以下の内容を決めていきます。
子どもがいる場合に取り決めること
- 親権
- 養育費
- 面会交流
子どもがいる場合は、親権や養育費、面会交流から優先的に話し合い、次に慰謝料や財産分与を決めてください。
ただし、お互いが一方的に主張すると話し合いがまとまらず、さらに関係が悪化するケースもあります。
親権やお金が関係する話し合いは慎重に進める必要があるので、交渉に不安があるときは弁護士に相談してください。
専門家が関わると冷静な話し合いができるので、離婚協議の決着も早くなります。
離婚慰謝料の取り決め
慰謝料の相場は離婚事情によって変わりますが、一般的には50万~300万円程度です。
高額な慰謝料請求は相手から拒絶される可能性もあるので、現実的な金額を請求する必要があります。
金額の決め方がわからずに迷ってしまうときは、離婚問題に詳しい弁護士に相談してみましょう。
また、慰謝料の支払方法・支払期日、支払期日に遅延した場合の損害金を話し合いで決めたうえで、相手に預金口座の番号も伝えてください。
相手が一括払いできないときは、分割払いの回数も決めておきましょう。
財産分与(年金分割)の取り決め
離婚時には、婚姻中に形成された財産を分け合う「財産分与」をおこないます。
夫婦の財産はお互いの協力によって築かれたもの、という法律上の考え方があるため、基本的には2分の1ずつの分配となります。
ただし、子どもの親権者になる方の人が、離婚後何らかの事情により生活に困窮することが明らかである場合は、扶養面を考慮するため、分割の比率を調整しなければなりません。
また、どちらか一方が婚姻前から所有していた財産や、贈与や相続で得られた財産は、財産分与の対象にはならないため注意が必要です。
分割する財産にもさまざまな種類があるので、漏れがないようにチェックリストを作成しておくとよいでしょう。
下記は、代表的な例になります。
財産分与の対象となる財産
- 預貯金や現金(婚姻後の財産であれば、名義人は問わない)
- 有価証券(株式など)
- ゴルフクラブなどの会員権
- 宝石や貴金属、家財道具
- 不動産
- 住宅ローン(返済の分担など)
- 生命保険などの解約返戻金
- 自動車
- 退職金や年金
人によっては、夫婦共有の財産から個人的な貸付けをしているケースもあり、債権としての財産になります。
また、暗号資産や、ネット銀行・ネット証券など、わかりにくい財産もあるので、パソコンや郵便物もチェックしてください。
なお、年金については、婚姻期間中に納付した保険料を夫婦で2分の1ずつ分割し、老齢年金の受給額を調整する「年金分割」の制度もあります。
年金分割の対象となるのは厚生年金と共済年金のみで、国民年金は対象ではありません。
子どもの親権の取り決め
親権を決めるときは、どちらが親権者であれば子どもが幸せになれるか、という観点で考える必要があります。
子どもの気持ちを尊重し、夫婦の事情や、経済的な余裕だけで決めないことが重要です。
保育園などに預けた子どもが病気やケガをした場合、早退して病院へ連れていくケースもあるので、親の職場が育児・子育てに理解があるかどうかも重要になるでしょう。
離婚後は住居も別々になるため、子どもにとってどちらの住環境がよいかという点も考えておく必要があります。
離婚後に引っ越しをする場合は、ひとり親世帯への支援が手厚い自治体を探すなど、行政のサポートも考慮しておくとよいでしょう。
子どもとの面会交流権
親権を持たない親でも、子どもが成人するまでは面会交流権があるので、面会頻度や時間なども決めておきましょう。
子どもが幼いうちは面会頻度が高くても構いませんが、いずれ学校生活やクラブ活動、受験勉強などで忙しくなるため、回数や時間は柔軟に調整する必要があります。
下記は、調整する必要がある項目の例です。
- 面会交流の内容(遠方への外出・宿泊の可否、プレゼントや小遣いの限度額など)
- 面会頻度(月に2回など)
- 連絡方法(誰に連絡するか)
- 面会場所や日時の指定、子どもの受け渡し方法
- 1回あたりの面会時間
- 発言内容の制限
- 親権者の付き添いの有無
- 学校行事などへの参加
- 面会交流にかかる費用
- 電話・手紙・SNSなど、面会交流以外の交流方法
- 祖父母との面会交流
面会は子ども主体で考える必要があり、子どもが会いたがっているのに会わせない、またはその逆パターンにならないよう注意してください。
また、相手にもよりますが、面会の度に子どもへ親権者の悪口を吹き込み、自分の親権を取り戻そうとするケースもあります。
相手と子どもだけの面会に不安要素があれば、発言内容の制限や、親権者の付き添いなども取り決めておきましょう。
養育費の取り決め
養育費はあくまでも子どものために使う費用なので、教育費や生活費用全般、医療費や適度な娯楽費なども考慮しておく必要があります。
食費や被服費、入学費用など、子どもの成長に伴う加算額も想定しておきましょう。
養育費については、以下の項目を決めておきます。
- 養育費の金額
- 支払日
- 支払方法(銀行振込)
- 支払期間
支払日は相手の給料日、または親権者の給料日前(生活資金が不足するタイミング)などに設定するとよいでしょう。
支払方法は銀行振込になるケースがほとんどですが、振込手数料の負担についても話し合っておくべきです。
相手と折半する、または親権者が負担するときは、手数料相当額を差し引いて振込みするなど、細かな部分も決めてください。
支払期間は、子どもの高校卒業や大学卒業など一定の区切りで決めますが、親権者が再婚し、経済的な余裕が出たときには、養育費を打ち切るケースもあります。
離婚協議書を作成する
養育費や慰謝料、財産分与などが全て決着したら、必ず離婚協議書を作成してください。
書面にすることで、離婚の合意内容の証明になります。
離婚協議書に決まった様式はありませんが、表題とともに合意内容を全て書き出し、双方の署名捺印と日付があれば要件は満たせます。
ただし、取り決め項目が多くなるほど内容も複雑になり、相手が約束を守らなかったときや、状況が変化した場合の対応についても記載しておかなければなりません。
自分で作成するのは無理だと感じたら、弁護士へ離婚協議書の作成を依頼しましょう。
なお、離婚協議書を公正証書として残しておけば、養育費などの支払いが滞ったときに、裁判所の手続きを経ずに、相手の給料や財産を差し押さえる強制執行ができます。
地方自治体の窓口に離婚届を提出する
離婚協議がまとまれば、夫または妻の住所地もしくは本籍地の地方自治体の窓口に離婚届を提出します。
本籍地以外の地方自治体に提出するときは戸籍謄本(全部事項証明書)が必要になるので、あらかじめ準備しておきましょう。
なお、離婚届には親権者の記載欄があるので、離婚成立を急ぐ場合でも、親権だけは決めておかなければなりません。
協議離婚には証人2名が必要
離婚届には証人欄もあるため、証人2名の署名捺印も必要です。
協議離婚のみ証人が必要となり、成人であれば誰でも証人になれるので、家族や友人への依頼が一般的です。
また、夫婦が別々に1人ずつ選ぶ必要もないので、どちらか一方が2人を選んでも構いません。
なお、「責任重大だから」という理由でなかなか証人になってもらえないケースもありますが、証人に法的な責任を問われることはありません。
身近な人に頼めないときは、弁護士に証人を依頼することもできます。
協議離婚をスムーズに進めるポイント
離婚の目的は、現在の生活状況を改善することや、子どもによい生活環境を提供することであるため、相手との協議は有利に進める必要があります。
協議離婚をスムーズに進めるために、以下のポイントを意識しましょう。
離婚協議書は公正証書にしておく
離婚協議書を公正証書にしておくことで、協議離婚をスムーズに進められます。
離婚協議書の原案は、依頼者(あなた)が公証役場の公証人に伝えることで、書面にする方法です。
法律のプロ(元裁判官など)が作成するため、離婚協議書の法的効力を担保できます。
公正証書の作成には3万~8万円程度の費用もかかりますが、強制執行が想定される場合には有効です。
相手がお金の支払いにルーズであったり、生活費をギャンブルにつぎ込んだりするタイプであれば、給料や財産を差し押さえない限り、1円も支払ってもらえない可能性があります。
相手に少しでも不安要素があれば、公正証書にしておいたほうがよいでしょう。
弁護士に協議離婚の代理交渉を依頼する
代理交渉とは、弁護士があなたに代わって相手方と交渉することをさします。
たとえば、相手からDVやモラハラを受けているようなケースでは、相手方と直接協議するのが難しい状況にあります。
このような場合、代理交渉を利用することで、加害者と距離を置きながら冷静に交渉を進められます。
直接相手と交渉することなく、協議離婚をスムーズに進められるでしょう。
感情的にならず冷静に対処する
当事者同士の話し合いは調整役やストッパーがいないため、どうしても感情的になりがちです。
売り言葉に買い言葉で協議を進めてしまうと、相手に揚げ足を取られてしまい、不利な条件で協議離婚が成立する可能性があります。
感情を抑えるのは難しいかもしれませんが、冷静に対処するよう心掛けてください。
相手もすぐに答えを出せないケースがあるので、無理にその場で結論を出さないことも重要です。
相手から即答を求められた場合も、勢いだけで答えないように注意してください。
話し合う内容を事前にまとめておく
感情的になると話し合いの論点がずれやすく、何も解決しないまま時間を浪費することになります。
話し合いが迷走しないよう、何について話し合い、何を決めるのか、事前にノートやメモに書き出しておくとよいでしょう。
ノートやメモは話し合いの場に持ち込み、感情的になったときは読み返してください。
地方自治体に離婚届不受理の申し出をしておく
離婚届は審査がないため、必要項目を記入して提出すれば、自治体はそのまま処理してしまいます。
子どもの親権を取るために、相手が勝手に提出するケースもあるので、もしもの場合に備えて、自治体に「離婚届不受理の申し出」をしておくとよいでしょう。
自治体が不受理の申し出を受け付けると、後から提出された離婚届は受理されません。
話し合いが決着し双方の合意のもとで離婚する際には、不受理の申し出をした本人が自治体に不受理の取り下げをおこなってから、離婚届を提出します。
なお、相手が勝手に提出した離婚届が処理された場合、家庭裁判所に協議離婚無効確認調停を申し立てます。
話し合いの末、離婚の取り消しについて双方から合意が得られると、離婚は無効となり、戸籍も訂正されます。
一方、調停で双方から合意が得られない場合、協議離婚無効訴訟を提起して、裁判で争います。
ちなみに、双方の合意がないまま勝手に署名捺印し、離婚届を偽造した場合は、有印私文書偽造罪として刑事罰が科せられる可能性もあります。
協議離婚がまとまらないときの対処法
協議離婚は、夫婦だけでなく子どもにも影響するため、きわめて重大な決断になります。
簡単に話し合いがまとまるケースは少なく、感情的になった相手が話し合いを拒絶する可能性もあるでしょう。
協議離婚がなかなかまとまらないときは、次のように対処してください。
別居して相手と距離を置く
お互いの主張が噛み合わないときや、顔を突き合わせるとどうしても感情的になってしまう場合は、別居して相手と距離を置くことも検討してください。
ひとまず実家に滞在する、または資金に余裕があれば、賃貸アパートやマンションを借りてもよいでしょう。
離婚は些細な言い合いが原因になっているケースも多いので、1人の時間をつくって冷静に考えれば、離婚せずに相手と和解できる案が思い浮かぶこともあります。
結果的に離婚するとしても、考え方を整理しておけば、相手と建設的な話し合いができるでしょう。
なお、別居中の生活費は婚姻費用となるので、別居開始から離婚成立までの費用に限り、年収の多い方へ請求できます。
ただし離婚の原因が請求者側にある場合には、請求が認められないこともあります。
いくら請求してよいかわからないときは、裁判所作成の婚姻費用算定表(子どもがいる場合の目安)を参考にしてみましょう。
離婚調停を申し立てる
当事者同士の話し合いがまとまらないときは、離婚調停の申し立ても検討してみましょう。
調停とは、中立的な立場の調停委員が間に入って双方の話を別々に聞き、話し合いで解決策を見いだす方法です。
裁判所というと、ドラマに出てくる法廷をイメージしますが、調停の場合は小会議室のようなスペースで話し合うので、特に身構える必要もありません。
申立先は相手の住所地を管轄する家庭裁判所になるので、別居している場合は以下のリンクから裁判所の住所などを調べてください。
なお、調停はあくまでも話し合いによる解決なので、法的な決定権がありません。
裁判官が判決を下すわけではないため、調停不成立のまま終了となる可能性もあります。
譲れるところは譲る、または離婚ありきの考え方を見直すなど、相手との和解も検討してみましょう。
離婚裁判を起こす
司法の判断で白黒はっきりさせたいときは、離婚裁判も検討してみましょう。
ただし、いきなり離婚裁判を起こすことはできず、調停離婚の不成立が前提となります。
離婚裁判も家庭裁判所に訴訟を提起しますが、裁判所の管轄は原告側(あなた)の住所地、または被告側(相手)の住所地のどちらでも構いません。
最終的には判決によって決着するため、双方が必ず従うことになります。
なお、調停よりもかなり複雑な手続きになり、離婚判決の訴状なども作成する必要があるため、弁護士に代理人を依頼するケースが一般的です。
自分で訴えを起こす(本人訴訟)こともできますが、「勝てる見込みがあったのに負けてしまった」といった事態になりかねないので、必ず弁護士に相談しましょう。
また、裁判離婚をするためには、離婚に至る原因として、以下のような理由が必要であると定められています。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
【引用元】民法|e-Gov法令検索
弁護士に相談する
弁護士には自分の代理人を依頼できるので、相手と冷静な話し合いができないときや、話し合いを拒絶されている場合は相談してみましょう。
法律の専門家が介入すると、相手も話し合いに応じやすくなるので、離婚協議も確実に進展します。
また、弁護士は交渉のプロであり、依頼者の利益のために活動するため、有利な条件で離婚成立となる可能性が高くなります。
裁判に発展した場合も手続きを任せられるので、多忙な方にとっては大きなメリットになるでしょう。
ただし、弁護士には専門分野があるので、全ての弁護士が離婚問題に精通しているわけではありません。
離婚のことは、必ず離婚問題に詳しい弁護士に相談してください。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を活用すれば、離婚問題が得意な弁護士を地域別に探せるため、1件ずつ弁護士事務所のホームページをたどる必要がありません。
あなたの町で活動する弁護士がすぐに見つかるので、協議離婚を急ぎたい方にもおすすめです。
まとめ|協議離婚で困ったときは弁護士に相談しよう
離婚はその後の人生に大きな影響を及ぼすため、決断には十分な話し合いが必要です。
離婚は今よりも幸せになるための選択肢のひとつですから、離婚によってさらに状況が悪くなると本末転倒です。
ただし、相手の暴力や精神的なハラスメント、浪費癖による貧困が原因の場合、時間をかけて話し合う余裕はありません。
あなた自身だけではなく、子どもにも危害が及ぶ可能性があるので、弁護士を交えた早急な対応が必要です。
離婚問題を解決できる専門家は弁護士しかいないので、ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)で近くの弁護士を探しておきましょう。
あなたの味方となって、離婚問題の早期解決をサポートしてくれます。