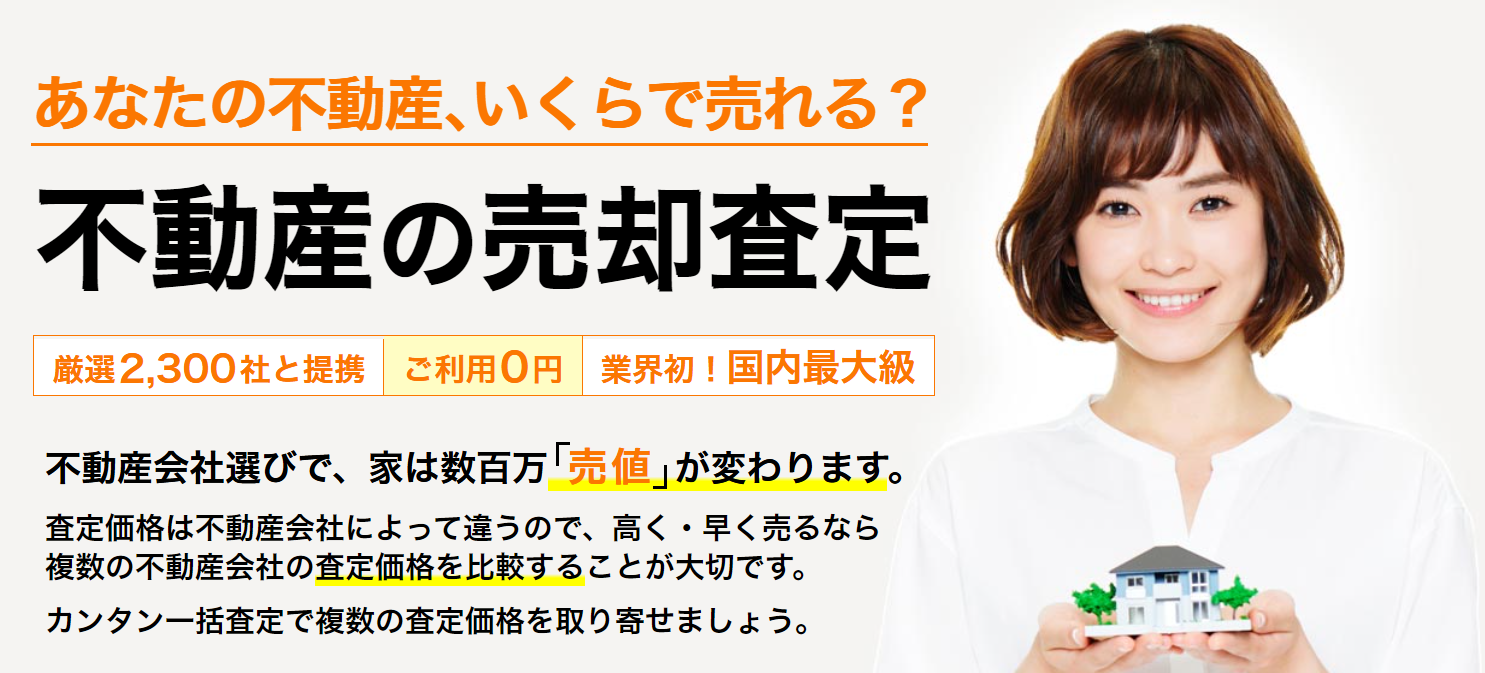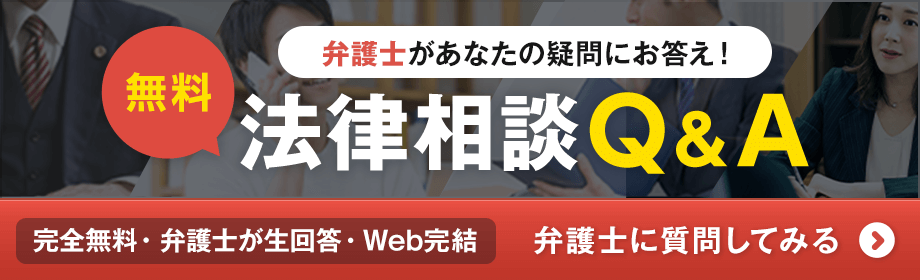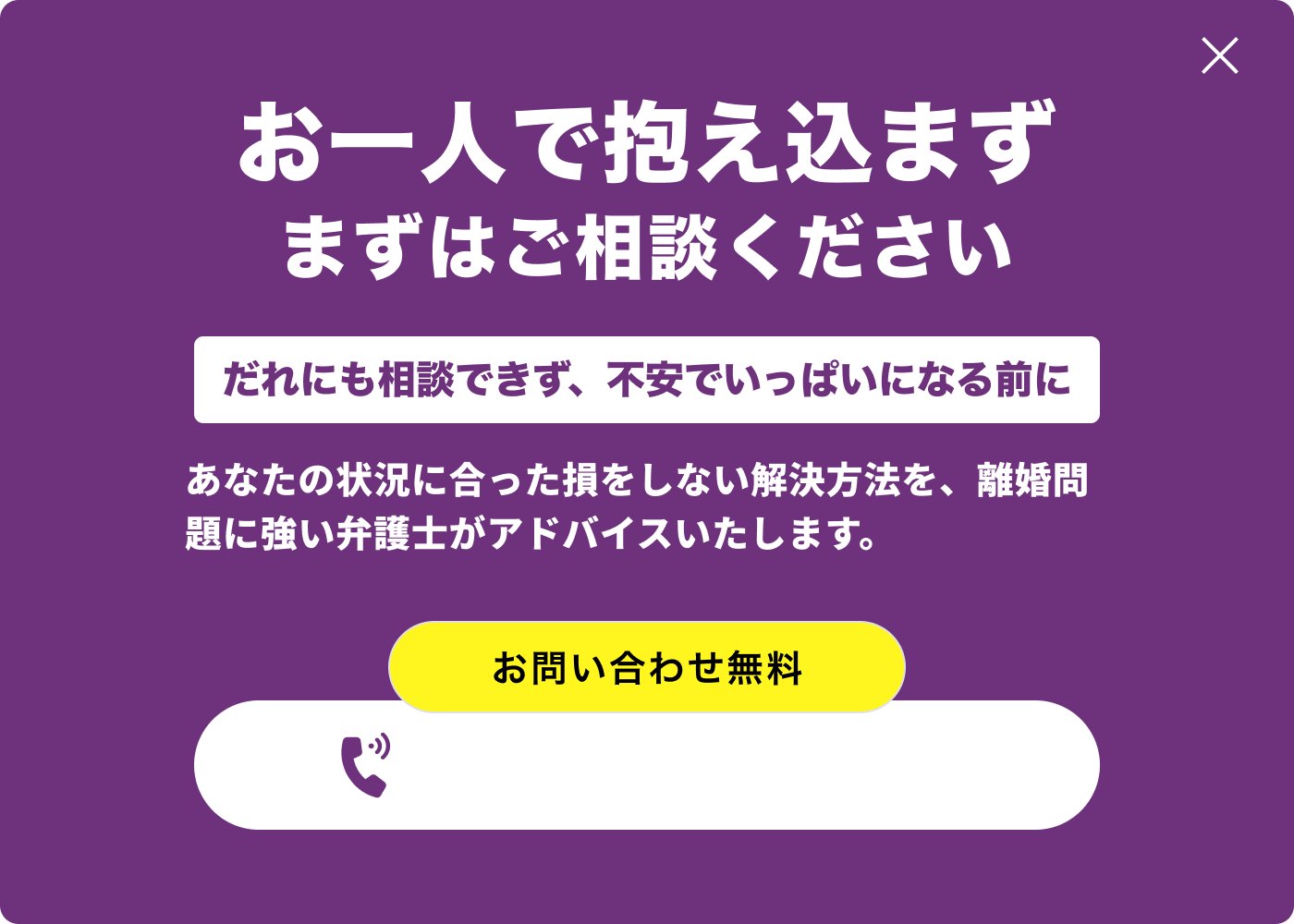本コンテンツには、紹介している商品(商材)の広告(リンク)を含みます。
ただし、当サイト内のランキングや商品(商材)の評価は、当社の調査やユーザーの口コミ収集等を考慮して作成しており、提携企業の商品(商材)を根拠なくPRするものではありません。
夫婦関係が悪化したときには離婚を考える方もいらっしゃるでしょう。そんな時に賢い離婚の仕方があれば知っておきたいですよね。
離婚するのは決して簡単な話ではなく、決めなければならないことがたくさんあります。やみくもに離婚することだけ決定してしまった後々取り返しの付かない事態になるのは避けたいですよね。
今回は離婚をする時に「有利な条件に」または「不利にならない」ようにするために考えておくべき5つのことについてお伝えしていきます。
離婚で損をしたくないあなたへ
配偶者と離婚することを検討していても、損はしたくない…と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、離婚で損をしないためには、まずは弁護士に相談することをおすすめします。離婚後の生活を考えて、あなたが損をしないよう法的観点からアドバイスをもらえるので、心強い味方となってくれるでしょう。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。
- 財産分与額や慰謝料、養育費の試算をしてもらえる
- 離婚交渉について法的観点からの注意点やアドバイスをもらえる
- 離婚までに準備しておくことを教えてもらえる
- 話を聞いてもらうことで精神的に楽になる
当サイトでは、離婚問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
離婚後の生活設計にお悩みの方へ
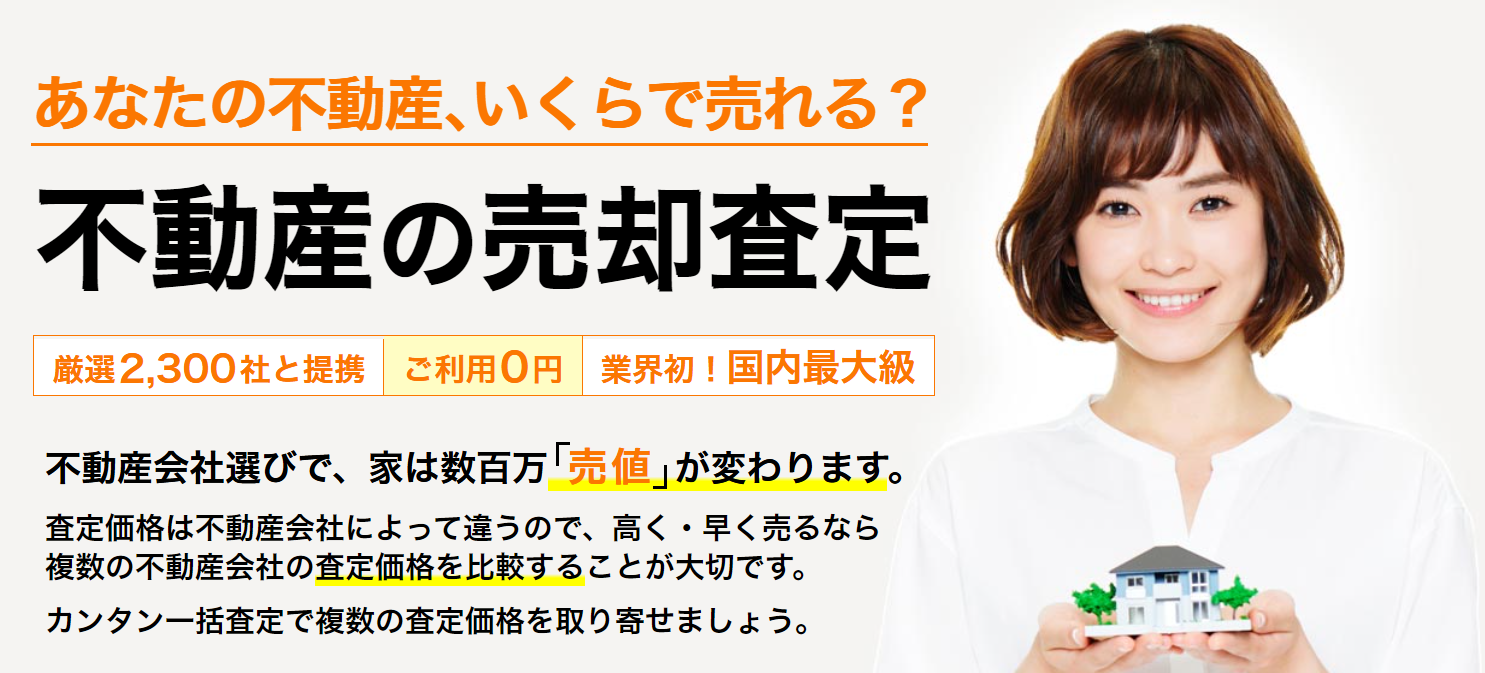
離婚検討時には様々な不安があります。
その中でも最も多いのが「離婚後の収入やお金の不安」です。
離婚後の生活設計に見通しを立てたい場合は、共有財産の中でも最も大きな割合を占めるご自宅の価格を確認すると良いでしょう。
入力はたったの1分で完了します。
まずは無料のAI査定で、ご自宅の価格をチェックしてみませんか?
1分で完了! 無料査定スタート
離婚をするときに考えなければならないのは
- 「慰謝料」
- 「財産分与」
- 「親権」
- 「養育費」
- 「離婚協議書の作成」
の5つです。
相手に嫌気が差していて一刻も早く離婚した気持ちもわかりますが、これらの項目をきちんと話し合わずに離婚してしまうと、後々大きなトラブルになる可能性があります。
それでは、それぞれの項目でどのようなことに注意しなければならないのか見ていきましょう。
参考:離婚の手順をスムーズに行うために知っておくべき6つのコト
まずはじめに、慰謝料についての基礎知識を知っておきましょう。
離婚慰謝料を請求できる人
「慰謝料」という言葉は日常的に耳に入ってきます。その意味は、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償です。離婚の場合の慰謝料は、離婚原因となる行為(不貞、暴力、モラハラ、理由なき同居の拒否、セックスレスなど)をした者に対する損害賠償請求です。
損害賠償とは違法行為によって他人に与えた損害を補填することです。すなわち、「慰謝料」とは、離婚の原因を作った者が、離婚相手の精神的苦痛を、お金によって穴埋めするものと言えるでしょう。
参考:離婚慰謝料の相場は?離婚理由など金額に影響する要素や請求方法を解説
1) 不貞行為(不倫)をされた人
相手が不倫をした場合、すなわち相手が自分以外の異性と肉体的関係を持つなどの行為を行っていた場合には、慰謝料請求が可能です。
しかし、相手が不倫をしていることは「疑わしい」という程度では足りず、「不倫」の事実が確実に立証される必要があります。確実に立証するために必要な浮気の証拠は自分で取ろうとしても無理があるのでプロの探偵に依頼することをお勧めします。
「不倫」の事実が立証されず、あくまで疑惑の範囲に留まる場合には、慰謝料を認められない、または認められても少額となる可能性が高いです。慰謝料をしっかりと請求し、さらに慰謝料額を引き上げたい人は「慰謝料相場と慰謝料を引き上げる重要な証拠」についてもチェックしてください。
不倫の完璧な証拠を手に入れるためには?
完璧な証拠を手に入れるためには、専門家の力を借りた方がいいでしょう。浮気調査の専門家である、探偵に相談してみませんか?
2) DVとモラハラの被害を受けた人
昨今、離婚の原因として取り上げられることの多いのが、DV(身体的暴力)とモラルハラスメント(言葉・精神的暴力)です。当然ながらこう言った事例でも慰謝料請求の対象になります。
【参考】
▶︎モラハラをする相手と離婚するために知るべき5つの知識
3) 理由なき別居があった人
夫婦にはそもそも同居・協力・助けあう義務があります。それの義務に反する行為があった場合は慰謝料を請求が可能となります。
例えば、夫が妻(専業主婦)に生活費を渡さない、理由がないのに同居を拒否する(家出)、妻と姑の関係が悪く妻が実家に帰ったままなどの状況が考えられます。
参考:悪意の遺棄となる行動と獲得できる慰謝料の相場
4) セックスレスだった人
夫婦片方が、性交渉を求めている状況でセックスレスとなった場合、慰謝料を請求できる場合があります。(参考→【慰謝料請求可能】セックスレス原因での浮気は違法なのか)
例えば、結婚後一度もセックスがないとか、セックスレスが原因で結婚生活が破綻したという場合には慰謝料を請求できる可能性があります。しかし、相手に身体的に性交渉が困難な場合(EDなど)の場合は、それを隠して相手が結婚したというような特別な場合でない限り、請求は難しいと思われます。
なお、重要なことですが、いずれの場合でもその事実を確実に証明する必要があるため、裏付けとなる証拠(メール、写真、音声、日記、診断書等)が必要となります。客観的な証拠は慰謝料の金額を左右する重要な要素となります。
離婚慰謝料を請求できない人
先ほど、離婚慰謝料を請求できる例を4つ挙げましたが、これらに該当する場合であっても、自分に責任・原因があり「お互い様」という場合には、慰謝料が認められないか、認められても大幅に減額されてしまう可能性があります。
一般的に、離婚の原因をどちらか一方が全て抱えているというケースは稀ではないでしょうか。双方に何らかの責任があるのが大半です。
例えば、性格の不一致・信仰上の対立・親族との仲違いなど、身に覚えがありませんか?このような場合は、どちらかに責任があると示すことは難しく、どちらかに責任があってもそもそもその原因を作ったのはもう一方の人だったりするのが普通です。
このような場合は、慰謝料を請求するべきかどうかも含めて、弁護士等の専門家に相談するべきでしょう。
相手が離婚に応じない場合、納得してもらうために「解決金」を支払うことがある
調停や裁判での和解によって成立する離婚では、「解決金」を支払う場合があります。解決金は発生原因(不貞・暴力)のある慰謝料とは異なり、これだけお金を支払うから別れてほしい、解決させようという趣旨のものです。
このような趣旨の解決金なので、相場はそれぞれのケースによってバラつきがあるため、安易に夫婦間で話を進めるのではなく、弁護士に相談することをおすすめします。
財産分与とは、夫婦が協力して築いた財産を、各々の貢献度に応じて分配すること言い、民法768条で規定され、基本的には夫妻共々半分にするのが一般的です。
(財産分与)第七百六十八条
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
引用元:民法第768条
法律で認められている権利ですので、きちんと夫婦間で取り決めをすることをオススメします。
2種類の財産分与|清算的と扶養的
①清算的財産分与
財産分与でメインとなるのは清算的財産分与です。夫婦として持っている財産は、共有財産とし離婚の際は互いの貢献度により公平に分配するという考え方です。
よって、離婚原因を作ってしまった側からも請求が可能となります。
②扶養的財産分与
離婚をした場合に夫婦の片方が生活をできなくなる場合に、生活の補助を目的とする扶養的財産分与が行われます。片方が病気、経済力に乏しい専業主婦、高齢である場合に認められます。
経済的に強い立場の配偶者が相手を扶養するため定められた額を定期的に支払う方法が一般的に採用されています。
共有財産と特有財産
財産分与を行う際、何が共同で築いた財産で、何が自分だけで作った財産(固有の財産)なのかを明確にする必要があります。
共有財産になるもの
基本的に共有財産としてみなされるものが、財産分与の対象になります。
- 現金
- 不動産
- 家具・家電
- 年金
- 預貯金や車
- 退職金
-
有価証券 など
共有財産としての判断が難しいものとしては、婚姻前から持っていたものやへそくり、別居したあとに得た財産などがありますが、基本的に別居後に取得された財産は、夫婦の力によって生まれた財産とならず、財産分与の対象となりません。
特有財産になるもの
特有財産に関しては民法第762条に下記のような規定があります。
(夫婦間における財産の帰属)第七百六十二条
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
引用元:民法第762条
「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産」とありますので、結婚する前から持っていた貯金や車、結婚中に買った家賃収入などは、独自の財産としてカウントされるということになりますね。
ただし、婚姻後に夫婦が協力したことによって価値が維持・増加された場合は、貢献度の割合に応じて財産分与の対象とされる場合もあります。
財産分与の分け方 専業主婦家庭と共働きの違い
財産分与の割合は基本的に半分にするとされていますが、夫婦の話し合いで自由に決めても問題ありません。実際に判断する基準としては、財産形成の貢献度、年齢、婚姻年数、資産、職業など様々です。
配偶者がひとりで生計を立てている場合
配偶者がひとりで生計を立てており、一方の配偶者が専業主婦(主夫)であった場合でも、家事労働などによって財産形成に貢献したと考えられます。受け取れる財産分与の割合は財産分与の対象になる財産に対しての貢献度によって決まります。以前は、貢献度の評価が50%を下回ることが少なくありませんでしたが、現在では専業主婦(主夫)の貢献度は原則50%として評価されます。
共働きの場合
共働きの場合の財産分与は50%の折半が基本です。夫婦の収入にめちゃくちゃ大きな差がない限り、50%の割合がそこまで開くことはないかと思います。
お金の問題 財産分与と慰謝料
ここまで書いてきたように、慰謝料と財産分与は性質が異なるものです。基本的には別々に算定して請求します。しかし、いずれも夫婦間での金銭問題なので、区別せず財産分与としてまとめることがあります。この場合、慰謝料的財産分与と呼ばれます。
このように、財産分与の内訳が事例によって異なってくるため、離婚の際はその内訳をはっきりさせておくことをおすすめします。
マンションの価格を手軽に知りたい方へ


ご存知でしょうか?
マンション価格は、AI査定ですぐに確認することができます。
マンション査定といえば
・手間と時間がかかる
・迷惑電話が掛かってくる
という印象をお持ちの方も多いでしょう。
すむたすなら、入力項目は6つだけ。
また、電話番号は不要なので、迷惑な営業もありません。
無料のAI査定で、ご自宅の価格をチェックしてみませんか?
※すむたすは首都圏のみ対応しております。 その他の地域の方はこちら。
1分で完了! 無料査定スタート 電話番号の入力なし
子供がいる場合は、親権についても取り決める必要があります。ここでは、親権についての基礎知識や親権を獲得する方法を解説します。
親権の獲得は女性の方が圧倒的に有利
離婚する際、未成年の子供がいれば必ず夫婦のどちらかが親権者となって、こどもの面倒を見る必要があります。法律上でも、未成年の子どもがいれば親権者決めないと離婚ができません。
(離婚又は認知の場合の親権者)第八百十九条
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
引用元:民法第819条
親権は親に与えられた権利といえば権利ですが、原則的に子供のためにある制度だと認識しましょう。親権に関する詳細な解説は「親権はどうやって決まる?子供の親権者を決める流れと知っておくべき基礎知識」をご確認ください。
ちなみに、調停や裁判で親権を争う場合は圧倒的に女性が有利だと言われています。特に未成年の子供の場合は父親よりも母親の愛が必要とみなされている傾向が強いからです。
それに、親権には監護権というのもありますから、子供を育てるために面倒を見るのは母親、父親はそのための養育費を支払いやすい環境にいるというのも大きな理由です。
親権者となるための判断材料
裁判で親権を決定される場合、どちらを親権者としたほうが子どもの利益になるかを第一に考えられます。具体的には、以下の点が判断材料となり総合的に判断されます。
- 子どもの意志
- 親権者の経済力
- 代わりに面倒を見てくれる人の有無
- 親権者の年齢や健康状態
- 住宅事情や学校関係などの生活環境
- 子どもの人数、それぞれの年齢や性別、発育状況
- 環境の変化による子どもへの影響度合い(見込み)
- 子ども本人の意思(10歳頃以上の場合)
上記のように、様々な事情を総合的に判断して行くため、母親が必ず親権者になれるとは言い切れませんが、それでも一般的には「親権の8割は母親が持つ」と言われています。よほど父親の方が親権者としてふさわしいと思われない限り、基本的には母親になるでしょう。
【関連記事】離婚で父親が親権を取るには?親権者になるポイントや手続きを解説
女性でも親権獲得が難しいケース
上記の通り、親権はだいたいの場合母親が持つとされています。それでも、母親が親権を獲得できないケースとはどんな状況でしょうか?考えられることは、上記した8つの判断材料が配偶者より下回った場合ではないでしょうか。
例えば、母親の健康状態が悪く長期の入院が決まっている場合や、子どもへの愛情が顕著に低い場合などが考えられます。
男性が親権を獲得するには
父親はフルタイムで仕事をしていることが多く、子供の面倒をみることが難しいと判断されやすいです。保育園、学童、民間の保育施設に預けながら養育するという方法もあり得ますが、必ずしもそれが子供の成長にプラスとなるものではありませんし、毎月のコストもかかります。
そのため、男性が親権を獲得するハードルは相当高く、上記のような判断条件を高い水準で満たす必要があります。そのため、男性が離婚にあたり親権を取りたいのであれば、弁護士への相談の必要は高いといえます。
もしあなたが父親で絶対に親権を獲得したいと思っているのであれば「離婚で父親が親権を取るには?親権者になるポイントや手続きを解説」もあわせてご確認いただくことをおすすめします。
子供がいる場合、離婚後でも養育費の支払いや受け取りが発生します。離婚前にしっかりと取り決めておくことで、後々のトラブルを防止できるでしょう。
養育費の金額は収入と子供の年齢に応じて決まる
養育費の支払い期間は、子供が18歳または20歳になるか、社会人として自立するまでが一般的です。明確には決められていませんので、「高校卒業」「20歳」「大学卒業」になるのかは、夫婦間で際的な範囲を模索してくのが良いかと思います。
養育費の相場は、3万~6万円/月と言われています。しかし、夫婦それぞれの経済状況や生活環境によって変化していきます。
養育費の金額は、裁判所でもある程度機械的に算定されており、インターネット上でも必要事項を入力すれば算定可能です。ただ、最終的な金額は、このような基準を目安としつつ、夫婦間の様々な事情を折り込みつつ両者の納得により合意するのが適切でしょう。
養育費は、あなたの子どもの生活費や教育費につかわれる費用です。夫婦間で子どもの生活を不自由がないものにするためにはどの程度の金額が必要なのか、きちんと話し合いましょう。
支払う側の経済状況によって金額が減ることもある
子どもの成長によって養育事情に変化が出てきますし、親権者の経済状況も時間の経過で変化する可能性があります。そのような変化があり、従前の養育費の金額では不相当といえる場合には、養育費の免除、増減額を求めることができます。
その場合、当事者間で再度金額を合意し直すのが適切ですが、合意がまとまらない場合には家庭裁判所に申請が必要となります。増額の理由として認められるものは、「入学・進学費用」、「病気や怪我などの治療費」、「親権者の収入の低下」などが挙げられます。
減額の理由として認められるものは、「支払う側の病気」、「支払う側の収入の低下」、「親権者の収入増」などが挙げられます。
ここまで書いてきたように、離婚をする際はまず夫婦で話合いの場をもちます。そこで離婚が決定して離婚届を提出する前に、一度立ち止まってください。話合いで離婚を成立させる場合、必ず離婚協議書を作成しましょう。
▶︎【サンプル付】離婚協議書の書き方と記載すべき内容|公正証書にする方法も解説
もし、離婚協議で決めた約束(慰謝料の支払いや・親権の有無など)を破った場合、離婚協議書がを残すことによって、約束した内容を明確に残す事ができ、そんなことはなかったという言い訳を防ぐことができます。
記載する内容としては、離婚の合意・慰謝料・財産分与・親権・養育費など、ここまで書いてきた事項が主になります。なお、公正証書とは、専門家である公証人が当事者双方の合意内容を確認して作成する公文書です。
したがって、通常の合意書よりも、証拠としての価値は比較的高いといえます。また、公正証書において特定の文言を記載すれば、通常は裁判手続を必要とするような場合でもこれを省略して強制的に支払いを求めることができます。
例えば、仮に支払いを取り決めた慰謝料や養育費の支払いが滞っている場合に、公正証書に所定文言の記載があれば、裁判を起こしその判決を待たずして強制的に回収手続きに入ることが出来ます。離婚協議書はネット上で検索することでもひな型を入手できます。離婚の話し合いの際は、離婚協議書の作成をおすすめします。
公正証書の効果や必要な手続きは「離婚時に公正証書を作成すべき理由と作成方法の手順」をご確認ください。
離婚したくても相手が離婚してくれない、といったトラブルはよくある話です。ここでは、相手が離婚に同意しない場合の対処法を解説します。
別居をしてみる
離婚に向けての話し合いがうまくいかない場合、裁判所での調停を行う方法があるとこの記事で紹介しました。ただ、法的手続は躊躇されるという場合、調停前にひとつの選択肢として、別居してみるというのはどうでしょうか。
同居し毎日顔を合わせながら離婚の話合いをするのは、精神的にも辛いですし、感情的な対立から話合いがうまくいかない可能性もあります。そのため、離婚の協議が進まなくなったら、離婚前でも別居を開始し、お互いに頭を冷やすのもあり得る方法といえます。
ただ、子どもがいる場合には、その後の親権のことに注意する必要があります。例えば、別居を開始する際に子供を残したままとして、相手が子供の監護を続けていた場合、一度手元から離れた子どもを連れ戻したり、その子の親権を取ることは通常よりも困難だということです。
離婚後に親権を持ちたい場合は子どもを連れて別居をすることも検討しましょう。離婚するために別居をお考えなら「別居から離婚する3つのメリット!損しないため別居前に知っておくべきこと」の内容も参考になると思います。
弁護士に依頼をする
弁護士への依頼は必要だろうけど、お金がかかりそうだな・・と思うかもしれません。しかし、ここまで書いてきたように、話合いで離婚が成立しない場合は、調停を行わざるを得ません。
そのため、「本気で離婚しようと思っている方」、「審判を有利に進めたい方」、「事務手続きの時間を省きたい方」はお金を払ってでも弁護士に依頼することをお考えください。
弁護士が離婚手続きで登場するのは主に調停までもつれ込むような場合です。調停では第三者の調停員を交えて夫婦間の話し合いが行われます。この時重要となるのが調停委員に対する印象です。弁護士を同席させることは、調停委員に自身の本気度合いを印象づけることができます。
調停が不調に終わると自動的に裁判官による審判に移ります。そこで裁判官が参考にするのは調停での中身や資料です。その質は弁護士がいるといないとでは、大きく変わってくる可能性が高いです。離婚調停にあたっては、多くの説明資料の作成が必要です。
仕事や家事に追われる中、不慣れな法律や判例を調べて資料を作る手間は大きいでしょう。その部分を弁護士に依頼すれば、専門的なアドバイスをもらいながら資料を作成してもらえるので、資料の質を上げつつ、自身の労力を節約できます。
ただ、弁護士に依頼するとなれば当然費用もかかります。離婚での弁護士費用や弁護士費用を抑える方法については「離婚にかかる弁護士費用はいくら?相場や内訳・支払いの際の注意点」で解説していますので、弁護士への依頼をお考えであれば参考にしてください。
今回の、賢い離婚の仕方についての内容はいかがでしたか?
繰り返しになりますが、離婚前には「慰謝料」、「財産分与」、「親権」、「養育費」、「離婚協議書」の5点について十分検討することをおすすめします。そして、話合いが行き詰まった場合は弁護士への相談をお考えください。この記事が少しでも皆さんの参考になれば幸いです。
離婚で損をしたくないあなたへ
配偶者と離婚することを検討していても、損はしたくない…と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、離婚で損をしないためには、まずは弁護士に相談することをおすすめします。離婚後の生活を考えて、あなたが損をしないよう法的観点からアドバイスをもらえるので、心強い味方となってくれるでしょう。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。
- 財産分与額や慰謝料、養育費の試算をしてもらえる
- 離婚交渉について法的観点からの注意点やアドバイスをもらえる
- 離婚までに準備しておくことを教えてもらえる
- 話を聞いてもらうことで精神的に楽になる
当サイトでは、離婚問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。