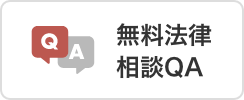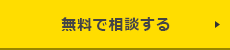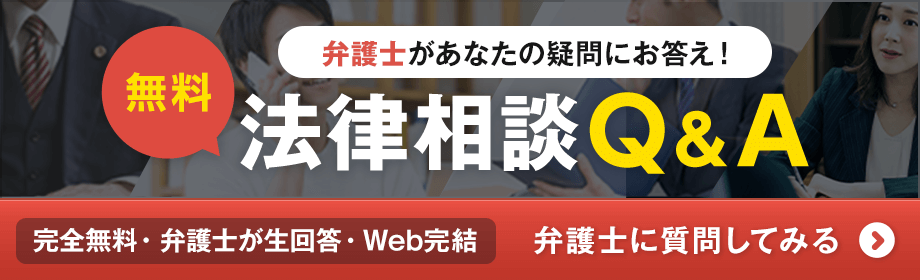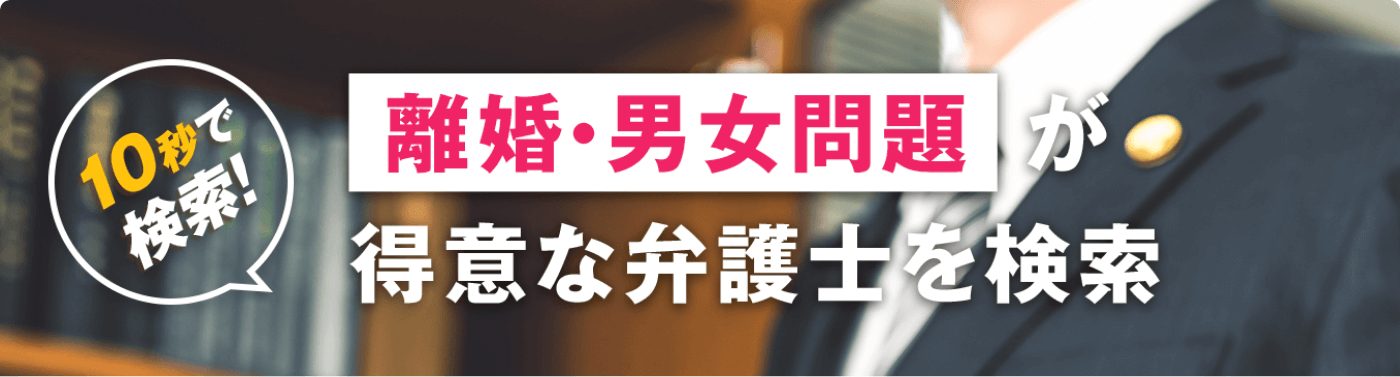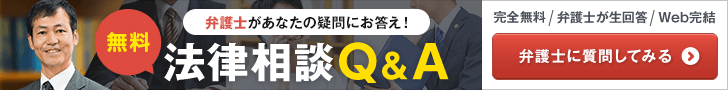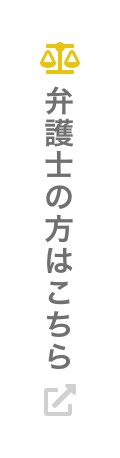本コンテンツには、紹介している商品(商材)の広告(リンク)を含みます。
ただし、当サイト内のランキングや商品(商材)の評価は、当社の調査やユーザーの口コミ収集等を考慮して作成しており、提携企業の商品(商材)を根拠なくPRするものではありません。

「財産分与」が得意な弁護士に相談して悩みを解決!
お悩み内容から探す
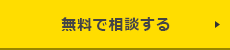
財産分与は、離婚後の経済状況に大きな影響を与えることもあり、離婚条件を決定するうえでもっとも争いが激しくなる要因のひとつです。
- 夫婦の財産はどうやって分けるの?
- どういった財産が対象になるの?
- ローンが残っている家はどういった扱いになるの?
財産分与について適切な判断をするためには、事前の対策が重要です。
本記事では、まず財産分与の基礎知識について説明したあと、財産分与の対象や流れ、注意点など財産分与について知っておくべきことを解説します。
この記事を参考に、財産分与への理解を深めて事前に対策を考えるようにしてください。
財産分与で損をしたくない方へ
財産分与の対象となるのは、「共有財産」に該当するものです。
ある財産が共有財産となるかどうかは、財産の名義によるのではなく、実質的な判断によります。
共有財産の判断や相手が財産を隠している場合の対処は、難しいことでしょう。
離婚の際に損をしたくないと考えている方は、弁護士への依頼がおすすめです。
依頼するメリットは次の通りです。
- 弁護士照会などにより財産分与の対象を正確に把握できる
- 配偶者との交渉を一任できる
- 調停・訴訟の対応をしてもらえる など
また養育費の交渉や慰謝料請求手続きなども任せることができます。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
離婚後の生活設計にお悩みの方へ

離婚検討時には様々な不安があります
その中でも最も多いのが「離婚後の収入やお金の不安」です。
離婚後の生活設計に見通しを立てたい場合は、共有財産の中でも最も大きな割合を占めるご自宅の価格を確認すると良いでしょう。
入力はたったの1分で完了します。
まずは無料のAI査定で、ご自宅の価格をチェックしてみませんか?
1分で完了! 無料査定スタート
この記事に記載の情報は2024年01月25日時点のものです
財産分与とは?財産分与の3つの種類
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同で築き上げた財産について、離婚のときに夫婦で分与することをいいます。
民法第768条には、以下のように定められています。
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
引用元:民法第768条|e-gov
財産分与には3つの性質があるとされており、それぞれ次のようなものがあります。
| 清算的財産分与 |
夫婦が協力して作った財産の公平な分配 |
| 扶養的財産分与 |
離婚後の相手方の生活保障 |
| 慰謝料的財産分与 |
離婚の有責配偶者による慰謝料 |
それぞれの財産分与の性質について確認しておきましょう。
清算的財産分与

清算的財産分与とは、結婚生活において夫婦間で協力して形成・維持してきた財産は、その名義にかかわらず夫婦の共有財産と考え、離婚時には公平に分配すべきという考えの基でおこなわれるものです。
例えば、婚姻期間中に働いて稼いだお金(現金・預貯金)、購入した物(家具、電化製品等)は、原則として「夫婦の協力で築いた財産」と考えられます。
清算的財産分与は離婚原因の有無などに左右されず、あくまで2人の財産を2人で分けるというものです。
したがって、離婚原因を作ってしまった有責配偶者の要求が認められない、というようなことはありません。
扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚したら一方の配偶者に経済的な不安が残る場合に、経済的援助を目的として、生活費として財産を分与するというものです。
財産分与の金額は当事者の状況を考慮して決めるべきものですが、夫婦の片方が病気であったり、経済力に乏しい専業主婦、高齢・病気であったりする場合に認められることがあります。
経済的に余裕のある方が余裕のない配偶者に対して離婚後も一定期間扶養するため、定期的に支払うという方法がとられることがあります。
【扶養的財産分与が認められるケース】
- 長年専業主婦をしていて、就職先が見つかるまでの間サポートが必要
- 長年専業主婦だった妻が病気等で就職が困難
慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、不倫など離婚の責任がある一方の配偶者が、慰謝料と財産分与をまとめて算定し「財産分与」とすることをいいます。
慰謝料は「精神的苦痛」に対して支払われるものですので、本来財産分与とは性質が異なります。
つまり、原則として両者は別々に算定されるものです。
しかし、いずれも金銭の問題ですので、慰謝料と財産分与を明確に区別せず、まとめて「財産分与」として請求したり、支払ったりすることがあります。
財産分与の割合はどうやって決める?
財産分与の割合は、基本的に夫婦の話し合いで取り決めます。
婚姻期間中に得た財産を2分の1ずつ分け合う(これを「2分の1ルール」という)ことを出発点として考え、個別的な事情があれば適宜考慮して決めることが多いです。
参考資料:第27表「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件数―財産分与の支払額別婚姻期間別―全家庭裁判所
夫婦が共働きの場合の割合
共働きの夫婦の場合、基本的には夫婦の収入の差に関係なく、財産分与は2分の1となります。
しかし、特段の事情がある場合には、財産形成・維持の寄与度に応じて割合を修正して考えるべき場合もあるでしょう。
配偶者が専業主婦の場合の割合
専業主婦の場合であっても、家事によって夫の労働を支え夫婦の財産形成に貢献したと考えられますので、財産分与の割合は原則として2分の1です。
しかし、個々の事情によってはそれよりも低く評価されるケースもあります。
なお、離婚によって専業主婦だった妻が生活に困窮するような場合には、扶養的財産分与が認められる可能性もあります。
子供がいる場合の割合
基本的に、子供がいるというだけで財産分与の割合が変わることはありません(原則通り2分の1)。
ただし、子供を育てる方の当事者が、離婚後の生活に困窮してしまうような場合、扶養的財産分与が認められることがあります。
なお未成年の子供がいる場合には養育費を請求することができますが、これは財産分与とは別の問題です。
財産分与の対象となる共有財産とそれぞれの計算方法

財産分与の対象となるのは、夫婦の財産のうち「共有財産」とされるものです。
共有財産とは、婚姻中に夫婦が協力して形成・維持された財産(結婚後に夫婦で築き上げた財産)のことです。
共有財産となるかどうかは、財産の名義によるのではなく、実質的な判断によります。
基本的にはプラスの財産はほとんどが対象になり、金銭だけではなく不動産なども含まれます。
ここでは、財産分与の対象となる共有財産について簡単に確認しておきましょう。
現金・預貯金
現金や預貯金に関しては、夫婦のどちらの名義であっても、また子供の名義のとしていたものであっても、婚姻期間中に夫婦の家計から捻出したものについては、財産分与の対象です。
離婚時の協議では、夫婦どちらも、自身が保有する現金・預貯金を開示して合計額を把握し、分与割合について協議するのが一般的です。
生命保険・学資保険
解約返戻金のある生命保険や学資保険についても、婚姻期間中に夫婦の家計から保険料を支払っていたものについては、財産分与の対象です。
こちらも、被保険者が夫婦のどちらかといった名義については関係ありません。
一般的には、保険会社に連絡をして解約返戻金を確認し、その金額に基づき財産分与額の協議をして決定します。
もちろん、保険を解約して、得た解約返戻金を分けるという方法もあります。
株券・出資金など
株券や出資金についても、夫婦の家計から支払って得たものに関しては財産分与の対象です。
株券に関しては、公開株式であれば時価によって評価します。
出資金についても、時価評価をして他の財産とともに分与割合を決めるのが一般的です。
車・宝石類など
車や宝石類などの動産についても、婚姻中に購入したものであれば財産分与の対象となります。
車は、ディーラーに査定を依頼するなどして評価額を決めることが多いです。
売却をする場合には、売却にかかった費用を差し引いて残った金額を財産分与の対象とすることがあります。
他方で売却をしない場合には、所有する側が所有しない側に評価額のうちの一定割合を支払うなどの方法がとられることが多いです。
持ち家・不動産
持ち家をはじめとした不動産も、財産分与の対象です。
不動産は、金額も大きく、財産分与の中でも大きなポイントの一つとなるでしょう。
不動産についても、査定をとり評価額を出してもらって分与の検討をすることが多いです。
売却してから分与する場合には、車のケースと同様、住宅ローンの残債務や売却にかかる費用などを差し引いて、残った金額について夫婦で分けることになるでしょう。
一方、売却しない場合には、所有する側が所有しない側へ評価額の一定割合を支払うことで財産分与をおこなうことが多いです。
なお、住宅ローンが残っている場合には、持ち家の評価額から住宅ローンの全額を差し引いた金額を分与の対象とするなどの調整をしたりします。
オーバーローンの場合
住宅を売却しても、住宅ローンの残債務が全額完済できないということもあります。
これを、オーバーローンと呼びます。
この場合、住宅を一方が取得するとともにその人がローンを負担し、オーバーローンの部分は他の財産の清算のなかで調整する、というケースがよく見られます。
なお、夫婦で連帯債務者であったり、夫婦の一方が債務者、もう一方が連帯保証人だったりなど、夫婦のどちらもがローンの契約者になっている場合は、離婚しても住宅ローンについての契約上の関係は解消できないケースもあるので注意してください。
退職金
退職金についても、近い将来退職金が支払われることがほぼ確実に見込まれる場合には、財産分与の対象となることがあります。
ただし、その場合でも必ずしも全額が対象となるわけではなく、婚姻期間(退職金形成に貢献した期間)に応じた部分が対象となるでしょう。
財産分与の対象とならない特有財産
特有財産とは「夫婦の一方が婚姻前から有する財産」と「婚姻中自己の名で得た財産」のことをいいます(民法762条1項)。
(夫婦間における財産の帰属)
第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
引用元:民法第762条|e-Gov法令検索
ここでは、この特有財産に該当し財産分与の対象にならないものについて確認しておきましょう。
結婚前に貯めたお金
結婚前に貯めたお金は、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産」に該当し、特有財産として財産分与の対象にはなりません。
別居後に築いた財産
離婚前に別居していた場合、別居後に築いた財産については基本的には財産分与の対象とはなりません。
基本的に財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産です。
別居後は共同生活をしておらず、夫婦が協力して築いた財産とみることは困難ですので、基本的には共有財産には該当せず財産分与の対象にはなりません。
子供の預貯金
子供名義の預貯金に関しては、夫婦の収入を原資としたものであれば、実質的には夫婦共有財産であり、財産分与の対象となります。
しかし、夫婦の収入を原資としたものであっても、子へ贈与されたものである場合や、子の自由な処分に委ねられたものに関しては、財産分与の対象とならないことがあります。
親戚からのお年玉や、子供が遺贈によって得た財産などが代表的な例です。
もっとも、子供名義の預貯金に関しては、長期にわたって混然一体となっており、それが夫婦の協力で築いた財産か、子への贈与などに該当するものかは判断がつきにくいこともあります。
財産分与の対象とするかどうかはケースバイケースで、夫婦間で協議をおこなう必要があるでしょう。
第三者名義の財産
第三者名義の財産は、財産分与の対象とはなりません。
代表的なものとしては、夫が経営者で、預貯金や不動産、車を会社名義で所有しているといったケースです。
会社名義の財産は夫の財産ではありませんので、財産分与の対象にはなりません。
年金
年金は財産分与の対象とはなりません。
しかし、「年金分割」という別の仕組みで分割することがあります。
年金分割とは、夫婦が婚姻期間中に納めた「厚生年金」と「共済年金」の年金保険料の実績について、夫婦間で分割するというもので、基本的に2分の1の割合で分割されます。
同じ公的年金ですが、国民年金は対象になりませんので注意してください。
財産分与の対象になるか判断が難しいもの
ここまで解説した財産以外について、「これって財産分与の対象になるのだろうか?」と判断が難しいものが頭に浮かんでいる人もいるでしょう。
ここでは、財産分与の対象になるか判断が難しいものについて、対象となるかどうか確認しておきましょう。
夫名義の預金
夫名義であれ、妻名義であれ、財産分与の対象となるかどうかは、共有財産に該当するか、つまり「婚姻中に夫婦で協力して築き上げた財産かどうか」が判断基準となります。
夫名義の預金であっても、それが夫婦の協力で築いたものであれば財産分与の対象となります。
一方、婚姻前からの預貯金であって共有財産に該当しなければ、当然に財産分与の対象にはなりません。
入籍前の同棲期間中の財産
入籍前の同棲期間中の財産についても、夫婦で協力して築いた財産があった場合には、財産分与の対象となりえます。
へそくり
へそくりは、夫婦共同生活のための預貯金と同じ性質ですので、原則として財産分与の対象になります。
両親に出してもらったお金
一方の親から夫婦の一方へ贈与されたお金は、原則としては特有財産であり、財産分与の対象にはなりません。
しかし、夫婦の生活費の援助のために出してもらったお金など、夫婦の共同生活のために出してもらったお金は共有財産と評価される可能性もあるので、注意が必要です。
配偶者の隠し財産を調査する方法
財産分与を有利に進めたいがために、相手方が自分の所有している財産について開示しないということもあるでしょう。
そのような場合の対策について確認しておきましょう。
別居前に調査
可能であれば、別居前にあなた自身で調査できればベストです。
財産隠しの手段として多いのは、現金を相手の目につきにくい場所に保管するケースです。
めったに開けない引き出しの奥にへそくりを隠していることや、最近では複数の電子マネーに分散させる方法も考えられます。
有価証券の資料や貴金属も、貸金庫や実家など相手の目の届かないところに隠している場合があります。
同居中に夫婦相互に財産情報を共有しておくのが基本ですが、その他自宅に隠されている財産はないかできるだけ調べておくとよいでしょう。
弁護士会照会
弁護士会照会とは、弁護士が訴訟その他裁判所での手続をおこなうために弁護士法23条の2に基づいて必要な資料や証拠を収集し、調査することができる制度です。
(報告の請求)
第二十三条の二 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
引用元:弁護士法第23条の2
弁護士でないと使えない手段であるため、弁護士照会を利用するためには弁護士に事件を依頼する必要があります。
しかし、事案によっては弁護士会が照会を認めない場合や、照会先が回答を拒否する場合もありますので必ず調査できるとは限りません。
調査嘱託
調査嘱託とは、裁判所から金融機関や会社に対して、預金口座の有無や残高などの情報開示を求める制度です。
弁護士会照会と異なり、調査嘱託は裁判所を介した調査手法です。
調査嘱託を利用することによって、相手名義の口座に関する取引情報について回答を得て隠された財産を突き止められる可能性が高まります。
なお、調査嘱託をする場合、相手方の口座の銀行名や支店名は特定する必要があることには注意が必要です。
負債・借金などのマイナスの財産はどのように扱う?
マイナスの財産がある場合には、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかによって扱いが異なります。
プラスの財産の方が多い場合には、プラスの財産とマイナスの財産を通算してから、財産分与をおこないます。
一方、マイナスの財産の方が多い場合には、マイナスの財産については財産分与の対象とはならず、夫婦のどちらか一方が引き継ぐことになります。
財産分与を決め方とは?話し合いで決める場合の流れ

財産分与は、一般的には夫婦間の協議でどういった割合で分けるか決定します。
ここでは、財産分与を決めるまでの流れについて確認しておきましょう。
財産をすべて把握し整理する
まず、財産のすべてを把握するために一覧表を作成します。
夫婦でどのくらいの財産を持っているのかをまとめ、整理することが大切です。
また、家や車など、自分たちで正確な評価が難しいものは、専門家に査定してもらうとより公平な財産分与が期待できます。
有価証券などの価値が変動する財産は時価の評価をおこなう必要があります。
借金についても調査して整理する
借金がある場合には、調査して負債額がいくらなのか整理します。
借金額が自分たちで把握できない場合には、信用情報機関に問い合わせるとよいでしょう。
日本には「CIC」「JICC」「KSC」という3つの信用情報機関があり情報を把握していますので、開示請求を依頼してください。
財産分与の割合を決定する
分与対象をすべて把握し整理したら、財産分与の割合を決めます。
原則2分の1ずつにしますが、お互いが合意すればどのような割合も可能です。
また、別途慰謝料を請求する予定である場合には、割合を決める際に慰謝料は別ということを明確にしておく必要もあるでしょう。
財産を引き継ぐか決める
共同財産のうち、誰がどの財産を取得するか決めます。
どちらが何を引き継ぐかに明確な決まりはありません。
話し合いで決まらなかった場合は、『離婚調停』内で話し合いをおこないましょう。
第三者を間に入れることにより、お互い冷静に話し合うことができるのでトラブルを回避することが期待できます。
離婚協議書を作成する
すべての話し合いがまとまったら離婚協議書を作成しましょう。
これには財産分与の他に慰謝料や養育費など離婚に関する条件を記載しておきます。
口約束では支払いがされなくなったときに対処することができませんが、離婚協議書を作成することにより、それを証拠として、後の裁判等で利用することが可能になります。
離婚協議書は、強制執行認諾文言を付した公正証書で作成することにより、支払いが途絶えた際に訴訟手続きをすることなく、強制執行をおこなうことができます。
具体的な離婚協議書の内容、作成方法については、弁護士にご相談ください。
離婚調停・裁判で財産分与を争う際の手順とかかる費用
夫婦での協議で財産分与の割合を決められない場合には、調停や裁判で解決しなければなりません。
ここでは、調停や訴訟での手順について確認しておきましょう。
1.離婚調停で決める
申し立てに必要な書類を用意する
- 申立書(財産目録を含む)
- 事情説明書
- 連絡先等の届出書
- 進行に関する照会回答書
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)※3か月以内に発行されたもの
- 夫婦の財産に関する資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳写し等)
申し立てに必要な費用
- 収入印紙:1200円
- 連絡用の郵便切手:1000円程度(※各家庭裁判所によって異なる)
申し立て先
原則は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
ただし、申立書と共に管轄合意書を提出する場合は、その家庭裁判所でも調停をすることができます。
2.離婚裁判で決める
離婚調停でも決着がつかない場合は、離婚訴訟を提起することになります。
裁判には離婚原因が必要
訴訟を提起する場合、法律が定める離婚の原因(民法第770条1項各号)が必要になります。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
- その他、婚姻を継続しがたい重大な事由
離婚裁判の流れ
離婚裁判は以下の流れで進みます。
- 訴状の作成
- 裁判所へ訴状の提出
- 相手方へ訴状の送達
- 第一回口頭弁論期日の決定
- 数回の期日を繰り返す(※和解が成立する場合もある)
- 判決
裁判では証拠が重要
裁判では、離婚協議や離婚調停の場合と比較すると、証拠の重要性が大きく増します。
きちんと証拠を揃えて財産分与の請求することが必要です。
3.財産分与の受け取り方
財産分与の額が決まった場合は、その受け取り方も決めておかなければなりません。
特にお金を受け取る立場の場合には、以下のような受け取り方が考えられますが、可能な限り早く支払いを受けるようにするとよいでしょう。
一括払いの場合
金額が大きくなると難しくなる場合もありますが、一括で支払ってもらうことが原則になるでしょう。
均等分割
相手の収入・資産を考えると分割でしか支払えないという場合は、分割での支払もやむを得ません。
注意すべきは、あまりにも長い支払期間を設けると、リストラ等の相手の経済状況の悪化によって支払いが滞るリスクがあるという点です。
初回は大きくもらう
上記のリスクを考慮して、分割払いであっても、例えば財産分与で800万円の支払が決まった場合、「初回の支払を半分の400万円で設定し、翌月以降は月10万円ずつ支払ってもらう」といった方法も考えられます。
4.弁護士に依頼した際の費用
調停や訴訟を弁護士に依頼した場合、当然費用がかかります。
費用は「着手金」「報酬金」の他、「相談料」や「実費」などがかかることが多いです。
離婚事件を依頼した場合の弁護士費用の相場は、どのような手続を依頼するかによって変わりますが、着手金・報酬金それぞれ50万円~70万円程度でしょう。
ただし、争点が多かったり、請求するものが多かったりする場合にはさらに金額が上がる可能性があります。
費用については事前に弁護士に確認しておくようにしましょう。
弁護士費用の例
財産分与を含む離婚事件を依頼した場合の費用例は次の通りです。
| 費用項目 |
内容 |
金額 |
| 相談料 |
依頼前の相談時にかかる費用 |
1万円 |
| 着手金 |
弁護士に実務をおこなってもらうためにかかる費用 |
20万円 |
| 報酬金 |
依頼が成功した時にかかる費用 |
30万円 |
| 実費 |
書類作成や交通費などの実費としてかかる費用 |
5万円 |
| 日当 |
裁判所での対応など、事務所以外で仕事をしたときにかかる費用 |
5万円 |
| 合計 |
61万円 |
なお、上記はあくまで一例です。
弁護士事務所によって費用体系が異なりますので、事前にいくつか見積もりを取って比較検討するとよいでしょう。
知らないと損する!財産分与で気を付けるべき注意点
財産分与をおこなう際に気をつけるべき注意点などを確認しておきましょう。
財産分与は原則非課税だけど税がかかる場合がある
財産分与は、現金で支払われたときには、分与する側も、受け取る側も原則非課税です。
しかし、あまりにも高額な財産と判断された場合には、受け取る側に贈与税がかかる場合があります。
また、不動産の場合には、受け取る側に不動産取得税が、分与する側に譲渡所得税がかかる場合があります。
| |
妻(受け取る側) |
夫(払う側) |
| 現金・預金 |
課税なし |
課税なし |
| 不動産 |
不動産取得税 |
譲渡所得税 |
財産分与の請求権は2年で請求できなくなる
財産分与は離婚と同時におこなうのが基本です。
もし取り決めがなかった場合でも財産分与の請求は可能ですが、離婚時から2年以内の期限があり、これを過ぎると請求できなくなってしまいます。
期間制限にはくれぐれも注意しましょう。
なお、「離婚時」とは、離婚方法によって異なります。
- 協議離婚:離婚届が受理された日
- 調停離婚:調停が成立した日
- 裁判離婚:判決が確定した日
一度放棄した請求権は取り戻せない
離婚する際に、財産分与の請求はしないと請求権を放棄した場合、後になってやっぱりやめたいと思っても、原則として請求権は取り戻せません。
ただし、相手の合意が得られる場合や錯誤があった場合、脅迫などによってそうした約束をさせられた場合など特別の事情がある場合は、財産分与の請求ができる可能性があります。
このような場合も弁護士に相談してみましょう。
配偶者に共有財産を使い込こまれてしまった場合
離婚時に貯金等の共有財産の使い込みが発覚した場合、その分の金額を財産分与に反映させることができる場合があります。
この場合、「相手が共有財産を使い込んだ」ということを証明できるかどうかが問題です。
ただ、日常生活に通常必要な費用については、配偶者に無断で使っても「使い込み」とはいえません。
「使い込み」というためには、使途が、日常生活に必要とは言えないもの(過度な浪費や別居のための費用、不貞行為のための費用等)であると言えることが前提になります。
また、「使い込み」の程度も関係します。
趣味や娯楽にある程度お金を使うことは認められるでしょうから、それだけでは「使い込み」とは判断されないでしょう。
収入と支出のバランス等、個々の事情を考慮して判断されることになると思われます。
なお、結婚前に貯めた自分の貯金から支出した場合は、特有財産からの支出となるため、夫婦共有財産の使い込みには当たりません。
離婚時の財産分与問題を弁護士に相談・依頼するメリット
財産分与について弁護士に相談するメリットは次の3つが挙げられます。
- 財産分与の対象を正確に把握できる
- 2分の1よりも多い割合を獲得できる可能性がある
- 交渉や調停・訴訟を任せられる
お伝えしたとおり、財産分与の対象となるのは、「共有財産」に該当するものです。
とはいえ、あなた自身ではどれが「共有財産」に該当するか判断が難しいというケースもあるでしょう。
弁護士であれば個別の事情を鑑みながら、財産分与の対象となるかならないかについて正確な判断ができますし、相手方が財産の開示に応じない場合には弁護士照会で相手の財産を把握することも可能になります。
また、弁護士に依頼すると2分の1よりも多い割合を獲得できる可能性が高まります。
とくに、財産分与が「扶養的財産分与」や「慰謝料的財産分与」としての性質を有するケースでは、弁護士が適切に交渉することによって相手方の譲歩を引き出し、より多い財産分与を実現できる可能性が高まるのです。
また、交渉だけでなく、調停や訴訟にまで移行した場合には、弁護士への依頼は必要不可欠だと理解してください。
交渉の場面だけでなく、調停や裁判になると、より法的な根拠に基づいた主張・立証をしなければなりません。
特に、調停や裁判とまでなると、法的知識のほか、調停委員とのやり取りに慣れているか、裁判で適切に主張・立証できるかなどによって、財産分与額が大きく変わってしまう可能性があるのです。
これらの手続きについて弁護士に依頼すれば、より有利に財産分与を進められる可能性が高まります。
財産分与は離婚条件の中でも激しく争われるものの1つで、非常にシビアな交渉になることも少なくありません。
財産分与に不安がある場合には、ぜひ弁護士に相談するようにしてください。
【関連記事】離婚問題を弁護士に無料相談できる窓口|相談すべきケースやタイミング、選び方を解説
財産分与トラブルの解決が得意な弁護士を選ぶ3つのポイント

財産分与のトラブルは弁護士に依頼することをおすすめしますが、弁護士であればだれでもよいかというと、そうとは言えません。
弁護士選びに失敗してしまうと、望んだような財産分与が実現できないだけでなく、弁護士費用だけかかってしまったという事態になりかねないからです。
ここでは、どういったポイントで弁護士を選ぶべきかについて確認しておきましょう。
1.財産分与を扱った実績があるかどうか
依頼する弁護士が、財産分与をはじめとした離婚トラブルに注力しているかというのは、もっとも重要なポイントです。
なぜなら、弁護士が取り扱う法律分野は多岐にわたり、すべての弁護士が離婚実務について知見や経験をもち合わせているということはないからです。
もし、離婚に注力していない弁護士に依頼してしまうと、「本来よりも少ない額しか分与できなかった」といった不利益を被る可能性があります。
相談する際は、離婚トラブルに注力している弁護士を選ぶようにしてください。
なお、離婚問題弁護士ナビは、離婚トラブルに注力している弁護士を多数掲載しており、お住いの地域を選ぶと一覧で弁護士事務所が表示され、比較検討したうえで相談先を選べるサイトです。
相談料無料の事務所も多数掲載していますので、ぜひ活用してください。
2.信頼できるかどうか
次に重要となるのが、「信頼できるかどうか」です。
「信頼できるかどうか」は、「自分と相性が合うかどうか」に置き換えてもよいかもしれません。
信頼できるか、相性が合うかが重要な理由は、財産分与についてのトラブルは弁護士と二人三脚で進めることも少なくないからです。
連絡を取り合う中で「相性がよくないな」と感じ、返答が億劫になって先延ばしにしてしまうと、弁護士がスムーズに事件を処理できず、有利な財産分与を実現できないことにつながりかねません。
相談時には、「信頼できるか」「相性が合うか」といった面についても確認するようにしてください。
3.複数の弁護士に相談してみて比較する
複数の弁護士に相談して、比較検討することも重要です。
比較の内容としては、「解決についての方針はどういったものか」と「弁護士費用はどうか」という2点を重視するとよいでしょう。
実は、弁護士であっても「相談を聞いたうえでどういった解決が見込めるか」には違いがあるケースもみられます。
一方の弁護士は「2分の1程度が現実的な割合です」と返答するけれど、もう一方の弁護士は「慰謝料も分与に含めてより多い財産分与を実現できる可能性がある」と回答することも考えられるのです。
どういった解決方針を目指せるかについて比較検討し、あなたの希望に近い返答をしてくれた弁護士を選ぶとよいでしょう。
また、弁護士費用も事務所によって違いがあります。
複数の事務所に見積もりを出してもらい、相性やどういった解決を目指すのかについても勘案しながら、弁護士を選ぶとよいでしょう。
【関連記事】離婚問題を弁護士に無料相談できる窓口|相談すべきケースやタイミング、選び方を解説
最後に|財産分与で不安なことがあるなら弁護士に相談しよう
財産分与の対応が不安な方は、弁護士のサポートを得るのが効果的です。
財産状況の把握や交渉対応など、必要な手続きを代理でおこなってもらうことで、スムーズな財産分与が望めます。
費用が気になる方も、無料相談可能な事務所も多くありますので、まずは気軽に相談することをおすすめします。
財産分与で損をしたくない方へ
財産分与の対象となるのは、「共有財産」に該当するものです。
ある財産が共有財産となるかどうかは、財産の名義によるのではなく、実質的な判断によります。
共有財産の判断や相手が財産を隠している場合の対処は、難しいことでしょう。
離婚の際に損をしたくないと考えている方は、弁護士への依頼がおすすめです。
依頼するメリットは次の通りです。
- 弁護士照会などにより財産分与の対象を正確に把握できる
- 配偶者との交渉を一任できる
- 調停・訴訟の対応をしてもらえる など
また養育費の交渉や慰謝料請求手続きなども任せることができます。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。