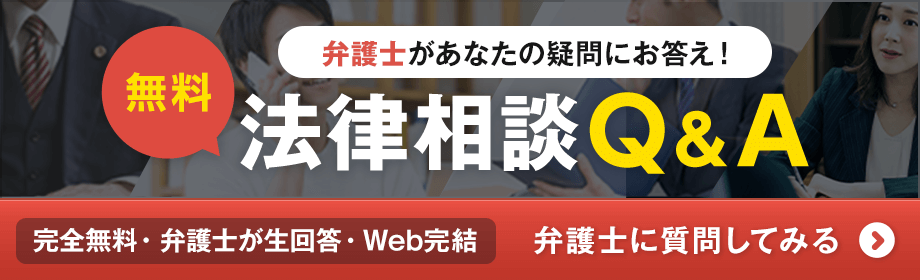婚姻とは1組の男女が法律上の夫婦となること|婚姻の要件と効果とは


婚姻(こんいん)とは男女の婚姻意思が合致して夫婦になることをいいます。民法上では婚姻という言葉を使いますが、世間一般では結婚という言葉が使われることが多いようです。
婚姻には事実上婚姻意思が合致している事実婚と婚姻届が提出される法律婚の2つがありますが、世間一般で「婚姻」「結婚」と言った場合には後者を指す場合がほとんどです。婚姻関係となった夫婦の間には事実婚・法律婚を問わず互いにいくつかの義務が生じます。この記事では婚姻とはどういったものなのかをわかりやすく説明した後に、婚姻の条件や効果を解説します。
※この記事は2022年5月の情報をもとに作成しています
婚姻とは

婚姻とは、男女の婚姻意思が合致して夫婦となる身分行為です。そして法律的にも夫婦として認められるためには婚姻意思が合致するだけでなく、役所に婚姻届を提出する必要があります。一般的に結婚といった場合は、このような法律婚を意味することがほとんどです。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
引用:日本国憲法
(婚姻の届出)
第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
引用:民法
なお、婚姻届を提出する行為を入籍と言ったりもします。入籍は厳密には他人の戸籍に入ることを意味しますが、結婚と同じ意味で使われることが多いです。
|
婚姻とは |
婚姻意思が合致して夫婦になること |
|---|---|
|
結婚とは |
法律婚をすること |
|
入籍とは |
他の人の戸籍に入ることだが結婚と同義で用いられることが多い |
婚姻の要件

婚姻関係は男女の意思の合致により成立するのが原則です。そのため、男女が相互に婚姻意思を有する状態となっていれば、婚姻関係は認められます。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
引用:日本国憲法
しかし、このような事実婚を超えて法律婚まで認めるためには以下のような要件を満たす必要があります。
- 婚姻適齢であること
- 重婚ではないこと
- 近親婚ではないこと
- 再婚禁止期間を過ぎていること など
婚姻適齢であること
男女ともに婚姻年齢は18歳以上です。
2022年4月の法改正で成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより、18歳以上であれば親の同意なく婚姻が可能になりました。
(婚姻適齢)
第七百三十一条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
引用:民法
なお、誕生日が2006年4月1日までの女性は、2022年4月1日以前と変わらず、18歳未満であっても婚姻が可能です。その場合には親の同意書が必要になります。
単婚であること
日本は一夫一妻制をとっているため、一度に結婚できる相手は一人のみです。そのため、既に法律婚状態にある男女は離婚等により当該状態を解消しない限り、別の異性との結婚届を提出することはできません(提出しても受理されません)。
なお、本規定は一応重婚となる事実婚も禁止するものではありますが、このような事実婚が法的に保護されるのかされないのかはケース・バイ・ケースとなるでしょう。
(重婚の禁止)
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
引用:民法
3親等以外であること
婚姻は祖父母、父母、子、孫などの直系血族や叔父叔母、兄弟、甥などの3親等以内の血族とは認められません。
(近親者間の婚姻の禁止)
第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
引用:民法
(直系姻族間の婚姻の禁止)
第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
引用:民法
(養親子等の間の婚姻の禁止)
第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
引用:民法
養子と養親の傍系血族(兄弟姉妹、おじ・おば、おい・めいなど)との婚姻は認められています。また、いとこなど4親等以上の親族との結婚は許されています。
再婚禁止期間を過ぎていること
妊娠している女性が再婚する場合、前の婚姻を解消してから100日以上経過していなければ婚姻は認められません。これは父子関係を明確にする制度ではありますが、現在はDNA鑑定で親子関係を証明することができますから、時代遅れの制度と言えるかもしれません。
なお、善婚解消時に妊娠していない場合や前婚解消後に出産済の場合には再婚禁止期間を待たずに婚姻が認められます。
(再婚禁止期間)
第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
引用:民法
婚姻の効果

婚姻関係(事実婚を含みます)が成立したことによって生じる効果を解説します。主に相互扶助義務・生活費分担義務・貞操義務などがあります。
相互扶助義務
民法では夫婦間で助け合い生活をする相互扶助義務や一緒に生活をする同居義務を定めています。
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
引用:民法
夫婦ですから当然といえば当然ですが、生活を共にして協力し合うことが義務となっています。もちろん同規定により同居や協力を物理的に強制されることはありませんが、これらの義務に正当な理由なく違反すれば何らかの法的責任を負う可能性はあります。
生活費分担義務
夫婦には資産や収入に応じて生活費、医療費、教育費などを分担して負担する義務があります。この義務は別居していたとしても、婚姻関係が破綻していない限り当然には消滅しません。
(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
引用:民法
貞操義務
民法で夫婦は互いに貞操義務を負うことが明確に定められているわけではありませんが、解釈上、婚姻関係にある夫婦は、配偶者以外の者と性的関係を持ってはならないと考えられています。不貞行為とはこの貞操義務に違反する行為のことです。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
引用:民法
婚姻の終了

婚姻関係の終了は事実婚と法律婚で異なります。事実婚の場合は夫婦の離婚意思が合致すれば直ちに離婚となります。他方、法律婚の場合は離婚意思の合致だけでなく、離婚届が受理される必要があります。
なお、相手配偶者が死亡した場合、事実婚であれ法律婚であれ婚姻関係自体は消滅しますが、相手配偶者との姻族関係は当然には消滅しません。姻族関係を消滅させるためには姻族関係終了の手続が必要です。
まとめ
婚姻について簡単に説明しました。婚姻に事実婚と法律婚があることは覚えておいて損はないでしょう。
事実婚であれ法律婚であれ婚姻関係を結ぶと当事者間には様々な義務が生じます。実生活でこれらの義務を意識することは多くないかもしれませんが、夫婦の関係性や生活に直結する内容でもありますので、一度確認しておくとよいかもしれません。


◆辛い胸の内をまずお聞かせください◆デリケートな問題だからこそあなたの心に寄り添い、新たな一歩を力強くサポートします!お子様の将来やお金の不安をなくすため<離婚後も徹底サポート>をお約束します◎
事務所詳細を見る
【初回相談0円・クレカ決済可】【女性弁護士・歴10年以上のベテラン弁護士在籍】|慰謝料・財産分与など、離婚条件のお悩みなら|≪雑誌ananにて紹介されました!≫|※夜間・早朝のご相談は、原則営業時間内にご返信します※
事務所詳細を見る
【全国対応】離婚・不貞問題、貴方の「権利」と「未来」を徹底的に守り抜きます。 感情論で終わらせず、法的ロードマップと生活設計で、一日も早い再出発を強力サポート。一人で悩まず、まずはご相談を。【24時間・オンライン完結・初回相談無料】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

その他に関する新着コラム
-
子どもの連れ去りは、状況によって違法となるケースがあります。本記事では、子どもの連れ去りが違法となるケース・違法とならないケースの具体例や、連れ去りが発覚した際...
-
配偶者の不機嫌な態度、いわゆるフキハラ(不機嫌ハラスメント)に悩んでいませんか?無視されたり威圧的な態度をとられたりといった行為は、フキハラといえます。この記事...
-
調査官調査とは、親権について争いがある場合におこなわれる調査です。必ずおこなわれるわけではなく、事件が長引きそうなときや裁判所が判断しにくいケースで実施されます...
-
育児放棄を理由に離婚することは可能です。ただし、裁判離婚で離婚が認められるには「法定離婚事由」に該当する必要があり、単なるワンオペ育児では認められない可能性が高...
-
パートナーが統合失調症で、離婚を考えていませんか?話し合いで離婚できない場合の手続きや、裁判になった場合の「法定離婚事由」について詳しく解説。離婚が認められない...
-
妻が勝手に家出した場合、離婚や慰謝料請求が認められますが、家出に正当な理由がある場合は認められないため注意しましょう。本記事では、妻が家出した場合の離婚や慰謝料...
-
夫の家出は「悪意の遺棄」として離婚理由になる可能性があります。生活費や慰謝料の請求も可能です。本記事を読めば、離婚を有利に進めるための証拠集めや法的手続きの全ス...
-
離婚届を書き間違えても焦る必要はありません。原則として、訂正印などは不要で、一部を除いて記載者本人以外の代筆による訂正も可能です。本記事では、離婚届を書き間違え...
-
本記事では、離婚時のマンションの選択肢3選をはじめ、売却で失敗しないための査定のタイミングや手続きの流れ、ローンの残債別(アンダーローン、オーバーローン)それぞ...
-
妊娠中の別れは、感情的な問題だけでなく、法律上の義務や経済的負担が大きく関わるデリケートな問題です。 妊娠中の彼女・妻と別れることが可能かどうか、そして別れた...
その他に関する人気コラム
-
事実婚をする人の中には同性であったり夫婦別姓が認められないために事実婚を選択していたりとさまざまなケースがあります。この記事では事実婚と認められるための要件や要...
-
【弁護士監修】夫や妻と離婚したくない場合に、どうすればよいのかわからない方に対して、今すべきこととNGなコトを徹底解説。離婚を回避するための詳しい対処法もご紹介...
-
産後から夫婦生活がなくなってしまう人は少なくありません。実際産後どのくらいの期間から再開すればよいのかわかりませんよね。この記事では、「産後の夫婦生活はいつから...
-
マザコンにはいくつか特徴があり、母親への依存心が強すぎると夫婦関係が破綻することもあります。状況によっては別居や離婚などを選択するのも一つの手段です。この記事で...
-
「旦那と一緒にいてもつまらない」「旦那が家にいるだけでストレスになる」と思いながら生活していませんか。ストレスを我慢して生活することはできますが大きなリスクも伴...
-
当記事では、夫婦別姓のメリット・デメリットをわかりやすく解説。制度の仕組みや日本の現状も簡単に説明します。
-
子連れで再婚したいけれど、子供の戸籍をどうすべきか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。戸籍によって子供の苗字や相続権なども変わるため、決断は慎重に行う必要が...
-
夫婦間の話し合いで離婚の同意が取れず裁判所を介して離婚をする場合、法律で認められた離婚理由を満たしていることが不可欠です。この記事では法定離婚事由と夫婦が離婚す...
-
弁護士会照会とは、弁護士法23条に定められた法律上の制度で、弁護士が担当する事件に関する証拠や資料を円滑に集めて事実を調査することを目的としています。
-
婚姻費用を払ってもらえたら、専業主婦の方などでも別居後の生活費にできるので、安心して離婚を進めることができるでしょう。この記事では、婚姻費用がいつからいつまで、...
その他の関連コラム
-
専業主婦の場合、最も不安なのが金銭面という方も多いでしょう。年金分割は、まだ自身が年金を受け取る年齢でなくても、請求することが可能です。この記事では、年金分割に...
-
別居中でも婚姻費用を負担する必要はあります。しかし、別居の理由や別居後の生活に不満があり、支払いに納得できないという方もいるでしょう。そこで本記事では、婚姻費用...
-
夫婦が別居する場合は、收入が高い一方が、收入が低い・收入がない一方の生活を「婚姻費用」として負担することになります。 婚姻費用とはどのようなものなのか、請求で...
-
最近、夫との会話が減ってきたと感じていませんか?会話がないと、このまま夫婦でいる意味があるのかと悩んでしまいますよね。この記事では、会話がない夫婦はこの先どうな...
-
公正証書とは公証人に作成される証明力と執行力を備えた文書のことをいいます。この記事では公正証書を作成するメリットや作成の手順を解説します。
-
マザコンにはいくつか特徴があり、母親への依存心が強すぎると夫婦関係が破綻することもあります。状況によっては別居や離婚などを選択するのも一つの手段です。この記事で...
-
離婚後の手続きで悩ましいのが、戸籍の問題ではないでしょうか。女性は親の戸籍に戻るのが一般的ですが、状況によっては戻れないこともあるので注意が必要です。本記事では...
-
夫婦の危機とは、夫婦関係が崩れるほどの状態をいいます。離婚の選択肢がよぎったり日常生活に深刻な影響が出たりしている状況であれば、夫婦の危機に陥っているといえるで...
-
不貞行為などが原因で夫婦関係に亀裂が生じると、どちらかが家を出て別居するケースがあります。モラハラやDVなどがあり別居した場合、家賃や食費などの生活費が問題にな...
-
育児放棄を理由に離婚することは可能です。ただし、裁判離婚で離婚が認められるには「法定離婚事由」に該当する必要があり、単なるワンオペ育児では認められない可能性が高...
-
子連れで再婚したいけれど、子供の戸籍をどうすべきか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。戸籍によって子供の苗字や相続権なども変わるため、決断は慎重に行う必要が...
-
婚約破棄とは、婚約後に一方的に婚約を解消することです。この記事では、婚約の定義・婚約破棄に該当する不当な理由・婚約解消の正当な理由・婚約解消で生じる慰謝料などの...
その他コラム一覧へ戻る