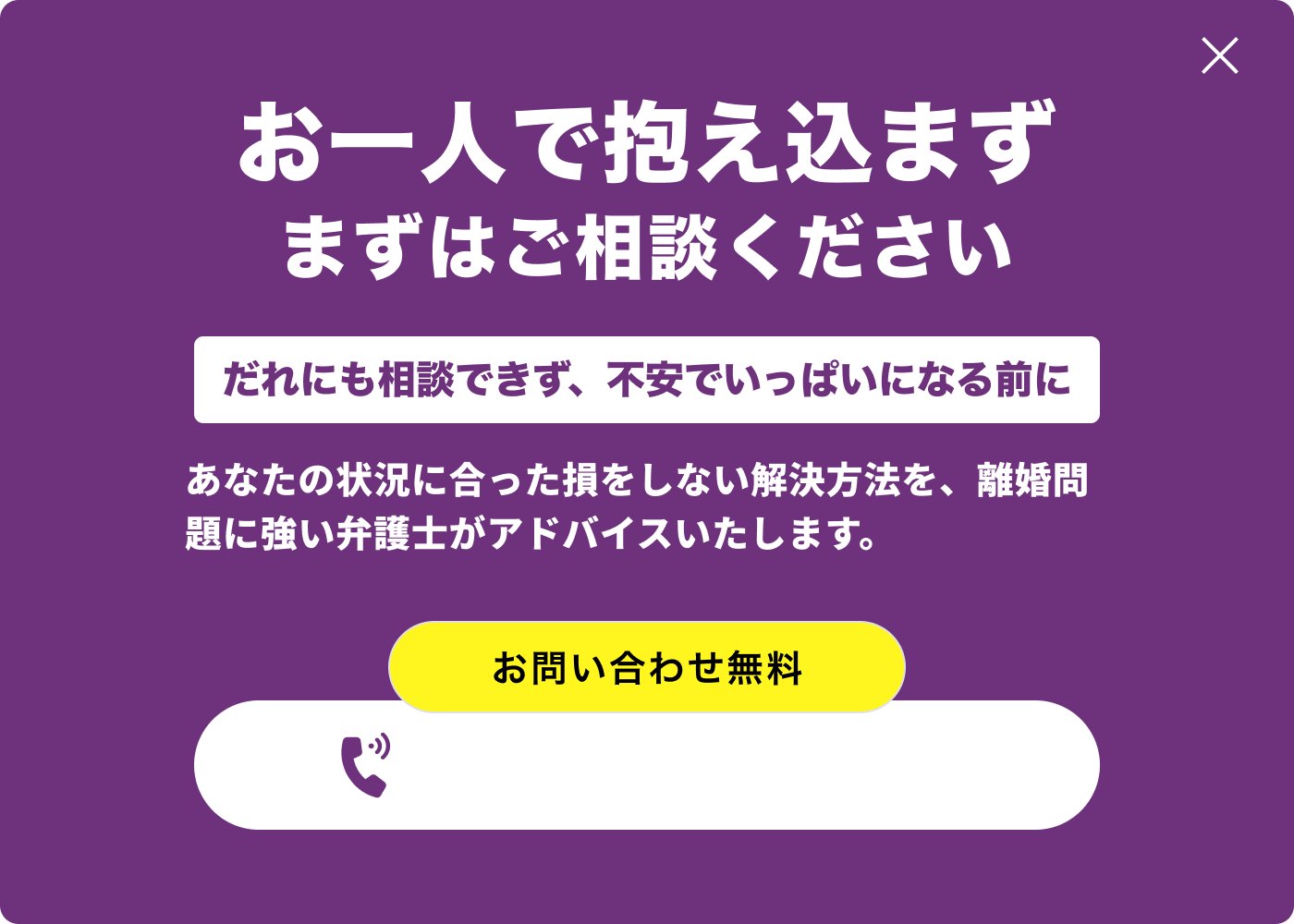離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える


母子家庭では、1人で家計を支えていかないといけないため、多くの人は仕事を探すと思います。しかし、自身のブランクの長さや、子供がまだ幼く手のかかることなどからどのような仕事でもよいというわけにはいきませんよね。
また、就労条件をよくみず就職してしまうと、残業で帰れない日が続いてしまったり、出張が多くて子供と一緒にいることができなくなってしまうかもしれません。
この記事では、母子家庭の方が仕事を探す際の5つのポイントや、おすすめの業種・子供の預け先などを紹介します。仕事を探す際の参考にしてください。

家事・育児をすべて自分で行った上で生活費を稼がなくてはいけないので、『働ければ何でもいい』というわけにはいきません。ここでは、仕事を探すときに押さえておくべき5つのポイントを紹介します。
母子家庭になると支援制度などはありますが、基本的には自身の収入だけが頼りです。仕事を探す際は毎月どのくらい収入が必要か明確にしておく必要があります。
2015年度の母子家庭の平均就労年収は200万円です。(参考:平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告|厚生労働省)月収で換算すると毎月約16万円になります。
離婚前に、家計簿をつけていた場合は、それを参考に1ヶ月の生活費を算出しましょう。
残業が多いと、子供を迎えに行けず延長保育に頼ることになります。そうなってしまうと子供に寂しい思いをさせますし、延長保育代の出費もかさむでしょう。
求人に月の残業時間が記載されているケースもありますので、参考にしながら検討しましょう。
また、面接の際に残業について聞きにくいかもしれませんが、しっかり確認しておくことをおすすめします。
子供の預け先から、病気になってしまった・ケガをしてしまったので迎えに来てほしいと連絡が来るかもしれません。父親に頼ることができませんのでそのような場合に、対応できる距離の職場をおすすめします。
もし育児に理解が足りない会社に就職してしまうと、学校行事はもちろん子供が急に病気になってしまった場合でも休みを取りづらいかもしれません。
最近では求人票に育児休暇などの取得実績や復帰率を記載している企業もあります。ただ、取得率だけを見て判断するのは危険です。理解とサポートを受け、長く働くことを考えるのであれば「えるぼしマーク」や「くるみんマーク」を取得している企業を探してみましょう。
このマークは、女性の活躍推進や育児サポートの取り組み状況が優良な企業として、厚生労働省より認定を受けていることを意味します。

【参考:厚生労働省 山口労働局】
ただし、競争率や就職への難易度が高いケースもありますので、あくまで参考にし自分の実績やスキルをもとに検討しましょう。
労働条件や給料などを検討し、働き続けても無理が出ないかをしっかり考えましょう。就業時間が長い・育児に理解がない・体力が必要な業種だと働き続けるうちに、最悪の場合倒れてしまうかもしれません。心身を壊してしまうとその後の仕事にも支障が出てしまいます。
また、働き過ぎは子供に寂しい思いをさせてしまうかもしれません。
母は仕事で忙しく、休日以外は殆ど会えません。でもそれは家計を支える為であって生意気は言えないのですが、母と一緒にご飯を食べたいです。(引用:助けて下さい|Yahoo!知恵袋)
仕事を探したいけどおすすめのサイトがわからない、良い求人を最短で見つけたい人は転職エージェントがおすすめ!あなたにおすすめのエージェントを年齢・性別・地域などからランキングで紹介します。
※別サイトへ遷移します
面接や給料面で少しでも有利に働くために、資格を取るべきか悩んでいる人は少なくないのではないでしょうか。ここでは、資格を持っている人の割合や種類、国が支援してくれる『母子家庭自立支援給付金事業』について紹介します。
厚生労働省が発表したひとり親に関する調査報告によると、母子家庭で資格を持っている人は全体の60%を超えることが分かりました。

(参考:平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告|厚生労働省)
資格保有者のうち半数以上の人が『役に立っている』と感じていますので、働くにあたり取得しておいて損はないと思われます。
取得人数が多い資格は以下のとおりになります。

(参考:平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告|厚生労働省)
最も人気のある資格は経理や会計への転職に有利になる『簿記』です。ここでは、上位5種の資格の内容や、どのような職場で利用できるのかについて紹介します。
なお、最近はパソコンでの作業が基本となりますので、基本的な操作(特に事務の場合はExcelなど)ができるよう勉強しておきましょう。
簿記(商工会議所の検定試験)は財政状態や経営成績の状態を明らかにするために、記録・計算・整理を行う技能で、経理事務への転職に有利になる資格です。
経理部や財政を管理する部署はどこの会社にもあるので、規模にかかわらず一定の求人があります。
ホームヘルパーは高齢者や障害者の家を訪問し、介護をしたり家事を代理・援助したりする仕事で、従事するためには資格が必要になります。
ホームヘルパーの資格は『介護職員初任者研修課程』を修了することで取得が可能です。約130時間の講義と演習を受け介護業務に必要な技能や基礎知識を身につけます。
取得後はホームヘルプを行っている事業所への就職が可能です。
厚生労働省の調査では、『パソコン』のみの記載でしたので、詳細まではわかりませんが、事務などのデスクワークを希望している場合『MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)』の資格がおすすめです。
この資格は、以下5つのマイクロソフトオフィス製品の操作技能や知識があることを証明するものになります。
試験は個別で行うので、どれか1つを受験することも可能です。オフィス製品を利用する業務への就職が有利になります。
医療事務の資格はいくつかありますが、基礎的な技能や知識を身につけるものとして『医療事務検定資格』があります。試験には授業で利用した資料の持ち込みが可能です。
医療事務は、病院の専門内容や規模にかかわらず必要になりますので、全国の病院に就職が可能です。
介護福祉士は、高齢者や障害者の介護を行ったり、利用者の家族への相談や助言を行ったりする業務を行う国家資格です。
ホームヘルパーと似ていますが、取得の方法・仕事の領域・待遇が違います。介護福祉士の方が、業務内容の幅が広く給料面などでも優遇されます。就職先は、社会福祉施設や老人ホームなどです。
『母子家庭自立支援給付金事業』は、就職経験が少なく経済的な自立が難しい母子家庭を支援するための制度です。対象の教育訓練を受講し、修了した際に経費の60%(1万2,000円~20万円)を支給してくれます。
仕事を探す際、正社員を第一希望にすると思いますが、子供がまだ小さい・求人の条件がパートの方がよいなど、正社員かパートかで悩んでしまうこともあるでしょう。
ここでは、迷った場合の判断基準を紹介します。
正社員のメリットはやはり給料がよいことでしょう。下の表は、母子家庭における就労年収の平均になります。

(参考:平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告|厚生労働省)
母子家庭全体の平均就労年収は『母子家庭が仕事を探す5つのポイント』で紹介したとおり200万円になっていますが、正社員の場合年収200万円以上の人が約80%を占めています。
逆にパートの場合、平均年収が200万円以下の人が80%を占めています。家計のやりくりに悩まずに暮らすためには、正社員を目指した方がよいかもしれません。
また、正社員で働く場合、認可保育園の入所が優先されるのも大きなメリットです。認可保育園なので、市区町村の補助を受けながら保育園に通わせることができます。
パートの最大のメリットは働く時間を自分で選べるところです。シフトの組み方によって、親も参加する学校行事などに無理なく行くことができますし、長期の休みを作りやすいでしょう。
また、働く時間がきっちり決まっているため、残業も基本的にはありません。子供と一緒にいられる時間が長くなるため、子供の精神的な負担も減らすことができます。
正社員のデメリットは、自分で仕事の時間や曜日が選べないため、学校行事に参加しにくくなったり、子供が急に風邪をひいたりしても休めなかったりすることです。
フルタイムで働くことで子供との時間が少なくなってしまうと、子供の精神的な負担になりますし、寂しい思いをさせてしまうかもしれません。
また、残業を頼まれてしまって定時に帰れない職場も少なくないでしょう。母子家庭や子供が小さいことを配慮してくれる会社であればよいのですが、残念ながらそうではない会社もあります。
パートの最大のデメリットは、収入が少ないことです。養育費を支払ってもらえない・子供の人数が多い・実家を頼ることができない場合パートだけでは生活が苦しくなってしまうかもしれません。ボーナスや退職金がでないのもデメリットです。
子供が待機児童になってしまった場合、パートでは優先順位が低いためなかなか入所できない可能性があります。無認可保育園に通わせることになると市区町村の補助(保育料の減額など)が受けられません。
『母子家庭が仕事を探す5つのポイント』に当てはまる場合は、雇用形態に固執せずとりあえず働いてみるというのも1つの方法です。条件がよいのに雇用形態ばかりを気にしてしまうと、自分に合った職場に就職するチャンスを失う可能性があります。
また、正社員かパートで迷った場合は、周囲に相談してみましょう。客観的な意見を聞くことで新しいメリットや、デメリットを発見できるかもしれません。
厚生労働省が調査した、母子家庭の方が就業している仕事内容は以下のようになります。

(参考:平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告|厚生労働省)
事務やサービス業、専門・技術職が多いことがわかります。ここでは、そのなかでもおすすめの職業を紹介していきます。
『事務』といってもさまざまな分野の事務があり多くの職場で活躍できるため、求人が豊富な職業です。また、資格や経験の有無を問われないことが多く、就職しやすいのではないでしょうか。
大企業でも事務職を募集していることがあるので、正社員になった場合月収20万円以上稼げる可能性があります。仕事はデスクワークなので、体力が心配な人にもおすすめの職業です。
また、事務職では営業などより残業時間も少ないケースが多く、迎えや子供の病気で急に休みを取得する際にも対応しやすいでしょう。
スーパーのレジ打ちのよいところは職場が家に近く、資格や経験を必要としないところです。また、スーパー側が『応募してくるのは主婦が多い』とあらかじめ想定していますので、子供がいることを理由に面接を落とされることはまずないでしょう。
同僚のなかには、子育て経験のある人や子育て中の人も多く、急に病気になってしまった場合にも寛容な態度を取ってくれるでしょう。
ヤクルトレディは、ヤクルトの配達以外にも各家庭からの健康相談を受けたりする仕事になりますが、1番の魅力は職場に専用の保育所が隣接しているところです。一般的保育所より安いので家計の負担を減らせます。
ケガや病気になった場合もすぐに連絡を受けることが可能です。また、会社やまわりの従業員も育児への理解が深いため、病気などでの急な休みを申請した場合にも対応してくれます。
仕事を探したいけどおすすめのサイトがわからない、良い求人を最短で見つけたい人は転職エージェントがおすすめ!あなたにおすすめのエージェントを年齢・性別・地域などからランキングで紹介します。
※別サイトへ遷移します

仕事をするにあたり、子供の預け先を探さなくてはいけません。実家に預けることができれば費用もかからないし、時間を気にすることもありませんが、実家を頼れない人も少なくないでしょう。
ここでは、子供を預けられる施設やサービスと特徴について紹介します。また、あらかじめこちら『よい保育施設の選びかた 十か条|厚生労働省保育課』を読んでいただくことでよりよい保育園を選ぶことができるでしょう。
認可保育園は国が決めた設置基準を満たしている児童福祉施設のことです。また認可保育は公費で運営されており、市区町村役場に相談することで、保育料の減額を認められる可能性があります。
入園希望の申し込みは市区町村役場で行います。
国が決めた設置基準を満たしていない場合、認可外保育施設になります。認可外保育施設は、国の規制を受けていないため、延長保育や休日保育などのサービスが充実していたり、認可保育園より入所が簡単だったりします。
ただし、保育料は各施設ごとに設定されているので、支払う金額が高くなりがちです。また、以下のようなサービスも認可外保育施設に含まれます。
日本ではあまりなじみがありませんが、ベビーシッターを利用するのも1つの方法です。基本的に家にベビーシッターを招き保育をしてもらうことになりますが、ベビーシッターによっては家以外の場所(最寄りの児童館など)で預かることもできます。
また、保育園の送迎や休日保育、宿泊保育などにも幅広く対応してくれます。料金は基本的に時間制なので、利用する際はあらかじめよく確認しておきましょう。
ベビーホテルとは、以下の条件のいずれかに該当する保育施設になります。
ア 午後8時以降の保育を行っているもの
イ 児童の宿泊を伴う保育を行っているもの
ウ 一時預かり(利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上を占めているもの)を行っているもの(引用:東京都福祉保健局)
どうしても仕事が終わるのが遅くなってしまう、出張に行かなくてはいけない場合に利用できます。
ファミリーサポートセンターは、市区町村で設立・運営を行っており、下の図のように、子育てや介護のサポートを受けたい人と援助したい人が会員登録し、必要に応じて地域でサポートする制度です。
(引用:ファミリーサポートセンター)
会員登録には特別な資格を必要としませんので誰でも利用できます。ただし、毎回同じ人にお願いすることや宿泊保育は難しいので注意しましょう。
このような事情がある場合は『病児保育施設』を利用できます。利用料金は各施設によりますが、東京都では1日およそ2,000円前後です。(参考:「全国病児保育協議会」)
1つの施設で受け入れ可能な人数が少ないので注意しましょう。

重度のうつや障害・持病を持っていて働けない場合は、生活保護の受給を検討しましょう。ここでは、生活保護を受ける場合の条件や相談先を紹介します。
生活保護を受ける場合は以下の条件をすべて満たす必要があります。
これらの条件が認められない場合は生活保護を受給できません。もし、条件を満たしている場合は、福祉事務所に申請してみましょう。
【関連記事】
▶母子家庭の生活保護は毎月いくら?受けるための4つの条件
▶母子家庭が児童扶養手当と生活保護を受ける際の基礎知識!
生活保護を取り扱っているのは福祉事務所ですので、生活保護について話を聞きたい、質問がある場合は福祉事務所の窓口に相談してみましょう。
最寄りの福祉事務所に関してはこちら『福祉事務所|厚生労働省』をご覧ください。
もし、生活保護を申請した際に、不当な扱いを受けた場合は弁護士に相談しましょう。弁護士に相談・依頼することで自身の代わりに申請をしてもらえます。
弁護士が代理で生活保護を申請することで、窓口の人に申請の必要性を説明してもらえます。なので、自分で行うよりスムーズに申請できるほか、ひどい言葉で申請を拒否されるといったことはないでしょう。
また、条件を満たしているのにもかかわらず申請が通らなかった場合、不服申立を行うことができます。
離婚後経済面で苦しい思いをしないためにも、養育費の請求と財産分与はしっかり行いましょう。元夫の住所や勤め先がわかれば離婚後でも養育費や財産分与の請求ができます。
また、その際に揉めごとが起こってしまったら早めに弁護士に相談しましょう。


★離婚弁護士ランキング全国1位獲得★【日本で唯一「離婚」の名を冠した事務所】経営者/開業医/芸能人/スポーツ選手の配偶者等、富裕層の離婚に強み!慰謝料相場を大きく上回る数千万〜億超えの解決金回収実績!
事務所詳細を見る
●お子様連れ歓迎/秘密厳守●不倫慰謝料請求は成功報酬【お問い合わせは写真をクリック】中央大講師●解決実績520件以上の法律事務所に在籍●負担を軽減し、元気になれる解決を目指します●練馬駅すぐ
事務所詳細を見る
【女性弁護士在籍】●夫・妻の不倫/慰謝料請求●証拠集めからサポート!●慰謝料や離婚では割り切れない気持ちも含め、どうか当事務所へご相談下さい。同じ目線に立った、親身な体制を整えております。
事務所詳細を見る
離婚すると、本籍地はどこになるのかが気になりませんか?本記事では、離婚後に本籍はどこになるのかやケース別に新たな戸籍を作る必要性や影響について解説します。当記事...
別居中に恋愛をしたい場合、どのようなことが問題になるか気になる方は少なくないでしょう。現在の夫婦関係や状況によっては、恋愛をすることで訴えられたり慰謝料を請求さ...
離婚を検討しているなかで、母親が親権をもつ場合に子どもの苗字を変えたくないと思っている方は少なくないでしょう。本記事では、離婚時に子どもの苗字を変えない場合は戸...
面会交流権とは、離婚に伴い、離れて暮らすことになった親と子が交流する権利のことです。定期的な面会交流は、子どもの健やかな成長にもつながります。この記事では、離婚...
離婚した後、子どもの苗字だけそのままにできるかが気になりませんか?本記事では、離婚すると子どもの苗字はどうなるのかや苗字を変えるための方法、苗字をそのままにする...
離婚をするには、どのような流れで進めればいいか気になりませんか?本記事では、離婚するための具体的な方法や流れ、注意点などを解説します。離婚に関する疑問や不安をな...
離婚後に再婚した際、戸籍謄本に離婚歴が載る場合と載らない場合があります。再婚相手に離婚歴や元配偶者の名前を知られたくない方に向けて、本記事では再婚後の戸籍謄本が...
専業主婦が離婚した場合、国民健康保険は自分で納める必要があります。 本記事では、専業主婦が離婚した場合の国民健康保険について、支払金額の目安や減額する方法など...
夫との離婚を検討しているものの、自身がパート主婦であるため、その後の生活に不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。本記事では、離婚後の生活費や配偶者に請求...
離婚に伴い発生する手続きのひとつが、健康保険の切り替えです。手続きを忘れてしまうと、医療費が自己負担になることもあります。本記事では、離婚後の健康保険について、...
【母子家庭(シングルマザー)の手当て・支援制度を完全解説!】母子家庭の場合、1人で子供を抱えて生きていくのは大変です。実感も頼れない場合、母子家庭の方が貰える手...
両親が離婚をしたという事実は、子供にどのような影響を与えてしまうのか、15個の項目をご紹介するとともに、どうすれば離婚が子供へ与える影響を最小限にできるのかご紹...
この記事では、だれでもできる児童扶養手当の計算方法から2018年に改正された所得制限限度額や控除対象など、児童扶養手当の計算に関するすべてを解説します。また、モ...
母子家庭になったが、持病や子供の障害など働けない事情により生活に困っている場合生活保護を受けることをおすすめします。離婚のせいで子供に貧しい思いをさせたくないで...
母子家庭の医療費は『ひとり親家庭等医療費助成制度』を受けることで全額負担をしてもらえる可能性があります。この記事では、『ひとり親家庭等医療費助成制度』の基礎知識...
離婚後はやらなければならない手続きが盛りだくさんです。できるだけ早く新しい生活を始めるためにも離婚後の手続きは確実&効率的に行うことが大切です。本記事では離婚...
離婚したら、何をすれば良いか悩むこともあるかと思います。子供のことや今後の生活のこと、新しい住居や仕事のことなど、そういった不安要素を取り除く手段をご紹介します...
育児休業給付金とは、育児休業を取得する父母に対する休業中の給付金です。受給条件を満たしていれば、月給の50%前後を受け取ることができます。この記事では、育児休業...
2010年、始まった当初は「子ども手当」と呼ばれていましたが、2012年から「児童手当」となりました。この記事では、東京などの支給日や支給が確認できなかった場合...
一度愛し合った人との離婚は踏みとどまる人が多いのも当然でしょう。今回は、離婚のメリットとデメリットを整理していきます。あなたが今後の生活を考えていく上で参考にし...
離婚後に再婚した際、戸籍謄本に離婚歴が載る場合と載らない場合があります。再婚相手に離婚歴や元配偶者の名前を知られたくない方に向けて、本記事では再婚後の戸籍謄本が...
両親が離婚をしたという事実は、子供にどのような影響を与えてしまうのか、15個の項目をご紹介するとともに、どうすれば離婚が子供へ与える影響を最小限にできるのかご紹...
別居中に恋愛をしたい場合、どのようなことが問題になるか気になる方は少なくないでしょう。現在の夫婦関係や状況によっては、恋愛をすることで訴えられたり慰謝料を請求さ...
専業主婦が離婚した場合、国民健康保険は自分で納める必要があります。 本記事では、専業主婦が離婚した場合の国民健康保険について、支払金額の目安や減額する方法など...
生活保護を受けるための条件は主に5つです。この記事では、受給するための5つの条件や受け取れる金額の相場について紹介します。また、条件を満たしているのに窓口で申請...
2010年、始まった当初は「子ども手当」と呼ばれていましたが、2012年から「児童手当」となりました。この記事では、東京などの支給日や支給が確認できなかった場合...
離婚したら、何をすれば良いか悩むこともあるかと思います。子供のことや今後の生活のこと、新しい住居や仕事のことなど、そういった不安要素を取り除く手段をご紹介します...
母子家庭では、1人で家計を支えていかないといけないため、多くの人は仕事を探すと思います。しかし、さまざまな問題からどのような仕事でもよいというわけにはいきません...
離婚後はやらなければならない手続きが盛りだくさんです。できるだけ早く新しい生活を始めるためにも離婚後の手続きは確実&効率的に行うことが大切です。本記事では離婚...
「もっと子どもと面会交流する頻度を増やしたい」など、離婚後にさまざまな要望が生まれることも少なくはないでしょう。そこで本記事では、他のご家庭の面会交流の頻度を知...
面会交流権とは、離婚に伴い、離れて暮らすことになった親と子が交流する権利のことです。定期的な面会交流は、子どもの健やかな成長にもつながります。この記事では、離婚...
いくら離婚を後悔しても取り返しはつきません。後悔を残さないためには、離婚後の生活を想定して納得のいく条件で離婚することが大切です。この記事では、離婚を後悔する理...