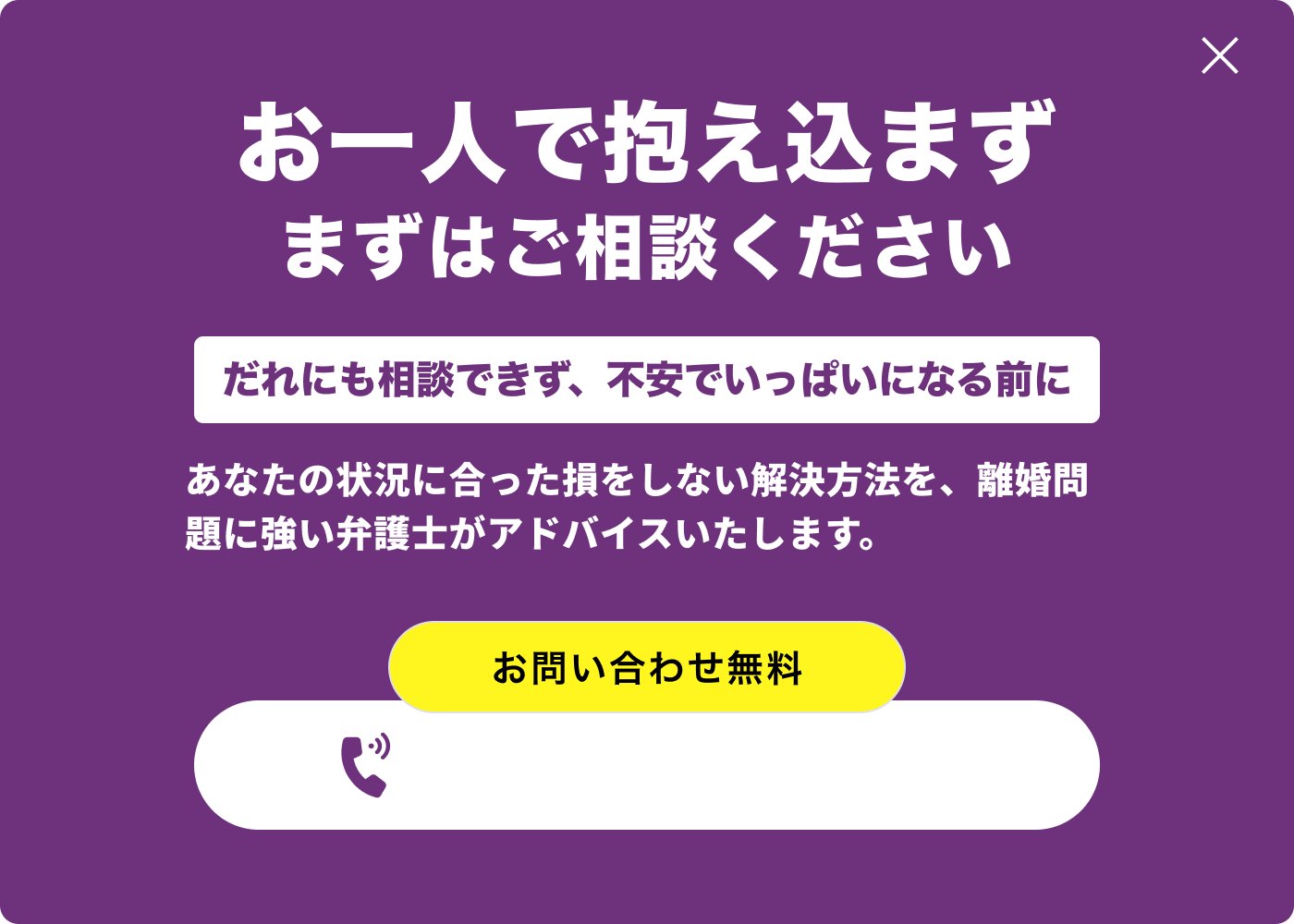離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える


子どもがいる状態で離婚をすると、相手方に対していくらの養育費を請求できるかが問題になるケースがあります。
なぜなら、養育費の金額次第で離婚後の生活プランが変わるほか、養育費に余裕がなければ子どもの成長にともない発生するさまざまな費用を捻出できない可能性が生じるためです。
そこで今回は、以下4点についてわかりやすく解説します。
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことです。
経済的・社会的に自立していない未成熟子が自立するまでに要する費用として支払われます。
夫婦が離婚をした場合、一方当事者は親権を失うので、子どもを監護する義務・子どもに教育を与える義務がなくなります(民法第820条)。
その一方で、離婚をして親権を奪われたとしても親であることに変わりはなく、直系血族として子どもに対する扶養義務は負った状態です(民法第877条第1項)。
ただし、一般的には親権を持つ親が子どもを監護しているケースが多いため、親権を持たない親(子どもを監護していない親)は一緒に生活をしていない以上、日常的に子どものために生活費などを直接支出することはなくなります。
そこで、親としての扶養義務を果たすために、子どもを監護していない親は「子どもを監護している親」に対して養育費を支払わなければいけないとされています。
養育費の金額は、夫婦間の話し合いによって決めるのが原則です。
ただし、養育費の金額について夫婦間の話し合いでは合意に至らなかった場合には、調停・審判・裁判(離婚請求と同時に判断される場合)という制度を利用して、家庭裁判所によって決定されます。
養育費の金額は夫婦間で自由に決定できるので、当事者双方が納得している限りは、養育費をいくらに設定しても問題はありません。
その一方で、子どもの親権をもつ親と子どもの親権を手放す親は、どちらも離婚後の生活を維持するために家計を維持する必要があります。
子どもを監護する親は「できるだけ高額な養育費が欲しい」と考える一方で、子どもを監護しない親は「できるだけ養育費を引き下げたい」と考えるため、夫婦間で養育費の金額について合意に至らないケースが少なくありません。
このようなときに参考になるのが「養育費算定表」です。
養育費算定表とは、過去の裁判実績などを収集・分析して裁判所が公表している養育費の目安で、家庭裁判所における調停や審判の際に養育費の金額を決定するときに参考にされる基準表のことです。
子どもの人数・年齢・親の年収等によって養育費の金額が細かく設定されています。
また、実際の調停・審判では、養育費算定表で求められる養育費の金額を基準に、個別具体的な増額事由・減額事由が考慮されます。
養育費について夫婦間で合意を形成できない場合には、調停・審判手続きを利用するしかありません。
しかし、調停・審判を使ったときの養育費の金額の基準が公表されていることを踏まえると、夫婦間の交渉段階においても、養育費算定表を参照することによって家庭裁判所の手続きを利用することなく合意形成に至る可能性が高いといえるでしょう。
なお、養育費算定表については裁判所のホームページを確認してください。
養育費算定表における養育費の考え方では、養育費は子どもの監護や教育のために必要とされる一般的な費用です。
そのため、養育費の内訳は以下のように分類されます。
①衣食住のために必要なお金(標準的な範囲に限る)
②通常の教育費(標準的な範囲に限る)
③医療費(標準的な範囲に限る)
④遊行費用(標準的な範囲に限る)
基本的には、経済的・社会的に成熟していない子どもに要する「平均的な公立高校までの学費」「平均的な生活費・医療費・遊行費用」が養育費の内訳に計上されます。
養育費算定表の養育費の考え方では、養育費は「子どもの監護や教育のために必要な“標準的な”費用」に限られます。
言い換えると、「突発的に発生する費用」「標準的な生活費を超えると考えられる費用」は原則として養育費の内訳に計上することができないということです。
たとえば、養育費算定表の考え方だけを前提にすると、以下の項目は別途養育費算定表の基準額に加算して請求することができません。
なお、夫婦間での合意によってこれらの費用を養育費に含めることは可能です。
ただし、離婚をする時点で子どもが私立学校に通っていたり、将来的に子どもが大学に進学することが想定されたりする場合には、養育費算定表の基準額に加算してこれらの増額要素が盛り込まれる可能性はあります。
教育費用金額は各家庭により異なります。
教育費用の準備方法について興味がある方は、
養育費の内訳に含まれない費用も、「特別費用」として相手方に請求できる場合があります。
養育費算定表の考え方を前提とすると、「養育費の内訳に含まれない」とされた費用については、原則として相手方に請求できないことになってしまいます。
たとえば、中学受験に要する高額な塾代や私立中学の入学金・学費などは、「標準的な金額」を超過していると扱われるので、相手方に養育費として請求するのは難しいでしょう。
ただし、突発的な病気・けがで高額の治療費・入院費が発生するケースや、進学時に高額の費用(入学金・学用品代)が発生するケースもあります。
このようなケースで毎月の養育費以外には一切相手方に請求できないとすると、子どもの経済的安定性が阻害されかねません。
そこで、このような突発的な金銭負担が発生する場面を救済するために認められているのが「特別費用」です。
子どものための一時的な大きな出費は、「特別費用」に該当するとして相手方に請求できます。
特別費用として請求できる可能性があるのは、以下の項目です。
なお、どこまでの内訳を特別費用に計上するかは当事者の合意や監護していない親の収入や学歴等によって決定します。
養育費の相場は「養育費算定表」によって導かれますが、特別費用の相場はありません。
どのような内訳のものを特別費用として請求するのか、臨時的に発生した支出を夫婦間でどのような比率で負担し合うのか、臨時的な支出が発生したときにどのタイミングで特別費用を支払うのかなど、特別費用の内容・条件は全て当事者間で自由に決定できます。
なお、特別費用の支払い条件などについては、協議の際に書面を交わしたり、調停・審判時の条件に盛り込まれたりするのが一般的です。
養育費を調停・審判で取り決めた場合や公正証書を作成した場合には、相手方が約束どおりに特別費用の支払いをしなかったとしても、強制執行によって取り立てをおこなうことも可能です。
ここでは、実際に特別費用の請求が認められた裁判例を2例紹介します。
本件では、4年制私立大学に通う子どもの学費相当分を養育費の特別費用として請求できるかが争われた事例です(大阪高裁平成27年4月22日)。
本来、養育費算定表の考え方を前提とすると、大学の学費や入学金などは「標準的な学費」の範囲を超えるために、非監護親に対して養育費として請求することができません。
これに対して大阪高等裁判所では、子どもが私立学校や大学に在籍する場合で、「義務者が当該私立学校や大学への進学を承諾しているとき」「義務者の収入及び資産の状況などを勘案すると義務者に学校教育費を負担させることが相当と認められるとき」には、公立学校の学校教育費平均額を超える学校教育費を双方がどのような割合で負担するべきかが問題になり得ると指摘しました。
そのうえで、本件では「夫婦の婚姻期間中、子どもが進学する高校を検討した際に、国立大学の進学を視野に入れて進学先を決定していたこと」「子どもが進学する高校を選ぶときに国立大学への進学を視野に入れていた話を夫婦が聞いていたこと」「夫婦が離婚をしていなかったとしても大学進学時の学校教育費の一部は奨学金やアルバイトで補填する必要があったこと」を総合的に考慮した結果、非監護親には「公立大学の学費相当分の1/3」を負担する義務があると判断されました。
本件では、子どもが私立大学の付属高校に進学したことを理由に、元妻が元夫に対して養育費の増額を求めた事案です。
争点は「私立高校及び私立大学の学校教育費を養育費として請求できるのか」「養育費の支払い期間を”成人に達する日の属する月まで”から”大学卒業時まで”に延長できるのか」の2点です(東京高裁平成29年11月9日)。
まず、大学の学校教育費を支払う義務があるかについては、「大学進学了解の有無、元夫の地位・学歴・収入などの諸般の事情を総合的に考慮して決定する」としたうえで、本件では、「元夫が子どもの私立高校への進学に反対しており、また、私立大学への進学自体も了解していなかったこと」「元妻の収入が極めて少なく、元夫には扶養すべき子どもが多数存在するため、私立大学進学時には奨学金やアルバイト収入で学校教育費を補填する必要があったこと」という事情があるため、子どもの私立大学の学校教育費については、元夫に負担義務はないと判断されました。
他方で、子どもが成人に達したとしても大学生であり、自立して生活できるだけの収入を得ていないこと、元夫は大学卒の学歴や高校教師としての地位を有し、年収が900万円以上あること等の事情が考慮され、通常の養育費については大学卒業時まで支払い期間が延長されました。
子どもの経済的安定性を確保するために、子どもを監護する側の親ができるだけ高額の養育費を求めるのは当然です。
ここでは、養育費算定表の内訳には含まれない、または含まれにくい項目まで相手方に支払いを認めさせるポイントについて解説します。
納得できる養育費を相手方に支払わせるためには、養育費の金額について話し合いをする段階で、内訳・根拠をできるだけ具体的に明示するのがポイントです。
たとえば、想定される進路、習い事や通塾費用など、子どもの年齢に応じて必要になる費用内訳をできるだけ具体化したほうが、夫婦間での協議が具体化され、相手方からの納得も得やすいでしょう。
また、協議段階で養育費の金額について合意に至らずに調停・審判段階に至ったとしても、一方当事者が具体的な請求根拠を示している点が斟酌されて、養育費算定表の基準額を超える養育費の金額が認定される可能性も高まります。
希望する養育費をもらうためには、離婚問題が発生した初期段階から弁護士へ依頼することを強くおすすめします。
なぜなら、弁護士は家庭の個別事情を踏まえた適切な養育費額を算出したうえで、相手方から合意を引き出すべく示談交渉を進めてくれるからです。
また、離婚時には慰謝料や財産分与、親権などのさまざまな問題を抱えることになりますが、弁護士への依頼によって離婚をめぐる全てのトラブルを解決できます。
さらに、双方が感情的になって前向きな話し合いが一切できない状況でも、弁護士が交渉窓口になってくれ、相手方と直接コミュニケーションをとらなくても円滑に離婚条件について合意を形成できるでしょう。
離婚をする段階で養育費についてしっかりと話し合いをしておかなければ数年後、十数年後になってさまざまな問題が顕在化する可能性があります。
ここからは、養育費について協議するときの注意点について解説します。
養育費について協議をするときには、金額だけではなく、支払い期間・支払い方法についても合意を取りつけておかなければいけません。
養育費の支払い期間は、夫婦間で自由に決定できます。
一般的に、以下の期限が養育費の支払い期限として決定されることが多いです。
養育費の支払い方法も夫婦間で自由に決めることができます。
一般的には「毎月〇〇日に指定銀行口座に振り込む」という形式が採用されますが、あらかじめまとまった金額を受け取ることも可能です。
また、夫婦間で合意を形成している限りは、現物支給の方法で養育費を支払っても問題ありません。
協議によって養育費などの離婚条件について合意に至った場合には、合意内容を公正証書にしておくことをおすすめします。
なぜなら、公正証書にしておくことによって養育費不払いなどのトラブルが発生したときにスムーズな対応が可能になるためです。
公正証書とは、「私人からの嘱託によって公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書」のことです。
文書の内容について公証人が証書として内容を証明してくれるので、後々争訟が生じたときに証拠として扱うことができます。
さらに、公正証書に強制執行認諾文言(債務不履行などの契約違反が発生したときには直ちに強制執行に服することを承諾する旨)を付しておけば、養育費の不払いが発生したときすぐに相手方の財産を差し押さえることが可能になります。
相手方が途中から養育費を支払わなくなるケースが多くあるため、養育費未払いトラブルへのリスクヘッジとして、協議段階で公正証書に残しておくことは重要でしょう。
離婚時には冷静な話し合いが難しいことが多いため、協議だけで離婚条件全てについて円滑に合意を形成できるわけではありません。
そして、養育費の内訳などについて協議がまとまらないときには「調停手続き」を利用することが可能です。
調停は家庭裁判所を利用する手続きのことで、調停委員が当事者双方の意見を交互に聞き、合意形成に向けて仲介をしてくれます。
当事者双方が直接顔を合わせることはないので、客観的に双方の見解をぶつけ合うことができます。
調停の結果、当事者間で合意に至れば、調停調書が作成されます。
これに対して、調停不成立の場合には、当事者の意見や個別事情を総合的に考慮したうえで、家庭裁判所が「調停に代わる審判」を下します。
最後に、養育費についてよく寄せられる質問についてQ&A形式で解説します。
養育費は「離婚時の諸状況」「当時想定される事情」を前提に決定されるため、離婚時に想定していなかった事情が発生したときには、養育費の金額を変更(増額・減額)することができます。
たとえば、養育者が病気で年収が下がった、非監護者の年収が増加したなどの事情がある場合には、養育費の増額を求めることになるでしょう。
これに対して、非監護者がけがで収入が断たれたときには、養育費の減額を求められることもあり得ます。
養育費の金額は当事者の合意によって変更することが可能です。
養育費の金額を途中で変更するときにも、後々のトラブルを回避するために公正証書を作成しておくべきでしょう。
また、養育費の金額変更について当事者間の話し合いでは決着しないときには、家庭裁判所の調停手続きを利用することもできます。
調停不成立ならば、変動事情を考慮したうえで家庭裁判所が増額・減額について審判を下します。
元夫婦のどちらが再婚したとしても、養育費の金額が見直されることがあります。
まず、非監護親が再婚をしたときには、再婚相手の収入や他に監護すべき子ができたか等の事情によって養育費が変動します。
たとえば、再婚相手が無職・低収入の場合には、非監護親が再婚相手に対する扶養義務を負いますし、再婚相手との間に新たに子どもが生まれた場合や再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合には、その子に対しても扶養義務を負うため、非監護親からの養育費減額請求が認められやすくなります。
次に、監護親の側が再婚をしたときには、再婚相手と子どもが養子縁組をするか否かで養育費の金額が変動する可能性があります。
たとえば、再婚相手と子どもが養子縁組をしなければ、養育費は従来どおりの金額を受け取ることができます。
これに対して、再婚相手と子どもが養子縁組をすれば、養親が子どもに対して扶養義務を負うので、非監護親の養育費が減額されたり、養育費の支払い義務自体が消滅することもあり得ます(ただし、再婚相手が充分な年収を得ていない場合には従来の養育費額は変動しません)。
養育費は子どもの進学や生活基盤に大きく影響するものであり、適正な内訳を計上して金額を決定しなければいけません。
しかし、離婚問題が発生したときや、離婚によって元配偶者が縁遠い存在になったときには、当事者同士で直接冷静に話し合いをするのは容易ではないでしょう。
弁護士へ相談をすれば、養育費をはじめとする離婚条件について有利な条件を引き出すことができますし、養育費不払いなどのトラブルにもスムーズに対応してくれます。
離婚問題の円満解決を希望するなら、念のために弁護士へ相談しておくことを強くおすすめします。


●夜間・休日対応●夫婦カウンセラー資格有●キッズルーム有●【30代・40代の離婚案件の実績豊富】離婚する決意をした方、財産分与で揉めている方、不倫の慰謝料請求を検討している方などぜひご相談ください。
事務所詳細を見る
【初回相談0円】【市ヶ谷駅徒歩1分】離婚問題でお悩みの方、まずは不安やストレスを軽減するためにもお気軽にご相談ください。依頼者様それぞれの思いに寄り添い、あなたの味方として徹底的にサポートします
事務所詳細を見る
【初回相談0円!LINE相談可!】※話がしやすい弁護士【超迅速対応|土日深夜電話が弁護士に通じる】不倫問題、離婚問題、男女問題なら相談しやすい弁護士をお勧めいたします
事務所詳細を見る
養育費の未払いで悩んでいる方は多いものです。しかし、子どものためにもきちんと支払ってもらわねばならず、諦めてはいけません。本記事では、養育費が支払われないときの...
養育費から逃げる方法はありませんが、場合によっては免除や減額が認められるケースもあります。ここでは、養育費の支払いから逃げた場合に科される罰則や、免除や減額の条...
本記事では、養育費を支払わないと言われたときの具体的な対処方法や、養育費が免除・減額される可能性のあるケースを解説します。本記事を参考にして、きちんと養育費を相...
離婚する際に養育費を支払うと取り決めをしたのに、支払われなくなることはよくあるようです。弁護士に相談したくても、弁護士費用などのお金の心配があり一歩踏み出せない...
養育費の未払分に関する時効は、話し合いによって決めたのか、裁判所の手続きで決めたのかなどによって異なります。 本記事では、手続き方法ごとの養育費の時効について...
離婚することになったが、夫から養育費を支払ってもらえるのか不安だという方もいるでしょう。実は、養育費の支払いを確実にするために、連帯保証人を立てることも可能です...
子どもを連れて離婚する場合、気になるのが養育費の金額です。元配偶者の年収が700万ほどであれば、貰える養育費の相場はいくらなのでしょうか。ご自身の収入が少なく子...
離婚時に養育費の取り決めをしていなかった場合、後から遡って請求するのは難しいといえます。しかし、不可能ではありません。状況によっては未払いの養育費を支払ってもら...
養育費を受け取っていて生活保護を受給したいと考えている場合、生活保護は受給できるのか。また養育費を支払っていて生活保護を受給することになった場合、養育費の支払い...
本記事では、年収1,000万の養育費はいくらが相場になるのか、算定表を使った確認方法や、増額のポイントなどをわかりやすく解説します。
養育費については、減額が認められるケースもあります。離婚後に再婚した場合や、収入が変動した場合などは、減額条件に該当するのかどうか確認しておきましょう。この記事...
養育が支払われないという問題を解決する最も手っ取り早い方法は、養育費の支払いに関する取り決めを公正証書に残しておくことです。
養育費を獲得したいと思っても、回収できないケースもあります。この記事では、養育費の概要から養育費の相場と計算方法、請求方法と手続き、養育費の支払いの知識、支払い...
子供の養育費を適切に示すために使用されている養育費算定表ですが、最高裁判所内司法研修所によって16年ぶりに改定が行われます。こちらでは、改訂版の養育費算定表の見...
一方が再婚したとしても、養育費が必ず減額されるわけではありません。しかし場合によっては、減額が認められることもあります。本記事では、再婚した際に養育費がどうなる...
離婚後に養育費が支払われないことに悩んでいませんか。差し押さえ(強制執行)を行うことで、強制的に養育費を確保できるかもしれません。この記事では、2種類の差し押さ...
未婚の母とは、結婚をせずに子供を産み育てる母親のことです。未婚となると経済的なこと、育児に関してなどさまざまな不安を感じますよね。この記事では、未婚の母に向けて...
養育費の請求を調停で求める時、どんなことをすれば有利に調停を進めることができるのか、またその具体的な方法をご紹介しようと思います。
児童扶養手当とは、一人で子供を育てる親が受け取れる給付金です。この記事では、児童扶養手当の支給日・所得制限・もらえる金額・申請に必要なものなどをわかりやすく解説...
養育費が支払われなくなった時の対処法として強制執行が効果的です。強制執行は、給料や預金口座を差し押えられますし、給料の差し押さえに関しては今後も効力を発揮するた...
この記事では、裁判での養育費の決め方や裁判以外の方法、養育費を決めるときに知っておきたいことなどを解説しています。
養育費については、減額が認められるケースもあります。離婚後に再婚した場合や、収入が変動した場合などは、減額条件に該当するのかどうか確認しておきましょう。この記事...
親には子どもの扶養義務があるため、離婚しても養育費を払わなければなりません。しかし、離婚後の状況によっては減額や免除も可能です。本記事では、養育費と法律の関係や...
離婚後も父母が共同で親権をもつことを、共同親権といいます。では共同親権が導入されたら、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。本記事では、まもなく日本...
本来、養育費の支払いは離婚時に決めるため、あとから請求するときは一定条件を満たさなければなりません。 本記事では、養育費をあとから請求するときの方法や、請求時...
養育費から逃げる方法はありませんが、場合によっては免除や減額が認められるケースもあります。ここでは、養育費の支払いから逃げた場合に科される罰則や、免除や減額の条...
法律上は不倫した配偶者でも養育費を請求できるため、非監護親は支払いに応じる必要があります。 本記事では、不倫した配偶者に養育費を支払わなければならない理由や、...
本記事では、養育費の強制執行にかかる弁護士費用の相場や、養育費を獲得する流れ、養育費に関する問題を弁護士に相談するメリットをわかりやすく解説していきます。
養育費は子どもを育てるための教育費や生活費に充てられる大切なお金であり、適切な取り決めがされているにもかかわらず振り込まれない場合は、状況に応じたしかるべき対応...
収入が減少していることや面会を拒否されたことなどを理由に、養育費の支払いをやめたいと考えている方も多いのではないでしょうか。本記事では、離婚後に養育費を払わなく...
養育費の支払いを求めても元夫が応じない場合は少なくありません。そのような状況になったら、強制執行をすると思いますが、お金が取れないケースもあります。この記事では...
元夫婦間で子どもの養育費をやり取りしている場合は、確定申告をおこなう際の養育費の取り扱いについて知っておく必要があります。養育費に関する確定申告時の注意点を解説...