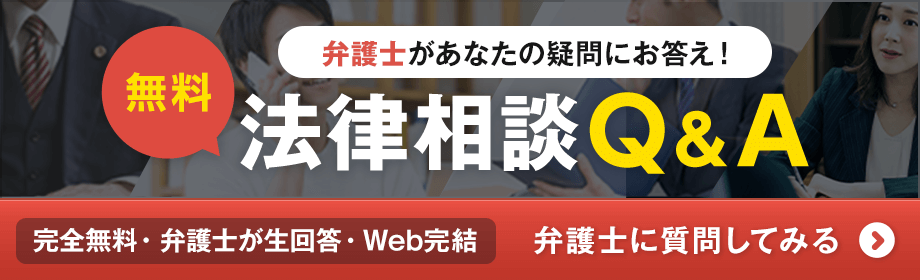本コンテンツには、紹介している商品(商材)の広告(リンク)を含みます。
ただし、当サイト内のランキングや商品(商材)の評価は、当社の調査やユーザーの口コミ収集等を考慮して作成しており、提携企業の商品(商材)を根拠なくPRするものではありません。
離婚したくても配偶者が何らかの理由で、なかなか離婚に応じてくれないことはよくあります。このような状況で重要になるのは離婚事由(りこんじゆう)があるかどうかです。
離婚事由とは離婚の理由や原因を意味し、法律に定められた法定離婚事由に該当している場合は、裁判で離婚が認めてもらえます。今回の記事ではその法定離婚事由について詳しく解説します。
配偶者が離婚に応じてくれない方へ
配偶者が離婚に応じてくれず、裁判で解決をしようと考えている方もいるのではないでしょうか。
裁判で離婚を認めてもらうには、法定離婚事由が必要です。
法定離婚事由がなければ、裁判を起こしても離婚は認められません。
配偶者が離婚に応じてくれず困っている方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
弁護士へ相談・依頼するメリットは、下記のとおりです。
- 自身のケースが法定離婚事由に該当するかが分かる
- 配偶者との交渉を任せられる
- 裁判手続きを一任できる など
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
裁判離婚の場合は離婚事由が必要
夫婦が話し合って離婚を決める協議離婚であれば、夫婦が合意の上で離婚届を提出するだけでよく、離婚の原因は問われません。
しかし、夫婦が離婚についてお互いの条件を譲らずに、話し合いでも調停でも離婚の合意が得られない場合、裁判によって離婚が争われます。裁判で離婚を認めてもらうには、法定離婚事由が必要です。
民法第770条に法定離婚事由として具体的な原因が4つ、抽象的な原因が1つ定められています。
5つの法定離婚事由
それでは、5つの法律離婚事由について解説します。
一般的に「不倫」と呼ばれるものは不貞行為を指します。法律で定められている不貞行為とは、「配偶者のある者が、自由な意志に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を持つこと」です。
夫婦として婚姻契約を結んだ後は、夫婦が同居してお互いに協力しながら扶助し合わなければならないという義務を負っています。
さらに、夫婦に課せられている義務として、夫婦がお互いに貞操を守らなければなりません。そのため、夫婦のどちらかが不倫などによって、配偶者以外と性行為をした場合、その配偶者は不貞行為を理由に離婚の請求が可能です。
また、不貞行為の証拠があれば、離婚を成立させることができるだけでなく、慰謝料も請求できますので事前に専門家に相談して証拠を取っておくとよいでしょう。
しかし、不貞行為があっても婚姻関係が破綻していなければ離婚を認めてもらえない可能性があるため注意しましょう。
完璧な証拠を手に入れるためには?
完璧な証拠を手に入れるためには、専門家の力を借りた方がいいでしょう。浮気調査の専門家である、探偵に相談してみませんか?
無料相談はこちら
悪意の遺棄とは、正当な理由がなく夫婦の共同生活を続けられなくなっても構わないという意志の元に、夫婦の同居・協力・扶助の義務を放棄することをいいます。このような状況では離婚請求が認められやすいです。
ただし、長期間の単身赴任など正当な理由があれば、夫婦が別居している場合でも悪意の遺棄とはなりません。悪意の遺棄と認められるケースと認められないケースの例は以下のとおりです。
悪意の遺棄が認められるケース
- 理由なく同居を拒否する
- 生活費は渡しているが不倫相手と同居している
- 生活費を渡す約束をして別居したが、一切生活費を振り込まない
- 収入があるのに配偶者に生活費を渡さない
- 家出を日常的に繰り返し行う
- 同居している姑との関係が悪く配偶者が実家から帰ってこない
- DVなどによって配偶者が家にいられない状況を意図的に作っている
悪意の遺棄とは認められない事例
- 仕事で出張や転勤の必要があり別居する
- 病気治療のための別居
- 険悪になった夫婦関係を見つめ直すために冷却期間と位置づけた別居
- 子供にとって必要な別居
何らかの理由で配偶者の生死を3年以上確認できず、現在までその状況が続いている場合は離婚請求が可能です。配偶者の生死が3年以上不明になった理由は問われません。
しかし、第三者がその配偶者の生死がわからないことを証明できることは必要であるため、配偶者本人とは連絡が取れずとも知人が連絡を取れる状況にあるなら、この法定離婚事由には該当しません。
配偶者が強度の精神病により、夫婦に義務付けられている婚姻生活の相互協力や扶助が果たせない状況にあれば、離婚請求が可能です。強度の精神病と回復の見込みが無いことを証明するには、専門医の鑑定と法的な判断が必要となります。
ただし、離婚によって病者の離婚後の生活状況が著しく悪化する可能性があるため、裁判所は安易に離婚を認めることはありません。
離婚を認めてもらうには、病者が公的保護などにより療養できる環境を整えることや、離婚後も療養のための資金提供を行い続けることによって、離婚後も病者が生活を続けられる具体的な手段が用意されており、今後の見込みが立っている必要があります。
この項目は民法第770条の抽象的な原因としての離婚理由と認定されるものです。離婚原因として認められる内容が幅広いため、同じような理由があったとしても離婚が認められる場合と認められない場合があり、それぞれの夫婦の状況によって判断されます。
その他婚姻を継続しがたい重大な事由として挙げられる主な条件は以下の7つです。
①:性格の不一致
離婚理由で上位に位置するのが性格の不一致です。この言葉は非常に意味の幅が広く、これだけで裁判によって離婚が認められることはあまりありません。
離婚請求が認められるのは、性格の不一致が原因となり夫婦生活を続けると精神に支障をきたす程愛情がなくなっている場合や、第三者からみて夫婦生活を維持することが困難である場合などです。
②:DVやモラハラ
近年の離婚理由として増加しているのがこのDVやモラハラです。DVやモラハラ関係のニュースを目にする機会も多くなってきました。たった1度のDVであっても、その程度や動機などによっては離婚原因とされることもあります。
裁判所も配偶者への暴力に対しては厳しい態度を取る傾向があり、DVによる怪我の診断書や傷の写真、暴力によって散乱した部屋の写真などが証拠として有効です。
モラハラについても、日常的に繰り返されたことによって夫婦関係の円満な継続が難しいことが明白であれば離婚請求が認められます。
③:家事や育児に協力しない
共働き夫婦であるにも関わらず、一方の配偶者が家事育児に一切協力しなければ、婚姻生活の義務違反として離婚理由になるケースがあります。
育児家事の非協力によって夫婦関係が破綻し、その改善が見込めない場合であれば離婚請求が認められる傾向にあります。
④:両親や親族間の不和・嫁姑の不仲
夫婦関係は悪くないものの、お互いの親同士が不仲となってしまったことが離婚原因となるケースも少なくありません。
これは、夫婦とその親が同居している場合によく見られるケースで、悪化した関係を持ち直そうと一方の配偶者が努力したにも関わらず、もう一方の配偶者が非協力的で配偶者のみを責め立てるなどの状況が続いた場合に離婚請求が認められやすくなります。
⑤:ギャンブルなどによる浪費や怠惰が続いている
健康で仕事に支障のない状態の配偶者が働こうとしない場合や、ギャンブルなどにより浪費や借金を繰り返して生活費が確保できない状況が続けば、離婚請求が認められます。
返すことのできない多額の借金や、日常生活ができなくなるほどの浪費もこの条件に含まれます。裁判に臨む場合には、浪費や怠惰の証明ができるように、預金通帳のコピーやレシートなどの証拠を集めておきましょう。
⑥:性的な欲求不満、性的異常
夫婦のセックスレスや配偶者の性的異常などによって、夫婦に性生活がないことは夫婦関係を悪くしてしまう一因になります。
性的異常は一概には定義できませんが、SM行為の強要や避妊に応じないなどの行為が継続的に行われている場合には離婚請求が認められます。
⑦:犯罪により服役している
配偶者が殺人などの重大な犯罪によって長期間服役する場合や、軽犯罪でも常習的に行うことで懲役が続いてしまい、家庭生活に重大な支障をきたしてしまう場合であれば、離婚請求が認められます。
相手が離婚に同意しないときの対処法
上記の離婚事由などがあるにも関わらず、相手から離婚に同意を得られない場合は、離婚調停を検討することをおすすめします。
離婚調停の流れ
離婚調停は以下のような流れで進みます。
- 離婚調停に必要な書類を用意する
- 離婚調停の申立てをする
- 調停期日通知書による通知
- 第一回目の調停
- 決まらなければ第二回目の調停に進む
- 決まった場合は調停証書を作成する
より詳しい流れは「離婚調停の流れを詳しく解説|5分で分かる離婚調停の進め方ガイド」をご覧ください。
離婚調停にかかる費用
離婚調停を自分で行う場合の費用は約2,600円
- 収入印紙代:1,200円
- 戸籍謄本取得費用:450円
- 切手代:800円
- 住民票取得費用:200円
離婚調停を弁護士に依頼来する場合の費用は70〜100万円
- 着手金:30〜40万円
- 報奨金:30〜40万円+経済的利益の10%
弁護士費用が不安なら法テラスの利用を検討
もし弁護士の費用が心配な場合は「法テラス」の利用を検討してみると良いでしょう。
離婚調停にかかる費用などは「離婚調停にかかる費用と弁護士に依頼した際のメリットまとめ」をご覧ください。
離婚調停を有利に終わらせたい場合
離婚調停が長引く理由の一つに「自分の主張を正しく伝えられない」といった問題があります。あなたの希望する条件で解決したい場合は、調停委員に共感してもらえるように話すことが必要です。
詳しい方法については「離婚調停を弁護士に頼むと最短かつ有利に終わる7つの理由」をご覧ください。
まとめ
夫婦両者が合意できれば離婚することができますが、お互いの意志が平行線をたどり離婚裁判に発展した場合は、今回ご紹介した5つの法定離婚事由のいずれかによって夫婦関係が破綻していることを証明しなければなりません。
ご自身のケースが法定離婚事由に該当するかわからないなど、少しでもお悩みのことがあれば弁護士に相談してみましょう。
当サイトベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)には無料相談を受け付けている事務所も多く掲載していますので、是非ご活用ください。
配偶者が離婚に応じてくれない方へ
配偶者が離婚に応じてくれず、裁判で解決をしようと考えている方もいるのではないでしょうか。
裁判で離婚を認めてもらうには、法定離婚事由が必要です。
法定離婚事由がなければ、裁判を起こしても離婚は認められません。
配偶者が離婚に応じてくれず困っている方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
弁護士へ相談・依頼するメリットは、下記のとおりです。
- 自身のケースが法定離婚事由に該当するかが分かる
- 配偶者との交渉を任せられる
- 裁判手続きを一任できる など
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。