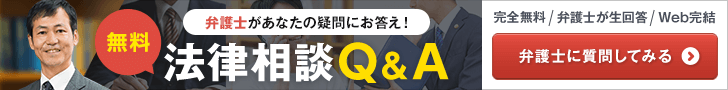「養育費」が得意な弁護士に相談して悩みを解決!
お悩み内容から探す

養育費を支払っている側も受け取っている側も、確定申告をおこなう際には、養育費の取り扱いについて知っておく必要があります。
特に養育費を申告所得に含める必要があるのかどうか、養育費を支払っていると扶養控除を受けられるのかどうかの2点については、正しい知識を備えておきましょう。
今回は、養育費に関する確定申告時の注意点を解説します。
子どもの養育費、適切額分もらえていますか?
離婚時に取り決めた金額分の養育費を毎月受け取っていても、本当はもう少し欲しい…と思ったことはありませんか?
結論からいうと、事情によっては受け取る養育費をあとから増額することが可能です。少しでも養育費について不満がある方は、まずは弁護士の無料相談を利用してみましょう。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。
- 養育費の適正額を試算してもらえる
- 養育費の交渉についてアドバイスをもらえる
- 万が一相手と揉めても、依頼すれば代理で交渉してもらえる
当サイトでは、離婚問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
養育費を受け取っている場合、確定申告時に所得に含めるべきか?
確定申告とは、所得税・住民税の課税対象となる1年間の所得を確定して、税務署に申告する手続きです。
元配偶者から養育費を受け取っている場合、その金額は所得に当たります。しかし、すべての所得について所得税・住民税が課されるわけではありません。
所得の種類によっては、所得税・住民税が非課税とされる場合もあります。非課税とされる所得については、確定申告時に所得に含める必要はありません。
養育費は非課税所得とされているため、確定申告時の所得に含める必要はありませんが、例外的に贈与税が課される場合があるので注意が必要です。
養育費は原則非課税|確定申告時の所得には含めない
養育費は原則として、「扶養義務者相互間において扶養義務を履行するために給付される金品」に当たるため、所得税・住民税は非課税となります。
そのため、確定申告をおこなう際には、養育費を所得に含める必要はありません。
例外的に養育費に対して課税される場合
養育費の精算方法や使途などによっては、受け取った養育費に対して贈与税が課される場合があります。
養育費に対して贈与税が課される場合の例は、以下のとおりです。
- 過大な額の養育費を受け取っている場合
- 養育費を一括で受け取った場合
- 受け取った養育費を預金や投資などに充てている場合
なお、1年間で受けた贈与額の合計が110万円以下である場合には、贈与税は課されません。
過大な額の養育費を受け取っている場合
養育費として受け取った金銭は、扶養義務の履行として「通常必要と認められるもの」と評価される範囲に限って、贈与税が非課税となります。
養育費の金額が「通常必要と認められるもの」であるかどうかは、子どもの需要と支払う側の資力、その他一切の事情を勘案して社会通念に従い判断されます。
扶養義務の履行として通常必要と認められる範囲の額を超えて養育費を受け取った場合、超過部分は贈与税の課税対象となります。養育費の名目で財産を移転し、贈与税を免れようとする行為を防ぐためです。
たとえば、養育費として適正な金額が月6万円程度であるのに、毎月100万円もの養育費を受け取っているとします。この場合、超過部分の月94万円程度に対して、贈与税が課される可能性があります。
これは極端な例ですが、あまりにも多額の養育費を取り決める場合は、贈与税申告の要否について税理士などに確認しましょう。
養育費を一括で受け取った場合
離婚時に養育費を取り決める段階で、将来分を含めた金額を一括で支払うケースが稀に見受けられます。
離婚する夫婦の間で合意すれば、養育費を一括で精算すること自体は問題ありません。ただし、養育費を一括で受け取る場合には、贈与税が課される可能性があるので注意が必要です。
贈与税が非課税となる養育費は、生活費または教育費として必要な都度、直接これらの用に充てるために受け取ったものに限られると解するのが税務署の運用です。「必要な都度、直接」という点がポイントになります。
毎月受け取る養育費は、月々の子どもの生活費等に充てるべきものなので、原則として「必要な都度、直接」受け取ったものに当たります。
これに対して、一括で受け取った養育費は「必要な都度、直接」という要件を満たさないため、その全額について贈与税が課される可能性があるので注意しましょう。
ただし、一括で養育費を受け取ったからといって、必ず贈与税が課されるとは限りません。相続税法基本通達の逐条解説では、一括で支払われた養育費の金額が相当と認められる限りは、「通常必要と認められるもの」として取り扱うとの記載があります。
つまり、一括で受け取った養育費が贈与税の課税対象になるかどうかは、金額を中心とした実質判断になるということです。
非常に判断が難しいポイントなので、一括で養育費を受け取ることを検討している場合は、事前に税理士などへ相談することをおすすめします。
受け取った養育費を預金や投資などに充てている場合
養育費として受け取った金銭は、法律上はどのように使っても構いません。必ずしも子どもの生活費や学費などに充てなくてもよいですし、資金使途を元配偶者に報告する義務もありません。
ただし、贈与税の課税との関係では、養育費として受け取った金銭の使途が問題になるケースもあるので注意が必要です。
養育費として受け取った金銭であっても、贈与税が非課税となるのは、生活費または教育費に充てるために受け取ったものに限られます。それ以外の用途に充てている場合は、贈与税が課税される可能性があります。
養育費として受け取った金銭をそのまま預金として寝かせているケースや、株式・不動産などへの投資に充てているケースでは、税務署に指摘されて贈与税が課される恐れがあるので注意が必要です。
養育費について、実際に贈与税の追徴課税がおこなわれるケースは稀ですが、念のため税法上のルールを理解しておきましょう。
養育費を支払っている場合、扶養控除は受けられる?
養育費を支払っている側が確定申告をおこなう場合に、問題となるのが「扶養控除」を受けられるかどうかです。
子どもの親権者でなくても、養育費を支払っていることを理由に、確定申告の際に扶養控除を
受けられることがあります。要件を確認したうえで、該当している場合には忘れずに扶養控除の適用を受けましょう。
扶養控除とは
「扶養控除」とは、控除対象扶養親族がいる人が、所得税・住民税の計算に当たって受けられる所得控除です。
自分以外に養わなければならない家族がいる場合は、生活費などとして支出する金額が多くなります。その分生活に余裕がなくなるため、所得税・住民税を軽減することでサポートしようというのが、扶養控除の趣旨です。
【参考】No.1180 扶養控除|国税庁
扶養控除を受けるための要件
扶養控除を受けられるのは、控除対象扶養親族がいる方です。「控除対象扶養親族」とは、その年の12月31日時点において、以下の要件をすべて満たす方をいいます。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または里子、市町村長から養護を委託された老人であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること
- 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
- 16歳以上であること
たとえば納税者と同居している子どもは、「配偶者以外の親族」であって、「納税者と生計を一にしている」と評価できます。したがって、上記3から5の要件を満たせば控除対象扶養親族に該当し、子どもの親である納税者は扶養控除を受けられます。
扶養控除の金額
扶養控除の金額は、扶養親族の年齢・同居の有無などに応じて、以下のとおり決まっています。
|
扶養親族
|
控除額
|
|
一般の控除対象扶養親族
(その年の12月31日時点で16~18歳、23~69歳)
|
38万円
|
|
特定扶養親族
(その年の12月31日時点で19~22歳)
|
63万円
|
|
老人扶養親族
(その年の12月31日時点で70歳以上)
|
(1)同居老親等※の場合
58万円
※同居老親等:納税者または配偶者の直系尊属で、納税者または配偶者との同居を常としている人
(2)(1)以外の場合
48万円
|
子どもが控除対象扶養親族に当たる場合、その年の12月31日時点で16歳から18歳であれば38万円、19歳から22歳であれば63万円の扶養控除が受けられます。
養育費を支払っている人が、扶養控除を受けられるケース
子どもについて扶養控除を受けられるのは、子どもと同居している親権者に限りません。子どもと別居している親や、親権を持っていない親であっても、子どもと「生計を一にしている」場合には扶養控除を受けられます。
子どもと日常の起居を共にしていない場合でも、常に生活費・学資金・療養費等の送金をおこなっている場合には「生計を一にする」ものとして扱われます。
養育費は生活費・学資金・療養費等に充てるべきものなので、養育費を支払っている人は、その子どもについて扶養控除を受けられる可能性があります。
国税庁の照会回答では、以下に挙げる2つに当てはまる場合には、養育費を支払う子どもを扶養控除の対象として差し支えないことが示されています。
- 扶養義務の履行として支払われる場合
- 子どもが成人に達するまでなど、一定の年齢等に限って支払われる場合
多くの例で見られるように、子どもが一定の年齢に達するまで毎月養育費を支払うケースでは、子どもをご自身の扶養控除の対象とすることができます。
また養育費を一括で支払った場合でも、それを信託財産として受託者から受益者である子どもへ継続的に養育費が給付されている場合には、給付期間中は子どもを扶養控除の対象にして差し支えありません。
信託を利用した養育費の一括払いは、将来にわたる養育費の支払い原資を確保し、不払いを防ぐ目的でおこなわれることがあります。
元配偶者に対して直接養育費全額を一括払いするのではなく、信託を介して継続的に支払うことで、子どもをご自身の扶養控除の対象とすることが可能です。
【参考】生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)|国税庁
養育費を支払っている人が、扶養控除を受けられないケース
養育費を支払っている子どもが「控除対象扶養親族」の要件を満たさない場合は、扶養控除を受けることができません。
具体的には、以下に挙げる場合には扶養控除の対象外となります。
子どもが16歳未満の場合
子どもが扶養控除の対象となるのは、16歳以上である場合だけです。
以前は16歳未満(15歳以下)の子どもも、扶養控除の対象に含まれていました。しかし、2012年度に16歳未満の子どもが児童手当の支給対象となったことに伴い、財源確保のために扶養控除の対象から除外されました。
なお、児童手当は子どもを養育している人、つまり一緒に住んでいる親が支給対象です。よって、離婚して子どもと一緒に住んでいない場合、養育費を支払っていても児童手当は受け取れない点にご注意ください。
養育費を一括で、相手に直接支払った場合
養育費を一括して、相手に直接支払った場合には、扶養控除の要件の一つである「子どもと生計を一にしていること」を満たさない可能性が高いでしょう。
「生計を一にする」とは、日常の生活の資を共にすることを意味します。生活費・学資金・療養費等に充てる養育費の送金を「常に」おこなっている場合には、「生計を一にする」ものと評価されます。
しかし養育費を一括で支払った場合は、「常に」養育費を送金しているわけではないので、「生計を一にしている」とは認められない可能性が高いのです。
ただし相手に直接支払うのではなく、養育費を一括で信託して子どもへ継続的に給付している場合には、給付期間中は子どもを扶養控除の対象にして差し支えないことが国税庁によって示されています。
慰謝料や財産分与から養育費を区分できない場合
夫婦が離婚する際、慰謝料や財産分与を一括で支払うことができないために、分割払いとするケースがあります。
扶養控除との関係で注意すべきなのは、慰謝料や財産分与を毎月払いとしたうえで、「養育費とまとめて月○円」などと取り決めるケースです。
この場合、慰謝料や財産分与から養育費を区分できなければ、養育費を支払う人が扶養控除を受けることはできないと解されています。
養育費を支払う人が、離婚後に子どもについて扶養控除を受けようとする場合には、内訳を明記して慰謝料や財産分与から養育費を区分できるようにしておきましょう。
子どもの所得が48万円を超える場合
養育費を支払う子どもの年間の合計所得金額が48万円を超える場合は、養育費を支払う人が扶養控除を受けることはできません。
「合計所得金額」とは、以下の所得の合計額です。
- 事業所得
- 不動産所得
- 給与所得
- 総合課税の利子所得
- 総合課税の配当所得
- 総合課税の短期譲渡所得
- 雑所得
- 総合課税の長期譲渡所得の2分の1
- 一時所得の2分の1
- 退職所得
- 山林所得
- 申告分離課税の所得
なお、給与所得については給与所得控除後の金額となるため、受け取った給与の額が103万円以下であれば扶養控除の対象となります(給与以外に所得がない場合)。
子どもがアルバイトや個人事業などをしている場合には、年間合計所得が48万円を超えるケースも想定されます。この場合、養育費を支払っていても扶養控除を受けることができないので注意が必要です。
養育費を支払っている人が扶養控除を受けるための手続き
養育費を支払っている人が扶養控除を受けるためには、勤務先に扶養控除等申告書を提出するか、または確定申告書の所得控除欄に扶養控除の金額を記載しましょう。
勤務先に扶養控除等申告書を提出する
会社員など事業主に雇用されている方であれば、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば、年末調整によって扶養控除を受けることができます。
扶養控除等申告書の中段に、「主たる給与から控除を受ける」「「B 控除対象扶養親族(16歳以上)」という記載欄があります。この欄に、養育費を支払っている子どもの情報を記載すれば、扶養控除を受けられます。
通常であれば前年末の段階で、会社から扶養控除等申告書の提出を求められますので、その際に所定の事項を記載して会社に提出しましょう。
【参考】[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁
確定申告書の所得控除欄に記載する
個人事業主の方などが確定申告をおこなう場合、確定申告書に所定の事項を記載することで、扶養控除を受けることができます。
また、会社員などの方が年末調整の際に扶養控除を受けられなかった場合にも、確定申告をすれば扶養控除を受けることが可能です。
まず、第一表の「所得から差し引かれる金額」「扶養控除」の欄に、扶養控除の金額を記載します。
養育費を支払っている子どもが16歳~18歳であれば「38万円」、19歳~22歳であれば「63万円」です。なお、16歳未満の子どもについては、養育費を支払っていても扶養控除を受けることができません。
「区分」の欄については、子どもが国外居住でなければ記載する必要はありません。
子どもが国外居住であれば、勤務先に「親族関係書類」と「送金関係書類」の両方を提出している場合には「2」、いずれか一方でも提出していなければ「1」と記載します。区分を「1」と記載した場合は、確定申告書に親族関係書類と送金関係書類を添付しなければなりません。
第二表の「配偶者や親族に関する事項」の欄には、養育費を支払っている子どもの情報を記載します。
なお、国税庁のサイトから電子申告を行えば、画面上の入力指示に従って、扶養控除に関する情報をスムーズに入力することができます。
【参考】国税庁 確定申告書等作成コーナー
【参考】確定申告書等の様式・手引き等(令和3年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
※令和3年分のものです。令和4年分以降は変更される可能性があるのでご注意ください
扶養控除は重複適用不可|父母両方が受けることはできない
扶養控除について注意すべきなのは、同じ子どもについて父母両方が扶養控除を受けることはできない点です。
扶養控除を両方の親が受けた場合、追徴課税を受ける可能性がある
扶養控除を両方の親が受けた場合、少なくともどちらかは所得を過少に申告したことになります。そのため、税務署から指摘を受け、追徴課税を受ける可能性があるので注意が必要です。
扶養控除をどちらの親が受けるかは選べる
子どもが両方の親の控除対象扶養親族に当たる場合、どちらの親が扶養控除を受けるかについては、親同士の取り決めに従って自由に選ぶことができます。
児童手当などとは異なり、所得の多寡によって扶養控除を受けられる親が決まるわけではありません。
そのため、年末調整や確定申告の際にどちらが扶養控除を受けるかについては、あらかじめ親同士で話し合っておきましょう。
扶養控除と親権は無関係
子どもについてどちらの親が扶養控除を受けるかは、離婚後だけでなく、離婚協議の段階でも問題になる可能性があります。
扶養控除を受けているからといって、子どもの親権争いで有利になるわけではありません。反対に扶養控除を受けていないことが、親権争いにおいて不利に働くこともありません。子どもの親権は、あくまでも養育の実態などを総合的に考慮して決定すべきものです。
子どもの親権について揉めている場合でも、扶養控除の取り扱いについては別の論点として話し合いましょう。
まとめ
養育費として受け取った金額は、確定申告時の所得に含める必要はありません。ただし、金額が過大な場合・一括で受け取った場合・養育以外の用途に使っている場合には、贈与税が課される可能性があるので注意が必要です。
養育費を支払う側は、年末調整や確定申告の際に、子どもについて扶養控除を受けられることがあります。
ただし、両方の親が扶養控除を受けることはできないので、どちらが扶養控除を受けるかをきちんと話し合っておきましょう。
養育費に関する税務上の疑問点がある場合には、税理士などに相談することをおすすめします。
子どもの養育費、適切額分もらえていますか?
離婚時に取り決めた金額分の養育費を毎月受け取っていても、本当はもう少し欲しい…と思ったことはありませんか?
結論からいうと、事情によっては受け取る養育費をあとから増額することが可能です。少しでも養育費について不満がある方は、まずは弁護士の無料相談を利用してみましょう。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。
- 養育費の適正額を試算してもらえる
- 養育費の交渉についてアドバイスをもらえる
- 万が一相手と揉めても、依頼すれば代理で交渉してもらえる
当サイトでは、離婚問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。