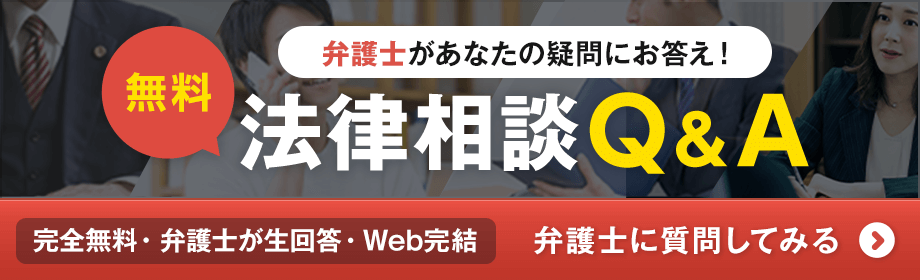離婚後の妊娠|生まれた子の実父と認知されるための方法3つ


民法772条2項によって、「婚姻成立から200日経過したあと」または「離婚後300日以内」に誕生した子供は婚姻中に妊娠したものと推定され、婚姻中の夫婦の間に生まれた子供として戸籍に記載されます。
したがって、離婚後に元夫以外の男性の子供を妊娠し出産したとしても、産まれてくる子供は元夫の子供でないにも関わらず元夫の子供とされてしまいます。これらは300日問題とも呼ばれており、規定内容が時代錯誤であるとして見直しを求める声も上がっています。
今回の記事では、離婚後の300日問題とその解決方法について紹介します。
離婚後の妊娠で起こる300日問題とは
離婚後の300日問題とは、離婚が成立してから300日以内に妊娠・出産した子供は、前の夫の子供と推定する法律(民法第772条)によって起こる様々な問題を指しています。
(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
引用元:民法第772条
この法律での規定は、子供の父親が100%前の夫であるケースであれば特に問題はありませんが、もしそうでない以下のようなケースでは非常に厄介になってきます。
自動的に前夫の子供になる
何らかの理由で夫婦関係が破綻しており、別の男性と不貞関係にあった。離婚は成立したのにその後300日以内に不貞関係にあった男性の子供を出産した。
上記のようなケースでは、生まれてきた子供は法律によって自動的に母親の前の夫の戸籍に入ることになり、前の夫の子供であるとみなされてしまいます。
出生届を出さず戸籍のない子供になる
この法律での決まりによって、前の夫の戸籍に入ることを避けるがために出生届けを提出出来ないことや、実の父親の名前を書いても戸籍が異なるため受理されないなどの問題が起こってしまうのです。その結果、戸籍のない子供が存在している現実があります。
ちなみに、離婚成立後から300日以上経過しており母親がまだ再婚していなければ、生まれた子供は非摘出子(婚外子)として母親の戸籍に入ることになります。非摘出子(婚外子)とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供のことをいいます。その生まれた子供が前の夫の子供であれば前の夫に認知を求めます。
認知をすれば現在の夫の子供として認められる
父親が別の男性であるならば、必要に応じて実の父親である男性に認知を求めます。生まれてきた非摘出子の父親が「認知」を行うことで、戸籍に父親の名前を記すことができます。認知をするには、認知届を子供の本籍地もしくは住所地の役所に提出すれば手続きが行われます。
なぜ離婚後に妊娠・出産した子は自動的に元夫の戸籍に入るのか
子供は母から生まれてくるので、子供の母親は明確にわかります。しかし状況によって父親が誰であるのかはわからないということが起こりえるのです。そのため法律では、以下のように妊娠についての規定を定めています。
・妻が婚姻中に妊娠した子供は夫の子供とする
・結婚して200日経過後もしくは離婚から300日以内に生まれた子供は婚姻中の妊娠とする
上記の規定により、離婚後300日以内に生まれた子供は前の夫の子供であると推定されるのです。仮に別居中で長く会っていない夫であったとしても、離婚後300日以内に生まれると前の夫の子供だと扱われます。
一般的に考えて、このようなケースでの子供は母親の新しい恋人や再婚相手の子供である可能性のほうが高いはずですが、法律での解釈は異なるのです。
つまり、いかなる理由があったとしても離婚後300日以内に生まれた子供の戸籍を取得するためには、とりあえず前の夫の子どもとして出生届を提出する必要があります。
【オススメ記事】
離婚問題のよくある相談事例と無料相談先まとめ
離婚後に妊娠した子の出生届を提出しない場合のリスク
離婚後の300日問題により、一時的ではあっても離婚した夫の戸籍に子供を入れるなんて考えられないという想いから、母親が出生届けを提出しないケースがあります。
無戸籍児童になる
そうなると戸籍は基本的に出生届けを元に作成されるため、生まれた子供は戸籍の取得ができず、一時的にであっても無戸籍児童となってしまいます。つまり、この世に存在しない子供とみなされてしまうのです。
無戸籍者は全国に少なくとも719人
法務省の調査によると平成29年に把握した無戸籍者の数は719人とされています。
【参考:法務省説明資料】
選挙権と被選挙権の行使ができない
出生届を出さずに戸籍を取得できないと「参政権の行使」はできません。つまり選挙権と被選挙権の行使です。これらについては、公職選挙法と地方自治法に規定があり戸籍なしの無戸籍の人は参政権を得る事ができません。
然るべき手続きをすれば住民票は作れる
出生届を出さないリスクはかなり大きいと思われがちですが、実は出生届を提出せずに一時的に戸籍がない状況でもしかるべき手続きを行えば住民票の作成が可能です。
住民票があれば行政サービスを受けることができます。詳しくは後述しますが、この勘違いで損をすることや不利な状況に追い込まれることは避けるように気をつけましょう。
法改正によって女性の再婚期間が100日に短縮
民法第772条によって規定されていた女性の再婚期間6カ月が、「100日を超える禁止期間は憲法に違反する」として、2015年12月の最高裁判決を受けて、100日に短縮するというが成立しました。
民法改正で何ができるようになったのか?
これまでの民法第772条では、子どもの父親「子供が離婚後300日以内に生まれたなら前夫の子」「200日過ぎて生まれたなら現夫の子」と定めていましたが、離婚時に女性が妊娠していないことを医師が証明した場合、離婚から100日以内であっても再婚を認める条文が盛り込まれています。
民法の改正の概要
1 女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から起算して100日としました。
2 女性が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎(妊娠)していなかった場合又は女性が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合には再婚禁止期間の規定を適用しないこととしました。
引用元:総務省|民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)について
この改正に伴い,平成28年6月7日から,前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻の届出の取扱いが,次のとおり開始されます。
(1)民法第733条第2項に該当する旨の証明書について
「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」とは,再婚をしようとしている本人である女性を特定する事項のほか,(1)本人が前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること,(2)同日以後の一定の時期において懐胎していないこと,(3)同日以後に出産したことのいずれかについて診断を行った医師が記載した書面をいいます。
引用元:総務省|「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付された婚姻の届出の取扱いについて
なぜ100日残したのか?
もしすぐに再婚した場合、離婚後から200日たった後に子が生まれると、前夫と現夫で推定が重なってしまうため、100日の再婚禁止期間は残したとされています。
【オススメ記事】
離婚問題のよくある相談事例と無料相談先まとめ
離婚後に妊娠した子の実の父親として認めてもらう方法

こちらでは産まれてきた子供と前の夫との親子関係を解消し、現在のパートナーを実の父親として認めてもらう4つの方法を紹介します。
1. 嫡出否認調停
産まれてくる、もしくは産まれた子供が前の夫の子供でないケースでは、前の夫に家庭裁判所へ嫡出否認調停を申し立ててもらいます。調停を通して元夫婦同士で前の夫の子供ではないと合意ができた上で、家庭裁判所が調査を行いその同意した内容が事実であると証明できた場合、前の夫と産まれた子供の間の親子関係がないことが証明されます。
この調停は子供が産まれてから1年以内に行わなければいけません。また、前夫が一度でも自分の子供であると認めた場合、この調停を申し立てることができないので、注意が必要です。戸籍法では子供が産まれてから14日以内に出生届を提出しなければならないと定められています。この調停の結果を待って出生届を提出するとなると14日以内に間に合わない可能性が高いです。
しかし、嫡出否認調停を行っていることを役所に相談しておけば、出生届が提出されていない時点でも産まれてきた子供の住民票の作成をしてもらうことが可能です。
2. 親子関係不存在確認調停
親子関係不存在確認調停は家庭裁判所に申し立てる調停です。離婚後300日以内に産まれた子供であっても、夫が何らかの理由(海外への長期単身赴任など)で妻が夫の子供を妊娠する可能性が客観的に無いと明らかになれば、夫と産まれた子供の親子関係を解消することができます。申し立ては産まれた子供、実の父親、その両親が行うことができ、申し立ての期限がありません。
3. 離婚後の妊娠の証明
離婚後に妊娠があったと医師の証明書があれば、前の夫の子供であると認定されずに実の父親の子どもとして出生届を提出することが可能です。しかしこれは妊娠が離婚前であるケースでは認められません。
離婚後に妊娠した子の住民票は任意で作成が可能

まずは「戸籍」と「住民票」の違いを整理しましょう。
戸籍
親子関係や婚姻関係などを公的に証明する書類。戸籍にいる人(家族)全員でひとつの単位となっている。
住民票
市区町村で作成される住民の居住関係を公的に証明する書類。1人に1つ設けられている。
戸籍は国が管理しており、住民票は自治体が管理しています。無戸籍者はそのまま無住民票者になるケースが多いですが、仮に戸籍がない人でも日本の市区町村に居住しているのであれば住民票を作成することは可能です。
出生届を提出していない、お金がないと住民票を作れないというような、誤った思い込みから住民票がなく公的なサービスが受けられない人は、居住している市区町村役所に相談してみましょう。調停などの最中であれば、相談の際に調停を行っていることが証明できる書類を忘れずに持参しましょう。
また、住民票がなければ取得できないと思われがちな健康保険ですが、健康保険の取得に住民票の添付は必要とされていないのです。
【オススメ記事】
離婚問題のよくある相談事例と無料相談先まとめ
まとめ
いかがでしたでしょうか?
離婚後の300日問題では、残念ながら産まれてくる子供は自動的に元夫の戸籍に入ってしまう可能性が高いです。
しかし、今回紹介した対処法を取れば、母親の戸籍・もしくは実の父親の戸籍に子供を入れることが可能ですので安心してください。


【初回相談料60分5500円】ご自身又はお相手が経営者・不動産を多数所有している方など複雑な財産分与も◎◆経験豊富な弁護士がご満足のいく解決を目指します◆別居・不倫など幅広い離婚問題に対応◎【茅場町・日本橋駅から徒歩5分・東京証券取引所前】
事務所詳細を見る
◆<夜間休日もOK>実施中!◆不倫・不貞の慰謝料請求したい/請求された方◆「離婚を決意」した方◆実績豊富な弁護士が、あなたにぴったりの具体的な解決策をアドバイス!【相談実績300件超】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

親権(子供)に関する新着コラム
-
この記事では、夫以外の男性との間にできた子どもを夫の子だと偽る「托卵」が露見するケースと、それが発覚した場合に日本の法律で何が起こり、どのように対処すべきかを詳...
-
離婚後子どもを育てられる自信がなく、夫に親権を渡したいと考えている方もいるかもしれません。しかし夫側も親権を拒否すれば、お互いに親権を押し付け合うことになります...
-
離婚を検討しているなかで、母親が親権をもつ場合に子どもの苗字を変えたくないと思っている方は少なくないでしょう。本記事では、離婚時に子どもの苗字を変えない場合は戸...
-
親権は必ず母親が獲得できるのか、夫に親権が渡ることはあるのかなど、不安に思う方もいるでしょう。この記事では、母親が親権を獲得できないケースや、親権を獲得したいと...
-
離婚をするとき、子どもの親権は大きな争点となるでしょう。 一般的には母親が親権を獲得しやすいイメージがありますが、必ずしもそうではありません。 本記事では、...
-
本記事では、離婚後に親権者を父親から母親へ変更するのが難しい理由や手続きの流れ、成功事例について解説します。本記事を読むことで、ご自身のケースで離婚後の親権変更...
-
親権争いは基本的に母親が有利とされていますが、夫も主体的に育児参加している場合などは夫が親権を持つ可能性もあります。本記事では、夫が親権を持つパターンを事例とと...
-
本記事では、親権変更が認められるケースや、親権変更を成功させるためのポイントなどをわかりやすく解説します。親権者変更は調停を申し立てる必要があるので、手続きの流...
-
離婚の際、子供の親権者をどちらにするか争いになる場合があります。 親権獲得のためにかかる費用や親権獲得までの流れ、親権に関する問題を弁護士に相談するメリットを...
-
夫婦が離婚する場合、未成熟子の親権者は母親になるケースが多いものの、調停や裁判で親権を争う場合、父親が親権を獲得する場合もあります。本記事では、親権がない母親と...
親権(子供)に関する人気コラム
-
離婚しても、どちらの親も親権をほしい場合、離婚協議や調停で揉める可能性があります。この記事では、離婚する際に子供の親権を獲得するために知っておくべき基礎知識や有...
-
親権を父親が獲得するにはどうすればいいのか?今回は離婚の際、親権を父親が獲得しづらい理由や、父親が親権を獲得するために離婚調停を有利に進める方法をお伝えします。...
-
親権と似た意味で捉えられるのが子供を育てる権利・義務である監護権。今回は親権と監護権の違いを把握するとともに、親権者・監護者を決める手続きの方法などをご紹介しま...
-
離婚する際、子供への説明は十分でしょうか?親の離婚は子供にとって大きな影響を与えます。この記事では、子供への影響や子供が受けるストレスを最小限に抑える対策、子供...
-
離婚後に元夫以外の男性の子供を妊娠し出産したとしても、産まれてくる子供は元夫の子供とされてしまう問題を「300日問題」と言います。今回の記事では、離婚後の300...
-
別居で子供と離れ離れになってしまった場合、そのまま放置するのは危険かもしれません。この記事では、妻が子供を連れて別居してしまった場合の対策から、子供を連れて別居...
-
「離婚後も子供に会いたい」と考えている方は少なくありません。この記事では、親権がなくても会えるのか?養育費を払わなければ会えないのか?面会する上での注意点はある...
-
子供がいる専業主婦が離婚を考えたとき、親権を持つことが難しいのではとためらっている方も多いでしょう。しかし、必ずしも親権を持つ上で専業主婦であることが不利になる...
-
離婚したあと、子どもの戸籍や姓をどうすべきか悩む方は多いでしょう。基本的には離婚しても子どもの戸籍や姓は変わりませんが、いくつか注意すべき点もあります。この記事...
-
親権とは、未成年の子の養育監護や財産管理をする権利・義務を指します。適法な手続きをとれば親権放棄は可能ですが、親権放棄が認められるのは子どもの福祉を守るためにや...
親権(子供)の関連コラム
-
親権を父親が獲得するにはどうすればいいのか?今回は離婚の際、親権を父親が獲得しづらい理由や、父親が親権を獲得するために離婚調停を有利に進める方法をお伝えします。...
-
夫婦が離婚する場合、未成熟子の親権者は母親になるケースが多いものの、調停や裁判で親権を争う場合、父親が親権を獲得する場合もあります。本記事では、親権がない母親と...
-
親権をなんとしても獲得したいなら、親権問題に注力している弁護士に依頼しましょう。親権を含む離婚の条件は、任意の話し合いから調停、訴訟へと進みます。話し合いから弁...
-
子どもの親権は子どもが成年に達するまで続きます。2022年4月には、改正民法が施行され、成年年齢が引き下げられました。この記事では、親権の存続期間・親権の内容・...
-
離婚の際に決めた子どもの親権者を変更するには、家庭裁判所に「親権者変更調停」を申し立てる必要があります。親権者変更調停について、手続きの流れや、家庭裁判所が主に...
-
離婚の際、子供の親権者をどちらにするか争いになる場合があります。 親権獲得のためにかかる費用や親権獲得までの流れ、親権に関する問題を弁護士に相談するメリットを...
-
親権問題を無料で相談できる機関や窓口はあるのでしょうか?この記事では、親権問題を無料相談できるおすすめの相談先のご紹介から、弁護士に相談すべき人と相談のタイミン...
-
子供の虐待は近年増加傾向にあり、厚生労働省の発表では平成24年度の児童虐待の相談対応件数は、平成11年度の児童虐待防止法施行前と比べて約5.7倍に増加し、66,...
-
子供がいる専業主婦が離婚を考えたとき、親権を持つことが難しいのではとためらっている方も多いでしょう。しかし、必ずしも親権を持つ上で専業主婦であることが不利になる...
-
別居で子供と離れ離れになってしまった場合、そのまま放置するのは危険かもしれません。この記事では、妻が子供を連れて別居してしまった場合の対策から、子供を連れて別居...
-
離婚を検討しているなかで、母親が親権をもつ場合に子どもの苗字を変えたくないと思っている方は少なくないでしょう。本記事では、離婚時に子どもの苗字を変えない場合は戸...
-
離婚後子どもを育てられる自信がなく、夫に親権を渡したいと考えている方もいるかもしれません。しかし夫側も親権を拒否すれば、お互いに親権を押し付け合うことになります...
親権(子供)コラム一覧へ戻る