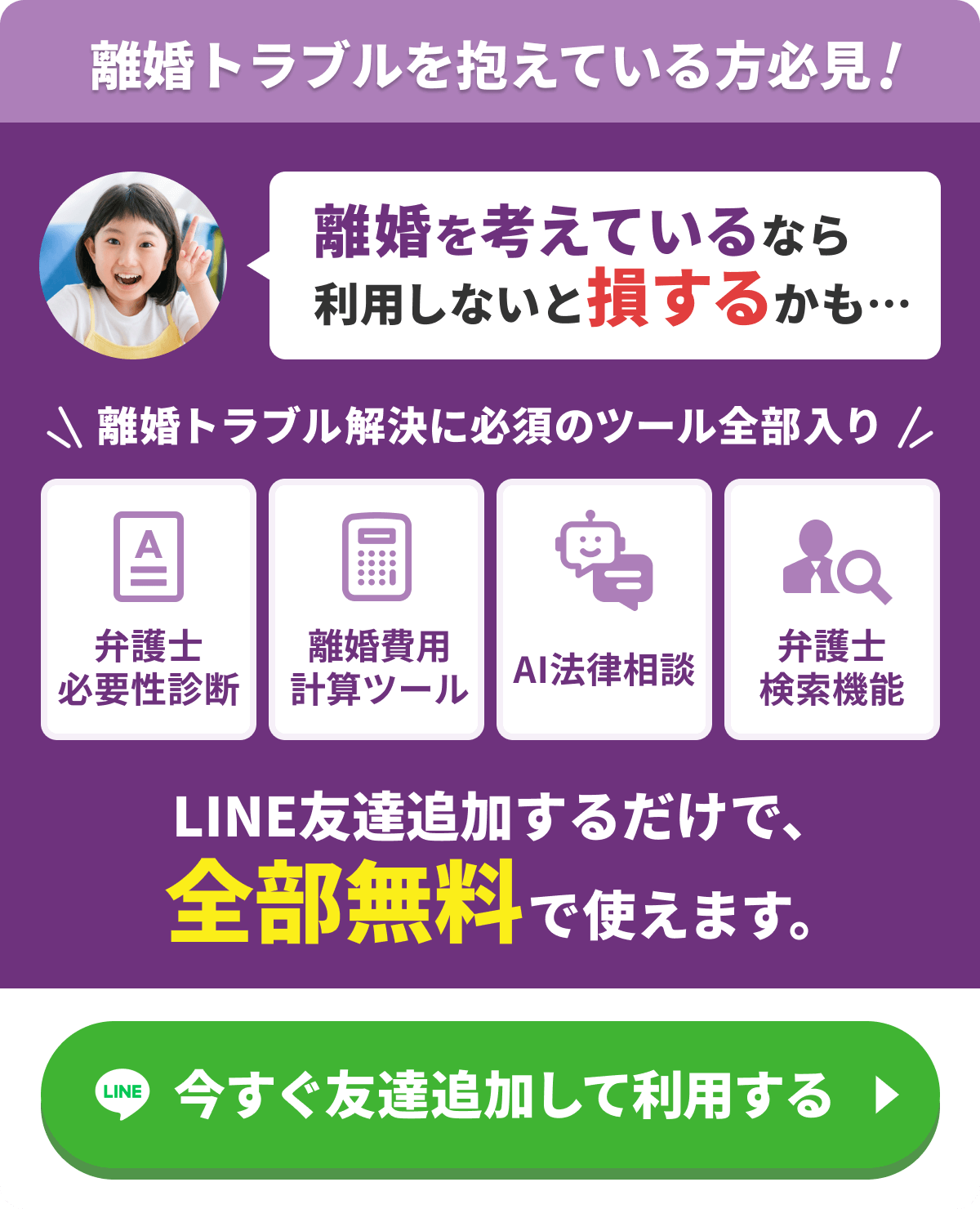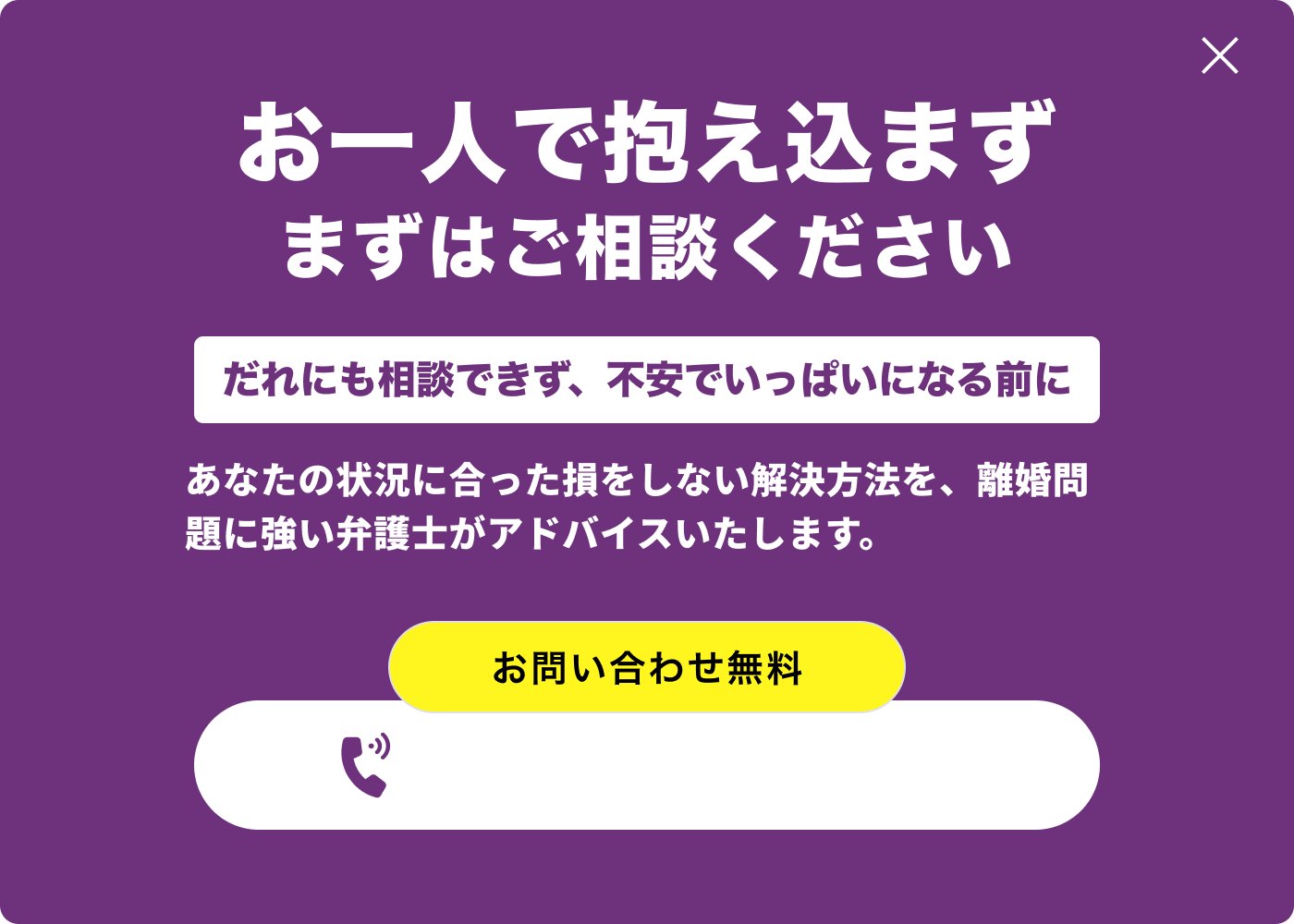「DV」が得意な弁護士に相談して悩みを解決!
お悩み内容から探す

現在、配偶者からの暴力に悩んでいる方やDVを理由に離婚を考えている方、またはその家族や友人にとって、「接近禁止命令(せっきんきんしめいれい)」はとても有効な法的手段です。
本記事では、接近禁止命令の効果や申し立て方法、注意点などを詳しく解説します。
配偶者のDVから今すぐ逃げ出したい方へ
配偶者からの暴力行為により精神的・身体的なダメージを受け、すぐにでも接近禁止命令を申し立てたいと悩んでいませんか?
DVに関する問題は弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
- 接近禁止命令の申し立てが可能か相談できる
- 依頼すると、配偶者と顔を合わせずに離婚の交渉ができる
- 依頼すると、接近禁止命令申し立て後の付きまといに対処できる
当サイトでは、DV問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
接近禁止命令とは?具体的な内容と効果
接近禁止命令とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)で定められている保護命令のひとつを指します。
「身体的暴力や生命・身体に対する脅迫(〇〇したら殺す・殴るなど)をしてくる配偶者の接近を禁止する」という制度です。
実際に接近禁止命令を利用している人は減少傾向にあるものの年間2,000人程度おり、多くの方が接近禁止命令によって暴力や脅迫などの恐怖から逃れています。

引用元:I-7-6図 配偶者暴力等に関する保護命令事件の処理状況等の推移 | 内閣府男女共同参画局
禁止できる2つの行為
- 身辺の付きまとい
- 住宅・勤務先・常在している周辺へのうろつき
ただし、この接近禁止命令は電子メールや電話での接触については禁止していません。
そのため、加害者からメールや電話で接触されたり脅迫されたりする可能性があります。
また、接近禁止命令は申立てをした本人のみ有効であるため、子どもへの接近や実家への押しかけは禁止できません。
もし、そのようなことに対して禁止したい場合は、接近禁止命令以外の保護命令を追加する必要があります。
接近禁止命令だけでは禁止できないこと(他に取るべき手段)
接近禁止命令だけでは、相手が電話・メール等を送信する行為や、相手が申立人の子どもや親族へ接近する行為(連れ去りや嫌がらせ等の暴力)から守ることができません。
そこで、相手からの電話・メール等の防止や子どもや親族を守るため、下記の禁止命令を申立てることも法律上可能です。
- 被害者への電話等禁止命令
- 被害者と同居中の子どもへの接近禁止命令
- 被害者の親族等への接近禁止命令
なお、これらは「被害者への接近禁止命令が発せられていること又はこれと同時に発せられるもの」となっており、被害者本人への接近禁止命令が発せられる状況にあることが前提条件となっています。
また、被害者が申立ての時点において相手と生活の本拠を共にしていた場合は、接近禁止命令と同時に、相手は被害者と一緒に暮らしている住居から命令の効力が生じた日から2ヵ月の間に退去し、さらにその間付近を徘徊しないよう命じられます(退去命令)。
期待できる効果
保護命令に違反した場合は、罰則があることから相手へのけん制ないし抑止力となります。
また保護命令が発令された場合、その内容が地方裁判所から警察や配偶者暴力相談支援センターへ通知されます。
これにより、関係機関からの迅速な対応を期待できます。
なお、配偶者暴力相談支援センターに通知をしてもらうには、申立の前に事前に支援センターに相談していることなどが必要となりますので、不明点がある場合は申立て前に支援センターに相談してみましょう。
違反した場合の罰則
接近禁止命令に違反した場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます。
第二十九条 保護命令(前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四項まで及び第十条の二の規定によるものを含む。第三十一条において同じ。)に違反した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
引用元:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 | e-Gov法令検索
なお、ほかの保護命令に違反した場合も同様に科されます。
接近禁止命令の申し立てが可能な対象者
相手方とどのような関係でも接近禁止命令ができるわけではありません。
接近禁止命令の申立ての可否については、厳格な要件が定められています。
- 申立人と相手方が、婚姻関係・事実婚関係・同棲関係のいずれかにあること
- 相手方による暴力行為または脅迫行為が①の関係継続中におこなわれたこと
- 将来的に身体的暴力を振るわれて生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きいこと
したがって、「相手と交際関係にあっても同棲関係に至っていない」という場合や、「婚姻関係・事実婚関係・同棲関係の継続中には暴力や脅迫がなく、同関係が終了後に暴力や脅迫が開始された」という場合には、接近禁止命令の申立てをおこなうことはできません。
「現在相手から暴力行為や脅迫行為を受けている」という場合には、接近禁止命令ではなく、暴行・脅迫について警察に被害申告して刑事事件として立件してもらうのが適切でしょう。
接近禁止命令をおこなう4つの手順
接近禁止命令は、以下のような流れで発令されます。

ここでは、接近禁止命令の申立て方法について解説します。
1.配偶者暴力相談支援センターか警察に相談(DVの場合)
事前準備として、まずは配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談をしましょう。
「このような機関に相談した」という事実が必要になります。
- 警察への相談:相談ホットライン「#9110」
- 配偶者暴力相談支援センターへの相談
もし「相談経験がない・相談以外の方法がよい」という場合は、公正役場に行って宣誓供述書を作成する必要があります。
2.接近禁止命令の申立て
接近禁止命令は、申立人もしくは相手方の住居地または暴力・脅迫がおこなわれた場所を管轄している裁判所に申し立てます。
また、接近禁止命令以外の保護命令も一緒に申し立てることが可能です。
必要書類
申し立てる際は、以下の書類を揃える必要があります。
- 申立書2部(正本・副本)
- 戸籍謄本及び住民票(法律上の夫婦である場合)
- 相手と同棲している事実を証明する資料(法律上の夫婦ではない場合)
- 身体的暴力・脅迫を受けていた証拠
費用
申立てに必要な費用は以下のとおりです。
- 申立て手数料(収入印紙):1,000円
- 予納郵便切手:2,500円
| 予納郵便切手内訳 |
| 500円 |
2枚 |
| 280円 |
2枚 |
| 100円 |
5枚 |
| 50円 |
5枚 |
| 10円 |
17枚 |
| 1円 |
20枚 |
手続きには何枚も必要になりますので、買い間違いや買い忘れがないように気をつけましょう。
3.口頭弁論・審問
口頭弁論・審問では、暴力や脅迫の真偽について相手側の意見を聞きます。
裁判所は、この意見を聞いて接近禁止命令を発令するかしないかを決めます。
ただし、緊急を要する事情がある場合(身体や生命に危険がある場合など)には、口頭弁論・審問をおこなわずに接近禁止命令を発令させることもあります。
4.接近禁止命令の発令
接近禁止命令は、基本的に口頭弁論や審問の際に直接言い渡されます。
しかし、相手が口頭弁論や審問に来なかった場合には、書留送達で相手宅に決定書が送付されます。
書留送達で送る際に相手が受け取りを拒否したとしても送達したことになり、効力が発揮されます。
接近禁止命令に関する4つの注意点
接近禁止命令に関する4つの注意点について解説します。
- 接近禁止命令が発令されない場合がある
- 相手が命令を守らない場合もある
- 街中でばったり遭遇した場合は罪に問えない
- 発令から時間が掛かってしまう場合もある
1.接近禁止命令が発令されない場合がある
裁判所は、接近禁止命令を発令する法律上の要件を満たすかどうかを証拠に基づき判断します。
そのため、申立書だけでなく、客観的な証拠が必要です。
客観的な証拠が不十分な場合は、接近禁止命令が発令されない可能性があります。
また、仮に証拠があったとしても、申立てから数か月前の暴力に関する証拠のみであり、現時点で暴力を受けている等の証拠がない場合、将来身体・生命等の心身に危害を受けるおそれが大きいとはいえないとして、申立てが認められない可能性もあります。
さらに、接近禁止命令を含む保護命令は、精神的なDVに対しては適用の対象外となってしまっています。
この点については内閣府の「女性に対する暴力に関する専門調査会」も保護命令の対象を拡大すべきと提言しており、法改正が待たれるところです。
2.相手が命令を守らない場合もある
違反すると罰則の適用がある接近禁止命令が発令されたとしても、相手方が罰則を恐れない場合は、命令を守るとは限りません。
接近禁止命令の発令後も、うかつな行動は避けるべきでしょう。
- 相手の行動範囲には近づかない
- 相手と通じる人物と接触をしない
- 夜間一人きりでの外出を控える
身の危険を感じたら、警察に連絡してください。
接近禁止命令が発令されると、裁判所から管轄の警察本部長または警視総監に連絡がいくことになっていますので、迅速に対応してくれるでしょう。
3.街中でばったり遭遇した場合は罪に問えない
「偶然町中で会ってしまった」という場合には、相手を罪に問うことができません。
ただし、偶然遭遇したことをきっかけに、声をかけられた・付きまとわれた・以降何度も会うなどの場合には、接近禁止命令に違反している可能性がありますので、警察または弁護士に相談しましょう。
4.発令から時間が掛かってしまう場合もある
申立人の生命や身体に危険が及ぶような事態を避けるため、接近禁止命令は基本的に優先的に処理されますが、状況によっては、もう一度裁判所に呼ばれたりして、なかなか発令されないこともあります。
医師の診断書がある場合でも、診断内容が軽い打ち身・切り傷・かすり傷などの場合には、判断が遅くなる可能性が高くなります。
接近禁止命令を延長するには再度の申立てが必要
接近禁止命令の期間を伸ばしたい場合には、再度申立てをおこなう必要があります。
ここでは、再度申立てをおこなう方法やタイミングなどを解説します。
申立てできるケース
接近禁止命令発令中、相手が「接近禁止命令が終わったら痛めつけてやる」「接近禁止命令が終わったら力ずくでも子どもに会う」などと発言しており、効力期間が終了してから身体的暴力を受ける恐れがある場合、申し立てることが可能です。
申立て方法
再度の申立てになるため、新しい事件として取り扱われます。
そのため、再び配偶者暴力相談支援センターや警察への相談、または宣誓供述書の作成が必要です。
以前に受けた暴力や、今の時点で身体的暴力を受ける恐れがあることなどを相談または記載し、再び接近禁止命令を申し立てる必要性があることを示すのが重要です。
また再度申立ての際にも、口頭弁論や審問が必要になります。
申立てから約1週間後におこなわれますが、現在発令されている命令の効力期間の終了と、再度申立てた命令の開始日が開かないように申立てをおこないましょう。
必要書類
必要書類は基本的に上記で紹介したものと同じですが、再度申立ての際は、前回申立てた際に作成した保護命令申立書と保護命令謄本の写しが必要ですので、それぞれ用意しましょう。
接近禁止命令は取消せる
発令後に状況の変化があった場合には、申立書を作成して接近禁止命令を発令した裁判所に申立てることで、命令の取消しを求めることもできます。
なお、申立人であればいつでも取消しの申立てが可能ですが、相手方は一定の条件が満たされない限り、命令の取消しを求めることはできません。
ここでは、命令の取消しに必要となる費用や、申立人ではなく相手方が申立ての取消しを求める場合の条件を解説します。
相手方が取消しの申立てをおこなう場合
相手方による申立ての取消しは、以下の条件のうち、①と②または①と③が満たされない限り認められません。
- 申立人の意義がないこと
- 退去命令の場合、保護命令の効力が生じた日から起算して2週間を経過した後に申立てたものであること
- 接近禁止命令・子どもへの接近禁止命令・親族等への接近禁止命令・電話等禁止命令の場合、保護命令の効力が生じた日から起算して3ヵ月を経過した後に申立てたものであること
したがって、申立人が取消しに同意していない限り、相手方からの申立てによって接近禁止命令が取り消されることはありません。
必要費用
申立てにかかる印紙代は、申立人・相手方ともに500円です。
しかし、予納切手の金額は「申立人が取消しの申立てをおこなう場合」と「相手方が取消しの申立てをおこなう場合」で大きく異なります。
申立人が取消しの申立てをおこなう場合
申立人が取消しの申立てをおこなう場合、82円切手が2枚で計164円かかります。
相手方が取消しの申立てをおこなう場合
相手方が取消しの申立てをおこなう場合、2,500円分の予納郵便切手が必要になります。
内訳は以下のとおりです。
| 予納郵便切手内訳 |
| 500円 |
4枚 |
| 82円 |
2枚 |
| 50円 |
3枚 |
| 20円 |
4枚 |
| 10円 |
9枚 |
| 1円 |
16枚 |
切手が全部で38枚必要になるため、十分注意してください。
さいごに
もし接近禁止命令が出ているにもかかわらず相手に付きまとわれた場合、加害者には罰則として200万円以下の罰金または2年以下の懲役が科せられます。
警察に相談をする場合には刑事事件として、弁護士に相談をした場合には民事事件として処理を進めるのが通常ですが、一番大事なことは現在の状態から脱却することではないでしょうか。
弁護士に相談して、裁判所で民事保全などの手段を講じることまでしなかったとしても、代理人弁護士として窓口にはなってくれるでしょう。
当サイトでは、DV問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずは気軽にご相談ください。