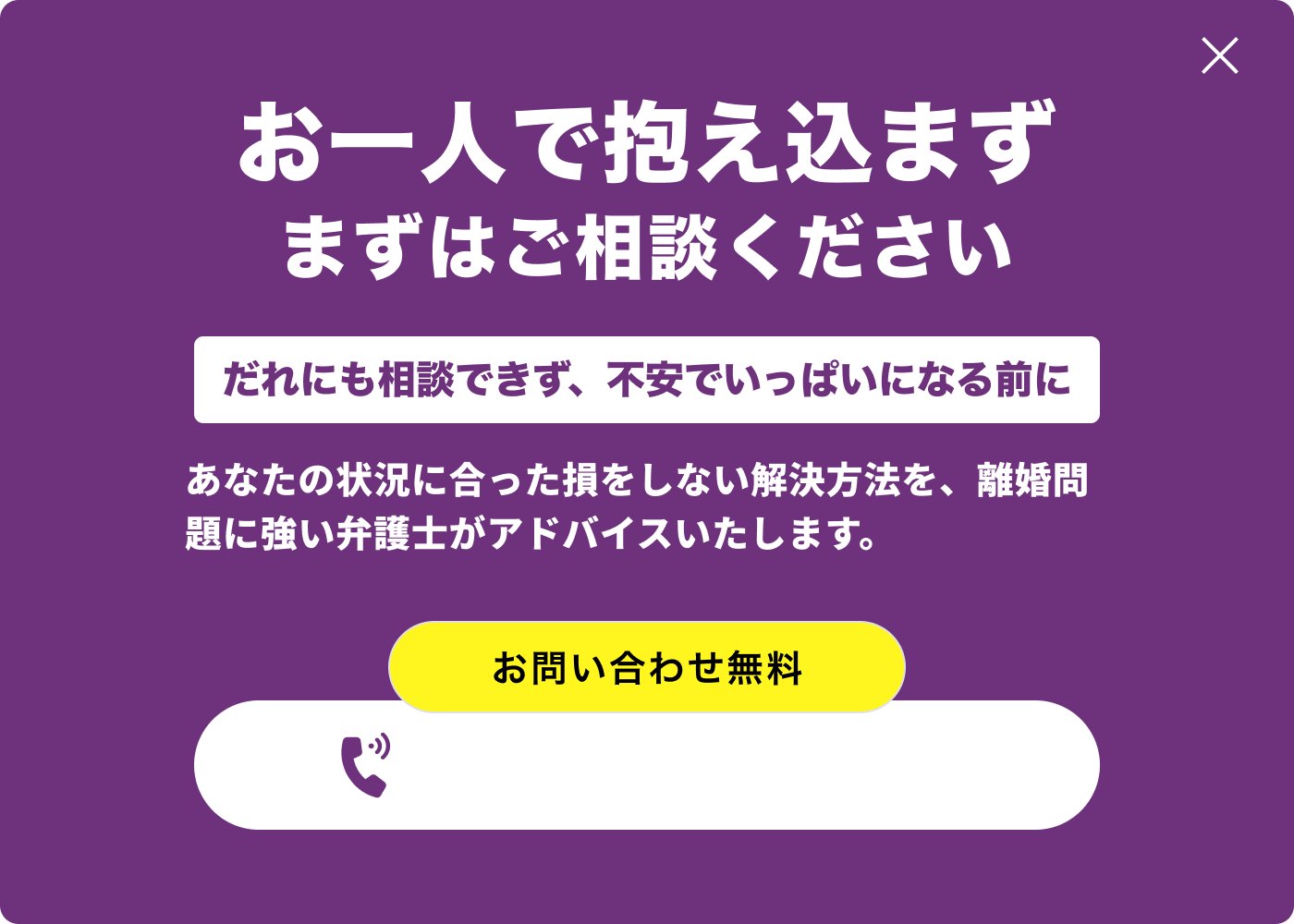面会交流は子どもが自分の親に会うための権利で、親の個人的な感情で拒否することはできません。
ただし、離婚する際にDVがあったなど、会わせることで心身や生命の危険性が懸念される場合、拒否することもできます。
ですが、一方的に拒否し続けてしまうと、訴訟などのリスクに発展します。
養育費を支払ってほしい、面会交流の内容を変えたい場合は、まず離婚問題解決が得意な弁護士へ無料相談しましょう。


面会交流の拒否や、面会交流の条件をめぐる、面会交流調停の新規受理件数は近年増加しています。
司法統計によると、令和元年は13,534件になっており、10年前の平成21年と比較すると約6,000件増加していることとなります(参考:司法統計平成21年、司法統計令和元年)。
親権者が面会交流を拒否する背景には、以下のようなトラブルや親の感情が潜んでいます。

元配偶者のせいで離婚になったので、子供を会わせたくたくない
養育費を払わないから面会交流を拒否する など
面会交流は子供の権利で、DVなど心身もしくは生命に危険がある場合を除き、養育費を支払わないことや元配偶者に離婚原因があったことなどは関係ありません。
離婚の際に取り決めを行ったにもかかわらず拒否し続けると、場合によっては訴訟に発展したり、親権を変更されたりする恐れもあるので注意が必要です。
そこで、この記事では、次の点について解説します。
ぜひ参考にしていただき、面会交流の意味と、あなたのケースに会った方法を見つけてもらえれば幸いです。
面会交流は子どもが自分の親に会うための権利で、親の個人的な感情で拒否することはできません。
ただし、離婚する際にDVがあったなど、会わせることで心身や生命の危険性が懸念される場合、拒否することもできます。
ですが、一方的に拒否し続けてしまうと、訴訟などのリスクに発展します。
養育費を支払ってほしい、面会交流の内容を変えたい場合は、まず離婚問題解決が得意な弁護士へ無料相談しましょう。
もしかしたら、まさに今「相手からしつこく面会交流を求められていて、迷っている。会わせるべきかどうするか…」と頭を抱えている方もいるのではないでしょうか。
面会交流の拒否は、場合によっては訴訟に発展してしまうなどのリスクもあるため、注意が必要です。ここでは、面会交流を拒否した場合に起き得るリスクについて解説します。
離婚調停など約束した面会交流の実施を拒否するような場合、家庭裁判所から履行勧告を受ける可能性があります。
履行勧告とは、調停などで取り決めをした面会交流について約束を守りなさいと裁判所から連絡を受けることです。
電話や書面などで、裁判所から指導を受けることになります。この履行勧告には強制力はありませんが、無視することで別の法的手段を受ける可能性があるので注意が必要です。
調停などで決定した面会交流の取り決めに従わない場合に、強制執行の一種、間接強制を受けるリスクがあります。
面会交流に関する間接強制とは、決定事項に従わないたびに、制裁金の支払いを命じるというものです。
面会交流の取り決めに違反するごとに、おおよそ5~10万円の制裁金の支払いが命じられ、これを支払わなければ別途の手続きで給料などを差し押さえられる恐れがあります。
この間接強制の狙いは、面会交流の取り決めに従わないたびに、制裁金が課されるプレッシャーを与え、面会交流を履行させようとするものです。
また、2017年には、長女を連れ去り、裁判で認められた面会交流にも応じない夫に対して、拒否1回に対して制裁金100万円とした判断も出されていますので、制裁金は5~10万円でおさまらない可能性もあります。
【参考】
面会交流の拒否で受けた、子供に会えない精神的苦痛に対して、慰謝料の支払いを求める、損害賠償請求をしてくるケースもあります。
慰謝料は、精神的な苦痛に応じた賠償を金銭で支払うことになるので、一概にいくらとは言えません。
約3年間の面会交流を再婚相手と協力し妨げたことに対し、元配偶者には70万円、再婚相手と連帯して30万円の支払いが命じられた判決もあります(平成28年12月27日 熊本地裁 2016WLJPCA12276003)。一方で、面会交流の拒否に対し慰謝料を請求した判例では、子どもが親との面会交流を拒否していたこともあり、20万円と判断されたケースもあります。
一見、間接強制と違いがないように感じられますが、間接強制は取り決めを履行しないことに対する制裁金で、履行すれば支払いをする必要はなくなります。
一方で、慰謝料は精神的苦痛に対して金銭で賠償をすることなので、その後の面会交流の有無に関わらず、下された支払い命令に応じなければなりません。
これが最も大きなリスクと言えるでしょう。面会交流を正当な理由なく拒否することを繰り返した場合、これを理由に親権変更の申立がされて、これが認められる可能性も否定できません。
父親が親権者の変更を申し立てた裁判では、母親から父親へ親権が変更されました。裁判では次の点などを考慮されて決定したということです。
|
裁判年月日 平成27年 1月30日 裁判所名 福岡高裁 裁判区分 決定 事件番号 平26(ラ)414号 事件名 親権者変更申立却下審判に対する抗告事件 裁判結果 変更 上訴等 確定 |
参考:文献番号 2015WLJPCA01307001
親権者の変更が認められるハードルはかなり高いようですが、このように親権者として不適格であると判断された場合、親権が変更される可能性はあります。
さまざまな事情があるかとは思いますが、無断で拒否をしたり、連絡を絶ったりすることは控えるべきです。
もし面会交流を拒否する正当な理由がある場合には、別途家事調停(面会交流調停)を申し立てて面会交流の可否及び方法について再協議するべきでしょう。
面会交流は、双方協議で方法や頻度を決定するのが通常ですが、なかなか当事者間で折り合いがつかないということもあります。
この場合、家事調停を申し立てることで面会交流の可否、方法について協議していくことになります。

面会交流は子供の権利であるため、親権者はこれを実施しなければならないのが原則です。しかし、以下のような場合は面会交流を拒否することができる可能性があります。
ただし、覚えておいていただきたいのは、裁判所は基本的には面会交流を実施する方向で検討するということです。
したがって、上記①~④のような事実があった場合であっても、その程度に応じて適切な面会交流の実施方法が検討されます。
【参考】
子供と直接関係のない事情を主張しても、面会交流の拒否は認められない可能性が高いです。よくある主張としては次のものが挙げられます。
例えば、子供の養育をせずに不倫相手を会っていたようなケースを除いて、有責配偶者であることは面会交流をする・しないとは直接関係しません。
相手が養育費を払わないといった事情も考慮はされますが、面会交流の拒絶と直接的な関係はありません。
面会交流は、離れてしまった親と交流ができ、子供の成長に欠かせない、子供のための権利です。子供の権利・利益とは関係のない事情では面会交流の拒否・制限はできないのが通常です。
また、意外かもしれませんが、相手のモラハラだけを理由として、面会交流を拒否しても、それだけで直ちに面会交流が中止されるわけではありません。
そもそもモラハラの事実を証明するのが難しいということもありますが、モラハラはあくまで親同士の問題であって、子供には直接関係ありません。
したがって、相手が自分に対してモラハラをするから面会交流をさせたくないと主張しても、これのみで裁判所が面会交流の実施を中止・制限するとは考えにくいです。
もっとも、相手のモラルハラスメント行為が、親権者による面会交流への協力を阻害するという判断をされた場合や、子供の生育に悪影響となると判断される場合は、面会交流が一定の限度で中止・制限される可能性はあります。
面会交流を拒否・制限したいのであれば、まずはこれを正当化する事実を証拠に基づいて立証する必要があります。例えば、以下のような証拠が考えられます。
|
面会交流の拒否を主張する際の証拠 |
|
|
子供が虐待されていた証拠 |
子供のケガの写真や診断書、警察や医師などに相談した記録など |
|
相手が暴力を振るっていた証拠 |
相手のDVでケガなどをしたことがわかる写真や診断書 警察へ相談をした記録 裁判所から出された保護命令の記録 シェルターを利用した記録 相手の暴力や暴言を録音したもの など |
|
アルコールや薬物依存であることがわかる証拠 |
アルコールや薬物依存で、子供を虐待していた音声や動画 ケガをしたことがわかる写真や診断書 など |
ただし、離婚後の面会交流を見越してこのような記録を残していない場合も多いでしょうから、弁護士に相談をして有効な証拠を集めることをおすすめします。
また、面会交流の取り決めを守らないと言った場合は、どういった部分を守っていないのか、記録を取っておきましょう。
証拠を残しにくい部分に関しては、どのように立証する方法があるのか、弁護士に相談したほうが早いでしょう。
面会交流は子供の権利ですので、可能であれば片方の親と会わせるのがよいということは誰もが思っていることでしょう。
もし、相手が子供に対して虐待や暴力をしないのであれば、やはり子供と会わせることを検討してみてもよいのではないでしょうか。
しかし、信用できない相手に大切な子供を少しの時間でも預けるのが不安という気持ちも当然です。

相手と2人きりで会わせるのには抵抗がある
相手が子供にどんなことをいうのか不安がある
直接会わせたくない
ここでは、元配偶者と子供が二人きりで面会交流に不安がある場合の対処法について紹介します。
面会交流で相手と子供が2人きりになるのが不安だから、一緒に面会をしているけど、本当は会いたくない、連絡も取りたくないといったケースもあるでしょう。
あるいは、相手が子供に何か吹き込む不安があるという方もいるかもしれません。
あなたの負担を少なくして面会交流をする方法の一つは、第三者立ち合いのもとで面会交流をすることです。
この第三者とは、面会交流をサポートしている支援団体のことです。面会・受け渡しだけなど、希望に応じた支援を行ってくれます。
希望に応じて費用の負担を求められる団体が多いですが、収入面など一定の条件下で無料支援を受けられる所もあります。あなたの条件に合う団体があれば、利用してみるのも一つの方法です。
面会交流支援団体
●公益社団法人家庭問題情報センター 大阪ファミリー相談室|面会交流のご利用について
もう一つの方法が、面会交流のやり方を変えることです。
面会交流というと、相手と直接会わなければならないイメージがあるかもしれませんが、文通や写真のやり取り、プレゼントを贈るといった方法で行うこともできます。
相手もなかなか応じないケースがあるかもしれませんが、第三者の支援団体を利用したり、文通などで交流をしたり、直接会う頻度を変えるなどすることで、面会交流への抵抗が減っていくかもしれません。
面会交流は子供が父母に愛されていることを実感できる、子供の権利です。相手が虐待やDVをするなど、よほどのことがない限り行うことが好ましいでしょう。
きっと、そういったことをわかっていても、相手が子供に暴言を吐いてきた、あなたにモラハラをしてきたなど不安に感じる要素があるのでしょう。
また子供が拒否している場合、それが親権者の顔色をうかがったものであるのかどうか、慎重に見極める必要もあります。
子供が親に遠慮してしまい、面会交流を我慢することは子供にとって不幸でしかありません。
面会交流がスムーズに行えるようになることは、あなたにとってもメリットがあります。万が一、子供のことで何かあったとしても、相手を頼ることができるからです。
今すぐできなかったとしても、少ない回数からスタートしたり、支援団体を活用して、徐々に回数を増やしたりするなどして、将来的には定期的な面会交流が可能になるよう、段階を踏んでいきましょう。
離婚時にもめるなどした夫婦は、面会交流の条件でも意見が食い違うことが考えられます。
もし離婚時にもめていたり、相手から面会交流を要求されていたりする場合は、相手が強硬手段に応じる前に、まず弁護士に相談しておくことを強くおすすめします。
相手が本当に虐待やDVをする相手であればなおさらです。お子さんを守れるのはあなたしかいません。
一方で、面会交流を拒否する理由が、ご自身の感情面で整理できていないといった場合でも、あなたが無理なく面会交流をできるよう、条件などを見直すよう交渉してくれます。
『ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)』では、無料相談を受け付けている弁護士事務所も掲載していますので、まずは相談だけでもしてみましょう。


【渋谷駅から徒歩5分】【毎週土日対応可】【お仕事帰りの夜間相談可】【初回面談30分無料】不倫の慰謝料を請求したい方、お任せください!実績豊富な弁護士が証拠集めから丁寧にサポート!【オンライン面談対応可】【LINE予約可】
事務所詳細を見る
不動産の売却が伴う離婚のご依頼は、着手金0円で依頼可◎|【マイホームやマンション、土地などを売り、大きな財産を獲得したい方へ】不動産売却に注力してきた弁護士が、密な連携でサポートします【初回面談0円】
事務所詳細を見る
【離婚を決意したらご相談を】◆財産分与/婚姻費用/不倫慰謝料請求/離婚調停/養育費/親権/面会交流など幅広く注力◎詳細は写真をクリック!
事務所詳細を見る
面会交流は非監護親と子どもの権利ではありますが、状況によっては実施しない方がいいケースもあります。この記事では、面会交流をしない方がいいケースや拒否したい場合の...
面会交流権とは、離婚に伴い、離れて暮らすことになった親と子が交流する権利のことです。定期的な面会交流は、子どもの健やかな成長にもつながります。この記事では、離婚...
非親権者が面会交流に再婚相手を同伴させていたことが発覚し、今後は同伴を拒否したいと考えている方もいるでしょう。子どもの心境を考えると、一刻も早く対処したいですよ...
面会交流(親子交流)とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が、子どもと定期的・継続的に会うことです。本記事では、面会交流しない方がいい場面の具体例、どのよう...
本記事では、親権変更が認められるケースや、親権変更を成功させるためのポイントなどをわかりやすく解説します。親権者変更は調停を申し立てる必要があるので、手続きの流...
祖父母が孫と面会交流する方法と、面会交流する際の注意点について解説します。自分の親にも孫の顔を見せてあげたいという方や、お孫さんに会いたい方はぜひ参考にしてくだ...
離婚後も父母が共同で親権をもつことを、共同親権といいます。では共同親権が導入されたら、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。本記事では、まもなく日本...
面会交流のルールは離婚時に決めますが、ベストな回数・頻度は判断が難しいため、「面会交流が多すぎる」といったケースもあるようです。 本記事では、面会交流が多すぎ...
しつこい面会交流に困っているときは、まず以下の不安や疑問を解消しておく必要があります。 本記事では、面会交流の嫌がらせに対処する方法や、拒否が認められやすいケ...
間接強制は一定要件を満たすと認められやすくなりますが、確実ではないため、過去の判例も参考にしておかなければなりません。 本記事では、面会交流の間接強制が認めら...
親権を獲得できなかった場合、面会交流権を獲得して子どもに会う権利だけは獲得したいと思うはずです。今回は子どもに会う権利を求める面会交流調停の流れと、面会交流が許...
面会交流を拒否しているけど、会わせてほしいと言われ、悩んでいませんか?面会交流の拒否は、制裁金などのリスクがあります。この記事では、面会交流の拒否4つのリスク、...
離婚後も父母が共同で親権をもつことを、共同親権といいます。では共同親権が導入されたら、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。本記事では、まもなく日本...
離婚時に面会交流の約束をしていても、離婚後に相手の都合で会わせてもらえないケースは多々あり、その場合は相手に慰謝料請求できる可能性があります。本記事では、面会交...
面会交流とは、離婚などで同居していない親と子供が交流をおこなうことです。本記事では、面会交流の概要から面会交流で決めるべき内容や取り決め方、拒否が認められるケー...
調停や審判で、面会交流の可否や内容が争われるケースはさまざまです。「自分の場合は面会交流が認められるか」を、非監護親だけで判断するのは困難でしょう。本記事では、...
面会交流のルールは離婚時に決めますが、ベストな回数・頻度は判断が難しいため、「面会交流が多すぎる」といったケースもあるようです。 本記事では、面会交流が多すぎ...
しつこい面会交流に困っているときは、まず以下の不安や疑問を解消しておく必要があります。 本記事では、面会交流の嫌がらせに対処する方法や、拒否が認められやすいケ...
相手と離婚や別居をし、子どもの面会交流について悩んでいるなら、面会交流支援団体の利用を検討するのがおすすめです。連絡調整から受け渡し、付き添いまで任せられます。...
祖父母が孫と面会交流する方法と、面会交流する際の注意点について解説します。自分の親にも孫の顔を見せてあげたいという方や、お孫さんに会いたい方はぜひ参考にしてくだ...
非親権者が面会交流に再婚相手を同伴させていたことが発覚し、今後は同伴を拒否したいと考えている方もいるでしょう。子どもの心境を考えると、一刻も早く対処したいですよ...
面会交流を拒否しているけど、会わせてほしいと言われ、悩んでいませんか?面会交流の拒否は、制裁金などのリスクがあります。この記事では、面会交流の拒否4つのリスク、...
調停や審判で、面会交流の可否や内容が争われるケースはさまざまです。「自分の場合は面会交流が認められるか」を、非監護親だけで判断するのは困難でしょう。本記事では、...
祖父母が孫と面会交流する方法と、面会交流する際の注意点について解説します。自分の親にも孫の顔を見せてあげたいという方や、お孫さんに会いたい方はぜひ参考にしてくだ...
面会交流とは、離婚などで同居していない親と子供が交流をおこなうことです。本記事では、面会交流の概要から面会交流で決めるべき内容や取り決め方、拒否が認められるケー...
本記事では、親権変更が認められるケースや、親権変更を成功させるためのポイントなどをわかりやすく解説します。親権者変更は調停を申し立てる必要があるので、手続きの流...
離婚後も父母が共同で親権をもつことを、共同親権といいます。では共同親権が導入されたら、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。本記事では、まもなく日本...
離婚する際や、元配偶者が子どもに会わせてくれない場合には、面会交流について話し合う必要があります。面会交流に関するトラブルは、弁護士に無料相談をするのがおすすめ...
子どもとの面会交流を拒否されると当事者間の解決が難しいため、専門家に相談しましょう。状況によっては調停や慰謝料請求も必要となるので、相談先は弁護士がおすすめです...
親権を獲得できなかった場合、面会交流権を獲得して子どもに会う権利だけは獲得したいと思うはずです。今回は子どもに会う権利を求める面会交流調停の流れと、面会交流が許...
しつこい面会交流に困っているときは、まず以下の不安や疑問を解消しておく必要があります。 本記事では、面会交流の嫌がらせに対処する方法や、拒否が認められやすいケ...
面会交流のルールは離婚時に決めますが、ベストな回数・頻度は判断が難しいため、「面会交流が多すぎる」といったケースもあるようです。 本記事では、面会交流が多すぎ...