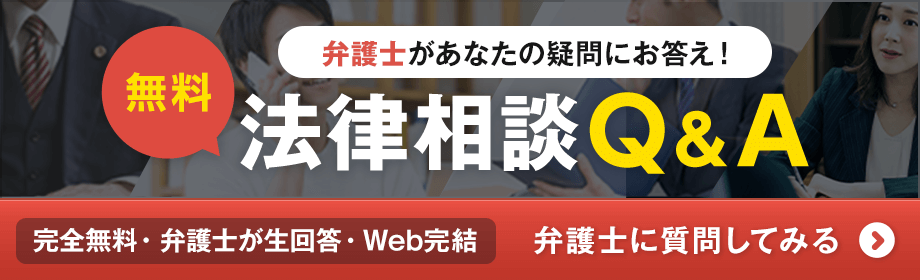夫が親権を持つパターンは?割合・決め方などを解説

親権争いは、基本的に母親が有利とされています。
しかし、夫も主体的に育児参加している場合などは夫が親権を持つ可能性もあります。
実際、離婚に向けた話し合いを進めるなかで、夫が親権を持つことになるのではないかと不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、夫が親権を持つパターンを事例とともに解説していきます。
親権争いで揉めている方、親権の行方が気になっている方は最後まで目を通してみてください。
親権は母親が有利?親権を決める際の基準やポイント
親権は母親の方が有利だといわれています。
それは「母性優先の原則」と「兄弟姉妹不分離の原則」という2つの法則があるためです。
しかし、経済状況や離婚に対する有責性なども考慮されるので、場合によっては夫が親権を持つ可能性も十分あります。
ここでは、親権を決める際の基準やポイントについて解説するので参考にしてみてください。
母性優先の原則
親権を決める際のポイントとしては、まず「母性優先の原則」が挙げられます。
母性優先の原則とは、「母性的な役割を担う親のもとで子が養育されることが望ましい」という考え方のことです。
子どもの年齢が小さければ小さいほど、親権争いでは母性優先の原則が考慮されやすくなります。
ただし、ここでの母性とは、当然に母親のことを意味するわけではありません。
子との間で深い結びつきを持ち、子を主に養育してきた親のことを意味します。
そのため、母性優先の原則は、考慮され得るポイントのひとつとして考えておくとよいでしょう。
兄弟姉妹不分離の原則
親権を争う際には「兄弟姉妹不分離の原則」の考え方も重要になります。
兄弟姉妹不分離の原則とは、強い絆のある兄弟姉妹はできるだけ一緒に暮らすことが望ましいという考え方です。
例えば、兄弟がいた場合に、兄の親権だけでも獲得したいといったような要望は受け入れられにくいでしょう。
ただし、子ども自身が同意している場合など、例外的に兄弟姉妹の分離が認められるケースもあります。
親権はあくまでも個々の事情に応じて、判断されるものであることを覚えておきましょう。
経済状況
経済状況も、親権を決める際に考慮されるポイントのひとつです。
子どもが不自由ない環境で生活していくためにも、親権者には最低限の経済余裕が求められます。
ただし、経済格差は養育費でカバーされるため、経済状況が親権争いに大きな影響を与える可能性は低いといえるでしょう。
離婚に有責性があるか
離婚の有責性は、基本的に子どもの利益とは別問題なので親権争いにも関係しません。
しかし、有責性の内容によっては間接的な影響を及ぼすことがあります。
例えば、妻が不倫相手と会うために子育てをおろそかにしていた場合や、妻の不倫相手が子どもを虐待していた場合などは、親権争いで夫が有利になるでしょう。
反対に、有責配偶者であっても子育てをしっかりとおこない、子どもとの信頼関係も築けているのであれば、親権を獲得できる可能性があります。
父親が親権をもつパターンとは?母親が親権争いで負ける4つの理由
親権争いでは、原則的に母親のほうが有利です。
しかし、以下の4つのケースでは母親が親権争いで負ける可能性があります。
- 母親に子どもへ愛情をもって育児してきたという実績がない
- 母親が子どもに虐待をしていた
- 母親が精神疾患を患っている
- 子どもが父親と暮らしたいと思っている
一つひとつのポイントを詳しく解説するので、自身に該当する部分がないかチェックしながら読み進めてみてください。
母親に子どもへ愛情をもって育児してきたという実績がない
親権争いでは、監護の継続性が重視されます。
監護の継続性とは、子どもの生活環境を離婚後も継続させることが望ましいという考え方です。
例えば、父親が育児のほとんどを担っていたケースにおいて、母親に親権を与えると監護の継続性が担保されません。
そのため、親権を争うことになった場合は、母親が負ける可能性も十分考えられます。
また、離婚によって居住地や学校が変わってしまうことも、監護の継続性に反するとして避けられる傾向があります。
母親が子どもに虐待をしていた
母親が子どもに虐待をしていたケースでは、当然親権争いでも不利になります。
虐待は殴る蹴るなどの身体的虐待だけではなく、暴言や罵声を浴びせるなどの心理的虐待も該当します。
また、「食事を与えない」「何日も同じ服を着せる」「お風呂に入らせない」「学校に行かせない」などのネグレクトも虐待のひとつといえるでしょう。
離婚する際に親権が認められたとしても、虐待を繰り返せば親権が停止し、子どもと引き離される可能性があります。
母親が精神疾患を患っている
母親が精神疾患を患っている場合は、親権を獲得できないことがあります。
精神疾患の状態によっては、育児が難しいと判断されるためです。
具体的には、以下のようなケースが挙げられます。
- うつ病を発症していて思うように活動できないことがある
- 幻覚・幻聴によって取り乱すことが頻繁にある
ただし、親権争いで不利になるのは、精神疾患によって最低限の育児ができない場合や、虐待・育児放棄などの問題行動が見られる場合などです。
精神疾患を患っていても、育児に問題がないと判断されれば、母親が親権を獲得できるケースもあります。
子どもが父親と暮らしたいと思っている
子どもが父親と暮らしたいと思っている場合も、母親が親権争いで負けることがあります。
そもそも親権は子どもに関する問題であるため、子ども自身の意思も最大限尊重されるわけです。
ただし、子どもが乳幼児である場合などは意思能力が乏しいとみなされるので、親権者の決定に与える影響も小さくなります。
一方で、10歳ごろになると子どもの意思が尊重されるようになり、15歳以上になれば原則として子ども自身が親権者を決められるようになります。
父親が親権を獲得した事例
親権争いにおいては、母親に母性優先の原則や兄弟姉妹不分離の原則が有利にはたらくケースが多く見られます。
しかし、父親が親権を持つ可能性もゼロではありません。
ここからは、実際に父親が親権を獲得した事例を見ていきましょう。
母親が子どもを勝手に連れて出ていった
母親が子どもを無許可で連れ去ったことで、父親が親権を獲得するケースがあります。
実際に子どもの連れ去りに気づいた父親が法的措置を講じ、親権を獲得している事例は存在します。
連れ去りは子どもの利益を害し、犯罪にもなり得る行為であるため、裁判などでは不利に働くことを覚えておきましょう。
母親が不貞行為のために育児放棄していた
母親が不貞行為のために育児放棄していたことを理由に、父親が親権を獲得した事例もあります。
例えば、不倫相手に会うために、未就学児の子どもを一人で留守番させるなどの行為に及んでいたケースです。
ただし、不貞行為はあくまでも離婚の原因となるものです。
上記の例においても、仮に育児をしっかりとしていたのであれば、母親が親権を失うことはなかったかもしれません。
子どもの意思が尊重された
子どもの「父親と暮らしたい」という意思を示し、父親が親権を獲得した事例も少なくありません。
子どもの意思は、親権争いに大きな影響を及ぼします。
特に10歳以上の子どもの意思は親権争いの際に重視され、15歳以上であれば基本的に子どもが親権者を決められます。
そのため、子どもが「父親と一緒に暮らしたい」と意思を表示した場合には、父親が親権を獲得できる可能性があります。
母親より父親が育児することが多かった
母親より父親が育児をすることが多かったため、父親が親権を獲得した事例もあります。
親権は、より子どものためになると判断されるほうの親に与えられるのが基本です。
父親が主に育児をしていた状況があるなかで母親に親権を与えてしまったら、これまで通りの養育環境を確保できなくなるので、親権争いでは父親が有利になるでしょう。
そのため、親権を争う場合には、これまで子育てにどの程度関与してきたのかを客観的に振り返ることが重要です。
別居中に父親が子どもと暮らしていた
夫婦別居中に父親が子どもと暮らしていたケースでは、父親が親権を獲得する事例が数多くあります。
親権争いでは、監護の継続性が重視されます。
離婚前後で、子どもの生活環境が大きく変わることのないよう配慮しなければなりません。
そのため、別居中に父親と長く暮らしていた実績があるのであれば、監護の継続性の観点から、そのまま父親に親権が認められる可能性が高くなります。
さいごに
親権を争う場合は、母性優先の原則、兄弟姉妹不分離の原則、監護の継続性、子どもの意思などが考慮されます。
そのうえで、日本においては母親が親権を持つケースが一般的といえるでしょう。
しかし、以下のようなケースでは父親が親権を獲得する可能性もあります。
- 父親が育児の多くを担っていた
- 母親が子どもに虐待をしていた
- 母親が精神疾患を患っている
- 子どもが父親と暮らしたいと思っている
上記に該当する場合なお、父親に親権をとられるおそれがある場合は、離婚問題が得意な弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼すれば、親権争いを有利に進められるように、証拠集めや裁判手続きなどのサポートをおこなってくれます。
対応が遅れると親権の獲得が難しくなるので、できるだけ早めに相談しておくことが大切です。


【初回相談0円・クレカ決済可】【女性弁護士・歴10年以上のベテラン弁護士在籍】|慰謝料・財産分与など、離婚条件のお悩みなら|≪雑誌ananにて紹介されました!≫|※夜間・早朝のご相談は、原則営業時間内にご返信します※
事務所詳細を見る
◆辛い胸の内をまずお聞かせください◆デリケートな問題だからこそあなたの心に寄り添い、新たな一歩を力強くサポートします!お子様の将来やお金の不安をなくすため<離婚後も徹底サポート>をお約束します◎
事務所詳細を見る
【全国対応】離婚・不貞問題、貴方の「権利」と「未来」を徹底的に守り抜きます。 感情論で終わらせず、法的ロードマップと生活設計で、一日も早い再出発を強力サポート。一人で悩まず、まずはご相談を。【24時間・オンライン完結・初回相談無料】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

親権(子供)に関する新着コラム
-
「認知はするけど結婚はしない」という選択も可能です。認知しない場合、子どもの将来や権利に悪影響を与える可能性があるため、パートナーと話し合い慎重に検討する必要が...
-
強制認知を検討している人必見!強制認知についてはDNA鑑定をはじめとした客観的な証拠が重要視され、十分な証拠がないと母親が負ける可能性もあります。DNA鑑定を拒...
-
この記事では、夫以外の男性との間にできた子どもを夫の子だと偽る「托卵」が露見するケースと、それが発覚した場合に日本の法律で何が起こり、どのように対処すべきかを詳...
-
離婚後子どもを育てられる自信がなく、夫に親権を渡したいと考えている方もいるかもしれません。しかし夫側も親権を拒否すれば、お互いに親権を押し付け合うことになります...
-
離婚を検討しているなかで、母親が親権をもつ場合に子どもの苗字を変えたくないと思っている方は少なくないでしょう。本記事では、離婚時に子どもの苗字を変えない場合は戸...
-
親権は必ず母親が獲得できるのか、夫に親権が渡ることはあるのかなど、不安に思う方もいるでしょう。この記事では、母親が親権を獲得できないケースや、親権を獲得したいと...
-
離婚をするとき、子どもの親権は大きな争点となるでしょう。 一般的には母親が親権を獲得しやすいイメージがありますが、必ずしもそうではありません。 本記事では、...
-
本記事では、離婚後に親権者を父親から母親へ変更するのが難しい理由や手続きの流れ、成功事例について解説します。本記事を読むことで、ご自身のケースで離婚後の親権変更...
-
親権争いは基本的に母親が有利とされていますが、夫も主体的に育児参加している場合などは夫が親権を持つ可能性もあります。本記事では、夫が親権を持つパターンを事例とと...
-
本記事では、親権変更が認められるケースや、親権変更を成功させるためのポイントなどをわかりやすく解説します。親権者変更は調停を申し立てる必要があるので、手続きの流...
親権(子供)に関する人気コラム
-
離婚しても、どちらの親も親権をほしい場合、離婚協議や調停で揉める可能性があります。この記事では、離婚する際に子供の親権を獲得するために知っておくべき基礎知識や有...
-
離婚時の子どもの親権は母親が有利になりやすいものの、父親でも親権を取れる可能性はあります。本記事では、離婚時に父親が親権を取りにくい理由や親権者の判断基準、父親...
-
親権と似た意味で捉えられるのが子供を育てる権利・義務である監護権。今回は親権と監護権の違いを把握するとともに、親権者・監護者を決める手続きの方法などをご紹介しま...
-
離婚する際、子供への説明は十分でしょうか?親の離婚は子供にとって大きな影響を与えます。この記事では、子供への影響や子供が受けるストレスを最小限に抑える対策、子供...
-
離婚後に元夫以外の男性の子供を妊娠し出産したとしても、産まれてくる子供は元夫の子供とされてしまう問題を「300日問題」と言います。今回の記事では、離婚後の300...
-
本記事では、別居中の子供に会わせない行為で慰謝料請求が認められるケースや、面会交流が拒否されるケースを解説します。
-
子供がいる専業主婦が離婚を考えたとき、親権を持つことが難しいのではとためらっている方も多いでしょう。しかし、必ずしも親権を持つ上で専業主婦であることが不利になる...
-
離婚したあと、子どもの戸籍や姓をどうすべきか悩む方は多いでしょう。基本的には離婚しても子どもの戸籍や姓は変わりませんが、いくつか注意すべき点もあります。この記事...
-
親権とは、未成年の子の養育監護や財産管理をする権利・義務を指します。適法な手続きをとれば親権放棄は可能ですが、親権放棄が認められるのは子どもの福祉を守るためにや...
-
本記事では、離婚後の面会交流の基礎知識や手続きの流れ、注意点について解説します。
親権(子供)の関連コラム
-
親権をなんとしても獲得したいなら、親権問題に注力している弁護士に依頼しましょう。親権を含む離婚の条件は、任意の話し合いから調停、訴訟へと進みます。話し合いから弁...
-
共同親権(きょうどうしんけん)とは、母親と父親のどちらもが子供に対する親権を持つ制度のことをいいます。現在の日本では、婚姻関係中にのみ共同親権が認められています...
-
離婚の際、子供の親権者をどちらにするか争いになる場合があります。 親権獲得のためにかかる費用や親権獲得までの流れ、親権に関する問題を弁護士に相談するメリットを...
-
子どもの親権は子どもが成年に達するまで続きます。2022年4月には、改正民法が施行され、成年年齢が引き下げられました。この記事では、親権の存続期間・親権の内容・...
-
離婚しても、どちらの親も親権をほしい場合、離婚協議や調停で揉める可能性があります。この記事では、離婚する際に子供の親権を獲得するために知っておくべき基礎知識や有...
-
親権とは、未成年の子の養育監護や財産管理をする権利・義務を指します。適法な手続きをとれば親権放棄は可能ですが、親権放棄が認められるのは子どもの福祉を守るためにや...
-
当記事では、子どもへの虐待の定義や具体的な虐待の種類を整理したうえで、虐待を理由にした慰謝料請求や離婚の可否について解説
-
離婚をするとき、子どもの親権は大きな争点となるでしょう。 一般的には母親が親権を獲得しやすいイメージがありますが、必ずしもそうではありません。 本記事では、...
-
離婚を検討しているなかで、母親が親権をもつ場合に子どもの苗字を変えたくないと思っている方は少なくないでしょう。本記事では、離婚時に子どもの苗字を変えない場合は戸...
-
離婚する際、子供への説明は十分でしょうか?親の離婚は子供にとって大きな影響を与えます。この記事では、子供への影響や子供が受けるストレスを最小限に抑える対策、子供...
-
離婚の際に決めた子どもの親権者を変更するには、家庭裁判所に「親権者変更調停」を申し立てる必要があります。親権者変更調停について、手続きの流れや、家庭裁判所が主に...
-
親権問題を無料で相談できる機関や窓口はあるのでしょうか?この記事では、親権問題を無料相談できるおすすめの相談先のご紹介から、弁護士に相談すべき人と相談のタイミン...
親権(子供)コラム一覧へ戻る